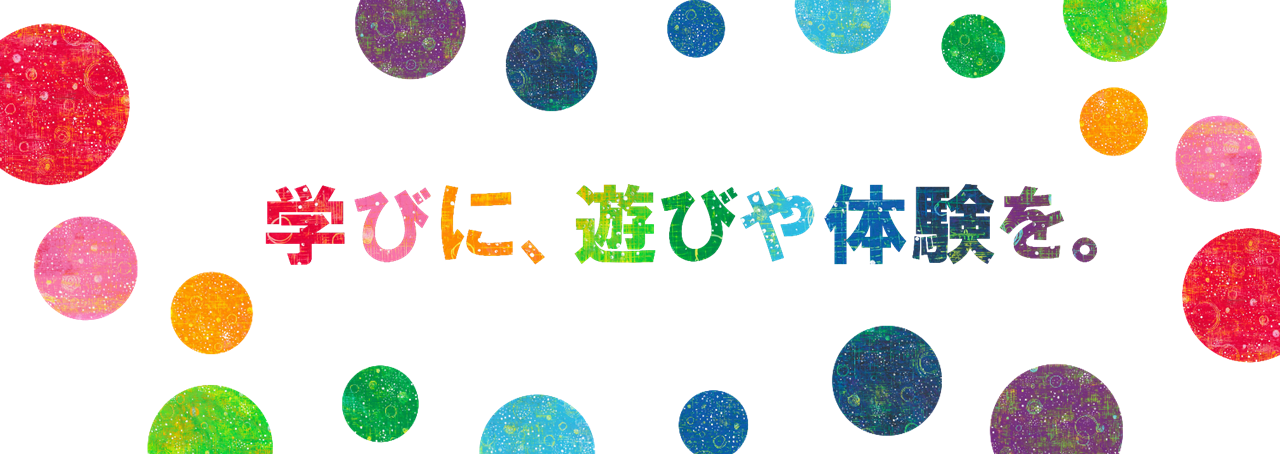本文
【令和6年度】ひきこもりについて語り合う会
【終了】第2回ひきこもりについて語り合う会
令和7年3月1日(土曜日)に開催し、無事終了しました。
当日は春の陽気となり、25名の方にご参加いただきました。
今回は、駒ケ根市にある(合同会社)夢倶楽部しらかば信州カウンセリングセンターの所長で臨床心理士の有賀和枝さんを講師にお招きし「ともに生きる ―そこに在るものー」と題して講演をいただきました。
有賀さんは約30年前から、当時「県下でいちばん人数が多い」と言われた駒ケ根市の不登校やひきこもりの子どもたちを訪ね、支援をしてきたアウトリーチの実践者です。退職後は、就労できる以前の人たちをフォローする団体がないため、その人たちの居場所や交流の場所としての「学び舎」を立ち上げ、主宰されています。
活動の様子は、4年前のNHKテレビ「知るしん」でも放映され、大きな反響があったとのことです。当事者同士で交流し、意見交換をすることをきっかけに「誰かの役に立ちたい」という意識が芽生えるため、ボランティア活動ができる場も提供しています。
後半は、有賀さんの講演内容をもとにした、参加者同士のグループワークを行い、意見及び情報交換の場となりました。
参加者の方々からのアンケート結果については、以下のファイルをご覧ください。
第2回ひきこもりについて語り合う会 アンケート結果 [PDFファイル/555KB]

【終了】第1回ひきこもりについて語り合う会
昨年度に引き続き、令和6年8月3日(土曜日)に開催し、無事終了しました。
当日は、猛暑の中、32名の方にご参加いただきました。
今回は、支援者団体「NPO法人グランド・リッシュ」の若林美輪さん、上兼裕さんを講師にお招きし、「社会活動量低下状態とは?体験して考えよう!」をテーマに講演をいただきました。
若林さんからは、「社会活動量低下状態とは、防御の意識が働く状態で、誰でも感じることではあるが、長引かせることはよくない。どうすれば良いかというと、『運動』をすることが大切である。『運動』とは、身体を動かすことの他に、人と交流して会話・共感・共有することも含まれ、ポジティブな感情や安心感を得られる。」といった主旨のアドバイスをいただきました。
また、上兼さんからは、ひきこもり支援相談員として、ひきこもりの方へのアプローチの実践事例を紹介いただき、ひきこもりの方たちが持つ様々な関わり方の糸口を把握し、アプローチをしようとする努力が感じられる内容でした。
講演後は、講師のお二人の進行でグループワークを行いました。参加者それぞれが「自身が社会活動量低下状態になったときに、支援してくれる人にして欲しいこと・して欲しくないこと」を考え、グループに分かれて話し合いました。最後には、各グループで出た意見を発表しあい、全体で共有しました。
参加者の方々からのアンケート結果については、以下のファイルをご覧ください。
第1回ひきこもりについて語り合う会 アンケート結果 [PDFファイル/602KB]