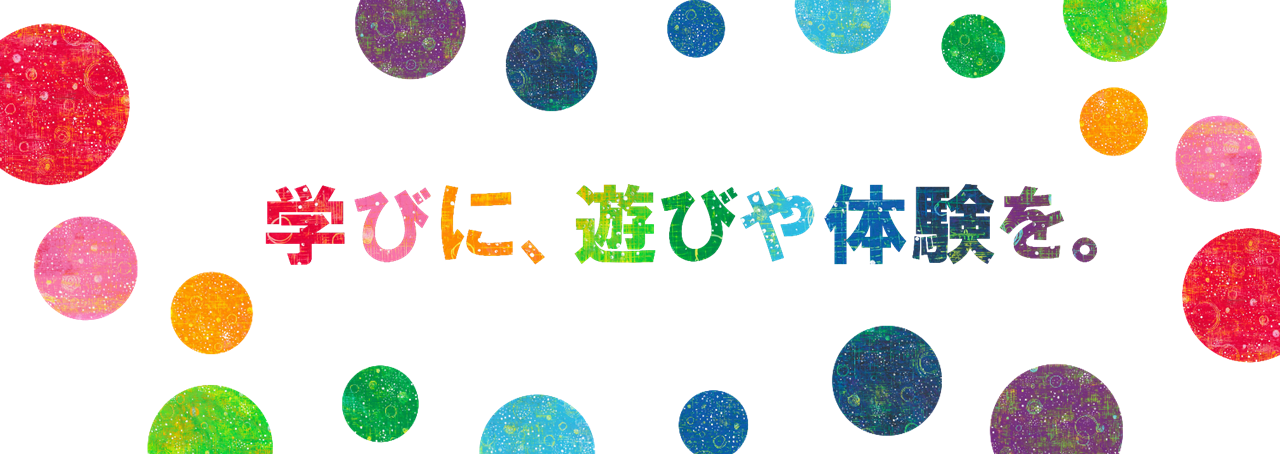本文
教育長通信(メッセージ)
第8回 「彼からの告白」

私は教員になる前、新宿の一流と呼ばれるホテルでウェイターとして働いていました。私が働き始めて1年後位でしょうか、Aさんという後輩がアルバイトで働き始めました。彼は、当時の私から見て怠け癖があり、きちんと仕事に向き合わない人に映りました。彼が働き始めて1,2か月後のことです。レストランは非常に混んでいるにも関わらず、彼はいつもと同じように、周囲の状況等には目を配らず、自分のペースでゆっくりと仕事をしているように見えました。さらに混んできた際、彼はパントリーと呼ばれる奥の部屋のアイスクリームケースの前で、先輩ウェイターと笑い合い、問答しながらアイスクリームを盛り付けています。フロアはこんなに忙しいのに、ゆったりと笑い合っている姿に堪忍袋の緒が切れ、「いい加減にしろ!遊んでないで仕事をしろ!」と怒りました。Aさんはその言葉に対して、「はぁ?あなたは神ですか!」と私に食って掛かってきました。
「そねさんがAと喧嘩した!」という噂はすぐに広まり、皆が気を遣い、私と彼を近づけないよう配慮するようになりました。私は、「何も間違ったことは言っていない」と信じていましたし、Aさんと話さなくても困ることは何もないので、全く気にしていませんでした。その後、私はホテルを辞めて、教員になりました。
令和8年1月中旬に、37年ぶりに、ホテルマン時代の仲間8名で顔を合わせました。その中にはAさんも含まれていました。会を主催した元同僚から、「Aさんも来るけど、そねさんは大丈夫?」と気を遣われましたが、今さら何のわだかまりもないので、「全く大丈夫!」と伝えていました。
当日、皆と久しぶりに顔を合わせました。容姿はだいぶ変わっていましたが、皆さん面影がありました。
Aさんとも顔を合わせ、普通に挨拶をすると、彼が「そねさんとじっくり話したい」と近寄ってきました。彼の話は、以下のようでした。
・ホテルで働き始め、覚えなければならないタスクがたくさんあったが、全く記憶できず、焦っていたこと
・様々なことができない自分に対し、表には出さないものの強い怒りを覚え、時にパニック状態になりそうになっていたこと
・私から叱責された時も、懸命に仕事をしているつもりであったが、いきなり私に怒られ、パニック状態から爆発し、言い返してしまったこと
・大学を卒業して新規に勤めた会社でも全く業務が身につかず、困ったこと
・上司から受診を勧められ、病院にかかると「ASD」と診断されたこと
・ASDを理解し、自分をコントロールできるようになり、その後は落ち着いて生活できて、家庭も持ち幸せに生活していること
この話を聞いて、今だから納得できる彼の様々な行動を思い出しました。私が叱責したあの時も、客からオーダーされたアイスクリームを盛り合わせていたところ、やり方が分からず、先輩ウェイターと「そうじゃない、ああじゃない」と笑い合いながら、彼なりに懸命に働いていたのだろうと。
彼からの告白を受け、私も彼に対して、「今は教員だから、ASDのことを理解している。あの頃の自分が今のように理解をしていたら、全く違う接し方をしていたと思う。いきなり怒って申し訳なかった」と伝えました。
あの頃、すべてを一気に一通り説明して理解を促すのではなく、目の前の一つ一つのタスクを状況に合わせて説明し、やってみせ、できたことを認めていく。彼も勤めながら、そのような丁寧な支援があったら、困り感を解消できたのだろうと思います。彼には、「自分自身を客観視して語ることができ、乗り越えて充実した人生を送っている姿がとても素敵だね」と伝えました。
教員の中には、その子の一面を見て、「〇〇ができない」「言うことを聞かない」等、自分の指示通りに動くことのできない子どもに対する不満の気持ちを抱える方もいると思います。若いころの私もその一人です。しかしながら、ASD等の特性を理解し、「それがその子の個性」と認識を深めれば、支援方法や接し方が変わります。そして、その子なりの懸命な姿に、いとおしささえも覚えました。
未来予測が困難な変化の激しい時代において、教育の知見も大きく変わっています。個に応じた新たな支援の考え方も示されています。「学び続ける教師」の大切さの真の意味を感じた再会でした。
第7回 「できない思考」から「できる思考」へ

中学校の同窓会がありました。その中で、ずっとアメリカのシリコンバレーで働いていたという友人と久しぶりに話をしました。面白いことに、アメリカでの生活が長いからか、日本語が英語なまりになっています。私が「アメリカと日本の違いは何?」と聞くと、「日本は変わることを恐れるけれど、アメリカは変わることを求める」「アメリカの企業は、3年前と同じことをやっていたら退化と考える。常に変化しようとする」との答えを得ました。
小中学校の不登校の児童生徒数は、R5の数値で10年前の3倍近くに急増しています。特別支援学級入級数は35年前の約4.6倍、通級による指導を受けている児童生徒数は30年前の約16倍です。これは、日本の学校教育のあり方を大きく見直す必要があることを示唆していると、私は考えます。
では、何を、どのように見直すのか。大きくは、日本の社会における学校が担う役割の見直しが必要と考えますが、細かくは学校教育目標、子ども観、授業観、教職員の働き方、登校日数、日課、校則、地域との連携など、視点はたくさんあります。様々な視点に沿った具体の見直しは、各校が、児童生徒や保護者の実態、それぞれの地域の実情等に応じて、それぞれ進めるべきと考えます。街中の学校と、山間部の学校では、状況が全く異なります。
何か見直しを進めようとする際、「できない理由を並べる」思考をする方と、「できる方策を模索する」思考をする方がいます。「××だからできない」「△△がないから取り組めない」等と懸念点を並べ、変化をしない方向へ導く方と、「〇〇のように進めればできそうだ」「◇◇は難しいけど、□□の方策ならば可能だ」と、変化をしようとする方向へ導く方がいます。私自身は、その変化が児童生徒にとって良い方向であると判断できるならば、常に後者であるように努めてきました。
今、教員の働き方改革の必要性が叫ばれていますが、これは、教師が働かないことを目指すものではありません。児童生徒が、「自分らしく あなたらしく ありのままに」いられて学べる学校創りを進めるために、教師に時間的・精神的余裕をもたらすための改革です。
すべての目的は、児童生徒のウェルビーイング(身体的・精神的・社会的に良い状態:ストレスなく、心地よい状態)の実現です。そのために、これまでの「当たり前」や「ふつう」を見返し、新たな学校づくり、授業づくりに挑戦し続ける「みんなの未来の学校(みんミラ)」への変化に、松本市のすべての学校が取り組んでほしいと願っています。変化を恐れず前へ進める管理職、教職員、学校であってほしいと、切に願っています。
第6回 「宿題を無くせるか」

7月25日に行われた、松本市全教職員による研修会「「結」まつもと学びの日」において、15分間お話をさせていただきました。その際、「宿題を無くす」ことに触れましたが、その後ご講演された木村泰子先生からも、宿題を無くすことに賛同いただきました。宿題を無くす、というのは、「子どもの学習を放任する」ことではありません。正確には、提出を求める宿題をやめて、子どもが「自ら学習を調整する力」の育成を目指すものです。
私は初任で小学校に配置され、単級の4年生を担任しました。児童40人の学級で、空き時間は音楽のみでした。小規模校ならではですが、係主任も4つ抱えていました。全員の生活ノートを見て一言を添える時間も儘ならない中、漢字や算数の宿題の提出ノートなど、点検できる時間はありませんでした。休み時間は、ずっと子どもと遊んでいました。
そこで考えたのが、国語や算数の時間の最初5分は漢字や計算等の小テストを行い、宿題の提出はやめる、というものです。漢字の場合、出題する漢字は毎時間指定します。算数も、出題する問題を10問指定したら、その中から5問を出題します。子どもたちには、「この問題を次の時間の最初にテストします。もうこの漢字は書けるとか、計算ができるというのであれば、学習はしなくてもよい。でも書けない、できないのであれば、できるようにしてきてください。例えば、漢字を1回書いて練習すれば大丈夫という人は1回でよいし、2ページ書かないと不安という人は2ページ練習する。計算も、もう解ける、というのであれば学習をしなくてもよいですが、不安ならば、きちんと解けるように準備をしてきてください。友達に聞いたり、先生に質問したりしてよいです。小テストに向けて、自分なりの方法で、学習してきてください」と伝えました。
小テストは、毎回作成するのは大変なので、A4を八分の一に切った紙をたくさん用意しておき、係の児童が授業前に配ります。授業開始と同時に小テストの問題を口頭か板書します。小テスト後、隣の友だちと交換して答え合わせをして、「5点満点だった人!」と聞いて挙手を促します。小テストに出る問題は分かっているので、次第に全員が5点満点を取るようになり、それが個々の自信につながっていきました。中には、なかなか5点を取れない子どももいます。そのような子には、漢字練習の仕方を対話しながら導いたり、計算方法を個別に指導したりしました。
中学校に転任し、専門の理科に加えて数学を担当しました。理科は実験の準備・片付けがあるので、数学の提出ノートを点検する時間が無く、困りました。そこで、小テストを行うようにし、次時に出題する問題を指定して、提出ノートは、分からない問題の質問のみとしました。理科も、基本的に宿題は無く、授業開始2分前に前の時間のノートを見返すことを推奨し、授業の最初に小テストを行いました。理科も数学も、私の担当しているクラスの平均点がとても高くなりました。
出題される問題が分かる小テストを行う→学び方は個々に任せる→5点満点が取れると自信がつく→益々個別に学ぶようになる→定期テストの点数が高くなる→さらに「この教科は得意」と言って学ぶ、という好循環が生まれました。児童生徒は自ら学ぶようになり、それぞれの学習方法で、小テストに備えるようになりました。教員も提出ノートの点検数が少なくて済みます。
自分なりの学び方で、学んだ結果がすぐに小テストでフィードバックされる方策を取り、学んだことの成果を実感できる環境をつくれば、児童生徒の学びに向かう力が伸び、自ら学習を調整できるようになります。
今はほとんど無くなりましたが、以前は中学校で、3点セットと呼ばれる提出ノートがほぼ毎日課されていました。その提出率が「関心・意欲・態度」の評価につながっていました。今思えば、提出ノートで関心・意欲を評価するという勘違いが、全県で普通に行われていました。提出ノートを課す際、もう一つよく言われたのが、「毎日の学習習慣を着けるために必要」という議論です。これは、高校の先生から、明確に否定された経験があります。「提出ノートを中学校で課すから、高校に入学すると、「提出ノートが無くなった!」と喜んで、自ら学習することができない」という指摘です。
与えられた学習に嫌々取り組むのではなく、自ら学ぼうとする力をつけることが大切です。学習を早く終えたら、自分の時間ができて、ゲームばかりでは困りますが、読書や楽器演奏、趣味等、好きや楽しい、なぜをとことん追求できる時間的ゆとりが大切であると思います。今の小中学生は、忙しく息苦しくないでしょうか。
宿題を無くすことは、まだ学び方が分からない小学校低学年では難しいと思われますが、「自ら学習を調整できる力を伸ばす」という、真の目的の達成に向けて、是非、挑戦していただければと思っています。
第5回 「主体的に学習に取り組む態度」の評価

県教育委員会にいた頃、保護者から、子どもの評定に対する疑問についての問い合わせが度々ありました。
・我が子は体育が得意で、大好きなのに、通知表の評定が2で、ショックを受けてやる気をなくしている
・社会での定期テストの点数が高いのに評定が3で、子どもは、何をどう頑張ればよいのか分からない、と困惑している
・数学は、ほぼ100点を取っているのに、通知表は4だった。先生に聞くと、「提出ノートの提出率がよくないので、5はつきません」と言われた。子どもに、「提出ノートを出したら?」と聞くと、「僕は数学を理解しているのに、なんで毎日、ノートを提出しなければならないの?」と聞き返され、何も言えないなどの問い合わせを覚えています。学校へ確認を行いましたが、「?」が付くことも多くありました。
保健体育について当該校へ問い合わせると、「剣道で、竹刀の持ち方が違っていたので、評定を低くした」等の答えが返ってきました。私は驚きとともに、「え?竹刀の持ち方が違っていると把握していたのなら、正しい持ち方を助言し、正しく持てるよう支援するのが教員の役割ではないですか?」とお伝えしました。社会について当該校へお聞きすると、「発言の回数が少ないので3でした」と答えられ、「え?発言の回数は、主体的に学習に取り組む態度の評価ですか?発言回数で、主体的かどうか判断できるのですか?」とお伝えしました。数学の提出率については論外です。提出などせずに、自分で学習を調整して理解を深めている児童生徒こそ、主体的に学習に取り組んでいる姿です。
令和3年の9月に、高校の先生を対象に、「評価の正しい理解と評価方法の具体」という研修会を行いました。私が説明をしたプレゼンの内容に触れながら、特に「主体的に学習に取り組む態度」の具体の評価について、記したいと思います。
評価には、診断的評価(児童生徒の実態を把握して指導計画を立てるための評価)、形成的評価(学習活動の途中に児童生徒がどの程度理解しているのかを確認し指導に生かすための評価)、総括的評価(通知表、指導要録などの評定につながる評価)があります。重要なのは、形成的評価です。
・授業中、学ぼうとしていない姿が見られたので、「主体的に学習に取り組む態度」の評価をCにした。
・授業中、理解していない(技能としてできていない)姿を確認したが、そのまま何も支援せず、ペーパーテスト(パフォーマンステスト)でもできなかったので、「知識・技能」の評価をCにした。
これらは、教員が適切な指導・支援を行わないまま評価を行っており、児童生徒に確かな力をつけるという、授業の目的から外れています。「評定をつける」ことを目的に授業をするのではなく、学習状況を把握したら、児童生徒が「できるようになる」ことを目的に、適切な支援を講じることが大切です。できていない状況を把握しながら、そのままCと評価することは、「だまし討ち」の評価です。
教師としての使命は、たくさんの児童生徒が「分かった!できた!」の喜びを味わえるよう支援し続けることで、理想は、全員に「A」「5」をつけられることです。
「主体的に学習に取り組む態度」の評価は、教員の主観に左右されるのではないか、という声を聞きます。主観的になりそうだからこそ、「妥当性」と「信頼性」の担保に努めることが欠かせません。「妥当性」では、観点別評価を、どんな項目(生徒の学習の状況)を対象に行うのか、各教員が考え、同教科の教員と共有して確認することで、教員が同じ項目で評価し、教員の違いによる評定の違いが生じないようにできます。「信頼性」では、どんな項目で評価を行うのか、どのような状況(生徒の姿)がA~Cになるのか、生徒に説明して共有することで、評定について生徒が納得し、これから何をどう頑張ればよいのか生徒が自覚し、学習の調整を自らできるようになります。総括的評価により評定を導くための補助簿の作成も必須です。評定について、いつ誰から問われても、根拠を明確に答えることができます。
最後に、私が授業を行っていた際の、「関心・意欲・態度」(昔は、「関心・意欲・態度」「思考」「技能」「知識・理解」の4観点)の評定につなげる評価について紹介します。
◎授業の学習問題に対する最初の考えのワークシートへの記述(正解を求めるのではなく、自分なりの考えを書く)
※書いてある:B、既習や生活経験等と関連付けて記述:A
〇授業における取組態度:AとCの生徒がいたら記録
※授業を促進(他者への好影響):A、指導をしても授業を受けない等:C
〇授業ノートの記述
※板書等がまとめられている:B、自分なりの工夫したノート作りがされている:A
〇忘れ物:必ず用意するよう指示した教材等を忘れた:C
◎を一番重要視していましたが、これらの内容とA~Cの具体については、年度当初の授業で生徒に説明し、通知表の評価を見ても生徒が納得するようにしていました。また、日常授業における具体の評価記録は、座席表や名簿に取りためておき、総括を行う際には、客観的な数値に置き換えて表計算ソフトに入力し、評定を導き出していました。
文科省中央教育審議会から平成31年1月21日に示された「児童生徒の学習評価の在り方について(報告)」では、関心・意欲・態度の観点について、「挙手の回数や毎時間ノートを取っているかなど、性格や行動面の傾向が一時的に表出された場面を捉える評価であるような誤解が払拭しきれていない」と指摘されています。すべての子どもたちの学力を保障することが一番の目的であることから、そのための評価としての「妥当性」と「信頼性」の担保、総括的評価を行う補助簿について、先生方に改めて確認をしていただきたいと思っています。
第4回 「結」まつもと学びの日
7月25日に、松本市教育会と松本市教育委員会が共催で、松本市全教職員研修会である『「結」まつもと学びの日』が開催されました。これは、「子どもが主人公」の学校づくりに向け、子どもの成長にかかわる松本のすべての先生方が共に学び、思いを結びあう研修会です。
音楽同好会の合唱で清々しく幕を開け、松本市教育会長や信濃教育会長の挨拶、教育会研究委員会の報告、木村泰子先生のご講演がありました。木村先生のご講演は、いつもと同様に心を打つものでした。私も15分の講話を行いました。その内容について、簡単に触れます。
講話の題は、「松本市の先生方へ伝えたいこと」です。(1)として、教師のあり方についてお話ししました。
松本市は、子どもの権利に関する条例を平成25年4月に施行しており、県内では松本市が1番最初に制定しました。条例の内容を紹介しながら、「お願い」として、「子どものいのちを大切にする教師」になってほしいと伝えました。いのちとは、生命に加え、子どもの尊厳です。子どもは、1個の人格として、大人と対等です。「子どもに素直に謝れる教師」「ほめる言葉も叱る言葉も愛語」「常に晴明(自然で明るくゆったりと)な佇まい」についてお願いしました。不機嫌な態度で接したり、子どもを目下に見てこばかにしたり、規則や権威で子どもを塞いだり、指示・命令で常に言うことを聞かせたり、といった態度があるのならば、改めてほしいと伝えました。
(2)として、これからの教育について話しました。教育が変わる理由として、日本は世界一の高齢社会であり、実質賃金指数も各国が伸びている中、日本は減少しており、1人当たりGDPも減り続け、世界競争力総合順位も、33年前の1位から、昨年は38位にまで後退している現実を紹介しました。また、国際学力調査(PISA2022)では、科学的リテラシーと数学的リテラシーが1位、読解力が2位という素晴らしい成績ながら、国や社会に対する18歳意識調査では、「自分の国は将来よくなる」「自分には誇れる個性がある」「自分の行動で国や社会を変えられると思う」等の質問において、調査した6か国中、すべて最下位という実態があります。また、社会変化のスピードが速くなり、今の子どもたちが大人になる未来社会は劇的に変化する予測や、人生100年時代という背景を受け、どんな力を育むことが必要なのか伝えました。このような状況から、学校教育は、20世紀のジグソーパズル型学力(情報処理をして1つの正解にたどり着く)からレゴ型学力(情報編集により納得解を導き出す)に変わること、それは、「教師主導の教育」から「子ども主体の学び」へ、「同質的な個の育成」から「多様で自立した個の尊重」へ、「同調圧力と競争」から「協働と共創」への変化であると説明しました。そんな中、「自由進度学習は目的ではなく手段」であることから、教師の役割の再認識と、一番の目的は「学習を自己調整できる力をつけること」の確認を行いました。
(3)として、松本市の「子どもが主人公 学都松本のシンカ」がめざすものを伝えました。目標は、「みんなの未来の学校(通称:みんミラ)」を実現することで、「みんな」とは、児童生徒、教職員、保護者、地域社会のすべての人を指すこと、「未来の学校」とは、これまでの当たり前やふつうを見返し、子どもの視点に立った新たな学校づくり、授業づくりに挑戦し続ける学校のことであると説明しました。また、「みんミラ」の目的は、児童生徒が「自分らしく あなたらしく ありのままに」いられて学べる環境を創ることで、子どもが子どもらしく、無理をせず、大人に忖度することなく、人と比べられることなく、「他者がその子らしくいる」ことを尊重できる、そんな学校生活を送れる学校を創りたい、と話しました。そして、その具現のための方略をいくつか紹介しました
最後に、学校の姿をイメージした次の短歌を提示しました。
「それぞれが 秀でて天を目指すとも 寄り合うたしかに 森なる世界」
広大な森林をイメージに、それぞれの先生が凛と立ち、同じ方向を向いて寄り合う、そんな学校となるよう、教育委員会として伴走支援に努めていくことを伝えました。
第3回 公立校の挑戦

ある教育社会学者が、学習指導要領における「資質・能力」論について、次のように異を唱えていました。
「生まれた家庭や育った環境の違いが子どもの学力に影響を及ぼすと、社会における格差の拡大につながってしまう。新しい学力観に沿った問題解決力、コミュニケーション力、学びに向かう力など、客観的な数値で表すことが難しい力を学力と定義すると、それはまさしく生まれた家庭環境の違いによる経験の差によって格差が生じる。本人にはどうしようもない要因によって差が生じる力を学力とすべきではない」「ペーパーテスト等の客観的な数値によって測ることができ、個人の努力によって伸ばすことが可能な、知識・技能のみを学力として評価すべきである」
国内の私立大学は、定員の半数以上を推薦入試での合格としています。これはさらに加速しそうです。国公立大学でも加速しています。某私立大学の教授の話では、総合型選抜の面接で、ある私立高校の生徒が学校の海外研修旅行の経験に基づいて、質問の答えをとうとうと語り、合格を勝ち取っていくとのこと。海外経験がなくても、公立校での豊かな学びの体験を語ることのできる生徒の育成は、どうすればできるのかと考えました。
資質・能力で整理された学力を伸ばすためには、どのような家庭学習に取り組めばよいのかと思い、新学習指導要領作成に携わった教授に伺いました。帰ってきた言葉は「家庭学習のみでこの力を伸ばすことは難しい」でした。
さて、前述の社会教育学者の論に対して私なりに考えたことがあります。
もっている知識量を学力と定義していた時代は終わり、OECDでもラーニング・コンパス2030として、「より良い未来の創造に向けた変革を起こすコンピテンシー (1)新たな価値を創造する力 (2)責任ある行動をとる力 (3)対立やジレンマに対処する力」と、これからの時代を創っていく力を資質・能力で定義しています。知識等の情報量はAIに任せ、それらをどのように活用し、課題解決を図っていくかという力が求められます。この「探究する力」を学力と定義し、その力を伸ばしていくことが、グローバルな時代におけるこれからの社会を創っていく人の育成につながるのではないでしょうか。
あるオンライン会議の最中、世界の方々とつながって仕事をしている方が、余談として興味深い話をして下さいました。「あるプロジェクトを一緒に行う際、海外の方は、日本人をどのように見ていると思いますか?」という話です。その方は、「日本人は協調性が無いと思われているのですよ」とおっしゃいました。「あれ?調和を大事にしてチームで物事を進めることは、日本人の得意技ではないのか?」と疑問に思いながら話を聞いていると、「協調性」の捉えが違っていました。海外の方の「チームで協調する」というのは、「自分なりの考えをしっかりと述べて、自分と違う他者の考えに耳を傾けて受け入れ、みんなが納得する最適解を導くこと」であり、日本人の思うところの「事を荒立てず、時には自分の考えを抑えても同調して丸く収める」とは全く違うことを知りました。この「協調性」の育成こそがグローバル教育であると、以前、文科省の方の講演でお聞きしました。その時、これがグローバル教育ならば、小学校1年生から実践できると思いました。
では、世界で通用する「協調性」を育むためには、どうすればよいのでしょうか。前述の「家庭学習だけでは、資質・能力は伸ばせない」という話も合わせると、「協働的な学び」や「探究の学び」の充実がその答えになると思います。
この社会教育学者は、公立校の授業を受けているだけでは子どもの資質・能力は伸びず、特別な塾等や有名私立校での体験から学ぶことが必要であり、経済的な差による学習環境の違いから学力格差が生まれる、と論じているように感じます。であるならば、公立校における「日常の授業の充実」を如何に果たすか。これは、公立校の挑戦です。すべての子どもが資質・能力を伸ばす授業の実現に向け、公立校の学校改革、授業改革を進める。そのために、先生方一人ひとりは何をすればよいのか、また、先生方を支える教育委員会として何ができるのかを、考えています。
第2回 教員としての根っこを張る

松本市の初任者に、教育長としての話をしました。これから長野県の教育の創り手となっていく方々に、これからの教員人生を送っていく上で大切にしてほしいことを伝えたいと考えていました。
一番伝えたかったことは、「子どもを大切にする」ということです。もっと言うと、子どもの「いのち」を大切にすることです。「いのち」とひらがなで示す理由は、「心身」と書くように、生命としての命だけでなく、心の「いのち」、もっと言うと、一人の人間としての尊厳を大切にする、ということです。子どもの尊厳を大切にしたら、わいせつ等の非違行為など起こさないだけでなく、学びを含むその子の生活のすべてに心を配ることができるでしょう。自分の親や兄弟、子ども等、家族に対する愛情と同等に、児童生徒を愛する教師になってほしいと伝えました。
二つ目は、「いい子を育てること」についてです。いい子と言われる子は、本当によい子なのでしょうか。教員の価値観から見た「いい子」は、本当にその子の素の姿なのでしょうか。そこには、教師の期待に応えようと無理をしたり、怒られないよう褒められるよう、忖度して行動している姿があるのではないでしょうか。松本市の教育長として、私は、「自分らしく あなたらしく ありのままに」いられて学べる子どもの姿をめざしています。「あなたらしく」というのは、その子らしく過ごしている他者の個性も尊重する、という願いです。子どもがこのような姿でいられる学校づくりについて、教員として探究し続けていただきたい、と伝えました。
三つ目は、「思考力、判断力、表現力」についてです。一番大切な表現力は何か、という問いとともに、教員は、子どもが自分なりにまとめた考えや理解したことの発表など、「分かったこと、できたこと」を発表する表現力の育成に注力しがちです。しかしながら、本当に大切な表現力は、「わからない、できない、教えて」と言える表現力です。これから先の人生、この力があれば、困ったときに他者に支えられ、生き抜くことができるのではないでしょうか。真に協働的な学びの充実をめざすのであれば、この表現力の大切さについて、子どもたちが理解できるよう、支援していただきたい、と話しました。
四つ目は、教員の一番の仕事である、授業についてです。長野県は、授業の型が明確にあるわけではなく、初任者に授業の進め方の定型を教えることはありません。個々の教員の裁量性がとても高い県です。授業づくりも自分の思うようにできますが、それ故の責任も伴います。教員は、自分の学校時代に体験した授業をそのまま再現する傾向があると言われています。社会が大きく変化する中、自分が体験した授業の再生産では、変化の激しい予測困難な時代を生き抜く人をはぐくむことにつながりません。そこで、授業づくりの「守破離」について話しました。まずは、先輩や同僚の授業を真似る「守」。その上で、自分なりのアレンジを加え、真似ている型を破る「破」。そして、型から離れ、自分なりの授業を突き詰めていく「離」。これが「型破り」な素晴らしい授業実践につながるのであり、他者の授業を真似ることもせず、適当な授業を日々行っていくのは「形無し」の授業で、子どもたちに失礼です。授業づくりには、完成はありません。生涯に渡って、よりよい授業を追い求め続けることが、教師の矜持です。この矜持を胸に、理想の授業を追い求め続ける教師であってほしい、とお願いしました。
最後に、「教育とは、未来を創造する営みであり、未来とは希望」という、県教育委員会の言葉を伝えて、初任者の前途を祈りながら、話を終えました。
第1回 伝統か革新か
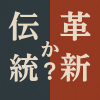
令和7年4月1日付けで、松本市教育長として着任した曽根原好彦と申します。これから、教育長通信に、様々なメッセージを綴ってまいりたいと思います。第1回は、学校改革、授業改善に挑戦しようとする学校への願いについてです。
○○ラーメンで有名な観光地へ行きました。「どうせ食べるなら名店で」と思うのは常で、昔はタクシーの運転手に聞いたりしたそうですが、ネット社会の今は、検索すれば様々な情報が得られます。私も様々なサイトで検索したところ、どうも伝統店と革新店があることが分かりました。伝統店は戦後このラーメンが作られ出した時からの味を守っているお店、革新店はその味を今に進化させ、東京ラーメンショーで過去5回売り上げNo.1を誇った店です。どちらを食べるか迷います。しかし、あるサイトに、「伝統店こそが昔ながらの本物の味。戦後、労働者が、ラーメンをご飯のおかずとして好んで食した味」と書かれており、「やはり伝統を食さなければここまで来た意味がない」と考え、伝統店へ向かいました。
店内に入ると、スーツケースや大きなカバンを持った方など、観光客も多いことが分かりました。いよいよラーメンの登場です。最初に一口、スープを飲みます。衝撃が走ります。味が濃い。一緒に頼んだご飯の上に麺をのせ、まさしくご飯のおかずとして食べられますが、普通に食べるのは躊躇してしまいます。その後、スープはほとんどすすらず、麺と具、ご飯を食して、店を後にしました。
翌日、革新店に向かいました。中に入ると、家族連れや仕事着の方等、地元と思われる方が多数来店されていました。ラーメン登場、見た目は昨日と変わりません。おそるおそるスープを飲むと、美味しい。ご飯のおかずとしてのラーメンではなく、ラーメンそのものを味わえます。東京ラーメンショー売り上げ1位を五回獲得は伊達ではありません。
2つの店を食べ比べ、この味の違いは、その時々の社会の有り様を表しているのだなと思いました。戦後、肉体労働で働き詰めた方々が、ご飯のおかずとして塩気を求めて食べた濃い味。その頃、お店にはすごい行列ができたそうです。その伝統の味は、今の私の口には合いませんでした。今の時代のニーズに合わせ、きっと試行錯誤しながら極めた革新店の味の方が、私には美味しく感じました。
さて、教育も、その時代や社会に合わせて、当然変わるべきものと考えます。平成の一桁代、学校は荒れました。私もクラス替えをしない荒れたクラスを途中から受け持ったことがありますが、「席に着いていられない」「他人を馬鹿にする悪口が横行し、順番に標的が変わるいじめがある」「カラフルで乱れた服装」「整列、挨拶、清掃はしない」など、思いやりも規律もない状況でした。その時は、「団結・協力」を重視し、集団に適応するための学級指導を精一杯行い、所属感や仲間意識を高めることに注力しました。みんなで揃え、心を合わせ、全員で行う行事の達成感を味わう。クラスとして落ち着き、卒業を迎えました。今思えば、荒れる集団をそのようにして統制していたように思います。今はどうでしょうか。荒れるように暴れる子どもはどのくらいいるでしょうか。今は、集団に馴染めない、学校に来られない、自己肯定感をもてない子どもを少なからず生み出している、学校のあり方に目を向ける必要があると考えます。
信州の教育は、子ども第一主義です。これは昔も、今も、これからも変わりません。これからも変わらないからこそ、今の時代、今の社会状況に合わせて、「変わる」べきことがあるように感じます。伝統の味は素晴らしかったと回顧されるものですが、今の私の口には合いませんでした。今の時代に合う教育の味は何なのか、模索し、「子どもが主人公 学都松本のシンカ」に精一杯注力してまいりたいと思います。