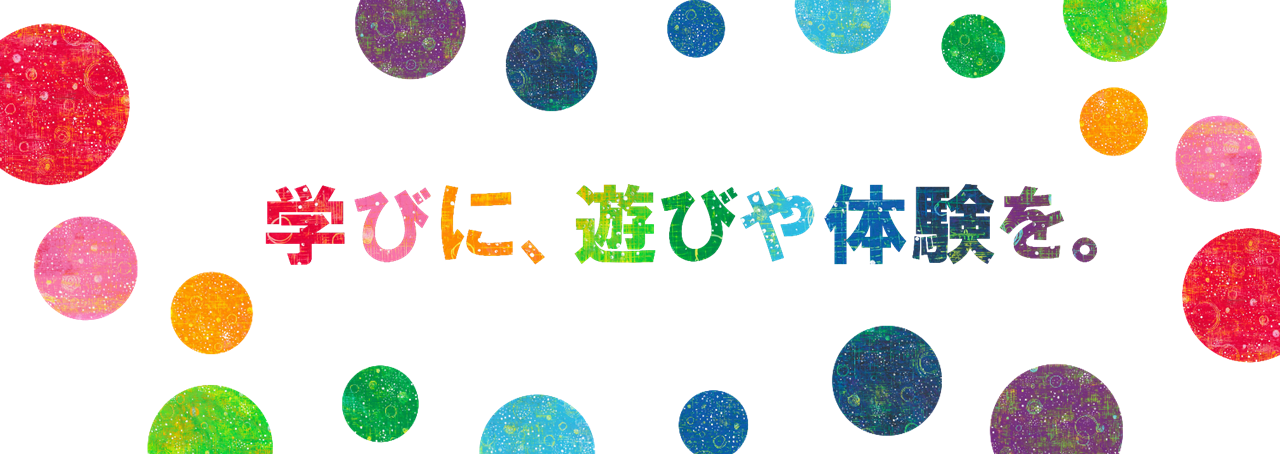本文
教育長所信表明
教育長所信表明(令和7年3月17日 議員協議会)
皆さん、こんにちは。曽根原好彦と申します。本日はお時間をいただきましたので、教育長予定者としての所信の一端について、日本の教育への思いと、松本市の教育への願いを重ねながら、申し述べさせていただきます。
2022年に行われたPISAという国際学力調査において、日本は、OECD加盟国37カ国中、科学的リテラシー1位、数学的リテラシー1位、読解力2位と、素晴らしい結果を収めています。しかしながら、日本財団が2024年に行った、国や社会に対する世界6カ国の18歳意識調査では、「自分の国は将来良くなる」「自分には人に誇れる個性がある」「自分の行動で国や社会を変えられると思う」などと問うた項目において、日本は全て最下位でした。児童生徒の「自分ならできる」という自己肯定感や、「社会の一員である自分の自覚」などの育成を鑑みると、日本の教育の現状は、このままでよいとは言えないのではないか、と思っています。不登校も増加の一途を辿り、公教育の真価が問われています。
このような、日本の教育への思いを根底に、松本市の教育への願いについて大きく2点述べさせていただきます。
1点目は、今の松本市教育委員会における先進的な取組を、さらに発展・充実させることです。「子どもが主人公 学都松本のシンカ」として、認知や発達に特性のある子ども等を支援するインクルーシブセンターの設置、不登校生に対する学校内外の教育支援センターやオンライン支援、また、市立(いちりつ)の特別支援学校の開校計画など、重層的な取組が充実しています。このような、一人の子どもも取り残されない、多様性を包み込む教育施策の展開を継承し、さらに発展していくよう、努めてまいります。
2点目は、市内の全ての学校の特色化・魅力化を進めてブランディングを図り、全国に誇る松本市の教育を創造することです。松本市では、リーディングスクールの事業により、特色ある取組を実践している学校が多くあります。この事業を、すべての学校の特色化・魅力化へと発展させ、学都松本のブランディングへ繋げたいと考えています。具体的には、全ての小中学校が、「みんなの未来の学校」となるよう、支援をしてまいります。通称は「ミンミラ」です。この「みんなの未来の学校」の「みんな」とは、児童生徒、教職員、保護者、地域社会の方など、すべての人を指します。すべての人にとっての未来の学校を創る、これが目標です。「未来の学校」とは、学校教育におけるこれまでの「当たり前」や「ふつう」を見返し、20年後、30年後の未来を見据え、子どもの視点に立った新たな学校づくり、授業づくりに挑戦し続ける学校のことです。この「みんなの未来の学校」を創る目的は、すべての児童生徒が、「自分らしく あなたらしく ありのままに」いられて、学べる場を創造していくことです。子どもが子どもらしく、無理をせず、大人に忖度することなく、人と比べられることなく、生き生きと日々を過ごし、自分と相手の自由に生きる権利を尊重し合って相互に承認できる、そんな学校を創りたいと願っています。
通称「ミンミラ」を創るために取り組む具体的な内容について、3つお話しします。
1つ目は、先生方の、子どもと向き合う時間や授業づくりに専念できる時間を生み出すことです。教員の働き方改革が叫ばれ、業務支援員の配置や会議の精選等に、全県の学校が取り組んでいます。しかしながら、教員の時間外勤務時間の減少は近年頭打ちで、これ以上減らすことが難しくなっています。1週間の授業時数は29時間が標準ですが、私が 教員になった頃は土曜日も3時間授業があり、小学校高学年や中学校でも、6時間授業は多くありませんでした。子どもたちにとっても、教員にとっても、学校の日課に余裕がありました。今は土曜日が休業となったものの、週の授業時数は変わらないことから、週5日の内、4日は6時間授業となっています。教員にも児童生徒にも、日々の学校生活に時間的な余裕がありません。そこで、松本市の小中学校は、できるだけ5時間授業の日を増やし、学校生活に余裕をもって過ごしてもらえるようにします。子どもたちも毎日の授業に余裕ができ、先生も、個別の相談や翌日の授業準備、他の先生との対話等による情報交換など、余裕のできた日課の中で、充実した時間を過ごすことができると考えています。
このような時間を創出しない限り、学校改革や授業改革に取り組むことはできません。
2つ目は、各校が、その学校、その地域ならではの学校改革、授業改革に取り組んでいくことができるよう、様々な支援をしていくことです。例えば、ずっと昔から変わらない学校教育目標は、今の状況と合っているのか、当たり前と考えている校則は、生徒を不要に縛り付けていないか、知識・技能を身に付けることに重きを置いた一斉一律に教える授業で、取り残されている子どもや先に進めず我慢している子どもがいるのではないかなど、学校教育の「当たり前」や「ふつう」を見返すことが欠かせません。「子どもが主人公 学都松本のシンカ」として、まさに子どもを真ん中において進化・発展する教育を、すべての学校がリーディングスクールとして展開していくよう、教育委員会としてアイディアを示したり、相談に乗ったりして、伴走支援をしていきます。
3つ目は、このように教育が大きく変わっていくことを、広く認知していただけるよう、情報発信に努めることです。「みんなの未来の学校」におけるみんなである、教員はもちろん、児童生徒、保護者、何より地域社会の方々に、教育の変化について理解してもらえるよう、私をはじめとする教育委員会で周知に努めてまいります。そして、保護者や地域の方々に、子どもたちの学びを支える応援団となっていただき、地域ぐるみで松本の子どもたちの成長を支え、各校が「地域と共にある学校」となることを目指します。さらに、学都松本の取組を、全県・全国へと発信していくことにも力を注ぎます。
最後になりますが、私は、教員として現場で22年、県教育委員会の教育行政として14年、その内1年は、広島県教育委員会にも勤めました。信州教育の伝統から、先進的な教育の実際、他県の取組等について、様々に学んできました。この経験を生かし、すべての子どもたちが、それぞれの家庭の状況等によらず、皆が学び成長できる、そんな学都松本にしたいと願っています。多様性を包み込む教育のさらなる充実と、「みんなの未来の学校」の実現に向けて、精一杯努めてまいります。よろしくお願いいたします。