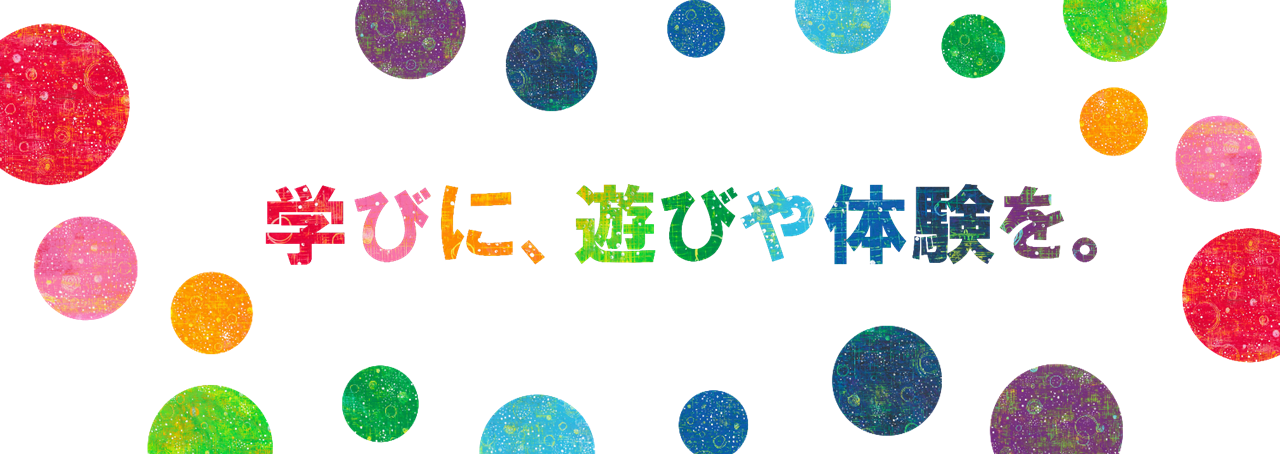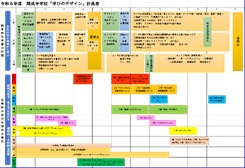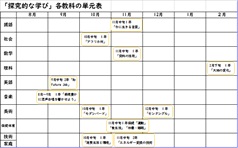本文
実施校の取組状況紹介
令和8年2月2日 更新
リーディングスクール 並柳小学校
『私のチャレンジ』をポジティブにふりかえろう!
1月14日、並柳小学校では「『私のチャレンジ』をポジティブにふりかえろう!」をテーマに、今年度の歩みを止まらない力に変える重点研究会が開催されました。
今回の研修の大きな特徴は、ふり返りの手法として「ポジティブKPT」を導入した点です。これまでの「Problem(課題)」を、自分を責める材料ではなく、アップデートの可能性を秘めた「次への伸びしろ」と捉え直しました。また、「Try」を「次へのワクワク」と定義することで、参加した先生方からは前向きなふり返りが次々と生まれました。
研修では、以前の研修で作成した「チャレンジしたいことの短冊」を活用しました。これが「チェックポイント」となり、過去の自分と比較することで自身の「思考の足跡」を可視化し、具体的な成果を実感する手助けとなりました。また、新たに一人一台端末に入った「ロイロノート」をフル活用し、短冊の内容をデジタルでアウトプット。提出箱機能による相互参照を使い、多様な視点に触れる相乗効果も生まれました。これは、教師が児童の立場でICT活用を体験する貴重な機会ともなりました。

研修の終盤、中川先生から「みんなが『仲間だよ』と言ってくれる安心感があるから、得意ではないアウトプットができた」という心温まるコメントがありました。この心理的安全性が、並柳小学校の先生方の深い省察と、次なる挑戦への源泉となっています。

60分という限られた時間の中で 、一人ひとりが「やってよかった」と実感し、次なるステップへ踏み出す大きなエネルギーを得た研究会となりました。
学びの改革リーディング校 波田中学校
「やってみる」を広げる授業づくり対話カフェ!
今年度は、波田中学校の先生たちは、教科やグループの枠を超えて、自身の強みや関心に基づいた「個人研究」に励んできました。その成果を共有する場として、1月末、6名の代表の先生たちによるアウトプットの場「対話カフェ」が開催されました。
テーマは、「教材開発・ICT活用」「コミュニティ・スクール」「デジタルとアナログを連携させたICT実践」「理科・探究活動」「個に応じた支援」「国語・表現の深まり」と多岐にわたります。先生たちは、興味関心があるテーブルを自由に選び、仲間の実践を聴き、熱く語り合いました。

「理科・探究活動」のテーブルの一コマ。S先生は、生徒が「やってみたい」実験方法を自ら選択し、主体的に考える授業実践に挑戦しました。気体の発生・収集において、あえて失敗の可能性がある自由な選択を生徒に認めることで、自ら考える姿が生まれた様子を語りました。これを受け、国語科のA先生は、「古典の授業は読解中心になりがちなので、『竹取物語』の学習では、生徒自身が『問い』を立て、調べる活動を取り入れた」と自身のチャレンジを共有。失敗を恐れず、生徒の「やってみたい」を尊重する姿勢こそが、波田中の目指す「生徒とともに学ぶ授業」の原動力であることを再確認する時間となりました。
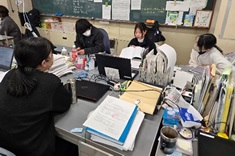
「やってみる」から生まれたそれぞれの手ごたえを分かち合い、先生たちが来年度の授業づくりに向けた「次なる一歩」を踏み出す機会になりました。
令和8年1月26日 更新
リーディングスクール 開明小学校
先生たちの「挑戦」と「軌跡」を分かち合う たい焼きアウトプットDay
1月19日、開明小学校では、「たい焼きアウトプットDay」を開催しました。
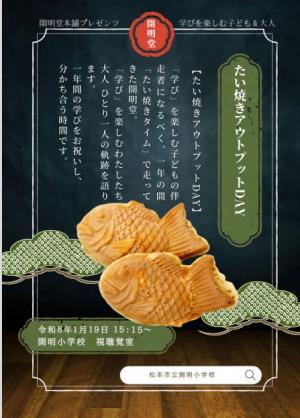
「『学び』を楽しむ⼦どもの伴⾛者になるべく、⼀年の間『たい焼きタイム』で⾛ってきた開明堂。『学び』を楽しむわたしたち⼤⼈ひとり⼀⼈の軌跡を語ります。⼀年間の学びをお祝いし、分かち合う時間です。」そんな素敵なメッセージがつづられた案内チラシの通り、オープニングで「みんなでがんばりました!おめでとう!」という掛け声とともにミニくす玉が割られ、会場は冒頭から温かな拍手と笑顔に包まれました。
この会では、開明小の全ての先生が1年間取組んできた「個人課題探究」の歩みをアウトプットし、フィードバックを得ます。2回目となる今年は、保護者や地域の方、他校の先生たちも開明小の先生たちとともに参加し、「学び」を分かち合いました。
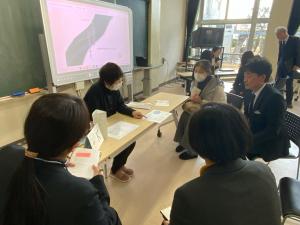
会場には7つのブースが設けられ、それぞれのブースでアウトプット・セッションが行われます。PCや資料を使い学びの足跡を熱心に語る先生、それをしっかり受け止め温かい言葉や感想を返す参加者の皆さん。会場全体が温かい活気で満たされていました。

セッション終了後、開明小の取組を1年間伴走されてきた信州大学の谷内先生は「大変だったことや悩みを語り合えるのが開明小の研究の特長。個の切実な課題があるからこそ、『子どもの事実』や『先生固有の経験』をベースにした豊かな対話が『たい焼きタイム』で生まれてきました。悩み・試行錯誤を共有し合えるのが素晴らしいですね。」と開明小の取組の意義を評されました。
「子どもも大人も『学び』を楽しむ」ことを目指し歩んできた開明小の先生たち。まさにそれが会場全体で体現された大きな節目の1日となりました。
リーディングスクール 旭町中学校
共に“創る” 旭町中学校~小中合同研修~
12月22日、旭町中学校を会場に、旭町小学校との合同研修会を開催しました。8月の研修に続き、軽井沢風越学園の岩瀬直樹先生を講師に迎え、小中合わせて55名の教職員が「対話」を通じて、教師としての“私のあり方”を考えました。
本研修の大きな特徴は、中学校の篠田先生と小学校の金宇先生が共同で後半の研修プログラムを設計した点にあります。岩瀬先生による心理的安全性を高めるワークに続き、両校が掲げる「生徒と共に創る学校」「今と未来をデザインする」という目標に向け、現場のリアルな葛藤を分かち合いました。
特に、子どもに任せることへの「不安」と「よさ」を可視化するワークや、ベテラン教員の挑戦と葛藤を聞くインタビューは、多くの先生方が共感するところでした。最後には、一人ひとりが明日から取り組む「マイチャレンジ」を宣言し、校種を越えた学校創りに向け、また一歩踏み出しました。

~先生方のふり返りから~
◎『人は言っていることではなく、やっていることについていく』という岩瀬先生の言葉が胸に刺さりました。生徒や仲間に求める前に、まずは自分自身が『ベストサイドワーカー』として変わっていこうと決意しました。
◎マイナス面ばかり見ていると不安になりますが、視点を変えて『やってみたらどんな良いことが生まれるか』を考えると、可能性が見えてきました。枠にはめた見方をせず、子どもの未来を信じる強さを持ちたいです。
◎教員が失敗を恐れすぎて子どもの可能性を奪ってはいけないと実感しました。覚悟を持って子どもを信じ、ただ任せるのではなく、共に悩み、共に考える存在でありたいと思います。
◎中学校と小学校の先生が自然に語り合い、支え合おうとする雰囲気がとても嬉しかったです。今回掲げたマイチャレンジを、具体的な一歩として職場のみんなで進めていきたいです。
令和8年1月19日更新
リーディングスクール 中山小学校
中山小学校の校内研修に学ぶ
12月2日、「実践校に学ぶ!探究の学び」研修講座が中山小の全面協力のもと、開催されました。
研修の初めは子どもの学びの参観です。数日後に控えた「中山っ子フェス」(探究の全校アウトプット会)にむけて、5,6年生がお互いのアウトプットを見合い、フィードバックし合ったり振り返ったりする場面です。参加者は子どもたちとともに参加、子どもの豊かなアウトプットの様子を参観するとともに、言葉や付箋を使ってのフィードバックを体験しました。

授業後の研修(2時間!)は、探究コーディネーターの山崎先生、研究主任の佐藤先生が中心となって構想・実施し、中山小学校の先生方と、参加者が一体となって研修を創り上げます。
まずは十分なアイスブレークを行い、その後、授業で参観した子どもの学びの姿のとらえ、解釈を小グループで台紙に付箋を貼りながら交流しました。
研修の後半は、「フィードバック」に視点をあて、自身が行ったフィードバックの振り返り、フィードバックを受けた子どもの様子のとらえ等を通して、「探究の学び」を支えるフィードバックの意義・役割についての気づきを交流しあいました。

今回の研修では、各グループのファシリテーションを中山小の先生たちが担当、普段から実施している対話型の研修スタイルに他校の先生たちを巻き込み、非常に豊かな対話の場を作られました。校内研修の継続により学校づくりを推進している中山小の「底力」に多くを学ぶ一日となりました。
リーディングスクール・アソシエイト校 筑摩小学校
地域・保護者を巻き込み「松本手まりづくりにチャレンジ」
筑摩小学校の4年生は、国語「未来につなぐ工芸品 工芸品のみりょくを伝えよう」と、社会科「地域の伝統工芸」を関連させ、「長野県の伝統工芸」についてリーフレットにまとめるなど教科横断的に学んできました。その中で松本手まりを自分たちで作ってみたいという願いを持つ児童がいました。松本市立博物館で、展示品の伝統工芸「松本手まり」の説明を聞いた児童は、「自分でもつくりたい」とさらに思いを深めました。
願いが実現する日がやってきました。12月17日、保護者・地域の方を交えた12名の講師とともに「松本手まりづくりにチャレンジ」の時間が始まりました。子どもたちは、もみを白糸でまいた芯に、好きな色の木綿糸を針で留めていきます。何周巻くかや配色を自分で決めながら、手まりを紡いでいきます。教室には、「Help、誰か助けて」「名人、次はどうやるの?」などの声が交わり、自然と教え合う雰囲気が広がりました。

「だんだん職人みたいになってきた」「自分でデザインが決められて楽しい」――― 笑い声と共に作業は進み、2時間で完成した手まりを手にした子どもたちは、「できた達成感がある」「ふだんはできない体験に感謝」「この伝統がつながるように守り続けることが大切」などと思いを語ってくれました。
この「松本手まりづくり」を実現するにあたり課題となったのは、約 70人の家庭科未経験の子どもに「手まりづくり」をどうやったら支援できるかということでした。そんな中、味方になってくれたのが、国型コミュニティースクールを実践する筑摩小の地域連携コーディネーターの清水さんでした。
筑摩小では、CS運営協議会の熟議の中で、「学校で放課後教室や、地域や保護者向けの講座を開きたい。」と考えていました。そこで清水さんは、まずは学校で地域の方や保護者向けに手まりづくり講座を開き、そこで受講した方たちが、今度はボランティアとして子どもたちの「手まりづくり」に支援に入ってもらおうと考えました。こうして10数名もの「手まり先生」をお願いすることができ迎えた当日。 「手まり先生」たちは、本当に楽しそうに子どもたちの手まりづくりを支えてくださいました。授業後、和やかに子どもとの関わりを語り合う「手まり先生」たちの姿が印象的でした。

「松本手まりをつくりたい」という子どもの声からスタートしたプロジェクト。CS運営協議会の願い、清水さんのアイデア、そして、何より地域と保護者の温かな協力のもと、子どもたちの「やりたい」を実現することができました。子どもを中心とした「学びの輪」の広がりを感じる時間となりました。
学びの改革リーディング校 丸ノ内中学校
丸ノ内中Jr.学会開催 ~対話から学びが広がる1日~
今年度も「丸ノ内中Jr.学会」が開催され、信州大学の安達先生、都市計画家の倉澤さん、小学生、保護者、地域の方など多様な参加者が、生徒の発表に耳を傾けました。生徒は原稿に頼らず自分の言葉で発表し、その後の対話の中でさまざまな立場の参加者から質問や意見を受け、学びを深めていきました。
会のオープニングでは、論理・批判・創造の三つの視点で考える「忠恕のメガネ」を全校で共有しました。参加者は、どのように問いを投げかけ、どう考えるかの基盤を整えたことで、会場では鋭い質問や素朴な疑問が自然に生まれ、対話が多方向へ広がっていきました。
参加した小学生は、中学生による明快な説明や深い調査内容に驚いていました。実際に制作物に触れる体験をした児童は、「自分もやってみたい」と目を輝かせていました。中学生の主体的に学ぶ姿が、小学生にとって学びの具体的なモデルとなっていました。
会の終わりには、発表を終えた3年生が「楽しかったね」と語り合う姿が見られました。その一言には、自分で問いを立て、行動し、対話から新しい学びを得ることに対する喜びがあふれており、丸ノ内中Jr.学会が次の学年へ学ぶ楽しさをつないでいく場となっていることを感じさせました。


令和7年12月22日更新
リーディングスクール 梓川小学校
6年生の笑顔が輝く学年マルシェ
梓川小の6年生は、総合的な学習の時間を利用して、「学年マルシェを成功させたい」という共通の願いをもち、クラスごとに準備を進めてきました。
12月6日に開催した「学年マルシェ」では、1組はリサイクル品で作ったおもちゃやキーホルダーの販売、2組は何度も改良を重ねたアップルパイの提供、3組は野菜販売とクイズ大会・的あてゲーム、これまでの活動をまとめた動画放映を行いました。

当日の子どもたちの姿は本当に素敵でした。膝を床につけて小さい子に心をこめて接客する子、前回の改善点を生かして時間の合間に進んで片づけに取組む子、クイズ大会直前に大きな声で呼びかける子。みんなが自分の役割に一生懸命取り組みながらも、まわりへの配慮を忘れず、仲間を支え、できることを考えながら活動していました。小さな子が急に泣き出したり、景品が足りなかったりと予想外の出来事もありましたが、その都度お客さんのことを第一に考え、子どもたち自身で工夫し、前向きに対応する姿が見られました。
200人以上の保護者や地域の皆様にご来場いただき、大盛況のうちに終了。すべての商品が完売し、子どもたちは大きな達成感を味わうことができました。

子どもたちからは、「前回の野菜マルシェよりも準備がスムーズにできた」「野菜が売れ残らないように工夫するなど、考える力がついた」など、自分たちの成長を実感する声が聞かれました。
3組担任の山守先生は、「これまでにないほど、生き生きと仕事に取り組む子どもたちの姿、互いに支え合う気持ちの強さが素晴らしかった」と話しています。
子どもたちの「やってみたい」という気持ちが、「やり遂げた」という自信に変わった一日。今回の収益で得た3学期感謝の会では、どんな素敵なアイデアが生まれるのか、今から楽しみです。
リーディングスクール・アソシエイト校 清水中学校
探究を軸とした『小中高連携』の充実
12月中旬、清水中学校区(清水中・清水小・源池小)の校長・教頭・教務主任・研究主任(総合主任)が一堂に会して、小中連携の充実に向けた協議が行われました。
この会は、「小学校6年間で育んだ資質・能力を、中学3年間で更に伸ばし、高校での学びにつなげていく」という子どもの成長のストーリーを大切にしていきたいという願いから立ち上がりました。清水中学校では、これまでに、『中高連携』として、松本県ヶ丘高校の生徒と互いに探究発表をしたり、高校生からプレゼン指導を中学生が受けたりしてきました。今後は更に、小中連携もより一層充実させて『小中高連携』を図っていきます。
会の冒頭に、目指すビジョンとして「地球規模の視野で考えながら、地域社会との協働を通じて、よりよい社会の形成に向けて行動しようとする姿 ~地域で学ぶ・地域と学ぶ・地域の一員になる~」の共有が行われました。ビジョン共有の後、役職ごとのグループに分かれ、小中が連携してどんなことができそうかアイディアを出し合いました。
子ども達が、地域のひと・もの・ことと触れ合いながら、とことん探究する中で、自分自身について理解したり、自分自身の在り方を考えたりしていくことができる。こんな探究的な学びが、一人ひとりの子どもに実現するように、今後は小中それぞれで育てたい力を明確にし、カリキュラム等を見直しながら、具体的な接続の在り方を検討していきます。
今後も、継続的にこの会を開催し、小中連携をより充実させていきます。


リーディングスクール・アソシエイト校 開成中学校
中学生の視点から伝統食にチャレンジ ~ 2年生の探究的な学び ~
開成中学校の2年生は、10月から「自然」「観光PR」「防災」「伝統文化」「SDGs」の5つのグループに分かれ、その中でさらに自分たちの興味・関心のあるテーマごとにチームになり探究的な活動にチャレンジしています。
「伝統文化」グループでは、「おやきづくり」「白樺細工づくり」「あめづくり」の3つのチームに分かれ活動をしています。「おやきづくり」チームでは、「おやきは、長野県の代表的な郷土料理と言われているが、若い世代にはあまり馴染みがないので、今後消費が伸び悩むのではないか」という課題意識をもち、「現代の若者が好む味やスタイルを取り入れた新しいおやき開発」に励んでいます。
12月下旬、この日は、前回の「生地づくり」の失敗を生かし、「生地を薄くし具材を入れる」ことを心がけ、おやきづくりに挑戦。具材は、開成中2年生のアンケート調査をもとに、「チョコレート」「マシュマロ」「キャラメル」の3種類で、「キャラメルチョコ」「マシュマロチョコ」など自分の好みに応じてアレンジしました。フライパンを使い蒸し焼きにすると、おいしそうなおやきの完成です。今回は、講座の先生や他のチームの2年生に味見をお願いしてみました。


「生地がパリパリして美味しかった。もっと生地が薄くてもいい」「キャラメルチョコが意外に美味しくて、新感覚のスイーツという感じ」「餃子の形にするなど、もっと形を工夫してもいい」などの声が寄せられ、次回に向け、新たなヒントをもらいました。
1月末には、1年生や来年度入学する新1年生に向けて、自分たちが学んできた成果をアウトプットする予定です。10月下旬に行われた3年生の開成タイム発表会も参考にして、どんなアウトプットを行うか、グループごと摸索しています。どんな会が実現するか、2年生のチャレンジが今から楽しみです。
リーディングスクール・アソシエイト校 鎌田中学校
「しらかばの日」
11月21日は、これまで続けてきたKMDタイムの発表会「しらかばの日」でした。生徒一人一人がここまで取り組んできた活動の発表を行いました。
1年生は個人で取り組んできたこと、2年生はグループで取り組んできたこと、3年生はグループやクラスごとの活動の発表でした。
個人で発表した1年生は上級生が見守る中での発表ということもあり、緊張感が漂う中での発表でした。中学校での探究の学びが初めての1年生は、問いづくりのきっかけにインスパイアハイを活用しました。インスパイアハイは、中高生向け探究学習プログラムで、生徒が自ら設定し深めていく「問い(リサーチクエスチョン)」を大事に考えています。世界中の大人たち(ガイド)との対話を通じて、多様な価値観に触れ、自分の「好き」や社会への疑問から生まれる「答えのない問い」を立て、それを探究し発表する活動全体につなげていきます。1年生は効果的な発表の在り方を学んだ上で、自分が問いを立てるまでの経緯、追究の方法、自分の学びえた成果を一人一人発表しました。温かいまなざしで見守る上級生はもちろん、同じ1年生の身を乗り出すように発表に聞き入る姿や発表後の移動時間に感想を語り合う姿が印象的でした。
 発表を見守る担任の先生の温かいまなざしも印象的です
発表を見守る担任の先生の温かいまなざしも印象的です
2・3年生は、グループや学級での発表となりました。仲間と一つの目標に向かって、楽しく、そして真剣に、学んできた様子がうかがえました。3年生のあるクラスは、自ら劇を作り上げ、地域の方々に披露した様子を発表しました。鎌田小6年生に向けた発表では、シンデレラをベースに三匹のこぶたなどの要素を入れた脚本を考え、笑顔のあふれる発表を作り上げていました。この日の発表では、発表に向けての工夫や努力が伝えられました。力の入った発表がどのように創られたのか、興味深く聞くことができました。また、ザリガニについての発表も印象的でした。特定外来生物であるアメリカザリガニとはどういう生き物か、アメリカザリガニが今ここにいる理由は何か、共存する方法は何かと、研究がどんどんと深まっている様子が見えました。実際にザリガニを調理しておいしく食べる方法も研究していました。張りのある声や見やすいスライド構成などからも充実した研究だったことが見えてきました。

KMDタイムはこの日をもって一区切りとなったわけですが、生徒一人一人の探究はこれからも続きます。来年度につながる活動ができたことが、新しい鎌田中学校の歴史に刻まれたと考えます。
令和7年12月15日更新
リーディングスクール 並柳小学校
先生たちも「学び合う」 全員でつくる、これからの授業づくり
12月3日に行われた校内研修「学び合いの日(4)」。今回はこれまでの指導案審議のかたちを変え、参加した先生全員が自分事として授業づくりにかかわれる「探究的な学び合い」の場となりました。
今回の研修の大きな特徴は、授業者の「困り感」や「悩み」をみんなで共有することから始まった点です。まずは恒例のチェックインからスタート。これにより生まれた和やかな空気の中、授業者が抱えるリアルな課題や願いが提示されました。

その思いを受け、先生方は授業の「すてきな点」と、悩みに対する「解決のアイディア」を付箋に書き出していきました。批判や評価ではなく、どうすれば子どもたちの学びが深まるかを全員が「自分事」として考え、模造紙の上で対話を重ねながらアイディアを出し合いました。指導案を模造紙の真ん中に貼り、一人一人の考えを付箋で可視化することで議論が流れず、視覚的に整理されるのもこの手法のよさです。

また、今回は指導案作成にデザインツール「Canva」を初めて導入し、共同編集ならではのメリットも実感しました。
「私もそう思った!」「自分ならこうするかも」。全体会のような堅苦しさはなく、建設的な意見が飛び交う活気ある時間となりました。一人の悩みをみんなの知恵で支え、最終的にどのアイディアを取り入れるかは授業者が選ぶ。並柳小学校では、そんな互いを高め合える協働的な授業づくりが進んでいます。
リーディングスクール 菅野中学校
高まる協働性 先生たちの「探究」
菅野中学校では、今年、先生たちの「自己課題」を元に8つのラーニング・グループ(LG)(「問い」「対話」「個別最適な学び」「フィードバック」「家庭学習」「教科横断的な学び」「授業UD」「自己肯定感」)を編成し、各テーマに基づいて先生たちが協働し探究してきました。そして全LGが集まり、振り返りを共有したり、共通のテーマで意見交流したりする機会を「SLS(菅野ラーニング・セッション)」と名付け、折々に交流を重ねてきました。
12月、この1年間の取組を振り返る「SLSをまとめる会」を実施しました。各LGが取組状況をアウトプット、その後ランダムに編成したグループで「(取組の)よさ」を中心に協議とフィードバックを行いました。


「先生方の熱量がすごかったです。」と話すのは、この会の進行を担当した臼井先生。「テーマに基づいた授業実践を紹介しながら、これまでの手応えを先生たちが熱心に発表されました。実践に基づいて語られる言葉の重みが心に残りました。発表後のセッションでも各グループで初めから勢いのある対話が交わされました。」と先生たちの前向きさの実感を語られました。西村教頭先生も「先生方が教科等の担当を越えて、教育観を交流し、深めあっていました。先生方の対話の質の高まりを感じています。」と話し合いの様子を振り返られました。
菅野中では、このような研修の場を年間計画に位置付け、研修日は4時間授業として午後の時間にじっくりゆったり研修・研究に取組めるようにしています。
このような時間や場・仕組みの工夫と、対話の積み重ねにより、先生たちの「協働性」が格段に高まっていることを実感する「SLSをまとめる会」となりました。
令和7年12月8日更新
リーディングスクール 岡田小学校
授業を協働で創る
「のびのび・わくわく学び、どんどん挑戦」を合言葉として学校づくりを進める岡田小学校では、先生たち一人一人が、この目標につながる自己課題を立て、授業づくりに取組んできました。11月以降は、学年を越えたラーニング・グループを編成し、今年度の「課題探究のまとめ」としての授業づくりを協働で行っています。
12月に行われた研究会の一コマを参観させていただきました。研究主任の伊藤先生の「みんなで授業づくりをして、ひとりではできないことを『できた』という思いを持てればと思います!」というエールの後、それぞれのチームで授業づくりの検討が始まりました。

「子どもが学び方を決める授業」「ロイロノートの活用」「家庭学習の見直し実践」等、先生たちが自身の実践を踏まえたアイディアを交流し合いながら子どもが主体的に学ぶ授業を構想したり、具体的な子どもの様子を共有しながら「願う学びの姿」を思い描いたりと、とても前向きで活発な協議がどのチームでも行われます。

この研究会は毎週確実に実施されるとのこと。「先生たちの対話の量や内容がすごく高まっているのを感じます」と染川校長先生もうれしそうに話されます。先生たちが、このような授業づくりを検討しあう学びの場を積み上げていることの大きな意義をあらためて実感する機会となりました。
リーディングスクール・アソシエイト校 寿小学校
「やったー!マイプラン学習だ」
3年生が楽しみにしていた「マイプラン学習(教科は国語と理科)」が始まりました。
これまでに「マイプラン学習」を何度か経験している子どもたちですが、ガイダンスでは改めて「自分で配分等考えて計画し自分のペースで学び理解を深めること」や「安全に関する注意事項」等を確認し、単元全体の見通しを持って学習計画を立てる姿がありました。
単元が始まると、一人で黙々と取り組む子、友だちと相談しながら進める子などそれぞれ自分の学習計画を元に学びに向かっていました。


学びの改革リーディング校 波田小学校
「やってみたい」が広がる輪 ~ 子どもたちが主役の学びの時間 ~
子どもたちや先生の「やってみたいこと、挑戦したいこと」の実現へ向け、学校づくりに取組む波田小学校。5年3組では、「5年生みんなに楽しんでもらおう」という想いを胸に、学級活動の時間などを利用して、自分たちがやりたいことを形にする会社を設立し活動しています。
12月4日の総合的な学習の時間のことです。「AEDの大切さをクラスのみんなに伝えたい」と、「AED会社」を設立したYさんとRさんが、初めての講師役に挑戦しました。この日のために、先生方の協力を得て、AEDの体験キットを3セット用意しました。
担任に代わり二人が前に立ち、「皆さんは、AEDを知っていますか?」と問いかけ授業がスタート。AEDを使う意味を丁寧に説明した後、動画をみんなで視聴し、体験キッドを使いながら救命の方法を実演しました。

その後、ペアごとに心臓マッサージとAEDの使用を体験しました。講師役の二人は、一組ずつ体験を見守り、「うまいですね」「心臓マッサージまでに16秒かかっているので、10秒以内を目指しましょう。命に関わる大切な時間です」と、事前に学んだ専門知識をわかりやすく、そして真摯に伝えていました。二人の姿は、本物の講師さながら、自信に溢れていました。

「AEDクイズ大会」の後、時間に余裕があることに気づいた二人は、「ベストペア」を発表し、示範演技を企画。子どもたちから「救急隊への電話係をつくった方がいい」「救急隊員役もいた方がいい」と提案がなされ、4人による迫真の演技へと発展しました。4人の演技を真剣に見つめる子どもたちの姿が印象的でした。
担任の小林先生は、「いつもの授業より子どもたちが集中して聴いていて、本当に驚きました」と語りました。来年は「全校のみんなのために会社を設立できたら」と、新たな夢も生まれたとのこと。子どもたちの可能性の芽が、また一つ大きく育ちました。
令和7年12月1日更新
リーディングスクール・アソシエイト校 開智小学校
国宝を地域の“たから”に! 開智小6年生が初企画「旧開智祭り」
11月21日(金曜日)・22日(土曜日)の2日間、国宝旧開智学校校舎にて、開智小学校6年生が企画・運営を手がけた「旧開智祭り」が開催されました。
このイベントは、6年生が行ってきた総合的な学習の時間「開智タイム」の集大成です。「旧開智学校を『守る』だけでなく、いかに『活用』していくか」というテーマのもと、子どもたちは学芸員の方から教えてもらった学びに加え、保護者や地域の方々との対話集会(語る会)を重ね、多くのアイデアを実現させました。
21日夜の「第1部」では、校舎壁面へのプロジェクションマッピングやライトアップを実施しました。手作りの竹灯籠やペットボトル灯籠が並ぶ幻想的な雰囲気の中、桜や松本城など四季折々の映像が投影されると、集まった大勢の地域住民から歓声が上がり、ダンスパフォーマンスも会場を盛り上げました。

22日の「第2部」では、児童によるチョコバナナなどの飲食販売、射的などのゲーム、オリジナルグッズ販売や学習展示が行われました。約400名が来場し、会場は「いらっしゃいませ!」という児童の元気な声と笑顔で溢れました。来場者からは「子どもたちが楽しみながら学ぶ素晴らしい催し」との声も聞かれました。児童の振り返りにも「旧開智祭りを通して、やっぱり旧開智は地域の人に大事にされていると思いました。旧開智祭りに地域の人がたくさん来てくれたし、みんな喜んでたのでそう思いました。」とあるように、国宝旧開智学校が地域の笑顔で包まれ、まさに地域の“たから”として輝いた2日間となりました。


学びの改革リーディング校 波田中学校
「あれ、どうして?」が学びの芽に! ~波田中3年のチャレンジ~
波田中の3年生の先生たちは、「総合的な学習の時間を生徒が探究する場にしたい」と願い、今年度「生徒たちの素朴な疑問や問い」からスタートする探究的な学びづくりに挑戦しています。
7月に「自分が探究してみたいテーマ」について希望調査を実施し、調査をもとに28のテーマを設定し、生徒たちの希望を尊重しながらグループ編成を行いました。
11月下旬の総合的な学習の時間の一コマです。受験シーズンを迎えようとしている3年生ですが、どのグループもとても楽しそうに生き生きと自分たちの「探究のテーマ」解決に向かい活動しています。

「『つまらない』時と『楽しい』時は、体内時計に違いはあるのか?」というテーマで探究しているグループは、「つまらないと感じる時間は長く感じるはずだ」という予想のもと、「好きな教科と嫌いな教科」について調べた結果をCanvaにまとめていました。今回はさらに「清掃の時間は長く感じるはずだ」という仮説を立て、実際に階段清掃を実施しました。ところが検証してみると、4人中3人が「嫌いなはずなのに短く感じた」という予想外の結果に。「あれ、どうしてだろう?」という新たな疑問が出てきて、探究心が生まれました。「集中して取組むと、好き嫌いに関係なく短く感じるのかな?」という新しい仮説へと発展させ、次の検証方法について仲間と相談を重ねています。

波田中の3年生は、「自分たちが興味をもったことについて探究しながら、こうやったらどうかな?」とワクワクしながら試行錯誤を続けています。そして、そんな生徒たちの学びを支える3年生の先生たちも、一緒に考え、試行錯誤しながら、温かく見守り、励ましています。波田中の後輩たちにとっても、素敵なロールモデルになることを願いながら。
令和7年11月25日更新
リーディングスクール 開明小学校
県外視察の学びをアウトプット 進化する教師エージェンシー
LSとして「みんなが幸せな学校」「学びを楽しむ子ども」を目指して学校づくりを進める開明小学校では11月、若手からミドルリーダーまで、5人の先生たちが石川県加賀市の学校に県外視察に赴きました。学校に戻った先生たちは、役割を分担し、それぞれ心に残った視察での学びを先生たちに報告するアウトプット会を持ちました。
5人の先生たちは「加賀市のめざすところ」「子どもの学びの姿(高・低学年)」「子ども自身が学びを調整する文化を開明へDL」「先生たちの学校づくり・授業づくりへの思い」と、それぞれのテーマに基づいたブースを設け、5分×3回のアウトプットを行います。参加者の先生たちは思い思いにブースを選んでセッションに参加します。視察での学びを熱く語る先生、身を乗り出して聴き、質問する先生たち。設定された時間では全く足りない程、熱気に満ちた学びの場となりました。

5人の先生たちはアウトプットに当たり、それぞれ工夫を凝らした資料を作成、それを示しながらわかりやすい説明をされました。伺うとGoogleのアプリNotebookLMを活用したとのこと。校内で主体的に行われた「AIツール活用研修」を経て先生たちに活用が浸透してきたといいます。開明小学校の先生たちの「学び」への前向きさがここからもうかがわれます。

開明小学校では1月に「大人のたいやきアウトプットDAY」を計画、地域の方や保護者も招いて、先生たちが1年間のチャレンジの足跡をアウトプットします。この機会を「ワクワク」している先生たち。
学び合いの中で「教師エージェンシー」を一層シンカさせている開明小の先生たちです。
※教師エージェンシー:教師が自身の役割を主体的に考え、目標を設定して変革を起こそうとする力
リーディングスクール・アソシエイト校 筑摩野中学校
深まる学びと広がる思考~筑摩野中の教室から~
筑摩野中学校では、11月に授業を見合う旬間を行っています。同じ教科の先生を中心に授業を見て、「問い」や「生徒の“広がる・深まる・高まる”学びの姿」について気づいたこと、考えたこと、感想などをGoogleフォームに入力し、授業者にフィードバックしています。問いの立て方や授業展開、生徒の学びの姿から得た気づきは、授業者への助言だけでなく、自分自身の授業づくりを振り返る機会にもなっています。「自分の授業にも取り入れたい」「参考にしたい」という感想が多く寄せられるなど、先生たち自身が「対話」や「学び合い」を通して授業改善に取り組んでいます。
11月17日の美術の授業では、「季節感・おいしそうな感じが表れるねりきりをつくろう!」を学習課題として、粘土で自分がイメージしたねりきりを制作していました。印象的だったのは、イメージ通りにつくりたいという願いから、一人ひとりの中に自然と「問い」が生まれていたことです。友達に相談する生徒、インターネットの画像を拡大して研究する生徒、作り方動画を繰り返し観る生徒、先生の作った見本品や他クラスの作品を見に行く生徒など、教室のあちこちで“問い → 探究の行動”につながる姿が見られました。

国語の授業では、「蓬莱の玉の枝~『竹取物語』から~」で、「五人の貴公子に難題を出した理由」について考えました。帝の求婚を断った事情を押さえたうえで改めて考える中で、「(月の都の者だから)結婚しても長くはいられない」「愛情が深まるほど、別れの悲しみが大きくなるから」「相手を悲しませたくない」といった、より深い読みへと広がっていきました。「なるほどね」「確かに」と友の意見に耳を傾けながら、自分の考えをさらに深めていく生徒の姿が印象的でした。
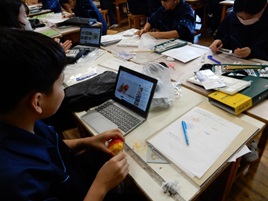
英語の授業では、Today’s Goal「“今〜しているところ”を使ってみよう」を達成するために、班対抗の並び替えゲームに取り組んでいました。「この場合どうなるの?」「これ逆じゃない?だって…」など、学んだことを確かめ合いながら班の仲間と「対話」し、最後まで熱気にあふれる活動になっていました。

このように、筑摩野中では「対話(聴き合い)」の良さが先生にも生徒にも浸透してきています。今後は、授業の中の「問い」が、生徒の学びの広がり・深まり・高まりにつながる過程を、さらに丁寧に研究していきたいと考えています。
令和7年11月17日更新
リーディングスクール 中山小学校
12月「中山っ子フェス」に向けて 先生たちの学び
中山小学校では12月5日に全校の子どもたちが「探究の学び」の成果をアウトプットする「中山っ子フェス」の実施を予定しています。
2学期が始まって間もない9月、「フェス」に向けての校内研修を実施しました。ねらいは「ビジョンの共有」です。昨年「フェス」を経験した先生たちが「フェス」振り返りを語り合う様子を、今年転任してきた先生たちが周りから参観、その後立場を入れ替えて「未経験者」の思いの語り合いを「経験者」が参観し、最後に両者が交流する「フィッシュボウル(金魚鉢)」セッションなどを通して、「フェス」についてのイメージと願いを共有しました。研修の終盤には今年の新任の先生が「フェス」への思いを力強く語るなど、大きな成果が感じられる研修会となりました。

さらに、「フェス」まで1か月を控えた11月初め、「フェス」でどのような子どもの姿を目指し、そのためにどのような支援をしていくかを思い描き、共有することを願い、校内研修を企画・実施しました。丁寧なアイスブレイクの後、風越学園のアウトプットの映像を視聴し、そこにみられる学びのよさ、それを引き出している支援等、気づきを小グループで交流しました。その後、「フェス」で願う子どもの姿「思いを込めて歩みを語る」「たくさんの人と関わりフィードバックをもらう」などを交流し、そのために行う活動や支援などについて具体的に思い描きました。

これらの研修会はいずれも研究部の先生たちが主体的に企画・実施しています。このような親密で、たゆみない先生たちの学びが、中山小の子どもたちの豊かな探究を支えます。
リーディングスクール・アソシエイト校 筑摩小学校
自分の「やりたい」を実現 ~ フリースタイルプロジェクト発表会 ~
昨年度から「自分の興味・関心のある活動を追究することを通して、自主性・社会性を養い、個性を伸ばす」ことを目指し、4年生から6年生を対象にフリースタイルプロジェクトを実施している筑摩小学校。
10月22日、今までの自分たちの追究の成果を、3年生以上の児童・保護者・地域の方にアウトプットしました。発表は、全体を20分間ずつ3部制に分け、その中で各々が8分の発表を2回続けて行う形式です。これにより対話が生まれ、発表者に新たな発見があったり、その場でもらうフィードバックを次の発表で活かしたりするなど、新たな学びの姿がありました。発表者以外の子どもたち・保護者・地域の方も、見るだけではないことで関心を高めていたようです。


「クオリティの高いプログラミングをつくりたい」という願いで制作したプログラムを、Canvaで視覚的にアウトプットした6年生のAさんは、後輩からの「この発表会が終わっても改良していくんですか?」という質問に、「これからも家でよりよいものを目指し改良したい」と答えました。後輩たちからは「プログラミングでこんなものがつくれるなんてすごいと思った」「ポケモンを使ったおもしろいゲームで、ものがたりがみられるのがびっくりした。もっとみたいと思った」などのフィードバックが寄せられ、Aさんは、「みんながすごいと言ってくれて嬉しかった」と笑顔で語りました。
やりぬいた充実感と「次はこんなことを」という更なるチャレンジへの想い。筑摩小の子どもたちの瞳が輝いています。
学びの改革リーディング校 丸ノ内中学校
誰もが安心して訪れたくなる 思いやりが息づく松本市を目指して ~ サニタリーボックス設置を松本市に提言 ~
10月20日(月曜日)、丸ノ内中学校では「一日忠恕(総合的な学習の時間)」が行われ、各グループが自分たちのテーマに沿って学びを進めました。その中で、3年生の「サニタリーボックス班」は、松本市役所を訪れ、自分たちの考えを市の担当職員に提言しました。
生徒たちが伝えたかったのは、「男子トイレにもサニタリーボックスを設置してほしい」という願いです。
「社会には、さまざまな理由で衛生用品を必要とする人がいます。それを利用する人数は少なくても、その配慮がすべての人の安心につながる。」生徒たちはそんな思いをもち、1年近くかけて集めたアンケートから得られた観光客の声や実態、医療従事者から得られた声、約8割が設置に賛成という市民の意見を根拠に課題と改善策を提案しました。
生徒たちの真摯な提案に、市の職員からは「必要としていた人はこれまでもいたが、もしかしたら声をあげられなかった人もいるのかもしれない」「多くの観光客が訪れる松本市にとって、誰もが安心して利用できるトイレ環境を考える大切なきっかけになった」との言葉が寄せられました。

生徒からは「私たちの思いを、市を支える職員の方に直接伝える機会をいただけて嬉しかった」「松本にさらに多くの観光客が訪れ、まち全体がいっそう活気にあふれることを願っています」といった感想も聞かれました。
丸ノ内中学校では、地域や社会の課題や疑問を自分たちの視点でとらえ、探究的に学びを進めています。今回の提言は、まちづくりを「ジブンゴト」として捉え、社会に働きかける探究的な学びの成果の一つです。
令和7年11月10日更新
リーディングスクール 梓川小学校
みんなで創る野菜マルシェ ~対話を通じた学級づくり~
自分が育てたい野菜を学級園で栽培し、野菜マルシェで販売しようと計画している6年3組。10月中旬、「自分もみんなも楽しめるお野菜マルシェを通して、話し合いにおける課題を見出し、よりよい学級を作ろう」という題材で、公開授業を行いました。
最初に、クラスで決めた「話し合い名人への道」(1 誰かが意見を言ったら反応する、2 声の大きさを適切に、3 意見を否定したり、嫌な気持ちになることを言わない、4 話を最後まで聞く……)をみんなで確認してから、「接客係」「CM係」「料理係」など10グループに分かれ、クラスの友から出たアドバイスをもとに話し合い活動が始まりました。

接客係では、アドバイスが書かれた付箋を4人で読みながら、「接客についてはここでいいかな?」「声のことはここら辺かな?」「電卓のことは、接客じゃないよね」などと話しながら、模造紙に項目ごとに分けて貼り直しました。その後、項目ごとに「これは接客における笑顔について書かれている」「これは声の大きさについて書いている」など4人で協議しながら、「笑顔で接客する」「大きい声で接客する」などとタイトルをつけました。4人が互いの考えを最後まで聴き、相手の意見を尊重しながら建設的に話し合う姿が印象的でした。

この取組を通じて、子どもたちは単に野菜を育てて販売するだけでなく、互いを尊重し、対話を大切にする学習者へと成長しています。本番のマルシェでは、子どもたちのこうした学びと成長が、お客様との素敵な出会いへとつながることを楽しみにしています。
リーディングスクール 並柳小学校
繰り返すから見えてくる校内研修の深化
並柳小学校では、毎月1回のペースで校内研修を継続的に実施しています。この継続的な取り組みが、並柳小学校の先生方のコミュニティの質を高める土壌となっています。
校内研修では、毎回研究主任の中川先生と副主任の鈴木先生がタッグを組み、研修の設計を共同で行います。今回企画されたのは、「授業のチューニング」です。これは、並柳小学校としては2回目の試みとなりました。
今回は「できるだけ多くの先生方に研修の主体として関わってほしい」という思いから、司会者を固定せず立候補を募る形式をとりました。すると、すぐに3名の先生方が立候補してくださり、スムーズに3つの授業のチューニングを開始することができました。教職員一人ひとりの積極的な参画意識が、並柳小学校の大きな力だと改めて感じています。
授業の概要説明では、発表者の先生方が、単に資料を読み上げるだけでなく、パワーポイント、体験活動、教材の音楽視聴など、工夫を凝らしていました。この工夫により、アドバイザーとして参加した先生からは「授業の状況が具体的にイメージできたため、アドバイスがしやすかった」との声が聞かれました。事前の丁寧な準備が、より深い議論を生む、原動力となりました。


しかし、今回の実践から、新たな課題も見えてきました。それは、「1時間の授業」という短いスパンでのチューニングの難しさです。授業の問いが限定的になる分、議論に「余白」が生まれにくく、結果としてアイデアが限定されがちになる側面がありました。この経験から、「チューニング」は、1時間といった枠に留まらず、単元全体や、さらに長いスパンで継続的に行うことで、より本質的で効果の高い改善が見込めるのではないか、という新たな発見と方向性が見えてきました。
このように、何回も繰り返していく中で、実践の「良さ」と「課題」が明確になり、研修の質が深まっていく。このサイクルこそが、並柳小学校の継続的な校内研修文化を生み出す源なのでしょう
リーディングスクール・アソシエイト校 開成中学校
探究する喜びが学びを深める ~3年生が見せた自律と貢献の姿~
今年度から新たに掲げた学校目標「自律・尊重・貢献」の実現に向けて、生徒も先生も意識を高めながら歩みを進めている開成中学校。
10月下旬、3年生による開成タイム(総合的な学習の時間)の発表会が行われました。1・2年生全員と地域、保護者の方々が8つの会場に分かれ、興味のあるテーマを選んで参加。3年生の発表を聴き、質問やフィードバックを通して交流を深めました。
「松本の自然環境」をテーマとした会場では、昆虫、トカゲ、ツバメ、川の水質など、身近な自然に関する疑問をもとに調査した成果が発表されました。「松本市の昆虫」について取組んだグループは、開成中周辺の昆虫の生息状況を紹介した後、自分たちで採集し作成した標本を見せながら、昆虫の特徴や標本づくりの工夫を説明しました。


1,2年生から「標本づくりは趣味ですか?」という質問が出ると、3年のAさんは笑顔でこう答えました。「はい、標本づくりは趣味なのでとても楽しいです。蛾の標本は羽を触らないようにしないと、きれいな鱗粉が取れてしまいます。開成中のまわりでは、結構レアな虫が採れるんですよ。」
標本を手に後輩の質問に優しく答えるAさんの表情には、好きなことを探究し続けてきた満足感と自信があふれていました。その姿はまさに、「自律(自分で考え行動する)」「尊重(自分も人も大切する)」を体現しているといえるでしょう。
今回の3年生の発表は、これからの1・2年生の開成タイムの取組みに大きく「貢献」したに違いありません。来年度、どんな新たな探究が生まれるのか、今から楽しみです。
リーディングスクール・アソシエイト校 清水中学校
教師も実践!「大人探究」発表会 ~わくわくの共有~
本ホームページで9月に紹介した「大人探究」とは、清水中学校の探究的な学びで大事にしている「地域で学ぶ・地域と学ぶ・地域の一員になる」を、教師自身が実践し体感しようとするものです。今回、約2ケ月にわたる探究成果を、職員研修で発表し合いました。
調理コンテストに挑戦した探究や校内の画びょうに注目した探究、趣味の音楽に関する探究や松本市の史跡や商業施設に関する探究など、それぞれの問いを大切にした探究成果の発表会でした。校長先生・教頭先生も一探究者として、発表会に参加する姿も印象的でした。
また、今回の発表資料は、探究の過程に基づく構成でCanvaを用いて作成することを必須としました。生徒の情報活用能力を育むためには教師自らがまず新しいものに取り組んでみる、という清水中学校の教師集団の心構えがここにも表れていました。
助言者の宮木慧美先生(一般社団法人KOkO代表理事)からは、「発表を聞きながら、一緒にわくわくした気持ちになりました。探究のわくわくをもつ教師が子どもの探究を支えることの価値はとても大きいです」というお言葉をいただきました。
探究の喜びや苦労を体感した教師だからこその、生徒への指導・支援がより一層充実していくものと期待されます。

令和7年11月4日更新
リーディングスクール 旭町小学校
「やりたい」から始まる学びのシンカ! 旭町小学校 プロジェクト型音楽会
旭町小学校の音楽会は、子どもたちの「やりたい」という純粋な願いを原動力とした、「プロジェクト型」の学習です。先生方は、子どもたちが心から楽しめ、成長できる場を整えることを大切にしてきました。そのため、演奏だけでなく、練習計画、ストーリーづくり、プログラム作成といったすべてのプロセスを子どもたちが主体となって考え、進めてきました。

このプロジェクトを通じて見られた子どもたちの成長は、素晴らしいものでした。一人ひとりが自分の役割を持つことで、「僕が頑張らないと、みんなの音楽会は成功しない」という強い当事者意識が育まれました。また、音楽が苦手な子も小道具係として得意を活かし、ステージを支える重要な役割を果たしました。中には、YouTubeを見てリコーダーを独学で練習し始めるなど、主体的な学びを見せる子もいました。このように、誰もが自分のやり方で参加し、お互いの多様性を認め合う関係性が育まれたことは、この音楽会の最大の成果です。
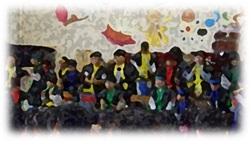
共に創り上げた先生方も、この実践に確かな手応えを感じています。子どもたちの満足度が高いのはもちろん、先生たちも、子どもたちの発想に刺激を受け、アイデアを出し合う楽しさを確認したようです。「子どもと一緒に音楽会を創り上げられる」という喜びと、教育活動の新たな可能性を感じたようです。
旭町小学校が掲げる「自分の願いや目的を、自分たちの力で解決し、くらしや学びをより良くする(創る)学習活動」。今回の音楽会は、その理念を体現し、子どもたちの学びを一層シンカさせた素敵な実践となりました。
リーディングスクール 岡田小学校
ひろがる「のび・わく・どん」スピリット
「のびのび・わくわく学び、どんどんチャレンジ(のび・わく・どん)」を合言葉にみんなで学校づくりを進める岡田小学校。
先月、5年生は、一人一人が鉢で大切に育ててきた「ミニ田んぼ」で収穫したお米を「いただく」活動に取り組みました。思いをかけて、手をかけて育ててきた、大切な大切な「私のお米」。土鍋、フライパンなどの用具、水の量、火加減…子どもたちは時間をかけ、調べたり、人に取材したりしながら、それぞれが納得する「炊き方」を探究してきました。(詳しくはリーディングスクール通信No,52をご参照ください。)
こうして迎えた本番。子どもたちは、それぞれが考えてきた「自分のやり方」で注意深くお米を炊いていきます。そして、いよいよ試食。子どもたちは炊きあがったお米を口にいれ、神経を集中し味わいながら「甘味がある!」「玄米の風味が感じられる!」といった感想を交流し合いました。炊いた際にできる、パリパリの「お米シート」も「おいしい!」と味わう子どもたちでした。担任のT先生は、「子どもたちを信頼し『任せる』と、こんなに集中し、探究的になるということを実感しました」と振り返られました。


岡田小学校では、学校の様々なところで、「のび・わく・どん」が生まれています。
先日行われた音楽会の練習期間でのこと。休み時間になると、子どもたちが「練習してもいいですか?」と次々に音楽室を訪れ、大賑わいでした。でもそんな混雑状況でも、破損や使いっぱなし、子ども間のトラブルなどは一切なく、みんなが気持ちよく使っていたといいます。「子どもたちが本当にやる気になると、特別な指導をしなくても人やものを大切にする力が発揮されるということをあらためて感じています」と音楽専科のO先生は語られました。全校のみんなの思いが響き合う、感動的な音楽会になったことはいうまでもありません。
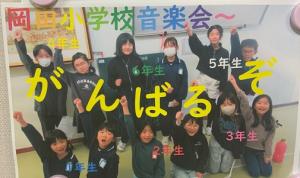
このように岡田小では「のび・わく・どん」のスピリットが、子どもたちにも、先生たちにも、確かに広がっています。
令和7年10月27日更新
リーディングスクール 菅野中学校
「協働」する生徒たち、そして先生たち
「協働」を生徒・先生たちが学びの合言葉として学校づくりを進めている菅野中学校。
10月末、全職員が公開授業を参観し、協働的な学びの授業実践から学び合う機会を持ちました。
授業は2年生の国語、「仁和寺にある法師(徒然草)」を読む場面、T先生は「法師の失敗の原因はどこにあったのだろう?」と問いかけます。生徒たちは「原因」となったと思われる記述をそれぞれ探し、4人グループの中で、自然に交流が始まりました。友の言葉にうなずきながら自分の考えを更新していく子どもたち。この後の全体交流の場面では、他グループの考えを真剣に聞き合う姿がありました。「法師の失敗」をめぐって多様な考えが交流され、「現代語訳・意味理解」にとどまらない、内容を自分に引き寄せた「解釈」が豊かに響き合う古文の授業となりました。

午後、生徒たちは早く下校し、「SLS(Sugano Learning Session)を深める会」が開かれました。全校の先生たちが子どもの「協働」が深まった姿や、「協働」を支えた支援のよさ等を付箋に記し、時に写真を示しながら授業から学んだことを交流し合います。4月以降、SLSを初め、様々な機会に交流を重ねてきた先生たちは、和やかな雰囲気の中で活発に協議されました。

助言者として来訪された畔上一康先生(長野短大学長)は、「協働の学び」の意義やそれを支える要件についてお話をされつつ、「豊かな授業だった。昨年と今年、生徒から受ける感じが変わっている。談話的でインフォーマルに言葉を交わし合う姿がある。職員組織が対話的であることが子どもの学びにも反映している」と菅野中の「現在地」を評されました。
「協働」を生徒とともに旗印に掲げ「学びの改革」を目指す菅野中学校の歩みが、また一つ刻まれました。
学びの改革リーディング校 波田小学校
~ 年長さんが楽しめる交流に! ~
2年2組の子どもたちは、「1年生の時から続けている波田中央保育園との交流を今年も続けたい」と願いをもち、年長さんと交流しています。
10月半ばに第1回の交流会を実施し、「バナナ鬼」「信号機鬼」を一緒にやり、保育園では、そこで教わった「信号機鬼」を、ルールを自分たちで工夫し楽しみながらやっているそうです。
10月末の第2回の交流会では、「年長さんが1回目よりもっと楽しめるように」と願い、自分たちが体育の授業で行った「宝とりゲーム」を一緒にやることにしました。園児が来ると、お互い手を振り合い、楽しそうに声をかけ、チームに分かれ座りました。

最初に2年生が、年長さんに身振りを交えルールを伝えました。ゲームが始まると、2年生と園児が混ざり、鬼のタッチをかわし、楽しそうに宝物を取りにいきます。作戦タイムでは、「今度は鬼になるので、前と後ろに分かれよう。真ん中にも一人いるといいね」など、2年生が中心になり作戦をわかりやすく伝えていました。

最後にチームごと宝物の枚数を数え、がんばりを認め合うと、園児からは、「もう1回やりたい」「もっとやりたい」などの声が上がりました。
交流を終え、2年生からは、「年長さんとの交流楽しかった」「また交流したい」などの声が多く聞かれました。担任の山口先生は、「交流は、2回の予定でしたが、子どもたちが『楽しかった、またやりたい』と言っているので、子どもたちと相談して今後の交流も考えたい」と話されました。「やってみたいこと・挑戦したいことを実現できる学校」を目指し、2年生のチャレンジは続きます。
令和7年10月20日更新
リーディングスクール・アソシエイト校 開智小学校
開智小学校の3年間のあゆみを公開します
10月31日、開智小学校にて、探究的な学びの実践が公開されます。開智小学校で取り組んできたこの3年間は、私たちに多くの気づきを与えてくれるはずです。
令和5年度、探究の第一歩として開智小・田川小・丸ノ内中の3校で一緒になって、「まずはやってみる」という姿勢で探究のサイクルを回すことから始まりました。3校合同研修から得られた体験をもとに、地域を学びの場とし、子どもと共に歩み出しました。
令和6年度には、「子どもに委ねる」を新たなテーマに掲げ、研究を大きく深化させました。教師が伴走者となり、子どもたちの「やりたい」という純粋な思いを原動力とした異学年探究にチャレンジしました。その活動から生まれた多様なテーマは、子どもたちの可能性を広げました。
そして令和7年度、これまでの歩みを経て、研究では「共に学び合う 子どもと教師」というテーマを掲げ、現在に至ります。今年度も教師の対話から、伴走するとはどういうことなのかを考え、実践を積み重ねています。
研究会当日午後は、4・5年生による「中間アウトプット会」が公開されます。光、自然、食、防災、布、交流といったテーマで、子どもたちが目を輝かせながら探究の過程を自らの言葉で語ります。これは完成された発表会ではありません。参加者の質問やフィードバックが、子どもたちの学びをさらに深め「わくわくする授業」の一部となる、対話的な学びの場です。また、午前中は「開智探究の日」として1年生から3年生まで、さらに6年生が授業を公開します。
★午前中の授業 参観申し込みフォームはこちら↓
https://forms.gle/nnBa3TcaLThmVjHs9
★午前中の授業 指導案等資料はこちら↓
https://drive.google.com/drive/folders/1IZV9e0dlHVimnnTE4XqRxAs_sEqXxTGQ?usp=sharing
★午後の授業は信濃教育会「学び創造研究会」です。信濃教育会ホームページを参照してください。

開智小学校の探究的な学びの進化を目撃するチャンスです。関心のある方は、ぜひ開智小学校にお問い合わせください。(Tel0263-32-0006)
学びの改革リーディング校 波田中学校
波田中学校 授業スタイルの転換にチャレンジ ~ つまずきから生まれる学び合い ~
「『やってみる』から生まれる、生徒とともに学ぶ授業づくり」をテーマに研究を進めている波田中学校。
数学科の塩崎先生は、日頃の自分の授業を振り返り、「もっと生徒同士が学び合える授業にしたい」と願いを強くもち、自由度を高める授業スタイルにチャレンジしました。具体的には、個人追究の時間から、生徒が自由に学びたい友の所へいき問題を解決する「協働的な学びの場」を取り入れました。
先生は、前時(1点と傾きから一次関数の式を求める場面)の終末に出題した練習問題で、グラフから切片がうまく読み取れなくて困り、給食の時間なども使って友と相談しながら粘り強く解決していく生徒の姿をみて、その追究力に感心し、協働的に学ぶよさを実感したそうです。

本時は、「2点(1,2)(5、-6)を通る一次関数の式を求める」場面です。個人追究に入ると、Kさんは、2点から二つの式をつくりましたが、その後どのように進めていけばよいか困っていました。しばらく一人で考えた後、近くのGさんの所へ行き、自分の困っていることを伝えました。Gさんは、「二つ式があるから、連立方程式にして求めればaとbがでて式が求められるよ」と助言しました。Kさんは、自席に戻り、連立方程式を解いて一次関数の式を求め、「連立方程式をつくってやればできるんだ」とつぶやきました。

塩崎先生は、「自分がつい説明してしまいがちになるので、これからも友と協働して問題を解決する時間を大切にしたい」と話し、授業に協働的な学びを取り入れた手ごたえを感じていました。生徒とともに学ぶ授業を目指し「やってみる」を合言葉に波田中の先生たちのチャレンジは続きます。
令和7年10月14日更新
リーディングスクール 開明小学校
「つながる良さを実感できる時間」~たい焼DAY 3
先生たちが授業公開をし、学び合う今年度3回目の「たい焼きDAY」が実施されました。今回も信州大学の谷内祐樹先生を助言者に、自ら希望された4人の先生の公開授業と授業の振り返りミーティング(たい焼きタイム)を通して、先生たちが学び合いました。
授業の振り返りグループは、授業者の先生の授業づくりを支えた仲間でもあります。みんなが「自分事」の目線で授業を振り返り、具体的な子どもの姿を紹介し合いながら思いを交流し合います。たい焼きタイムの会場は、楽しげで温かい空気に満ちていました。

開明小の先生たちは「たい焼きタイム」を以下のように振り返っています。
「子どもたちの見えなかった姿が見えるようになった」
「話しながら自分の頭の中が晴れるような時間だった」
「授業の成否だけに目が向いていたが、『このチャレンジにはこういう意味があった』と意味づけてもらえて前向きな気持ちになった」…
このような先生たちの姿から、助言者の谷内先生は「たい焼きタイム」を「対話により新たな発見や視点を見つけ、先生同士で思いや願いを共有し、人と人とがつながる良さを実感できる大切な時間」と価値づけられました。
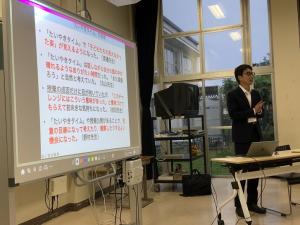
開明小では3学期に「先生たちのアウトプットDAY」を予定しています。「個別最適かつ協働的な学び」を積み上げる先生たちの語りが楽しみです。
リーディングスクール 旭町中学校
「創る・創れる学校」を目指して ~旭町中学校 軽井沢風越学園視察レポート~
「自分たちで創る・創れる学校」を目指す旭町中学校の先生方6名が、軽井沢風越学園のアウトプットデイを視察されました。帰校後、フィッシュボール形式での報告会が開かれました。
「正直、最初は驚きの連続でした」と語るのは、視察に参加された先生の一人。服装や髪型が自由で校則が少なく、生徒が自分で学習を選択できる環境。上級生と下級生が自然に混ざり合って劇の発表をしている光景。そして何より印象的だったのは、生徒主体の探究学習の在り方だったそうです。

「発表は完成形でなくてはいけない」と思っていた先生にとって、「未完成でもいい」という風越学園の発表スタイルは驚きだったようです。途中段階の報告も、失敗談も、すべて歓迎される雰囲気。生徒たちは「もっとアドバイスが欲しい」と積極的にフィードバックを求め、聞く側も真剣に考えて応答する。そんな密度の濃い時間が展開されていたといいます。「こういう形だと、子どもたちも安心して挑戦できますね」と語る先生は、今後の学級経営に何かヒントを得ているようでした。
視察の学びを受けて、学年ごとに話し合いが行われました。「まずは授業中に簡単なアイスブレイクを取り入れて、子どもたちがおしゃべりする機会を増やしてみよう」「アウトプットの機会を増やして、未完成の発表もOkにしてみよう」などと、旭町中学校でもすぐに実践できることから始めよう、という前向きなアイデアがたくさん出されました。

子どもたちが主体的に学び、安心して挑戦できる環境づくりは、教職員の一歩から始まります。見て感じたことを共有した旭町中学校の先生方の「創る・創れる学校」づくりが進んでいきます。
リーディングスクール・アソシエイト校 筑摩野中学校
授業や学校の様子から見える、子どもたちの学びと主体的なつながり
10月6日の中学3年生のある英語の授業では、「日本文化を紹介するパンフレットを作成する」学習活動の第1時でした。
教科担任の先生が夏休みにパキスタンの学校に視察に行った時の様子を写真や動画で紹介し、熱心に聞き入る生徒たち。そのパキスタンの中学3年生に向けて日本の学校文化紹介のパンフレットを作成して、実際に送ります。先生の現地報告の後、実際にそれぞれのタブレットでパキスタンの教育事情(制度や学校の様子)を調べ始めました。

生徒たちは皆、黙々と真剣に自分の画面を見つめています。しばらくすると、調べて発見したこと、特に日本との違いについて、「毎日7コマも授業がある。」「でも、下校は昼の1時だって。」「えー、いいな。羨ましい。」「給食はないらしい。」「特に、女子の就学率が低いみたい。」「学校に行けないってこと?」と自分の気になった点をつぶやきながら、近くにいる級友と会話が紡がれていきました。

クラスには英語の得意な生徒、そうでない生徒が混在しています。しかし、「パキスタンにいる現地の中学3年生に筑摩野中の学校文化を紹介するパンフレットを送る」という学習活動が自然と学びのモチベーションにつながっているのがよく伝わってきました。日本ならではの(筑摩野中の)学校文化を伝えるために、どんなテーマで紹介しようかと、期待感を高めている生徒たちの姿が印象的でした。そして、気になる点をすぐ近くの級友と語り合えるそんな関係性が筑摩野中の授業風景に息づいています。
その日、渡り廊下にはカラフルな短冊がたなびいていました。全校生徒が作成した短歌や俳句を、クラスごと吊るしているそうです。筑摩野中は1学年7クラスの市内最大規模の中学校です。一人ひとりの思いが込められた短歌や俳句が大切に飾られ、クラスや学年を超えて、ふと足を止めて読み合う生徒たちの姿に、筑摩野中全体のまとまりやあたたかさを感じずにはいられませんでした。これもまた、「協働の学び~対話を基盤とした授業づくり~」を大事にしてきた成果です。

令和7年10月6日更新
リーディングスクール 中山小学校
「みんなで創る」機運を育む
中山小学校には水曜日のお昼休みに「ニコニコ・タイム」という時間があります。1~6年生まで、すべての学年の子どもによって編成された縦割りのグループで、「遊び」を楽しみます。ニコニコ・タイムの前の週には「ニコニコ・ミーティング」が開かれグループのみんなでどんな遊びを行うかを話し合います。(これらの「ニコニコ」シリーズに加え、各学級でレクを楽しむ「ワクワク・タイム」を加え、3週を1サイクルとして進めています。)

中山小では子どもたちが主体的・協働的に学ぶことを大切に考えていますが、それを支える自然で豊かな関係性を育みたい、という願いから、令和6年度からこの活動を実践しています。
「ミーティング」で、低学年の児童が自分の考えを進んで発言したり、6年生が全てのメンバーに配慮しながら話し合いや活動を進めたりなど、主体性やリーダーシップが確かに育っていることを、中山小の先生たちは実感しています。

1年と半年取組んできて、「遊びが固定化してきた」という課題も出てきました。これを打開する一助として「まずは先生たちが『遊びのアイディア』を学ぼう」と職員研修を実施しました。
中山小では、この「ニコニコ・タイム」をもとに、子どもたちが自分たちで「校内ルールづくり」等、学校づくりにかかわっていく動きを創りたい、という願いをもち、少しずつ種まきを始めています。
身近なところから『自分ができる』経験を積み上げ、「みんなで創る学校」につなげようと歩みを進める中山小学校です。
リーディングスクール・アソシエイト校 筑摩小学校
子どもたちの「やりたい」の実現に向けて!
9月半ば、プロジェクトの成果・課題を共有し、今後の方向を検討する「職員研修」を実施しました。この日は、4年生から6年生を対象に昨年度から実施している「フリースタイルプロジェクトの発表会をどのように企画するか」の検討を、みんなで行いました。
最初に、軽井沢風越学園のアウトプットデーの様子を視聴しました。その後、立石研究主任から「風越学園のように参加者からフィードバックをもらえると、自分が取組んできたプロジェクトでの学びの意味が深まるのではないか。今年度は同じ会場にブースを3つ程度つくり、子どもたちは、自分が観たいブースに自由にいけるようにしたらどうか」という提案が行われました。

研究主任の提案を受け、4つのチームに分かれ、自分が担当しているグループの子どもたちの様子を思い浮かべながら、活発な意見交流が進みます。「子どもたちが、あの発表はおもしろそうだと自由に行けるのはいいですね」「自由に行けるのはいいけど、ブースに誰も来ない子がいるとかわいそうだから何か対策を考えなくては」「昨年のように発表して終わりだと自己満足で終わってしまうので、やっぱり見ている人の感想をもらいたいよね」…等々、先生たちが、発表する子どもの気持ちになり考え合っている様子が伝わってきました。その後、各チームの代表者がどんな意見や課題が出たか発表し、みんなで共有しました。

筑摩小では、これからも職員研修を定期的に行い、職員の対話を大切にし、子どもたちの「やりたい」の実現に向け協働し歩んでいきます。
学びの改革リーディング校 丸ノ内中学校
みんなにとって幸せな松本をめざして
市内の観光について調べていた2年生のあるグループの生徒たちは、松本城周辺に多くの外国人旅行者が訪れていることに気づきました。帰宅して家庭で話題にする中で、外国人が日本の道路標識に戸惑い、事故につながる危険があると感じ、「観光客も市民も安心して過ごせる松本にしたい」と考えました。
そこで、グループで縄手通りへ行き、外国人旅行者に道路標識に関する簡単なアンケート式のクイズに回答してもらうことで、同じ標識の図柄でも、国によって受け止め方が異なることが確認できました。調査を終えて学校に戻った生徒たちは、外国語で書いた看板やリュックを下ろし、水筒を口にしながら満足そうな笑顔を見せました。その姿には、「自分たちの行動が、みんなの幸せにつながる」という実感があふれていました。


生徒たちは、集めた回答の分析データを進めるうちに新たな課題にも気づき、「もう一度調べ、データを収集してみたい」という思いが自然に生まれてきました。観光客も市民も安心できる松本をめざす生徒たちの姿は、協力しながら学びを深めていく姿そのものでした。
この日、松本市教育研修センターの研修講座「実践校に学ぶ 探究の学び」も、丸ノ内中学校を会場に行われ、講座に参加した先生方が生徒の活動を参観しました。先生方からは「1年から3年までの探究の深まりと生徒の成長に感心しました」「教師が寄り添いながら進める姿勢が、生徒の主体性を支えていると実感した。改めて、本研修に申込んでよかった」といった感想が寄せられました。
令和7年9月29日更新
リーディングスクール 旭町小学校
子どもと共に創る音楽会プロジェクト ~実践校に学ぶ研修~
旭町小学校で実施されている「音楽会プロジェクト」は、「子どもと共に創る学校行事」の実践です。9月26日には、4年生の取り組みが公開されました。
主体性を重視した取り組み
今年度は昨年度の振り返りを踏まえ、子どもたちの主体性をより重視した改善を行いました。教師は発表曲のみを提示し、セリフやストーリー、ステージバックの装飾デザインは全て子どもたちのアイデアに委ねました。また、係活動を少人数化(5〜6人)することで、一人ひとりが明確な役割と責任を持ち、自分の願いを反映できる環境を整えました。
公開授業では、子どもたちがプロジェクトカレンダーを活用して見通しを立て、活動の優先順位を話し合いながら決定していく主体的で生き生きとした姿が印象的でした。

実践校に学ぶ「子どもと共に創る行事」研修会
授業参観後、他校からの参加者、大学生、旭町小学校の教職員が「子どもと共に創る学校」をテーマとした研修会を実施しました。
研修では、公開授業で見られた「子どもの主体的な姿」を具体的に振り返り、「なぜその姿が見られたのか」を深く掘り下げて話し合いました。参加者からは「自分たちで作っている様子がとても楽しそうだった」「質問すると、いきいきと答えてくれる子どもたちがたくさんいて、本当に自分事になっているのが伝わった」などの声が聞こえてきました。
続いて、「子どもと共に創るために大切なことは何か」をテーマに協議し、「子どもが決める」「励ます・認める」「教師も楽しむ」などの重要な要素が挙げられました。研修の締めくくりとして、各参加者が「明日からどう活かすか?わたしの『はじめの一歩』」を宣言し、実践への具体的な意欲を共有しました。

旭町小学校の取り組みは、行事を教師主導で行うのではなく、子どもたちの「願い」や「問い」を出発点として、試行錯誤のプロセス自体を学びとして大切にしています。子どもたちの「やりたい!」という気持ちがたくさんつまったプロジェクト。来月の音楽会本番がとても楽しみです。
リーディングスクール 梓川小学校
語り合う中で広がるアイデア!
9月初旬、2学期最初の校内研修を実施しました。今回は、提案を希望した5人の先生たちのプランを各グループで検討することで、「探究的な学習を単元にどのように位置づけるか」をみんなで学び合います。いつものことですが、それを通して、先生たちのコミュニケーションを深めることも大切にしています。

各グループでは、提案をもとに、具体的な活動状況や授業場面を思い描きながら、考えを付箋に記し、模造紙に貼りながら活発な意見交流が進みます。「夏休みの職員研修で使ったピザ窯で焼く予定なら、火起こしや窯の使い方を練習しないといけないね」「実際に焼くとうまくいかないから、そこからどうしたらいいんだろうと、失敗から学ぶことが大切だ」…等々、参加者が、自分ごととして考え、検討し合っている様子が伝わってきました。
研修後、提案した先生たちは、「先生たちから意見をもらい、こうやっていけばいけそうだなと、自分自身が早く子どもと一緒にやってみたいなと思うようになりました」「一人で考えていると苦しくなるけど、先生たちのアイデアからその視点はなかったと、自分にない考えをもらえ、とても参考になりました」などと話していました。

参加された先生たち一人一人が、「探究的に学ぶ子どもの姿」を思い描き、授業展開について考えを交流する場となった研修会。この「共に考え、語り合う」先生たちの関係性が、梓川小の学校づくりの大切な推進力になっています。
リーディングスクール・アソシエイト校 清水中学校
問いの立て方を学ぶ子ども達 ~あらたな探究のサイクルを回し始めるために~
9月の総合的な学習の時間、2年生はこれまで探究してきた自分の問いを一度見つめ直す場として、インスパイア・ハイを用いた学年合同授業を行いました。インスパイア・ハイは動画内ファシリテーターの投げかけを活用することで一定程度の進行が保障されるものではありますが、授業者の逢澤先生は生徒の様子をよく見て臨機応変に発問をすることで、より深い学びになる授業を実践していました。
「問いを解決すると、新しい視点が広がって、創造力がつく。」と発言したある生徒と逢澤先生のやり取りの一部を紹介します。
生徒:(新しい視点が広がって創造力がつくと)古い先入観に気づく。
先生:先入観に気づくと、どんないいことがあるの?
生徒:時代の常識やあたり前が変わる。そうすると、常識やあたり前の前提が変わる。
このように、生徒のその時の意識をとらえ、ここぞというタイミングで問い返すことで、生徒自身が立ち止まって考え直すことができていました。教師と動画内ファシリテーターの双方の強みを生かし、生徒一人ひとりの中にある問いや願い、こだわりを言語化していくことができる授業でした。それぞれの生徒がどのように問いを修正したり、あらたに問いを立て直したりしていくのか楽しみです。
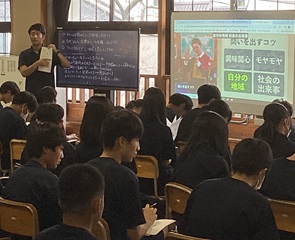
令和7年9月22日更新
リーディングスクール 並柳小学校
「やってみたい」を大切に、公開授業をチューニング!
並柳小学校では、9月末に予定されている公開授業のチューニングを実施しました。今年度は、「やってみたい!を大切に、共にチャレンジしよう!」を研究テーマに掲げ、全職員で授業づくりに挑んでいます。
今回のチューニングでは、2名の先生方が授業の構想を発表しました。A先生は、家庭科「できるよ、家庭の仕事」の単元で「子どもたちの『やってみたい』を引き出す導入の工夫」を、B先生は、算数「分数」の単元で「一人一人が『知りたい』という願いをもち、自分なりに課題を追究することができる」授業を目指し、それぞれが熱い思いを語りました。

発表者の問いに、参加した先生方は真剣に向き合い、活発に意見を交わしました。「子どもたちが思わず『やってみたい!』と声に出してしまうような導入は?」「どうすれば、自分の課題として分数に向き合えるだろう?」など、具体的なアイデアが次々と飛び出しました。
授業のチューニングは、単に授業を改善するだけでなく、お互いの授業を知る貴重な機会です。発表者に関心を寄せ、継続的に関わり続けることで、授業がより良いものへと磨かれるだけでなく、先生方自身の関係性も深まります。今回のチューニングを通して、並柳小学校のチームワークはさらに強く結びつきました。
「やってみたい!」という子どもの願いを大切に、先生方自身も「やってみたい!」というチャレンジ精神をもって授業づくりに励む並柳小学校。子どもたち一人ひとりを大切にする先生方の教育にかける情熱が伝わる、素敵な重点研究会でした。
令和7年9月16日更新
リーディングスクール 菅野中学校
「協働」を先生たちから
菅野中学校では、「学びのテーマ『協働』」を生徒たち・先生たちが共有し、様々な場面で対話しながら学びを深める授業づくり・学校づくりをめざしています。
菅野中の先生たちが日頃から大切にしているのは、「先生たち自身が協働的に学ぶ経験を重ねること」です。夏休み中に行われた職員研修「サマーセミナー」は、このような歩みを続けてきた菅野中の先生たちの協働性(=同僚性)の高まりを実感する機会となりました。
この研修の【お題】=「心惹かれたものを写真にとって、紹介し合いましょう」を胸に先生たちは市立博物館~松本城をフィールドに「探索」し、それは楽しそうに語り合いながら、興味深く、それぞれの「問い」を見つけていきました。
教頭先生は、「先生たちが、みんなで一緒に学び合うことを本当に楽しんでいる様子に突き動かされました。」と、その時の様子をまとめた「絵巻」をつくり、昇降口に掲示。また校長先生は「先生たちの様子に触れ、本当に幸せな気持ちになりました」と、「先生たちの協働的な学び」の様子を2学期始業式で生徒たちに紹介しました。

 先生方の学び「絵巻」
先生方の学び「絵巻」
「子どもは『学んでいる大人』が大好き」といいます。先生たちが感じている「協働」の楽しさは、きっと生徒たちの心に伝わり、広がっていくことでしょう。
リーディングスクール・アソシエイト校 寿小学校
自分たちで考えて「さあ、やってみよう!」
スポーツ参観日に向け、各学年で「子どもに委ねる」ことを大切にしながら体育の表現の学習を進めました。1年生の表現「まねっこダンス」では、誰がどの曲でリーダーをするかを子どもたちが決めて行いました。4年生のリズムダンスでは、ダンス委員や班長が中心となって、振付や並び方などを自分たちで考えました。

これから、10月に行われる音楽学習発表会でも、決まった曲を言われるままに練習するだけでなく、どんな場面で子どもたちに委ねられるかを職員間で考えながら進めていこうと考えています。
学びの改革リーディング校 波田小学校
「職員アウトプットデー」にチャレンジ!
「一学期の各学級の総合的な学習の時間の取組み状況の中間発表会をやろう」と、8月29日「職員アウトプットデー」を実施しました。職員数が多い波田小学校の全担任が発表できるよう、1学年~6学年と特別支援学級を2会場に分け、1回に8~9ブースを設置し、計4回開催しました。発表者は、A41枚程度の資料を作成してブース来訪者に配布し、それをもとに「3分発表・8分フィードバック」を基本として進行しました。タブレットで子どもたちの様子を提示しながら発表する先生もいました。
参加者は、「松林の魅力を探ろう」「仲良し大作戦!中央保育園での交流の振り返りと次の交流に向けて」などの発表内容一覧表をもとに、関心のあるブースに行き、実践のよさやアイデアに触れ、意見交換を行い、最後に感想を付箋にまとめて発表者にフィードバックしました。


「波田小のおいしい給食について保育園の年長さんに伝えたい」と子どもたちと活動を進めている4年担任のK先生。「グループ別に活動しているが、グループ間の進捗に温度差があることや、アンケートの取り方に悩んでいる」と課題を共有しました。参加者からは「3年生以上ではなく、全校アンケートにしてはどうか」「1年生がフォームでアンケートに答えるのが難しかったら、6年生がタブレット操作を支援するよ」などの改善案が出されました。K先生は「確かにそうすれば全校アンケートになりますね」と新たな気づきを得ていました。
限られた時間の中で実践を語り、考えを交流し合った初めての職員アウトプットデー。「3分という短い時間だからこそ、何を伝えようか真剣に考える機会になった」との声も聞かれました。波田小学校では、互いの実践から学び合いながら、「やってみたい・挑戦したい」を実現できる学校を目指し取組みを進めていきます。
令和7年9月8日更新
リーディングスクール・アソシエイト校 島立小学校
みんなで単元内自由進度学習の授業を創る
島立小学校では、夏休みの一日を利用して、単元内自由進度学習の授業づくり研修を行いました。
まず1学期に行われた筑摩小学校の公開授業に参加した先生から、視察報告がありました。具体的な学習の場や環境づくり、先生のチェックの際に子どもを待たせない工夫などの報告からは、3年目となる筑摩小学校の取組みの成果が伝わってくるようでした。また、研究会で語られた内容(自由進度学習に適した単元、適さない単元など)についても詳しい報告があり、これからの自由進度学習の授業づくりについて、実践的なヒントが得られた時間となりました。
また、指導主事が実践した単元内自由進度学習の授業について発表する時間をいただき、実際に子ども達に使用したプレゼンを用いて、先生方には子どもの気持ちで説明を聞いていただきました。
そのような研修報告や実践発表を受けて、個々に授業づくりに取り組みましたが「特別支援学級の児童はどう取り組んでいけばよいか」「2教科同時進行の場合は、ガイダンスはどのタイミングで行えばよいか」など、具体的なシチュエーションをイメージした疑問が多く出されていました。また、多くの学年で「2教科同時」の授業に挑戦しようとする意欲が高く、学年を越えて学習プリントづくりの相談をする姿が見られました。

終了後、校長先生から「ぼやっとしていた自由進度学習の姿が、明確にイメージできた時間になった」という感想が聞かれました。2学期の自由進度学習の実践に向けて、授業づくりの熱が高まる島立小学校の先生方でした。
学びの改革リーディング校 波田中学校
先生たちもワクワク探究!
8月20日、「職員探究の日パート2」と位置付け、7月初旬に全職員で行った「問いづくり」研修の第2弾を実施しました。前回の「グループの中で様々な問いが出てくると、探究してみたいとワクワクした」などの先生たちの声を受け、今回は各グループ(3~5人)で「問い」を練り直し、企画書を作成して実際に探究活動に入ることをゴールとしました。

「波田の山は地図上で名前がついていない山が多いが、実際に登ることができるのか」との思いをもったグループは、「唯一名前のある白山の登山道を実際に調べに行こう」と計画を立て、登山道の散策に出かけました。
「物価高というが本当に物価高といえるのか。物価高は悪いことばかりなのか」と問いを立てたグループでは、「物価が上がると給与も上がるはずだが、日本はアメリカなどに比べ給与が上がっていないのでは」など、それぞれの考えを交流し合いました。そして「SNSだけでなく、実際に現地に行き調べることが大切」という共通認識のもと、「物価高を波田のスイカを通して考えよう」という結論に至りました。そこで「波田の個人商店やスイカ農家を訪問し、スイカの値段の推移について聞こう」という計画を立て、地域巡回に向かいました。
このようにグループごとに「自分たちの問い」について語り、企画書を作成する先生たちの姿は、ワクワク感と「早くやりたい」という意欲に溢れていました。

探究を動かす「問いづくり」を全職員による共通体験として実際に学び、楽しみながら探究活動を行ったこの経験は、これからの総合的な学習の時間での学びを、よりワクワクする学びへと導くことでしょう。次回は、9月初旬に、チューニング形式で中間発表を行う予定です。「まず先生たち自身が学んでみる」波田中のチャレンジは続きます。
令和7年9月1日更新
リーディングスクール 開明小学校
「学び観」「教材観」を深め合う「たい焼きタイム」
9月初日、2学期初の「たい焼きタイム」(重点研究会)を実施しました。
この日は、8つのチームに分かれ、2学期に授業公開を行う先生が提案する授業プランの検討を、みんなで行いました。

各グループでは、教材(題材)の価値、子どもが学ぶこと、声がけのあり方など、具体的な授業場面を思い描きながら、活発に意見交流が進みます。「このことは先生が伝えるより、子どもと一緒に考えてみたらどうだろう」「完成したものを発表するよりも、『中間発表』として意見交流する場面にしたら」…等々、先生たちが授業者に親身になり、自分ごととして考え合っていることが伝わってきました。話し合いは、それは熱心に行われ、いくつかのグループは時間を越えて協議を続けていました。

「たい焼きタイム」の後、一人の提案者の先生に感想を聞くと、パッと明るい顔で「自分が気づかなかったたくさんの視点をいただき、授業の見通しが立って、楽しみになりました。本当に良かったです」と話してくれました。
このように先生たちが授業観・教材観・学び観を交流し深める場になっている「たい焼きタイム」が当たり前に継続されている開明小。来週からは、子どもの姿を通しての先生たちの学び合いが続きます。
リーディングスクール 旭町中学校
旭町中学校の授業改革「KJK」~気軽な公開が生み出す新しい学び合い~
「今度の水曜日、ちょっと見に来ませんか?」
旭町中学校で始まった「KJK(気軽に授業を公開しよう)」は、こんな自然な声かけから生まれる新しい授業研究のスタイルです。「プチチャレンジ」をキーワードに教員同士の学び合いを進めています。
授業者はまず「気付きシート」に「こんなことにチャレンジしてみた」を記入します。大掛かりな準備や完璧な授業は必要ありません。「今日は○○を試してみたんです」という小さなチャレンジが、参観者にとって授業を見る視点となります。この「プチチャレンジ」の考え方が、先生方の心理的ハードルを下げ、気軽な授業公開を実現しています。

授業後の振り返り会は、お菓子と飲み物を囲みながらの和やかな時間です。堅苦しい研究協議会ではなく、リラックスした雰囲気の中で授業者のプチチャレンジについて語り合います。授業を公開した先生も、この気楽な対話の中から新たな気づきや発見を得ることができ、次への意欲につながっています。

今年度からは小中連携の視点を取り入れ、旭町小学校の先生方も参加しています。小中9年間を見通した対話が自然に生まれ、子どもたちの成長をより長期的な視点で捉える機会となっています。参加した先生方からは「研究の方法やあり方への考え方が変わった」という声が聞こえてきます。この取り組みは、これまでの授業公開の枠を超え、新たな教員同士の学び合いを創っていきそうです。
※次回KJKは、9月3日(水曜日)。関心のある先生は、ぜひ旭町中学校にご連絡ください。
リーディングスクール・アソシエイト校 筑摩野中学校
生徒の考える良い授業とは?
筑摩野中学校では、生徒対象の学校アンケートで「良い授業とはどんな授業だと思いますか?」と聞いてみました。その回答には生徒一人ひとりの授業への思いや願いが書かれていました。多かった意見を中心に一部を紹介します。
〇全員が集中して取り組める授業
〇集中できて「なるほど」とわかる授業
〇わからないことはすぐ聞ける授業
〇静かにやる場面と友達と考えを出し合う場面のメリハリのある授業
〇お互いに意見を出し合って理解を深められる授業、考え合える授業
〇友達と意見を言い合いながら、見方を変えたり、新しいことに気づいたりする授業
〇深く考えて誰もが学びを楽しめる授業
〇成長したと感じられる授業
7月21日には全職員で3回目のLG(ラーニンググループ:校内研究グループ)研究会を開き、生徒の考える「良い授業とは?」を共有し、1学期を振り返るとともに、2学期の見通しをもちました。1学期の振り返りでは研究主任の新村先生の授業の実践からより「広がる」「深まる」「高める」授業にするにはどうしたらよかったのかが提起されました。先生たちは、「自分だったら…」「自分の授業でもこんな場面があった。そのときは…」と考え合いました。4人グループを基本とした授業づくりを積み重ねていく中で、職員も生徒も「協働の学びの良さ」を実感しています。
8月22日、3年生の国語の授業では、「挨拶-原爆の写真に寄せて‐」という詩の第1時でした。心に残った言葉や表現、疑問に思ったことをスプレッドシートに書き出していきます。どんどん書き込む生徒もいる中で、自分のタブレット画面の級友の打ち込んだものをじっと見つめ、読んでいる生徒がいました。手にはシャーペンをもち、教科書とタブレット画面を見比べています。その生徒の頭の中では、級友の考えをもとに、自分と対話しながら考えを紡いでいるのだろうと感じる一場面でした。筑摩野中学校ではグループでの学習に限らず、授業のさまざまな場面で協働の学びの姿が見られます。

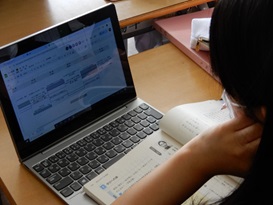
2学期は、教科内の授業参観・授業公開を通して、生徒の姿から効果的な「問い」のあり方について研究を進めていきます。
令和7年8月25日更新
リーディングスクール 中山小学校
校内研修で学校を創る
中山小学校では先生たちのコミュニケーションを深めながら学び合う「校内研修」を真ん中において、学校づくりを進めています。(詳しくはリーディングスクール通信No47をご参照ください。)
中山小のすごいところは、職員研修日を年間計画に位置付け、その日は子どもたちの下校を早め、先生たちが十分に研修に専念できる環境を作っていることです。
夏休み明けには、「学級レクを楽しもう研修」を実施しました。先生たちがそれぞれ持っている「お奨めレクのネタ」を持ち寄り、そのやり方や楽しさを共有し、各学級で実践することで、中山小で大切にしている子どもたち・先生の「関係づくり」を一層進めることを目指します。
レクの提案者は「ルーレット」で決めだします。ここからもう何やら楽しそうです。提案されたレクを実際にやってみる先生たちは笑顔・笑顔。教室中に歓声が響きます。この日は4つのレクが紹介され、あっという間の45分が過ぎました。

この日の後半は市教委の米山指導主事による「インクルーシブ研修」も行われました。研修の中のグループワークでも、先生たちの親密な語り合いが続きました。

研修会に一緒に参加させていただいて、先生たちが「ともに対話し、学ぶこと」を心から楽しいと感じられていることを実感しました。中山小の学校づくりの推進力の源泉は、ここにあることを強く感じました。
リーディングスクール・アソシエイト校 筑摩小学校
主体的な学びを保護者と共有!
7月中旬の参観日、3年生と5年生が「単元内自由進度学習」を実施しました。ここでは5年生の授業の様子を中心に紹介します。
5年生は、算数「合同な図形」保健「けがの予防」の2教科から、自分で学びたい教科を選択・計画し、自分のペースで進めていきました。一人で黙々と取り組んだAさんは、計画より早く進み、発展学習までチャレンジ。「算数が好きになってきて、うれしかった」と達成感にあふれていました。当初の計画を変更して保健を選択したBさんは、「けがの手当ての仕方や犯罪の特徴がわかった」と、選択した学習内容を振り返っていました。友達と意見交換をしたりアドバイスし合ったりしながら、自分で考え集中して取り組めたと感じたCさんは、「自由進度で学習したことを生かしてこれからも学習していきたい」と意欲を新たにしていました。

保護者の皆様も積極的に参加され、お子さんの学習の様子を間近で参観したり、時にはアドバイスを送ったりして、子どもたちの主体的な学びの様子を共有してくださいました。参観された保護者の皆様からは、「家ではあまり見られない自分でどんどんやる姿が見られてよかったです」「今、こんな学習をやっているのですね。驚きました」などの声が寄せられました。
筑摩小学校では、これからも子どもたち一人ひとりの「主体性の育成」と「個性の伸長」を目指し、単元内自由進度学習の実践を積み重ねチャレンジし続けます。
学びの改革リーディング校 丸ノ内中学校
丸ノ内中学校「1学期の学習活動の振り返り」
これまでは、主に3年生の活動を紹介してきましたが、今回は1学期に取り組まれた1年生と2年生の「忠恕の時間」(総合的な学習の時間)の様子をお届けします。
1年生:「探究ってなんだろう?」から始まった初めての一歩
4月の全校オリエンテーションでは、「探究とは何だろう?」という問いから学びが始まりました。これは、生徒だけでなく先生方も共に考えることを目的としており、「忠恕の時間」をどのように進めていくのかを、生徒と教師が一緒になって考えました。
5月に校外学習で上高地を訪れた生徒たちは、観光客やお店の方々にインタビューを実施。訪れた方々がどんな目的で、どこからいらしたのかなど、そこに込められた思いやエピソードを聞き取っていきました。
こうした“人の気持ち”や“出来事の背景”といった、数字では表せない情報は「質的データ」と呼ばれます。生徒たちは、その集め方やまとめ方を体験的に学びながら、探究の第一歩を踏み出しました。また、教師も担当を決め、クラスの枠を超えて生徒たちとかかわりました。

2年生:経験を力に、自分たちで切り拓く探究への一歩
同日、2年生は昨年度の経験を踏まえ、飛騨高山へ。松本市との文化の違いをテーマに、各グループがより細分化された課題に基づく探究に挑戦しました。
生徒たちは、自らお店に連絡を取り、アポイントを取り付け、インタビューの日程調整まで行いました。こうした自主的な準備や実行を通して、昨年度よりも一歩踏み込んだ探究的な学びを実現しました。

令和7年8月4日更新
リーディングスクール 旭町小学校
聞くこと」「伝えること」の大切さ ~旭町小学校 サマーセミナー~
旭町小学校・中学校の先生方が集まり、軽井沢風越学園の岩瀬直樹先生による「コミュニケーション・インストラクション」研修が行われました。
研修では、学級制度の歴史や組織の三要素といった理論的背景を踏まえつつ、「聞くこと」の本質が深く掘り下げられました。オープンクエスチョンを用いたロールプレイングや、「コミュニケーションを阻害する聞き方」の体験を通じて、先生方は無意識のうちに相手の話を遮っていたことや、自分の都合で聞いていたことに気づき、「良い聞き手」について考えることができました。特に、「コミュニケーションはまず量、そして質」という考え方により、「コミュニケーション」のハードルが下がり、普段の児童との関わりや学級づくりにおいて、体験的に学んだ短い・浅いコミュニケーションを多く取り入れることの大切さに気付いたようでした。

また、「インストラクション設計シート」は、今後の実践に役立つツールとして紹介されました。授業の導入における5分間の重要性や、そこに盛り込むべき要素の多さを改めて整理する機会となり、「無駄のない言葉」「子どもへの目線」「教師自身の楽しさ」「伝えたい価値の明確さ」といった効果的なインストラクションの秘密を具体的に学ぶことができました。

「教師は『これでよかったのかな?』と常に迷い続けていく仕事」という岩瀬先生の言葉は、先生方にとって大きな励みとなると同時に、「省察的実践家」として、機械的に業務をこなすのではなく、立ち止まって問い直すことの大切さも感じたようです。「早く子どもたちとやり取りしたい」と、今回の研修で得られた気づきや学びを、2学期からの授業や日々のコミュニケーションの中で積極的に実践し、対話の価値を子どもたちや同僚に発信していくことへの意欲が高まった研修となりました。
リーディングスクール 梓川小学校
子どもたちと共に学ぶ喜び!~タブレット活用で広がる探究的な学び~
梓川小学校の3年生は、地元・梓川のりんごに関心をもち、それぞれの興味に基づいてりんごについて調べています。調べた内容は、国語の単元「しらべたことをまとめよう」と連携し、作文用紙にまとめる活動に取り組んでいます。
7月7日に実施した授業の一コマです。子どもたちは授業前から「先生、もう調べていい?」「早くやりたい」とやる気満々です。「りんごには、どんな栄養がふくまれているのか」「アップルパイの作り方を調べたい」など、調べたいテーマは一人ひとり異なります。タブレットを使い、子どもたちは自分だけの「りんごの探究」を進め、新たな発見をノートに丁寧に記録していきました。わからない言葉に出会ったときは、友達に相談したり先生に質問したりしながら、協働的に学びを深めています。

授業者の竹内教務主任は、意欲的に取組む子どもたちの様子について次のように話されます。
「子どもたちは、タブレットで見つけた新しい発見をいろいろ教えてくれるので、私自身も新しい学びがあってとても楽しいです。先日も社会の授業で、子ともたちに地図を渡すと、様々な記号があることに気づいたので、『地図記号というんだよ』と伝えました。すると子どもたちは、タブレットで地図記号を調べ始めました。中には『電子基準点』という、私も知らなかった記号について、クラスみんなに紹介してくれた子もいました」

子どもが楽しく追究する学びの姿と、その姿に共感し「楽しい」と感じながら成長を見守る教師の姿。この相互作用の中に、梓川小の目指す「その子がその子らしく学ぶ探究的な授業」への可能性を感じます。
リーディングスクール・アソシエイト校 清水中学校
『探究的な学び』を探究する校内研修」サマーセミナーの開催
答えのない問いに自律的に取り組むことが求められる今、授業がより探究的な学びとなるよう、2日間にわたり集中的に校内研修を実施しました。講師には、主に高校生の探究を支援している宮木慧美先生(一般社団法人Koko代表理事)と松本県ヶ丘高校探究科担任の中村祐介先生、そして長野県教育委員会中信教育事務所指導主事の小沢正太郎先生をお招きしました。
宮木先生からは、学校の中だけでは完結しない探究的な学びが重要視されている背景や高校生と地域の方々をつなげていく大切さを教えていただきました。
中村先生からは、「探究のテーマづくりに関しては、生徒が一歩目を踏み出せるものにすることが重要。テーマが壮大すぎたり、具体的でなかったりする場合には、生徒との相談を重ねる」というお話をいただきました。

テーマ設定の重要性については小沢先生も触れられ、「閉じた問い(Yes/Noで答えられるもの)よりも開いた問い」を立てることについて、生成AIも活用したワークショップを通して実践的に学びました。
清水中学校の先生方はこの夏、これらの研修にとどまらず、「大人探究」を実施します。これは、清水中学校の探究的な学びで大事にしている「地域で学ぶ・地域と学ぶ・地域の一員になる」を、先生自身が実践し体感しようとするものです。それぞれの先生が立てた問いをもとに個人探究を行い、9月以降の職員研修でリフレクションを行う予定です。

信州教育の大先輩である牛山榮世先生はかつて、「材に対する探究体験をリアルにもっていない教師、その教師が子どもに探究のことを教えられるか」という言葉を残されていますが、まさに清水中学校の研修はいつの時代も変わらない根っこの部分を大切にした取組みだと言えます。
夏休み明けの授業が、より一層探究的な学びを実現していくものとなる意欲が高まる集中研修となりました。
令和7年7月28日更新
リーディングスクール 岡田小学校
校長先生からのメッセージ
岡田小学校に最近の学校の様子を伺ったところ、校長先生からメッセージと写真をいただきました。岡田小の子どもたちと先生たちの「今」を豊かに語られる素敵な言葉を、ご了承を得て、皆さんと共有させていただきます。
「本日も暑いですね。いつも本校のことを気にかけていただき、うれしいです。
夏祭り3.4年の写真を送ります。左側男子が4年、右側女子が3年で工作コーナーで作りたいものを見本から選んで、一緒に折り紙を折っている姿です。ほのぼのしていて、可愛かったです。『そこは、難しいから僕のをよく見て。』とか『ここ折ってもいいですか。』なんて涙が出そうでした。
いかだ(2年生)は、子どもたちがペットボトルや牛乳パック収集のお願いに交流学級に行ったときのものと、私が一番よくとれた進水式の様子です。『つくりたい』から始まり、翌日から子どもたちは家にある牛乳やペットボトルを持って登校していました。保護者の応援のもとでの進水式、浮かべて乗るまで、その場にいたみんなが祈り、子どもたちの嬉しそうな顔に拍手と涙でした。

子どもたちの願いを引き出し、どんどんチャレンジ!!
支援級でも『揚げずに作るポテトチップス」とジャガイモ販売。いろいろなチャレンジに子どもの笑顔や頑張りが見れて、それを見る先生方のうれしそうな顔と一緒に活動する姿。少しずつでも確実に『のび わく どん』が大きくなっていくのだなと感じています。
昨日、下校で『校長先生、夏休みが終わったら元気で学校に来るね」『また会おうね』と言って帰宅する子どもたちを見送ることができました。1年生が、ハイタッチをして『校長先生、また会おうね。』とわざわざ言いに来てくれました。とても幸せで、先生方にも感謝を伝えました。
幸せのおすそ分けで学級通信もいくつかお送りしますね。
2学期も至らぬ点が多々ありますが、よろしくお願いいたします。」
リーディングスクール 並柳小学校
サマーセミナー:体験を通した探究的な学びの入り口
並柳小学校のサマーセミナーは、「チョコレート探究」。異なる種類のチョコレートを使った探究活動です。先生方はまず一人で丁寧にチョコレートを観察し、その後グループで気づきを共有。そこから自然と「ダークチョコのダークって何?」「チョコレートと準チョコレートの違いは?」といった疑問が生まれ、オープンクエスチョン・クローズドクエスチョンの分類を通じて、素朴な疑問から問いが生まれてくることを体験的に学びました。
この活動は、「共通テーマ(チョコレート)×個別素材」で様々な視点をもち、「個人作業から協働。そして個人またはグループ探究へ。」と、探究活動の一つの流れを体験するものでした。ある先生は、「指示しすぎない自由な空間が居心地良く、『やらされる』のではなく『やりたくなる』時間だった」とふり返り、また「教師が『~しなさい』という言葉が必要なくなる」と、素材選びや素材との出会い、環境構成(教師のかかわりや場づくり)の大切さを実感したようです。
今回の研修で先生方は、「学習者視点」に立ち返り、自らワクワクする学びを体験しました。同時に、「教師自身が学び手としてワクワクすること」が子どもの探究心を育むという教育観を共有しました。
自分のための時間ができる夏休みだからこそ、この機会に先生方自身がミニ探究を楽しんでみることで、子ども視点の学びのイメージが膨らみそうです。夏休み後の並柳小の先生方と子どもたちの学びが楽しみです。

リーディングスクール・アソシエイト校 鎌田中学校
日常的な探究を目指して ~夏休み前最後のKMDタイム~
7月23日(水曜日)は夏休み前最後のKMDタイムでした。2学年の2つのグループ(お笑いグループと謎解きグループ)、は8月5日(火曜日)に鎌田公民館で行われる「KMDサマーフェスティバル」に向け、自分たちの発表をよりよくするための活動を繰り広げました。
2年1組に集まったお笑いグループは2~3人に分かれ、自分たちの「ネタ」を仕上げようとしていました。教室に一歩足を踏み入れると、はち切れんばかりのエネルギーが教室中に満ち溢れていました。生徒たちはもちろん、担当の湯澤先生も純粋にその場の空気感を楽しんでいました。それぞれのグループを見ると、ノリがよく話し言葉でどんどん進めるグループと、パソコンに向かいながら緻密にシナリオを創るグループと、その方法は多岐に及んでいます。

湯澤先生は総合的な学習の時間の主任も務めておられますが、2学年を講座別総合にしたねらいを「関係の枠にとらわれず、興味関心を尊重した日常的な探究につなげたい」と語っています。お笑いグループの生徒たちは、日々人が笑顔になることを思い浮かべながら過ごしているのでしょう。他のグループにも日常化につなげる仕掛けとして、昇降口に各学年学級のKMDタイムの取り組みを見える形にする掲示板を設置し、普段から自然と生徒や職員、保護者の目に触れるようにすることで、日々の探究のエネルギーにつなげています。

令和7年7月22日更新
リーディングスクール 菅野中学校
先生たちの協働的な学びが始動
生徒たちと学びのテーマ「協働」を共有し、対話をベースにおいた授業づくりを目指す菅野中学校では、先生たちも「4人グループで学ぶ」体制づくりに挑戦しています。
まず、研究推進にあたり、「問い」「対話」「フィードバック」等、「協働の学び」を支える要件を先生たちが考えました。そして、それをもとに8つのラーニンググループ(LG)を編成し、授業づくり等を協働的に学び合う体制を作りました。6月16日にはLG立ち上げの会を実施しました。研究主任の飯森先生は、会場にBGMを流し、カフェのようなリラックスした雰囲気を創ります。集まった先生たちは初めての体制に、初めは戸惑いながらも、次第に会話を弾ませ、授業計画や役割分担などを模造紙に書き込んでいきました。

6月末からは「見合Week」と名付けた授業の相互参観を実施、それぞれのLGメンバーで授業参観を行い、グループテーマの観点からフィードバックを交流しました。
そして7月16日には「第1回SLS(Sugano Lerning Session)」として、LGの振り返り・交流の会を実施しました。見合Weekの授業の手応えや、指導主事のアドバイスを共有するとともに、互いの思いを語り合う機会を持ちました。SLSは今後も定期的に開催していく予定です。

一般に、中学校では教科や学年のつながりが強く、この壁を越えた先生たちのフラットな交流が難しくなりがちです。菅野中ではこれを乗り越え、先生たち自身が生徒たちと相似形の「協働の学び」にチャレンジしていきます。
リーディングスクール・アソシエイト校 寿小学校
「自分でやりたい!」 「こうしてみたい!」 自ら動き出す子どもたち
6月30日、松本市幼年教育研究会が寿小学校を会場に行われました。「さあ、やってみよう」を合言葉に積み重ねてきた今までの実践をもとに、低学年部会では、園小のスムーズな接続を願い「スタートカリキュラムの作成」と「単元内自由進度学習(マイプラン学習)」の2つを柱に研究を進めています。
今回は2年生の「国語」と「図工」の「マイプラン学習」の授業が公開されました。子どもたちはそれぞれが考えた「マイプラン」を手元に置き自分がこの時間にやる活動をどんどんと進めていました。
 【図工】選べる材料がたくさん!
【図工】選べる材料がたくさん!
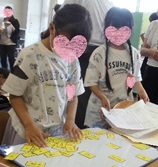 【国語】上位語はどれかな。
【国語】上位語はどれかな。
「楽しかった」「次の時間は〇〇をする」「計画したところまでできた」など子どもたちの感想からは、充実した学びの時間となったことがうかがえました。
学びの改革リーディング校 波田小学校
~ 互いの強みを活かし合う職員集団の挑戦 ~
波田小学校では、2年間「多様性を受容し、やってみたいこと、挑戦したいことが実現できる学校」を目指し歩みを進めてきました。子どもたちだけでなく先生方も「やってみたいことに挑戦しよう」と職員研修を中心にチャレンジを続けています。
7月14日には、「身近な先生方のやりたいこと・得意なことから学び合おう」と職員研修を企画・実施しました。先生方は、次の4講座の中から、前半・後半30分ずつ2回講座を選択受講しました。
(1)「熱中症や応急処置について:(講師)保健室 小松・北原先生」
(2)「自分自身に必要なエネルギー量を計算してみよう:(講師)栄養教諭 荻上先生」
(3)「AIを使ってみたくなる研修:(講師)3年担任 齊藤先生」
(4)「『読める』って大事!LITALICOまなびの教材の紹介:(講師)通級指導教室 西川先生」
「AIを使ってみたくなる研修」の一コマです。講師の齊藤先生から「AIのGemini」を使い「体育の授業で使えるリーグ戦を組む方法」を教わった後、受講した先生方がClassroomに入り、リーグ戦表を作成しました。先生方からは、「これは、すごいね」「こんなに簡単にできちゃうの。すばらしい」などの感嘆の声とともに、「齊藤先生のように的確な指示ができないとうまく作れない」などの感想が聞かれました。参加された先生方は、AIをうまく活用すれば、仕事の効率化が図れそうだと実感する機会となりました。

多様性を受容し、一人ひとりの「やってみたい」が花開く学校づくりを目指す波田小学校。この日の研修は、先生方が互いの専門性や情熱に触れ、自らも学び手となって新たな可能性に挑戦する貴重な機会となりました。
令和7年7月14日更新
リーディングスクール・アソシエイト校 島立小学校
同僚の実践から学ぶ!
島立小学校の子ども達の主体性を育む授業づくりが、先生方によって広がりを見せています。日々の授業の中でも、子どもが自分で学びを進める場面、自分で学び方を選択する場面を意識的に設けて、子どもに委ねる学習にトライしています。
6月23日には、算数「たし算のひっ算」の単元で自由進度学習に取り組んだ3学年の先生の実践から学ぶ研修会が開かれました。授業者の先生からは、子ども達が振り返りをしやすいように計画書に工夫を加えてみたこと、単元の3か所で「先生チェック」を設けたことで、しっかり理解できていない児童を把握することができ個別指導につながったことなどが語られました。一方で、「振り返りが感想になってしまい、その日の学びについて記述できるようにするにはどうしたらいいか」といった率直な悩みも話されました。その後のグループワークでは、授業で使用した学習プリントや計画表をもとに語り合いました。
 教科書、タブレット、辞書など、自分で選択した方法で、自分のペースで課題に取り組む子ども達
教科書、タブレット、辞書など、自分で選択した方法で、自分のペースで課題に取り組む子ども達
先生方は、「課題の共有はどうやったの。」、「プリントに書かれている“ミニレッスン5分”ってどんな時間なの。」など、矢継ぎ早に質問したり、「自分なら…」とさらなるアイデアを伝えたりするなど積極的に参加していました。教室全体に、同じ学校の同僚の実践から学び、自分の授業づくりに活かそうとする先生方の熱気があふれているようでした。
リーディングスクール・アソシエイト校 開智小学校
探究的な学び~目の前の出会いから「なぜ?」が生まれ、やりたいが広がる~
開智小学校では、水曜日を「開智タイム(探究の時間)」と位置づけ、子どもたちの「やりたい」という気持ちを大切に、学びを進めています。クラスの枠を超えた学年グループや、4・5年生の連学年グループなど、テーマ別の探究活動が行われています。4,5年生は【自然・食・光・布・防災・交流】の探究テーマから興味のあるものを選び、そのテーマの中で様々なアンカーイベントを通して、特に興味を持った「こと」を深掘りし、「問い」を作って活動を進めています。
4,5年「光」グループ ~コップと矢印の不思議から広がる探究~
「光」グループは、理科室で“アンカーイベント”からスタートしました。それは、「水が入っていないコップと、水が入ったコップ。これらを通して矢印を見るとどう見えるか?」といったごく身近な実験です。実験をした子どもたちは、水が入ったコップを通して見た矢印が「逆さに見える」という事実に出会いました。すると「なんで?」「どうして逆なの?」と、次々に疑問の声をあがってきました。さらに、近くにあった色水を見つけると「色水でも見ていい?」とコップに入れてみたり、矢印以外の絵を描いて試してみたり。ある子は「顔を半分描いて見ると面白いよ」と新しい発見を共有し、また別の子は「『春』って漢字だと逆にならないんだよ」と、自分なりの考察を加えていました。

開智小学校の探究は、このように目の前の事実に触れ、子どもたち自身が「なぜだろう?」と感じ、そして「こんなことをしたら面白いんじゃないか」、「やってみたい」という意欲が湧き上がるところから始まります。学校で見つけた「やってみたい」があるからこそ、夏休みに入り、子どもたちもゆったりとした時間の中で、独自の探究が進むかもしれませんね。

学びの改革リーディング校 波田中学校
新しい英語学習への挑戦!
英語科では、生徒が「英語を学ぶって楽しい・英語をもっとやってみたい」と意欲をもち、生徒自身が「問い」を立て、解決していく「探究的な学び」を導入できないかと考え、2学年で2クラスを3つに分けて行うコース別学習に挑戦しました。
事前調査で明らかになった「英語に対する興味・関心・できるようになりたいこと」を踏まえ、生徒の希望と「先生方が授業でチャレンジしたい」と考えていた内容を考慮し、「洋楽探究コース」「コミュニケーション探究コース」「自己表現探究コース」の3コースを設定しました。
第1時の授業を終えて、「洋楽探究コース」を担当した山口研究主任は、「最初に『問い』づくりから始めましたが、生徒が『やってみたい』と思うような探究の『問い』を引き出すことが難しかったです。試しに洋楽を歌ってみようということで、ALTの先生に解説してもらいながら歌唱の活動を行いましたが、生徒の『問い』づくりとうまく結びつきませんでした。洋楽を聞かせて生徒から興味や疑問を引き出して『問い』づくりの練習をし、その後、解説や歌唱の時間をとり、『問い』づくりを行うなど展開を変えていけば、もっと主体的に活動できたと思います」と、生徒の「思い」に沿った教材研究の重要性への気づきを話されました。チャレンジしたからこそ見えてきた新たな気づきです。こうした先生方の挑戦する姿勢は、きっと生徒たちの心に響くことでしょう。

波田中学校では、「『やってみる』から生まれる、生徒とともに学ぶ授業づくり」をテーマに研究を進めています。今回の英語科による探究的な学びへの挑戦もその一環として行いました。これからも生徒の思いに寄り添いながら、生徒とともに学ぶ授業づくりにチャレンジし続けます。
令和7年7月7日更新
リーディングスクール 開明小学校
梅雨のたい焼きDayは晴れ予報♪
「たい焼き」は開明小学校の「学び」キャラクター。目指す子ども像「『~たい』をもって挑戦し、ステップアップを楽しむ中で育むエージェンシー」から命名され、子どもたちとも共有しています。

毎週の「たい焼きタイム」(重点研究会)では、先生たちが豊かに対話しながら校内研修や「自己課題」への挑戦を進め、それぞれの「たい焼き授業デザインシート」(指導案)を練り上げます。
折々に発行される「たい焼き通信」(研究通信)では、主任さんのメッセージ、研究のリフレクション、お知らせなどが先生方に届けられます。ワクワクするこれらのネーミングからも、開明小の先生たちが「学びを楽しむ」雰囲気が伝わります。
6月23日には第1回の「たい焼きDay」(授業公開)を実施。助言者(信州大教授 谷内祐樹先生)を招き、3人の先生が授業を公開しました。(授業者は手上げ式で決定、今回もすぐに候補者が決まったそうです。)
授業後、同じ授業を参観した先生でグループを編成、授業者へのフィードバックタイムを持ちます。すでに多くの対話を重ねてきた先生たちは、授業での子どもの学びや先生のチャレンジのよさについて、豊かに思いを交流し合いました。先生たちの気づきは「たい焼きフィードバックシート」で授業者に届けられます。

谷内先生は、各授業のよさや先生方の自己課題の意味づけを話され、「先生たち一人一人の『味』がでるのが開明小のよさ」とエールを贈られました。
「梅雨のたい焼きDayは晴れ予報♪」はこの日の「たい焼き通信」のタイトル。その言葉通り、開明小の先生たちのチャレンジと同僚性が晴れやかに光る一日になりました。
リーディングスクール 旭町中学校
学びを深める「チューニング」の実践 -旭町中学校での取り組みから-
旭町中学校の1学年の総合的な学習の時間では、生徒たちは街歩きを通じて見つけた年間を通した追究テーマを設定しています。6月17日(火曜日)の学年プレ発表会では、設定したテーマについて、なぜそのテーマを選んだのか、今後どのような活動を計画しているのかを話しあいました。ここで活用されたのが「チューニング」という話し合いの手法です。
「チューニング」では次のような手順で話し合いを進めました。まず発表者が自分の追究テーマとその設定理由、今後の展望を4分間で説明します。次に、参加者が発表者に質問をすることで、テーマを明確にしたり、さらに深く掘り下げたりする時間を7分間設けます。その後、参加者は発表者抜きで、発表内容から感じたことを7分間話し合い、発表者はその様子を聞き、印象に残ったことをメモします。最後に発表者が、参加者の話し合いから得られた気づきを2分間で共有します。
この活動を通じて、生徒たちは自身の考えを整理し、テーマをより明確にすることができたようです。参加した生徒からは、「自分のことを話すことで考えが整理された」「調べたいことが明確になってきた」といった感想がありました。また、発表に向けてCanvaを用いてポスターを作成するなど、工夫を凝らす生徒も見られました。初めは緊張感があったものの、回を重ねるごとにお互いに聞き合う姿も印象的でした。
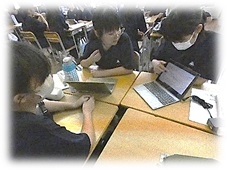
今回篠田先生がリーディングスクールラボで得た学びを、このように生徒の学びへとつなげる実践。教師の学びが、子どもの学びにいかされる。まさに「教師の学びと子どもの学びは相似形」です。
リーディングスクール・アソシエイト校 筑摩野中学校
「対話を基盤とした学び」の成果
筑摩野中学校では、この2年間、「協働の学び~対話を基盤とした授業づくり~」をテーマに、4人グループを基本とした授業づくりに取り組んできました。先生たちは、生徒たちの豊かな思考と対話を引き出す「問い」や「教師の関わり」のあり方を工夫しながら、日々の授業づくりを進めています。
この6月27日~7月20日に「授業を見合う月間」として、校内研究グループ(ラーニンググループ:LG)の先生たちがお互いの授業を見合う機会を設けました。終業式後には、LGで振り返りを行う予定です。
6月30日、1年生の英語の授業です。「Where(どこ?)」の学習場面で、生徒たちはプリント上の「自分の部屋」で4つのアイテムを好きなところに配置し、どこにあるかを尋ね合いました。設置した場所によって答え方が異なることで、思考と対話の必然性が生まれます。生徒たちはペアで豊かに対話しながら確認していきました。さらに、先生が数秒見せた部屋の様子を記憶して、どこに何があったかを当てるMemory Gameを行いました。丁寧に学習した「物の場所の伝え方」を活用した、大盛り上がりの時間となりました。

筑摩野中学校では、多くの授業で、ふとした疑問や考えを生徒が近くの生徒につぶやき、またその生徒が答えるというように、自然な対話が生まれています。また、積極的で発言の得意な生徒だけでなく、さまざまな生徒が考えを表現しています。生徒たちがお互いを尊重し合えていること、そして、先生方がそのような場面を大事にしていることが伝わってきます。

筑摩野中の先生たちが日常的に取り組んできた「対話を基盤とした授業づくり」の営みの成果が、ここに、確かにあります。
令和7年6月30日更新
リーディングスクール 中山小学校
自分らしく探究する子どもを支える
5年生の授業「アルプスタディのしおりを作ろう」の一コマです。この単元で、子どもたちはしおりづくりを通して「アルプスタディ」の様々な場面や役割をグループで分担し、自分たちでこの学習活動の企画を作り上げていきます。
授業開始前からやる気いっぱいの子どもたち。授業が始まるとグループで話し合ったり、クラス全体に問いかけたりしながら、各分担の内容を考え、工夫して「しおり」の協働編集ファイルを作り上げていきました。学級の全ての子どもたち一人一人が、自分の「課題」に没入し、自分らしい学びに浸りこんだ素敵な時間となりました。

中山小学校では、「探究の学び」をインクルーシブな教育環境づくりの視点からも研究しています。一人一人が「やりたいこと」を自分のやり方で、時に友に支えられながら心行くまで「探究する」ためには、一人一人が「よさ」を認められながら安心して「自分らしく学ぶ」ことが不可欠と考え、それが豊かに両立する授業づくりをみんなで目指しています。今回の授業でも、子どもたち一人ひとりへの先生たちの温かいまなざし、思いに寄り添った支援、そしてこれまでに培われてきた子どもたちの温かい関係性が、豊かな学びを支えました。

授業後の研修会では、先生たちが授業中に撮影した写真をもとに、それぞれがとらえた「自分らしく探究する子どもの姿」を交流しました。さらに授業での子どもの姿をベースにした米山指導主事の話を聴き「インクルーシブな教育環境づくり」の視点を共有しました。子ども一人一人の「思い」と「学びのよさ」が響き合う温かい時間となりました。
リーディングスクール実践校3年目、中山小では「探究の学び」のさらなるシンカを目指して歩みを続けます。
リーディングスクール・アソシエイト校 筑摩小学校
「やりたいことを追求しよう!」
「子どもたちの主体性を育てる授業づくり」をテーマに、歩みを進めている筑摩小学校。今年度も、4~6年生を対象に「フリースタイルプロジェクト(FSP)」を実施し「自分の興味・関心のある活動を追求することで、主体性を育て、個性を伸ばす」ことを目標としています。
2年目を迎えた今年は、子どもたちからの「もっと時間を増やしてほしい」という声に応え、昨年度より活動時間を拡大。発表会を含め、全15時間のプログラムとなりました。
6月5日には第1回目の活動が行われ、「自分の興味・関心にもとづいて学習テーマを設定し、年間計画を作成する」ことを目指してスタートしました。
子どもたちが選んだ活動は多彩で「裁縫、人形づくり、手芸、折り紙、将棋、タイピング、けん玉、野球、ボール投げ、サッカー、陸上、ジャベリックボール、ハードル走、音楽、ピアノ、好きな歌を歌う、段ボールハウスづくり、粘土細工、水族館の研究、英語、韓国語、エレベーターの研究…」など、多岐にわたります。

昨年度に引き続き、「エレベーターの研究」に取組むAさんは、計画を立て終えると、「昨年よりも上手にエレベーターの写真を撮りたい」と語り、自ら写真館に電話をかけて「写真の撮り方を学ぶ」ための交渉まで行いました。
裁縫や手芸に取組むグループでは、活動の終了を告げられると「えー、もう終わっちゃったの?」「明日もFSPがあったらいいのに」「1時間目から6時間目まで全部FSPがいい!」などと、名残惜しむ声があちこちから聞こえてきました。担当のB先生は笑顔で、「やっぱり、好きなことって本当にやりたくなるんですね」と話していました。

筑摩小学校の新たな挑戦は、今年も力強く動き出しました。子どもたち一人ひとりの「主体性の育成」と「個性の伸長」に向けた歩みが、これからますます楽しみです。
学びの改革リーディング校 丸ノ内中学校
丸ノ内中学校「1日忠恕の時間」
丸ノ内中学校では、総合的な学習の時間を「忠恕の時間」と呼び、生徒自らがテーマを設定して探究活動を行っています。中でも「1日忠恕の時間」は、生徒が主体的に探究的な学習を深める日です。この日、3年生のあるグループは、「男子トイレへのサニタリーボックス設置」に着目し、松本市内を歩いて調査を始めました。
 松本市内を調査する生徒たち
松本市内を調査する生徒たち
このグループが男子トイレのサニタリーボックスに注目したのは、「まちづくり」という大きなテーマのもと、松本城周辺を歩いて題材を探していたときのことです。実際に歩いてみると、居心地の良い空間や快適なトイレの存在が、街歩きには欠かせないことに気づきました。さらに調べを進める中で、観光地の公衆トイレには男子トイレにもサニタリーボックスが設置されている地域が少なくないことを知り、関心が高まりました。
そして修学旅行で訪れた京都では、京都市のまち美化推進課の方と交流し、すべての男子トイレにサニタリーボックスが設置されていることを知って、大きな驚きと学びがありました。
こうした学習をきっかけに、グループの関心は「男子トイレにもサニタリーボックスを設置するべきではないか」という具体的な課題へと深まっていきました。男子用サニタリーボックス導入の利点を松本市に伝えたい、医療従事者の方にもお話を聞きたい、必要としている人がどのくらいいるのかを知りたい――。そんな思いを胸に、このグループは松本市内の公衆トイレや施設を実際に訪れ、現地の様子を見てまわりました。
今後、このグループは、地域住民の声や統計データなども参考にしながら、男子用サニタリーボックスの設置が病気や障害のある方にとって、どのくらい支援となるのか、心理的な安心感や生活の質の向上といった面からも考察を深めていく予定です。
令和7年6月23日更新
リーディングスクール 旭町小学校
学年経営ビジョンミーティング
校内研修において「学年経営ビジョンミーティング」が開催されました。ここでは、各学年が今年度取り組む学年目標や単元計画を発表し、全職員で共有する場として設けられました。
ミーティングの主な目的は以下の2点!
〇子どもたちの1年間の学びと暮らしを先生方で対話しながらデザインし、先生方が安心して新たな取り組み(トライ&エラー)に挑戦できる機会をつくること。
〇職員間の連携を深め、一人ひとりが主体的に各学年の経営ビジョンを共に考え、共につくっていくこと。
ミーティングでは、高学年、低学年、特別支援、専科、院内等と、各学年の先生方が模造紙にまとめた経営案を基に、約2分間で発表を行いました。発表内容は、特に工夫したい点、今年度の目玉となる取り組み、そして他の先生方に相談したい事柄が中心でした。
発表後には「付箋おしゃべりタイム」が設けられ、発表内容から感じたこと、興味をもったこと、アイデア、自身の経験などを付箋に書き出し、発表者と直接対話しながら共有しました。この時間は、単なる共感に留まらず、各自の経験に基づく具体的なアドバイスやアイデアを出したり、「私も挑戦してみたい」という前向きな意欲を伝えたりする場となりました。
ミーティングの終わりに、校長先生から「このミーティングを保護者にもしたらどうだろうか?」という言葉がありました。この問いかけは、先生たちだけでなく保護者や地域も巻き込み、学校全体のコミュニティをさらに発展させていく可能性を感じた瞬間でもありました。
この研修からも、開かれた職員集団の関係性が感じられ、どこでもすぐにコミュニケーションが生まれる旭町小学校の同僚性が見られました。

リーディングスクール 梓川小学校
人とつながり、アイデアを広げる喜び!
「その子がその子らしく学ぶ探究的な授業の実現」をテーマに研究を進めている梓川小学校。6月12日、「核となる単元」から「探究的な授業の構想」を考える協働的な学びの場となることを願い、職員研修を位置付けました。
研修冒頭、「核となる単元」による授業実践で知られる富山県堀川小学校の視察報告が行われました、研究部の沼尾先生からは「子どもたちの自己選択・自己決定の機会を増やし、もっと子どもに委ねること。『待つ』という教師の出を大切にしたい」と熱い思いが語られました。

続いて、「核となる単元からの探究的な授業づくり」の一助となるように、ウェビングマップ作成に取組みました。各学年では、「あさがお」「宝」「りんご」「水」「米作り」「カフェ」などのテーマを中心に据え、アイデアを自由に広げていきました。先生方は、楽しそうに語り合いながら、キーワードから関連する活動や概念をつなげ、相互のアイデアを交流させていきました。

研修後、先生方からは「一人で考えるより、たくさんアイデアが出ておもしろい」「学年で考えることで、みんなの考えが一つにつながって驚いた」との声が聞かれました。研修を通して、「人とつながり」協働的に学ぶ楽しさを実感した梓川小の先生方は、これからも「探究的に学ぶ子どもの姿」を思い描き、「共に考え、語り合う」文化を大切にしていきます。
リーディングスクール・アソシエイト校 清水中学校
「子どもの自己決定を促す授業づくり」に向けて
清水中学校では、全校研究テーマ「子どもの自己決定を促す授業づくり」の具現に向け、毎月、職員研修が行われています。6月16日には、自己課題の解決に向けて取り組んだ4月から6月の授業実践について、対話をとおしてふり返る研修を行いました。
生徒が考えたくなる学習問題の設定を自己課題に据えている先生は、「どのような学習問題を設定するかとともに、生徒自身が意識的に見方・考え方を働かせられるような授業づくりを進めることの大切さに気づいた」と語っていました。別の先生は、「これからの社会では、自分の考えを表現することがより一層求められている。『あなたは〇〇についてどのように考えますか』という問いに答えることができる資質・能力を育成するには、年間を見通した単元設計が大事だ」と授業改善・充実への思いを新たにしていました。
今回の研修を取材して感じたことは、子どもの学びと教師の研修は相似形であるということです。思考ツールによって整理された各自の考えはリアルタイムに共有され、他者参照をしながら自分の考えを随時、更新していくことができる研修でした。未来社会を切り拓く生徒には、多様な他者との対話をとおして、新たな価値を創造していく資質・能力が求められています。この資質・能力を育成できるような授業を実践する先生自身が、新しい学び方のよさを体感している姿が印象的でした。

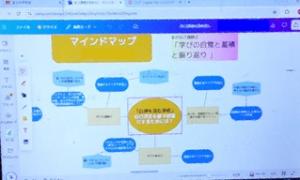
朗らかな雰囲気で語り合った今回の研修を機に、先生方の創意工夫によって授業改善・充実がさらに進んでいきます。
令和7年6月16日更新
リーディングスクール 岡田小学校
子どもとともに進める先生たちの『探究』
「のびのび・わくわく学び、どんどんチャレンジ」を合言葉に学校づくりを進める岡田小学校。6月17日に「おいしいお米作り」に挑戦する5年生の「総合」の1時間を全校で参観し、学び合う機会を持ちました。授業に臨んで担任の先生は、「これまで『引っ張る』ことが多かったけれど、今回は『子どもにゆだねる』ことを意識してきました。」と挑戦を語られました。
授業が始まると、植木鉢を活用した「ミニ田んぼ」に走って行って思い思いのかかわりをしたり、外部講師のJAの職員さんのもとに集まって質問したりなど、それぞれの「やりたいこと」にどんどん向かっていく子どもたち。自分の手で植えた「苗」が子どもたちにとって大切な存在になっていることが豊かに感じられました。
先生たちは予め参観するグループを決め、子どもたちの学びの様子を写真に記録します。そして、授業後の研修会では、撮影した写真を共有しながら「子どもたちの活動から感じられる『ねがいや思い』」「子どもたちが『探究』する姿」について、それぞれが見取った思いを交流し合いました。 一人一人の学びの「よさ」や「意味」をみつけようという温かい空気に満ちた研修会となりました。
岡田小学校の研究テーマは「ひとりひとりのやる気が生まれる支援や授業のあり方」。子どもの姿を語り合い、学び合いながら、みんなでテーマに向かって探究を進める岡田小の先生たちです。
リーディングスクール 並柳小学校
先生方の「やりたい」を大切に、主体的になれる研究づくり
並柳小学校では、「『やってみたい!』を大切に 共にチャレンジしよう」をテーマに、教職員による研修が行われています。研究部では、先生方一人ひとりの「やりたい」という思いを研究活動へとつなげ、その実現をサポートするための研修づくりを大切にしています。
6月に行われた研修の最終場面では、先生方から率直な声が聞かれました。「漠然とした『やってみたい』が、こうして話すことで明確になり、やる気が出た」「一人ではなかなか実現しないことも、誰かと繋がることで前に進める」といった前向きな意見が次々と上がりました 。
ある先生は、「子ども主体の学び」が長年言われ続けているにもかかわらず、学校現場で新しい実践が生まれにくい現状に課題意識を抱いており、「見聞を深めるためにも新しいことに挑戦したい」と語りました。さらに、やりたいことが多様に広がっている中で、「それを無理に一つにまとめるのではなく、グループ内でそれぞれの『やりたいこと』を支え合う形が良い」という、協働的な研究のあり方の提案もありました。
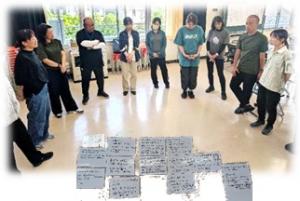
これまでの学校の研究活動は、決められた部会に所属し、与えられたテーマに取り組むのが一般的でした。しかし、今回の研修を通して、先生方の「やりたいこと」を共有し、共感し合うことで、共通の思いを持つ「仲間」と協働して研究を進める思いが高まっています。また、たとえ個人で研究を進める場合でも、それを支え、応援する職員間の「仲間意識」が育まれていることも伺えます。「できなかったことも含めて共有し、互いに学び合える場にしたい」という意見からは、失敗を恐れずに挑戦し続けることを肯定する、心理的安全性が保障されている並柳小学校です。

先生方それぞれの「やりたい」という思いが原動力となり、活発なコミュニケーションを通じて互いを認め合う関係性が築かれています。このような教職員間の協働は、子どもたちの「やってみたい」という探究心を育むことにつながる、「教師の学びと子どもの学びの相似形」を体現する、新たな学校づくりの一歩となりそうです。
リーディングスクール・アソシエイト校 鎌田中学校
地域貢献を目指して ~KMDタイム、スタート~
鎌田中学校伝統のKMDタイムが今年も始まりました。5月22日に行われたオリエンテーションでは総合主任の湯澤先生より「KMDタイムを練習しよう」と「メダカで地域貢献」をテーマにより良い松本市の未来に私たちがどうかかわれるかを考えました。この日は季節外れの猛暑となり、教室でのオリエンテーションとなりましたが、生徒たちが真剣なまなざしで放送を聞いている姿がありました。湯澤先生の「君たちには無限の可能性がある」「グループでの活動がより良い地域貢献につながる」「日々の生活や授業がKMDタイムにつながる」「仲間との活動が自分の未来につながる」といった熱いメッセージが生徒一人一人に届いていました。

その後、学年ごとに分かれてのオリエンテーションとなりました。2年生は8つの講座のうちのどれかに所属し、地域とかかわることになります。大まかな活動の計画が提示され、昨年の経験を自分の武器として、自分自身の学びを考えることになります。自分自身の生き方に迫る大きな学習です。生徒たちはもちろん、それを支える先生方のまなざしも温かくもありながら真剣そのもの。学校全体での取り組みに期待が膨らみます。

令和7年6月9日更新
リーディングスクール 菅野中学校
「対話による学び」の楽しさを味わう
「協働」をテーマとして生徒たちとも共有し、学校づくり・授業づくりに取組んでいる菅野中学校では、全校集会で学年・学級をごちゃまぜにして対話し合う「ワールド・カフェ」を実施しました。
体育館の周りに貼られた、番号・記号のカード。これを目印に生徒たちは「8C」など、自分のグループの場所に集まります。(1年生が理解できるよう、社会の単元を入れ替えて緯度と経度を学習したそうです。)全ての生徒が5~6人、計72の縦割り小グループに分かれ、第1ラウンド「なんのために学ぶ?」、第2ラウンド「学んで楽しいと感じるのはどんなとき?」について、考えを模造紙にメモしながら話し合いました。

初めは、ぎこちなさが感じられた生徒たちでしたが、3年生のファシリテーションにより、次第に考えの交流が広がっていきます。友達の考えをうなずきながら聞き、自分の気づきを時間いっぱい模造紙にメモしようとする、素敵な学びの姿が体育館中で見られました。
普段、深くは考えない「問い」に向き合い、自分の考えが受け止められたり、友の考えに触れたりすることで、考えが深まっていく、そんな「対話による学び」の楽しさを感じている生徒たちでした。

今年度、菅野中学校では、先生たちの「学び」も小グループによる「対話」をベースに進めていきます。学びのテーマ「協働」に相似形で挑む、菅野中の先生たちと生徒たちです。
リーディングスクール・アソシエイト校 寿小学校
「子どもたちの『できた』『わかった』に出会いたい」
昨年度、寿小学校のあいことば「さあ、やってみよう」と、「子どもに委ねる」をキーワードに授業づくりを追究してきた寿小学校では、自ら学ぶ場や方法を選択しながら学習を進めるマイプラン学習等の取り組みを通して、子どもたちが「学び方や学びの進め方は一つではない」ことを知り「さあ、やってみよう」と自ら動き出す姿へと変化する様子を感じてきています。
 フィードバック研修をする先生方
フィードバック研修をする先生方
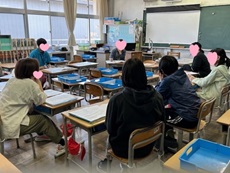 今年度の実践を構想する先生方
今年度の実践を構想する先生方
今年度初めての研修では研究主任を中心に「フィードバック研修」を行いました。子どもとの会話に生かし、子どもの願いや思いをより大切にした授業づくりをしていくことで、子どもたちの「できた」「わかった」の姿にたくさん出会いたいと願っています。
学びの改革リーディング校 波田小学校
~「つながろう 語り合おう!」 まずは職員から ~
今年も「多様性を受容し、やってみたいこと、挑戦したいことが実現できる学校」を目指し歩みを進めている波田小学校。学校運営の中心を担う教頭先生方・青柳教務主任・清沢研究主任は、「学校教育目標『まつかぜ “ま”学び合おう “つ”つながろう “か”語り合おう “ぜ”全員が』の実現に向けて、職員間の対話の機会をもっと増やしたい」と共通の願いを持っていました。
職員数は69名。校舎改築により校舎間の移動距離が長く、一堂に集まることが難しいという現状の中で、まずは職員同士が「つながり、語り合う」場をつくることにしました。これは、教頭先生方の発案により、今年5月から月に2~3回行われる職員連絡会の後に、10分程度の職員同士の語り合いの時間を設けるという新たな試みです。語り合いのグループは、さまざまな先生方と関われるようにランダムで編成されます。
第1回(5月19日)のお題は、「自分がおすすめしたい給食のメニュー」。自校給食で好きなメニューを紹介する先生もいれば、県外出身の先生から郷土色あふれるおすすめメニューを聞き、みんなで調べて「おいしそう!」と盛り上がるなど、和やかな雰囲気に包まれた語り合いの場となりました。
第2回(5月26日)のお題は、「最近あった嬉しい子どもの姿」。子どもとの心温まるエピソードを、目を輝かせながら嬉しそうに語る先生方の姿が印象的でした。

「やってみたい、挑戦したい」を実現できる学校を目指し、まずは職員同士が「語り合い、つながる」波田小学校の新たなチャレンジが、今、始まっています。
令和7年6月2日更新
リーディングスクール・アソシエイト校 開智小学校
子どもも教師も、わくわくする探究的な学びへの取組み
開智小学校は今年で3年目を迎える「探究的な学び」の全校研究に、これまでの経験を活かしより力を入れています。そこでは「先生方とつくる研究」「先生方と語り合う研修」を核に、子どもたちと教師が共にわくわくしながら学び合える授業づくりを目指しています。
令和7年度の研究テーマ「共に学び合う子どもと教師~わくわくする授業をつくる~」は、先生方みんなの対話から生まれました。自分たちがどこに向かい、何のために研究するのかという問いを大切にし、全員で作り上げたこのテーマが学びの羅針盤となっています。

各学年では特色ある探究活動が展開されています。4・5学年では異学年縦割りによる「テーマプロジェクト」が進行中で、泥団子作りや布を使ったアクティビティ、地域の防災倉庫見学などの共通体験(アンカーイベント)を通じて子どもたちの探究心を引き出しています。6学年は旧開智学校について、2学年は学区内の緑地を開墾して大豆畑を作るなど、地域や生活に根ざした学びを進めています。
今後は10月31日(金曜日)に行われる『学び創造研究大会』を節目として、「探究的な学び」の授業づくりと研修を計画的に進めていきます。また、教科で深める探究的な学びについても各学年で単元計画を作成し、「学年一公開」を通じて授業公開を行う予定です。先生たちは研究を通じて生まれる悩みや成長もありのままに共有しながら、わくわくする学びの探究を楽しんでいます。
リーディングスクール・アソシエイト校 島立小学校
「自ら動き出す子ども」を目指して
島立小学校では、アソシエイト校として2年目のスタートを切りました。昨年度、先生方からの「自由進度学習にチャレンジしてみたい」という声をきっかけに発生した取組みを、今年度は全校研究としてさらに深め、広げていきます。
4月25日には、2度目の職員研修を行い、昨年度の自由進度学習で見られた子どもの姿、先生の手ごたえ、感じた課題などを語り合い、新しく来られた先生も含めて、全員で昨年度の成果と課題について共有しました。
後半では低中学年と高学年に分かれ、単元内自由進度学習が行えそうな単元について協議しました。

高学年部会では、「つけたい力が何なのか、明確にしてから授業を作り始めないといけないね」、「体験的な学習場面があった方が、子ども達の意欲も向上するのでは」といった意見が出されました。また、自由進度学習に限らず、授業の中でどのように「子どもに学習の主導権を委ねる場面」を設けているかについても話が及び、互いの実践について熱心に語り合う先生方の姿が印象的でした。
低・中学年部会では、算数「わり算のひっ算」について自由進度学習で行えそうか検討する中で、「自由進度学習に適した単元と、そうでない単元があるのではないか」、「“一斉”と“委ねる”をハイブリッドでやっていくのもいいのでは」といった声が聞かれました。自由進度学習を行う上での率直な不安や疑問点についても語り合われ、真剣な声にこれからの授業づくりに向けた熱を感じました。
今年度、島立小学校では「自ら学び 共に学び合いながら わかる喜びを実感できる子どもの育成」を研究テーマに据え、単元内自由進度学習を一つの窓口として、自分から「こうしてみたい」と
動き出せる子どもの姿を願って、研究の歩みを重ねていきます。
学びの改革リーディング校 波田中学校
「気になること」から「“問い”づくり」へ
今年度も「全員が主役となる学校」を生徒と共に創ることを目指し歩みを進めている波田中学校。研究主任の山口先生は、「総合的な学習の時間をもっと一人ひとりが主人公となる学び」にしたいと願い、「総合」の係の先生たちとともに探究を動かす「問いづくり」を学ぶワークショップを計画・実施しました。

市教育研修センター堀内主事のファシリテーションのもと、身のまわりから「気になること」を見出し、対話しながら問いの形を創り上げていった先生方。
生徒の立場になって行った「問いづくり」の経験を通して、「自由度があると難しいけど楽しい」「“問い”といわれると身構えるが“気になること”というと出しやすい」「気になることをたくさん出して“問い”に変えていくのも一つ方法かも」など、多くの気づきを交流しました。

山口先生は、この「問いづくり」の体験を、全職員による共通体験にしたいと考え、職員研修の計画を進めています。「一人ひとりが主人公」を目指し、「まず先生たちが学んでみる」波田中の新しい挑戦が動きだしました。
令和7年5月25日更新
リーディングスクール 開明小学校
「学びを楽しむ子ども・先生」をめざして
昨年1年間、アソシエイト校として「子どもと先生の『~たい!』から始まる授業・学校づくり」をすすめてきた開明小学校。今年度はリーディングスクールとして2年目の歩みをスタートしました。
4月28日には学校を計画休業とし、先生たちが1日中学びを深める「職員研修の日」を実施しました。今年の1日研修の目玉は、先生たち全員が地域に出かけ、発見した魅力を持ち寄る「地域フィールドワーク」です。「地域とつながる学びを活性化したい」という願いの下に企画・実施されました。
子どもの「ヒキガエルがいる」情報をもとにひたすら追い求めた先生、「コンテナ」に着目し調べ回った先生、様々な「公園」にいる人にインタビューし続けた先生…。夢中になってそれぞれの「旅」を楽しみ、4時間の時間があっという間に過ぎました。
学校に戻った先生方は、今度は、この「学び」をアウトプットし合います。一人一人に割り当てられた3分の時間が「全く足りない!」ほど、楽しそうに、豊かに自分の体験した地域の魅力を語り合う先生方の姿がありました。

このような先生方の学びを支えたのが、研修主任の下平先生が「悩み抜いた末(本人談)」考案された「視点カード」です。「つながり」「くらし」「景色」など、「素材を見つめる視点」をカードとして用意し、先生たちがそれらをもって接することで地域素材の「価値」を見出せるように工夫されました。

今年も開明小では、校内研修を通して「主体的・対話的」に学びを楽しむ先生方が、それぞれの教室で子どもたちと「学びを楽しむ」歩みを重ねていきます。
リーディングスクール 旭町中学校
生徒が創る学校、そして深まる連携(篠田先生にインタビュー)
旭町中学校では、リーディングスクール2年目を迎え、「生徒が創れる学校」を目指しています。篠田先生は、教師が生徒の「やりたい」を引き出し、それを実現できる環境づくりや支援のあり方を探究しています。
学校全体には、生徒主体を尊重する気風が生まれつつあり、特に学級では生徒のアイデアが形になり始めています。今後はこの動きを学年、学校全体へと広げ、「生徒が創る瞬間」に光を当てていきたいとのこと。先生方も各自が「プチチャレンジ」に取り組み、学びを深めています。
先日行われた小中合同ワークショップは、先生方の内にあるものや「話したい」気持ちを引き出す場となりました。企画段階から先生方の意見を尊重し、対話を重ねたことで、「よりよくなりたい」という意欲や、気兼ねなく話せる関係性の重要性を改めて実感したそうです。参加した先生方からも、「知らない先生とテーマを持って楽しく話せた」「相手を否定しない大切さを学んだ」「堅苦しくなく自分の意見が言えた」といった前向きな感想が寄せられました。研究主任としては、今後も意図的に先生方との対話や研修の機会を増やしていきたいと語られました。

今後のチャレンジとして、7月のKJK(気軽に授業を公開しよう!)での授業公開にプチチャレンジや小学校の先生方の参観を絡めること、生徒が主体的に活動する様子、特に1学年の個人探究で生まれる学びや非認知的能力の高まりなどを捉え、発信していくことを挙げられました。
旭町中学校は、旭町小学校と連携をふかめつつ、生徒と教師が「共に創る」学校づくりを進めています。
リーディングスクール・アソシエイト校 筑摩野中学校
「問い」のシンカを目指して
筑摩野中学校は、2年前より「協働の学び~対話を基盤とした授業づくり~」をテーマに4人グループでの学びに取り組んできました。今年度は「協働的で探究的な学び」をテーマにより深い学びをめざし、「広げる問い」「深める問い」「高める問い」の3観点で「問い」に重点をおき、問いのシンカを目指します。
5月1日には麻布教育ラボの村瀬先生を招き、授業クリニックを行いました。
全職員で参観した1年生の理科。先生は初めに10種類の植物の名前や特徴の書いてある短冊をグループに配布し「分類するとしたら?」と問いかけます。わずか30秒の導入で、生徒たちは「同じ説明どうしでまとめてみよう」「これはどうする?」と対話し「分類の仕方」について考えだしました。その後、一人ひとりが分類チャートを思い思いに作成し、グループ内で交流しました。「いいね!」「なるほどね」という言葉が飛び交いました。

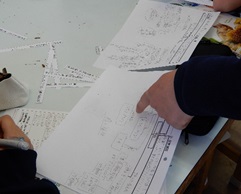
「教えたいことを生徒自身に発見させる授業であり、理科好きの生徒が育っている、安心感のある授業」(村瀬先生評)を通して、問いの大切さ、協働的な学びのよさを先生たちみんなが学び合いました。
また、5月7日には第1回LG(ラーニンググループ)研究会を開き、4人グループで「問い」について体験的に学び合いました。生徒のどんな具体的な姿が「広がった」「深まった」「高まった」のかについて、教科の枠を超えて生徒の姿を熱心に語り合う先生たちの姿がありました。

今年度も学校全体で「対話を基盤とした協働の学び」を推進していきます。
令和7年5月19日更新
リーディングスクール 梓川小学校
先生方の存在の大きさが改めてわかりました!
今年度から「その子がその子らしく学ぶ探究的な授業の実現」をテーマに、リーディングスクール校として歩み始めている梓川小学校。
5月12日、今年から研究主任になった山守先生が中心になり職員研修を開催しました。最初に研修の目的と本日の流れを説明し、5つのグループに分かれ、アイスブレク後、和やかな雰囲気のもと研修は始まりました。
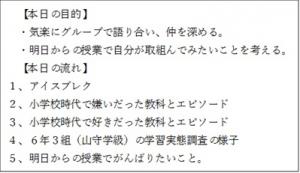
「嫌いだった教科とエピソード」は、「体育が嫌いだった。走るのが遅くて、おまえがいると負けるからと避けられ、先生が守ってくれなかった」など、小学校時代を思い出し、グループごと楽しそうに思い出を語り合っていました。「好きだった教科とエピソード」では、「国語で、本を読むのが好きだった。音読を先生に褒められた」「理科で、専科の先生が好きだった。自分たちで自由に授業をやらせてもらった」など、先ほど以上に目を輝かせて語る先生方の姿が印象的でした。

ファシリテーター役の山守先生が、「嫌いだった・好きだだった教科とも、先生方の影響が大きいことが改めてわかりました。私たちが何気なく毎日子どもたちにかけている言葉が大きいですね」とまとめると、先生方も「本当だ」「そのとおりだ」と大きく頷いていました。
最後に「明日からの授業でがんばりたいこと」を一人一人短冊に記しました。

研修を終え、山守先生は、「先生方がとても協力的で、予想した以上に楽しそうに話してくれたので、とっても嬉しかったです。次回もがんばります」と手応えを感じていました。今後の梓川小の挑戦が楽しみです。
リーディングスクール 中山小学校
新たな問いを立て、歩みを踏み出す先生たち
これまでリーディングスクールとして、全校での「探究の学び」の実践をしてきた中山小学校。3年目を迎える今年度、「探究」をベースとした「インクルーシブの実現」「教科横断の学びへの挑戦」の2点をあらたな重点として先生方は決めだしました。子どもの願いを大切にした「心ゆく学び」の中で、すべての子どもが個性を輝かせながら確かな力を育む学びの実現を目指します。
研究のスタートにあたり、先生方全員が「風越学園岩瀬校長先生に学ぶ学級づくりワークショップ」に参加し、すべての子どもが安心して互いのコミュニケーションを深められる学級づくりのあり方を学び、まなざしを共有しました。
そして5月12日、2つの研究グループが、それぞれの公開授業の構想の検討をしました。それぞれの授業者の先生が語る「願い」や子どもたちの様子を踏まえ、先生方がフランクに対話を重ねながら授業づくりを行う「チューニング」のスタイルが中山小では定着しています。「教師が余計な一言を言っちゃうと『探究』じゃなくなっちゃう…」というつぶやきなど、子どもの意識を大事にして授業に創りたい!というスタンスが先生方に共有されているのが感じられます。

このように新たな「問い」を設定し、さらなる「探究」の歩みを踏み出す中山小学校の先生方です。
学びの改革リーディング校 丸ノ内中学校
生徒とともに歩む忠恕の時間
昨年度、丸ノ内中学校では「忠恕の時間(総合的な学習の時間)」を中心に、生徒が自らの興味・関心から問いを立て、課題を設定し、仲間と協働しながら調査・分析を行い、思考を深める姿が見られました。こうした活動は、生徒一人ひとりの学びを深めるだけでなく、他者や社会へのまなざしを育む貴重な機会にもなっていました。
一方で、昨年度までの様子から、興味関心をもとにテーマを決めたものの、調査の方向性が定まらず、インターネット検索に終始してしまうグループもありました。そうした様子を受け、担当の先生はそのグループが、なぜそのテーマに取り組んでいるのかという原点に立ち返りながら、どのような「問いかけ」が効果的かを模索しました。後日、先生の一言が生徒の探究活動のきっかけとなり、活動が大きく動き出しました。
この経験から、教師による「良質な問い」は、生徒の探究的な学びを支える重要な要素であることが改めて実感されました。また、教師自身が生徒の興味関心や活動内容を理解し、見通しをもって関わることの重要性も再認識されました。
そこで、今年度の第1回職員研修では、生徒のこれまでの姿や取り組みに加え、PPDACサイクル(Problem・Plan・Data・Analysis・Conclusion)を意識しながら、生徒の興味・関心から問いを立て、課題を設定し、データに基づく探究を進める視点を共有しました。続く第2回の職員研修では、探究活動の中でも特に難しさを感じやすい「問いを立てる」場面に焦点を当て、教師自身が生徒の思考のプロセスを追体験する機会としました。
今後も、これまでの取組から見えてきたことを生かし、職員研修を有効に使って、生徒の学びを支援していきます。
 生徒の「問いづくり」の思考をたどる先生方
生徒の「問いづくり」の思考をたどる先生方
令和7年5月12日更新
リーディングスクール 並柳小学校
先生方の「小さな一歩」がつなぐ探究の輪 ~並柳小WS~
並柳小学校では、4月16日の教職員ワークショップ(以下WS)に続き、5月9日に第2回WSを開催しました。前回のWSで先生方一人ひとりが掲げた「小さな一歩(プチチャレンジ)」をふり返った後、改めて「探究的な学び」について考えました。
グループワークでは、「探究的な学びとは何か」をテーマに、子どもの主体性を大切にし、知識を「教え込む」のではなく子どもに「伴走する」、答えを提示するのではなく「問いを広げる」、そして子どもの試行錯誤を温かく「見守る」ことの重要性が共有されました。
WSの最後には、先生方一人ひとりが今後の具体的な「小さな一歩(チャレンジ)」を考え、それを記入したカードをみんなで見合いました。「子どもの失敗を見守る」「子どもの『なんで?』に寄り添い、発想をいかす」「知る喜び、感動のある授業を創る」「児童理解を深め、効果的な助言を目指す」といった具体的なチャレンジが書かれ、子どもの主体性を尊重し、学びの質を高め、教師自身も成長しようとする前向きな姿が見られました。

子どもたちの「なぜ?」「どうして?」という知的好奇心を大切にし、主体的な学びを支えるために、今後も授業研究や教師自身の探究プロジェクト等を通じて、学校全体で探究的な学びを進めていく並柳小学校です。
リーディングスクール・アソシエイト校 筑摩小学校
運動会をみんなでつくろう!
今年度からアソシエイト校としてさらなる歩みを進めている筑摩小学校。今年度は「子どもたちの主体性を育てる授業づくり」をテーマに、「自由進度学習」「フリースタイルプロジェクト」のさらなるシンカに加え、運動会や音楽会などの「学校行事を子どもたちとつくろう」プロジェクトを始動しました。
このプロジェクトに向けて、教務主任の北野先生が、3月に3年生~5年生の子どもたちに概要を説明し、募集をしたところ、「自分からやってみたい」と11人のメンバーが集まりました。そして「今までより楽しい運動会、みんなでつくる運動会にしたい」という願いを共有し、次のように運動会の目的を決め出しました。
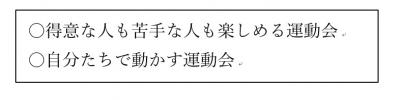
4月下旬のプロジェクト会議では、この目的に向かい、形式的になりがちな「開会式、閉会式」をもっと楽しくしたいと、お互いのアイディアを出し合いました。「開会式で集まったら、みんなでジンギスカンなどのダンスを踊ったら楽しいんじゃないかな」「閉会式に、保護者の方へのインタビューを入れてみたらどうだろう」などのアイディアがいくつも出されました。今後は、児童会にも協力を依頼し、委員会ごとの仕事分担を具体的に決めていく予定です。

本番は5月31(土曜日)。“みんなでつくる運動会”を目指した、子どもたちと先生方との挑戦が続きます。
リーディングスクール・アソシエイト校 清水中学校
一人一台端末を活用した授業づくり研修
「子どもの自己決定を促す授業づくり」を全校研究テーマに据えた今年度のスタートにあたり、文部科学省学校DX戦略アドバイザー事業企画調整委員長の東原義訓先生(信州大学名誉教授)をお招きして、職員研修が開催されました。
東原先生からは、清水中学校が目指す「自律を育む学校」はまさに、これからの未来を生きる子ども達にとって大切な方向であることを価値づけていただきました。変化の激しい不確実な社会の中で、学びを通じて自分の人生をかじ取りし、社会の中で多様な他者と共に生きる力を育むことは、一人ひとりが自律することに他ならないと教えていただきました。
さらに、自律を育むための授業改善の視点も示されました。学びを主体的に調整できる学習者を育むためには、多様な他者との対話や協働をとおして新たな価値を生み出すことが大切であること。単に対話の場を設定するのではなく、一人一台端末を活用した対話のレベルを意識した授業づくり(写真参考)を進めることを教えていただきました。
研修後にある先生は、対話のレベルを意識することで、ねらいをより明確にした授業づくりができそうだと語られました。早速、翌週には、問いやグループ編成等など授業構想を練り直して実践されました。
子ども達にとってよりよい授業を追求し続ける清水中学校の先生方です。

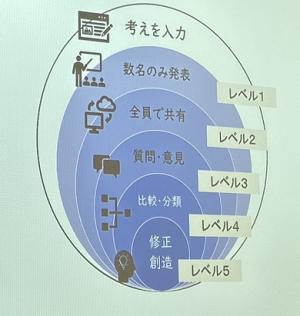
令和7年4月28日更新
リーディングスクール 旭町小学校
「ゆる研」の魅力に迫る
今年度リーディングスクールとなった旭町小学校では、先生方が主体的に楽しむ研究活動「ゆる研」が始まりました。研究主任の金宇先生にお話を伺いました。
Q: 「ゆる研」とは、どのような研究活動ですか?
「ゆる研」は、先生たちが共通の課題や願い、「やりたい!」という熱い思いで集まり、グループを作って研究を進める場です。与えられたテーマではなく、自分たちのペースで繋がり、楽しみながら、ゆるく、でも深く、研究を掘り下げていくことを目指しています。
Q: 今年度は、どのようなグループが活動していますか?
今年は、「プロジェクト活動グループ」「学びとくらしをデザインできる子どもと教師の授業づくりグループ」「対話やトライ&エラーを大切にできる子どもと教師の学級学年づくりグループ」の3つが発足しました。
Q: 4月9日の「ゆる研びらき」は、どんな様子でしたか?
自己紹介アイスブレイクで和やかに始まった後、グループごとに分かれました。これまでの実践をふり返り、自分の課題や願いを共有。模造紙や付箋も活用しながら、今年度の研究計画について話し合いました。

Q: 先生方の反応はいかがでしたか?
最初は少し緊張気味だった先生方も、次第に笑顔や笑い、時には拍手も生まれ、活発な意見交換がなされました。気づけば予定時間を超えるほど議論は白熱し、先生方の「子どもたちのために、もっと良い教育をしたい!」という熱意が伝わってきました。最後には、各自Googleスライドで気づきや感じたことを記録するリフレクションタイムも設け、静かに自分と向き合う時間も大切にしました。「ゆる研」の素晴らしいスタートを切ることができたと感じています。
終始笑顔で、熱く語る金宇先生の姿も印象的でした。さあ、旭町小学校の先生たちの「ゆる研」が始まりです。
リーディングスクール 岡田小学校
「のびのび・わくわく・どんどん」を目指して
岡田小学校は今年度より、リーディングスクール実践校として、「子どもが主人公」の学校づくりへの歩みをスタートしました。岡田小学校の学校づくりのテーマは「のびのび表現・わくわく学び・どんどんチャレンジ」。これを子どもたち、先生たちみんなで共有して、毎日の取組を重ねていきます。
岡田小の研究で大事にしているのは、先生たちも「のびのび・わくわく・どんどん」学ぶこと。「先生たちも探究的に学び、お互いに聴きたいことをどんどん聞き合える、そんな研究をめざしたい」と研究主任の伊藤先生は語られます。そのために、先生方のコミュニケーションの機会をたくさん位置付けています。4月の重点研究会は、先生たちが「自己課題」について、思いを語り合うことからスタートしました。グループを組み替えながら交流を重ねる中で、話し合いが一層活発になり、先生方の「問い」がぐんぐん深まり、具体的になりました。

さらに、4月22日に行われた市の研修「学級づくりワークショップ」(講師:軽井沢風越学園 岩瀬直樹先生)には、すべての先生が参加し、3時間たっぷり楽しみながら学びました。「例えば『リワイヤリング』といえば、先生たちみんなが『あの感じ!』とイメージと実感を共有し実践に活かせるなど、全員の『共通言語』ができたことが大きな成果でした!」(校長先生)
岡田小学校の先生方は研修意欲も旺盛です。松本市の教職員研修には前述の「学級づくりWS」以外にも全部で50回の研修にエントリーされました。職員室におかれた「研修計画」冊子には先生方の貼られた付箋がびっしり。
「のびのび、わくわく、どんどん」を目指し、「主体的な学び」に踏み出した岡田小学校の先生方です。
令和7年3月24日更新
リーディングスクール・アソシエイト校 開明小学校
1年間の学びを語る先生方
2月19日、開明小学校では、先生たちによる「1年間の学びのアウトプット」を実施しました。
先生たち一人一人が、願う子どもの姿「『学び』を楽しむ子ども」を目指して設定した自己の課題に一年間取組んできた、その学びのあしあとを、各ブースでアウトプットしました。
会場には、開明小の先生方のほか、保護者・地域の方も参加され、先生方の「学びの語り」に耳を傾けました。参加された先生たちは「本当に楽しかった!」と口々に話されます。
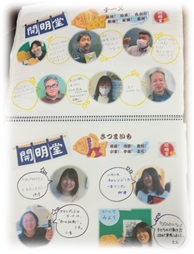
初めて「単元内自由進度学習」に取組まれた柏原先生は「どの子も生き生きと学び、理解度を高めました」とその手応えと「ひとり一人の学びのよさがよく見えるようになりました」とご自身の子ども観の変化を語られました。
また、「子どもたちの自己肯定感を高めたい」という自己課題に取組んできた保科先生は「今では子どもたちがそれぞれの方法でアウトプットを楽しむようになりました」と子どもたちの成長を話され、また「先生たちに相談する機会が増えました」と、学び合い、支え合う開明小の先生たちへの感謝も語られました。
このような開明小の研究推進を担ってきたのは、研究主任の横澤先生、教務主任の武田先生、研修主任の下平先生。いつも相談しながら「先生方の学び」づくりを進めてこられたということです。
「先生たちが小さな『困った』を迷わず口にし、相談し合える雰囲気ができたのが大きな収穫です。」「子どもたちが様々な場面で失敗を恐れずに、主体的に挑戦するようになりました。」「『私たち成長したでしょう?』という子どもの声を嬉しく聞きました」と、それぞれの「確かな手応え」をお話しされました。

「決して、うまくいったことばかりだったわけではありません。」と、横澤先生。「でも、悩みこむたびにみんなに相談し、助けてもらいながらやってきました。」
ご自身の、そして先生方の「学び」を豊かに語られる先生方。それぞれの先生方の胸に、価値ある学びの物語が確かに刻まれた開明小学校の1年であったことが、お話から強く伝わりました。
リーディングスクール 清水中学校
話すことだけではない、新たな方法による表現力の育成
「表現力が育つ~すべての活動を通して~」を全校研究テーマに据え、表現することについて生徒も教師も共々に意識をして取り組んできた清水中学校。今年1月のアンケートでは、「学級の活動の中で自分の表現力を生かした活動ができているか」という質問に肯定的に回答した生徒の割合は、9月よりも13.4%増え、8割を超える生徒が肯定的に回答しました。表現することを意識している生徒が増えてきた一方で、自分の意見を言う勇気がないという生徒もいる現状も把握しました。学級・学年・全校での様々な活動において、多様な意見にふれた上でよりよい合意形成をしていくことが欠かせません。
そこで2月の校長講話では、話す・聞くだけではない新たな意見交流の在り方として、全クラスでクラウドによる同時共同編集機能を用いた活動が取り入れられました。はじめに、校長講話を聞いて感じたことをスプレッドシートに入力しました。次に、1人の入力に対し複数の級友が「なるほど」と思ったことや友達に聞きたいことを入力しました。写真は、あるクラスでの意見交流の場面です。席が近い4、5人のグループで話し合っていましたが、クラス全員のコメントがリアルタイムに更新されていく画面を見ながら、席が離れた級友の意見も取り入れながら話し合っている姿です。

終了後、別のクラスの先生から、「普段の授業や話合いでは発言が少ない〇〇さんですが、今日のこの1時間の最後に書いた記述では、最初に入力したものよりも記述量が3倍近く増え、内容もよく考えられているんです。」と生徒の姿を語っていただきました。同時共同編集機能の活用により、瞬時に多様な意見に触れること、そして、瞬時に級友からフィードバックが入ることにより、話合いだけでは見られなかった姿が確かにあったのだと言えます。
多様な表現方法によって、さらに清水中学校の生徒が成長していく場面に立ち会うことができました。
学びの改革パイオニア校 開智小学校
開智小の探究的な学び:子どもと教師が共に成長する一年
今年度は「子どもに委ねる探究」をテーマに掲げ、教師は伴走者として、子どもたちの主体的な学びを支えることに力を入れてきました。この一年のあゆみと来年度の展望について、探究コーディネーターの江口先生にインタビューしました。
「今年1年間、子どもに委ねる探究を大事にしてきました。その中で、先生方の意識が変わり、子どもたちの考えや思いを聞けるようになったことが大きな変化でした。先生方の変化は、研修会や普段の重点研究会などを通して、先生同士が話し合う機会を増やしたことで生まれました。お互いの考えを聞き合うことが大切だと改めて思いました。
具体的な変化としては、教師主導になりがちだった授業を、子どもたちの声に耳を傾けながら進めるようになった先生や、子どもたちの失敗も大切な経験として位置づけ、子どもたちの『やりたい』という気持ちを尊重するようになった先生など、様々な変化が見られました。先生方は、問いを意識するようになり、子どもたちに問いかけることで、子どもたちの主体的な活動の広がりが見られるようになりました。これらの変化は、研修会での対話だけでなく、授業公開や互いの実践を共有するチューニングなどを通して、先生方が互いに刺激し合い、学び合ったことが大きかったと思います。
来年度に向けては、S君のように『今年の探究は自分の好きなことができたから楽しかった』と、主体的に探究活動に取り組む姿や、異学年探究で、異なる学年の子どもたちがお互いの知識や考え方を共有し、アイディアを広げることができたことから、希望学年でテーマ別縦割り総合や学年総合を行いたいと考えています。」

江口先生は、今後も子どもたちの思いを大切にし、子どもたちに寄り添いながら、伴走する職員集団を目指し、校内研修のあり方も考えています。開智小学校全体で、子どもたちが「自他を認め合い、自分らしく学び続ける学校」を目指し、挑戦を続けていきます。
学びの改革パイオニア校 波田中学校
「全員が主役」の学校づくりを目指して ~ 波田中の挑戦 ~
波田中学校では、「全員が主役となる学校」を目指し、生徒と共に学びを創ることに取組んできました。今年度、初めてリーディングスクール・フェスに参加し、1年間の歩みを発表した横山先生と、研究主任の藤原先生に、その手応えを伺いました。
横山先生は、次のように話されます。「初めてフェスに参加し、その熱気に圧倒されました。他校の先生方が波田中の実践に関心をもってくださり、とても嬉しかったです。同時に、他校の取組みから学ぼうとする熱意もすごいと感じました。発表を通して、日頃からもっと視野を広げ、学校全体を見ていく大切さを実感しました。また、波田中は職員室の雰囲気も温かく、授業準備をしていると周りの先生方がアドバイスをくれるので、とても助かっています。先生同士が授業について語り合う姿を見ると、自分ももっとがんばろうと思えます。生徒たちも『自分たちで楽しんでやろう!』という意欲が強く、その姿勢に刺激を受け、私自身もさらにチャレンジしようという気持ちになりました。」

藤原先生は、この2年間の変化について次のように振り返ります。「今年度は、先生方の研修意欲の高まりを特に感じています。研究通信を読んでくださる先生が多く、『A先生の実践はすごいね。参考にしたい』『教材研究のヒントになった』といった声をいただくことが増えました。職員室でも生徒や授業について語り合う機会が増え、昨年度よりも校内公開授業を見に行く先生が多くなりました。また、今年度は小中連携の取組みがさらに進展しました。特に 10月末には、小学校の授業を自由に参観できる時間を設けたことが大きな成果となりました。同じ教科や学年の先生同士が気軽に声を掛け合い、波田小を訪れて授業づくりについて語り合う姿が見られました。来年度も授業を変えようとチャレンジする先生方を支えていきたいです。」

波田中では、今後も学年や教科の枠を超えた対話を大切にしながら、「全員が主役となる学校」を目指し、挑戦を続けていきます。
令和7年3月17日更新
リーディングスクール 開成中学校
開成中の2年間の歩みを振り返る(市教委担当者の視点から)
前回、2学年の「『総合的な学習(開成タイム)』発表会」を取材したWebページの結びに「開成中学校の2年間にわたるリーディングスクール事業を通した取り組み。その1つの区切りの姿として、大変印象深い光景でした」と記しました。
この2年間の取り組みは、大袈裟ではなく、開成中にとって『革命』と表現すべき大改革だったと感じています。長年にわたり「総合」では行事に関連した定型的な学習を主として行ってきた開成中が、『「教師が教える学校」から「生徒が学ぶ学校」へ』を研究テーマに据え、「探究的な学びとは?」を考えるところからスタートし、教科毎に「探究的な学び」に挑戦した1年目、「生徒が自らの学びをデザインする学校づくり」をテーマに据えて、「各教科における探究的な学び」を土台に「総合的な学習の時間」に一本の軸を通した2年目を経て、生徒自身が、「こういうことをやりたい」「こういう自分になりたい」を実現する学校が形づくられてきました。
冒頭に紹介した1月31日の開成タイムは、本当に印象深い光景でした。しかしそれは、あくまで1つの通過点であり、「開成革命」が3年目を迎える来年度はさらなるシンカが進むことでしょう。今の2年生が秋になって行う総合的な学習発表会では、いっそう、自由に、深く学ぶ子どもたちの姿がそこにある!そんな期待をしています。来年度も益々開成中学校から目が離せません!

1月31日の発表会の日、廊下には「『CIC』メンバー募集中」のポスターが掲示されていました。CICとは「Comfort Improvement Committee」の略で、2学年生徒会の「居心地向上委員会の略称です。
探究的な学びを通して、開成中学校の生徒の中に自治の精神が芽生え始めています。1月31日は、「授業」の中だけにとどまらず、自らの手で学校をよりよく変えていこうとしている生徒が育っていることを実感する機会にもなりました。
リーディングスクール 筑摩野中学校
ICT活用で協働の学び
昨年度から「協働の学び~対話を基盤とした授業づくり~」を研究テーマに4人グループでの学びに取り組んできた筑摩野中学校。一人一台端末もその学びに大きく貢献しています。
1年生の体育の授業では、「『切り返し』に詰まっている剣道の大切な要素とは何か?」という問いで学習が展開されていました。大切な要素を考え(意識)しながら、練習し、仲間とタブレットで撮影し合います。動画を見ながら、豊かに言葉を交わし合う生徒たちでした。


2年生の国語の授業では、「『走れメロス』とその基になった作品『人質』とはどこが違うのだろうか?」という問いで両作品の比較読みをしました。生徒たちは書き換えられた部分、書き加えられた部分を探し、スプレッドシートにまとめていました。資料をじっくり読み込む生徒、級友の記入した内容を見ながら考え込む生徒、級友と話し込む生徒、様々な学びの姿がありました。

ある授業では「学びの足あと」として、共同編集スライドの自分のページに授業で学んだことや振り返りを蓄積し、いつでも自分や仲間の振り返りを見ることができるようになっていました。一人ひとりが真剣に入力し、記入を終えると他の人の振り返りを時間いっぱい読んでいる姿が印象的でした。

一人一台端末を活用し、他者の意見に自由に触れ、そこから自然と対話が生まれる授業が、このように、あちこちの教室で展開されています。昨年度から筑摩野中学校全体で取り組んできた「対話を基盤とした協働の学び」はこれからも進化し続けていきます。
リーディングスクール・アソシエイト校 菅野中学校
アウトプットにチャレンジ
今年度、「協働」を学びのテーマに据え、「探究的な学びの実践」「対話を重視した授業づくり」に取組んできた菅野中学校の1年生。3学期の最後の参観日にこれまで取り組んできた「探究的な学び」の成果を保護者、生徒向けに発表する「アウトプット・デー」に挑戦しました。
会場には5つのブースを設けられ、学年のすべての生徒たちがグループごとに学びの足跡を、スライドを使いながら発表します。発表を聞いた保護者や生徒からは感想や質問などがフィードバックされ、会場全体が熱気に包まれました。
参加された保護者の皆さんはうなずきながら熱心に生徒たちの発表を受け止め、「こういう形の参観日がとてもよかった」「わが子がこんな(すばらしい)発表をするなんて、いつもの姿からは想像できませんでした。」といった感想も寄せていただきました。

発表をやり遂げた生徒たちからは「緊張したけれど、楽しかった」「発表に対して質問をしてもらったこと、それに応えられたことがうれしかった」「(質疑の)やりとりがうまくできた。自信につながった」という感想が聞かれました。
菅野中学校の先生方は、今年度の取組を振り返り、「生徒の自己肯定感をさらに高めたい」「『学び』に向かう気持ちを一層高めたい」といったあらたな「願い」を見出しています。1年間の取組の中で、それらが確かに育ちつつあること、そしてそれを実現するためのヒントをたくさん示してくれた1年生のアウトプット・デーでした。
令和7年3月10日更新
リーディングスクール 明善小学校
「子どもの学びを温かく支える」
明善小学校では、昨年までの園小接続期における子どもの理解や学びのあり方の研究から得た視点を大切にし、今年度は、中・高学年の学びを充実させたいと考え、「主体的に学び合う子ども」を研究テーマに据え取り組んできました。

「学びノート」の活用や生活科を中心にやりたいことをとことん取り組める授業づくり等、低学年期の学びのあり方を整理し中・高学年期の学びはどうあったらよいか研究を重ねてきました。それは、子どもに委ねることや子どもが自ら課題解決に向けて他者とかかわり自己調整しながら取り組む姿を大切にすることの意義を改めて考え、先生方が試行錯誤しながらこれまでの授業を見つめ直すことでもありました。

2年間のリーディングスクールの取り組みをとおして、子どもの学びを温かく支えるやわらかな雰囲気が広がっています。今後も、主体的な学習者である子どもを支える先生方の取り組みは続きます。
学びの改革パイオニア校 田川小学校
1年間の探究的な学びをアウトプットしました
田川小学校では、1年を通して探究的な学びを全校で行ってきました。2月の参観日では、1年間の探究活動の成果を発表する機会が設けられました。6年生の先生は学級通信で「参観日の発表会は、おうちの方に向けたものではありながら、実は発表者自身の学びの場とすることが第一目的です」と伝えています。
参観日に至るまで、子どもたちは、ポスターの作成、発表原稿の作成、発表練習など、様々な準備に取り組んできました。ポスターの内容や構成は、子どもたち自身で考え、それぞれに工夫を凝らしていました。グループによって、クイズを取り入れたり、劇をしたり、またはゲームを用意するなど、参観者に楽しんでもらえるよう工夫していました。5年生の先生は学級通信で、「参観日は結果ですが、このようにして創っている過程にも大きな学びがあります」と振り返っています。

参観日当日、子どもたちは、自分たちの探究活動のあしあとを、保護者やお世話になった地域の方に自分たちの言葉で思いを込めて伝えました。発表後には、保護者から多くの質問や感想が寄せられ、子どもたちは熱心に耳を傾け答えていました。4年生の参観日では、5 年生が保護者の後ろに座って参加し、感想を伝えたり、質問したりする場面もありました。 発表だけで終わるのではなく、双方向のかかわりも大切にしていました。

田川小学校の参観日は、子どもたちの1年間の学びのあしあとをアウトプットする場であると同時に、子どもたちの主体的な学びや協働的な学びを育む貴重な機会となっています。
学びの改革パイオニア校 波田小学校
~「まずやってみよう!」 多様性を受容する柔らかな学校へ ~
パイオニア校として「多様性を受容する学校づくり」に2年間取組んできた波田小学校。今年度も、子どもたちも、先生方ともに「まずやってみよう!」を合言葉に「やってみたいこと・挑戦したいことを実現できる学校」を目指してきました。
三輪校長先生は「学校が柔らかい雰囲気になり、自分たちがやりたいことに挑戦しようという機運を感じます」と話されます。「今日も1年生から6年生の有志20人程の子どもたちが、休み時間に『ありがとうコンサート』を企画し演奏会を開きました。会場の音楽室には大勢の子どもたちが演奏を聴きに詰めかけました。また、6年生のあるクラスでは、総合的な学習の時間のまとめとして、『松本市の魅力を発信しよう』とCanvaでチラシを何種類も作成し、近々電車で松本駅に行き、観光客に配布してくるそうです。このように自分たちのやりたいことを『まずやってみよう。失敗したらまたやり直せばいい』という姿がいくつも見らます。」と、子どもたちの姿を紹介いただきました。

校長先生は先生方についても次のように話されます。「子どもの声を聴くことを大切にしようと変わってきたのを感じます。先生方も『まずやってみよう』を合言葉に、放課後の時間を利用し、より研鑽を深めようと自主的に研修会を開いています。職員室もとてもいい雰囲気で、日常的に授業や成長している子どもの姿を語り合っています。今は、校舎改築で移動の時間がかかるという子どもや先生の声を受け、休み時間を長くしよう!と教務主任が中心に企画提案をし、『40分授業におためしチャレンジ!』をしています。子どもが変わると先生も変わるのか、その逆なのかはわかりませんが、子どもたちと先生方が連動してチャレンジしていこうとするエネルギーを感じます」。
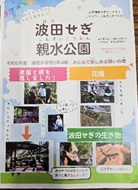
子どもと先生が「まずやってみよう」を合言葉に実践してきた「多様性を受容する柔らかい雰囲気の学校づくり」をもとに更に次への挑戦が続きます。
令和7年3月3日更新
リーディングスクール 寿小学校
「かわる授業 広がる挑戦」― 令和6年度 重点研究会まとめの会 ―
2月10日に令和6年度の重点研究会まとめの会が開催され、2年間の成果と次年度の展望について活発な議論が交わされました。
まとめの会の後半では、各学年に分かれて次年度の単元内自由進度学習の実施単元について具体的に検討を行い、子どもたちの主体性や自己調整力を重視した学習のあり方について議論が深まりました。また、学びを子どもたちに委ねることの意義や、主体的に取り組む姿勢の重要性が改めて確認され、寿小学校全体の教育活動へと広げていく意欲が一層高まりました。
今年度で2年目を迎えたリーディングスクールの取組を通じ、寿小学校の合言葉「さあ、やってみよう」という前向きな姿勢が学校全体に浸透し、次年度に向けた新たな挑戦への機運が高まっています。今後も、より良い授業・学校づくりを目指し、挑戦を続けていきます。

リーディングスクール・アソシエイト校 女鳥羽中学校
「本物」に触れる価値
自分たちで創る「飛騨高山学習」、職場体験学習など、この1年間の様々な学びの中で成長してきた自分を振り返り、「私の学びの物語」としてアウトプットをした女鳥羽中学校の2年生。令和7年度初めに行われる修学旅行のスタートに当たり、薬師寺の執事長、大谷徹奘(てつじょう)師を学校に迎え、お話をお聴きする機会を持ちました。
エネルギッシュで深い示唆に満ちた大谷先生のお話に触れ、生徒たちにとって、遠い存在であった「お寺」「お坊さん」「仏教」が、自分とつながりのある「生きた存在」に変わっていく時間となりました。
放課後は職員研修で先生たちが大谷先生のお話を伺いました。
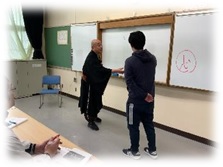

○「『自分は正しい。でも絶対ではない』ということをいつも心においてください。そう思って子どもの話を聴きましょう。」
○「『言葉』や『行動』を生み出しているのは『心』です。心を創るのはその人の『経験』『体験』。さらにその背景には『家庭、教育、地域、時代』といった環境があるのです。それを知ろうとすること」
○「その子の今の力の『10cm先』が『一番がんばれるところ』。そこに球を送りましょう」…
仏教の考え方や具体的な事例を紹介いただきながら「子どもの主体性を大事にすること」「ひとり一人をよく理解しようとすること」の大切さ、そして「心を育てること」と大切さが胸に深く落ちる、あっという間の1時間でした。
生徒たち、先生たちにとって、これからの学びに向けた「問い」を導く、大切な「足場架け」の時間となりました。
リーディングスクール・アソシエイト校 旭町中学校
Canvaで創る学校説明会パンフレット
旭町中学校では、来年度入学予定の6年生に向けて、1年生が学校紹介を行うという新しい試みに挑戦しました。これまでは先生が作成していた説明会資料も生徒たちが作ります。
授業の中でCanvaの使い勝手の良さに気づいた生徒たちは、Canvaで説明会資料を作成することを決めました。ICT支援員のサポートを受けながら、テンプレートや画像を自由に活用できるCanvaの機能をいかし、生徒たちは表現力豊かな資料作りに取り組みました。テーマ別に分かれたグループでアイデアを出し合い、共同編集機能を使って資料を完成させていく過程で、生徒たちは意見交換を活発に行い、協働性を発揮していきます。

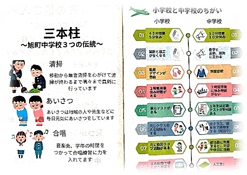
完成した資料は、見やすく分かりやすいだけでなく、生徒たちの個性や熱意が溢れる魅力的なものとなりました。この取り組みを振り返り、生徒たちは「中学校が楽しそうだなと思ってもらえるような資料になるよう心掛けた。」「見やすくてわかりやすくなるように作った。」「資料を見て少しでも中学校が楽しみだなと思ってもらえるように、見やすく楽しい感じにすることを意識して作れてよかった。」等、手応えを語りました。担当の松井先生も「表現することを楽しみ、相手意識が高まっている」と生徒の成長を喜んでいました。
旭町中学校では、夏に職員研修でCanvaの活用法について学び、その後の教育課程でもCanvaを使って授業研究会を行いました。「教師の学びは、子どもの学びと相似形」と言われるように、先生方と共に旭町中学校の子どもたちの学びもシンカしています。
令和7年2月25日 更新
リーディングスクール 筑摩小学校
「自分で学ぶって楽しい!」 ~単元内自由進度学習~
「子どもの“学びデザイン力”を育てる学校づくり」をテーマに全校で「学期に1回は自由進度学習」に挑戦してきた筑摩小学校。
2月12日、2年生の教室には 「よし、これくらいかな?」 「えっ92cm?惜しい!」「私は、95cmだった!もう少しか!」
など楽し気な声が響きました。この日、子どもたちは「100cmをこえる長さ」の学習に自由進度学習のスタイルで取組みました。

授業が始まると、子どもたちは、1mのものさしを手に取り、教室や廊下など自分が測りたい場所へ移動。まずはテープで1mと思うところを切り、長さを測かり「1mってどれくらい?」を体感しました。次に黒板の高さや机の幅、教室の入口など、長さを予想し、測定を繰り返していきました。中には教室の入り口を測りたいという共通の目的から一人がものさしの端を押さえもう一人が目盛りを読んだり、二人で1mものさし2本と30cmものさしをつなげて協力して廊下の横幅を測ったりする子どもの姿も見られました。測定が終わり、「mをつかった長さの計算」に挑戦する子、「他にも1mくらいのものを探したい」と意欲を見せる子、それぞれが自分のペースで学びを深めていきます。


振り返りの場面では、「れんらくこくばんのたての長さがいがいにみじかくてびっくり。87cmしかなかった」など実体験にもとづくまとめが記されました。
自由進度学習を通して、子どもたちは、自分で考え、自分のペースで学びを進める「自己調整力」を身につけています。
筑摩小学校の先生たちは、こうした経験をどう日々の授業にいかし「子どもの自ら学び、デザインする力」を伸ばしていったらよいか試行錯誤を続けています。
学びの改革パイオニア校 開智小学校
学びのシンカ:開智小学校における探究的な学びの深化と進化
「子どもに委ねる」ことを大切に、子ども主体の探究的な学びを進めてきた開智小学校。 今年一年間、先生方がどのような実践を重ね、子どもたちと学びを育んできたのかを語り合う、研究まとめの会が行われました。
全体会では、リーディングスクールフェスでアウトプットとフィードバックの大切さを体験的に学んだ江口先生より、 オープンクエスチョンや相づちといった聞き手の役割と、アウトプットする先生がどんなフィードバックが欲しいのかを伝えることの必要性が語られました。
会が始まると、 先生方が一年間の取り組みを、スライドや写真、ポスターや実物などを用いて、子どもの姿を通して語り合いました。聞き手の先生方も、発表者に質問したり大きくうなづいたりするなど、 お互いに話しやすい場となっていました。


発表された内容は多岐に渡り、水族館をテーマに総合的な学習をしたクラスでは、スタンプ作りや音楽を作曲などを通して、一人一人が経験を生かしながら一つの水族館を創り上げていったそうです。水族館という多様性あふれるフィールドが、子どもたちのアイディアの可能性を広げたことが感じられました。また、開智学校の掃除をしたクラスでは、普段の清掃のあり方も見直し、より清掃に対して前向きになったという報告もありました。飴について探究した子どもたちを伴走した先生は、初めてあめ市に行き、人とのつながりを体験的に感じたというエピソードも紹介されました。
パイオニア校2年目を終え、 開智小学校は、今年度見えてきた「子どもに委ねる」ことの良さをさらに深掘りし、新たなことにチャレンジします。異年齢の探究、教科学習における探究など、探究ベースの学びをさらに発展させていく予定です。
学びの改革パイオニア校 丸ノ内中学校
探究の芽生え、そして未来へ ~丸中 Jr.学会~
2月17日に第5回丸中Jr.学会が開催されました。1、2年生が探究的な学習の成果をポスターセッション形式で発表し、会場は生徒たちの熱意と真剣な眼差しで溢れていました。
1年生にとっては、中学校で初めての本格的な探究的な学習。丸ノ内中学校が大切にしている「批判的思考力、創造的思考力、論理的思考力」を育むために、先生と共に学びながら、興味関心のあるテーマを探究してきました。初めての経験に戸惑いながらも、仲間と協力し試行錯誤しながら、探究の第一歩を踏み出していました。
2年生は、昨年の経験を生かし、夏休み明けからテーマ選定、計画立案、実験・調査、考察、まとめまでを自分たちの力で進めてきました。昨年度からの学びを生かし、より専門的な探究に挑戦していました。発表の言葉にも力が入り、質疑応答も実物を見せたり根拠を示したりしながら話し、自分たちの探究を楽しんでいるようでした。
どのグループも個性豊かなテーマを設定し、工夫を凝らした発表を行っていました。校地内外で採れる野草を調理、加工して食用にする過程で、試食して得た感想をレーダーチャートにまとめて比較したグループ。髪の毛の悩みに関する市街地での調査結果をもとに、髪の毛の痛みを数値化して検討し、ニーズに応じたヘアシャンプーのおすすめを考えたグループ。参加した開智小学校の5年生、保護者・地域の方も興味深く聞き入っていました。


生徒にとって一つの通過点として位置づく1,2年Jr.学会。教科等横断的な視点からの教科学習をこえて育まれる問題解決の力や、数学で学んだ統計を使った根拠の示し方等、様々な学びを総合的に結び付け、発揮しながら、引き続き、生徒の探究は続いていきます。
令和7年2月17日 更新
リーディングスクール 中山小学校
新たな取組み「ニコニコタイム」
中山小学校では水曜日の給食後に位置付けられている「わくわくの時間」を使って、クラスでの遊びの他に、なかよし班で遊びの内容を話し合って決め(ニコニコミーティング)、次の週にその遊びを楽しむ(ニコニコタイム)取組みを1年間続けてきました。全校縦割りの6つのグループに分かれ、6年生を中心にグループ内の意見を調整してニコニコタイムを迎えます。
この日は、児童会の引継ぎに合わせ、5年生による2回目の運営でした。校舎全体を舞台にした「全校かくれんぼ」を企画したあるグループでは、「鬼」決めを行っていました。低学年の子を中心に立候補者がたくさん出ました。すると、5年生を中心に、「どうやって決める?」「じゃんけんでいい?」などの声掛けがありました。「(じゃんけんで)いいよ」と鬼の立候補者が応えます。「じゃあ、じゃんけんでいいですね。いくよ、じゃん・けん・ぽん」で、鬼が決まりました。鬼になれなかった子どもも出ました。しかし、不思議と不満の声は出ませんでした。
何気ない場面ですが、「自分たちが納得した決め方だから、その結果を受け止めますよ」という雰囲気が感じられました。子どもたちは民主主義を学んでいるのです。多様な他者と、意見を交換しながら折り合いをつけ、みんなで決めたことをみんなで楽しむ。そんな素敵な時間が流れています。


リーディングスクール 鎌田中学校
アルプちゃんとくまモンの夢のコラボレーション!
総合的な学習の時間「KMDタイム」では、「私たちはこの地域のために何ができるか」を問いの出発点として学びを深めていきます。2年生のある学級は、高齢者との交流を深めたいと考えています。松本市の高齢者は若い世代と関わる機会が薄れている現状にあることから、「紙芝居」を通じて交流することが、私たち中学生にできる役割ではないかと自覚するようになりました。
この紙芝居には、熊本県PRキャラクターのくまモンが登場します。紙芝居は、アルプちゃんがくまモンに松本の魅力を伝えるという内容です。アルプちゃんは、実に案内上手です。松本を訪れたくまモンは、松本城に入り、天守閣に続く急な階段を体験します。そして松本名物のそばとおやきに舌鼓。その後、四柱神社に行くと、松本ぼんぼんの音色に心を奪われます。美ヶ原温泉で汗を流し、見上げた空には、満点の星が輝いています。松本の魅力に魅了されたくまモンはきっと満足して帰郷したものと思います。
担当する生徒は、「今は、(高齢者)施設に行っているけれど、紙芝居を通じて、元気になって、こういうところに行きたいと思ってほしい」「(高齢者への発信だけでなく)松本の魅力を、外国の方にも発信して観光に来てほしい」と述べています。生徒の思いが、筆先から鮮やかな色彩となってキャンバスに広がり、生き生きと表現されています。

リーディングスクール・アソシエイト校 梓川中学校
後輩にエール! 6年生に届けた中学校生活の魅力
梓川中学校1年生は、総合的な学習の時間を活用し「SDGsを知ろう・気づこう・楽しもう」というテーマで活動しています。今回は特に「住み続けられるまちづくり(SDGs目標11)」に焦点を当て、地域のつながりを意識しながら学びを深めてきました。
そんな中、取組んだ活動が「地域の後輩たちに中学校の楽しさを伝えるよう!」。1月に行われる梓川小学校6年生の中学校参観に向けて、「中学校っていいな!」と感じてもらえる紹介動画を作成しました。動画では、「中学校生活・部活動・授業風景・梓流祭」など、1年生が実際に体験してきた楽しい場面を詰め込みました。また、ただ映像を見せるだけではなく、ストーリー仕立ての寸劇を交えながら紹介することで、6年生にもより親しみを感じてもらえるよう工夫しました。
迎えた発表当日。6年生146名とその保護者が見守る中、1年生の進行役と演技者が舞台に登場しました。ユーモアたっぷりの寸劇に、会場はすぐに笑い声でいっぱいに。スクリーンには、クラスごと制作した様々な学校生活の映像が映し出され、6年生は興味津々な表情で見入っていました。動画の紹介が終わり、進行役の生徒から「感想をお願いします」と問われると、6年生からは「とってもおもしろくて中学が楽しみです」という声が寄せられました。


発表の締めくくりには、1年生から6年生へのサプライズがありました。「自分たちも6年生の頃は、不安だった。でも実際に中学校に入ったら、楽しいことがたくさんあった。その気持ちを伝えたい」。そんな思いを込めて、1年生一人ひとりが6年生一人ひとりに書いた手紙をプレゼントしました。
寸劇を担当したある生徒は、「中学校は大変なこともあるけど、楽しいことの方が断然ある。その思いを6年生に届けられてよかった。安心して入学してほしい。」と語りました。

「中学校は楽しい場所だよ!」という思いを、自分たちの言葉と表現で6年生に届けることができた1年生。この経験は、自分たちの思いを伝えるという大きな学びとなったことでしょう。
令和7年2月10日 更新
リーディングスクール 清水中学校
長いスパンでのその子の成長のストーリーに軸足を置いた授業研究会
岩川直樹先生(埼玉大学教授)・中村麻由子先生(大東文化大学准教授)を校内研修の講師に招き、2月5日に研究授業と授業研究会が行われました。2年生の国語は、自分の好きな歌詞の工夫とその効果について、表現の特徴に着目して交流し合う活動でした。授業研究会では岩川先生から、「すごく深い授業だった。今日は『これを言いたいけど、言えない』ことを助けてもらう授業だった。こういう子どもと子どもの関係性が修学旅行につながっていくと考えられている。これはまさにカリキュラムだ。教科のカリキュラムではなく、自己形成のカリキュラムだ。それぞれの子どもの表現がひらかれるとはどういうことか。どの子も迎え入れる清水中学校の風土をずっと続けてほしい。」というお話をいただきました。
1年生の道徳は、哲学対話の一つの手法である「本質観取」を用いて「思いやり」について考え合う活動でした。岩川先生からは、「『思いやり』と『おせっかい』について、子ども達が悶々としていた。きれいな答えが必ずしもあるわけではない。4人組で一定の解釈を見出したが、その向こうに新たな問いが見えてくる。これが哲学ではないか。しかも、言葉だけでなく、自分の経験をくぐって考えようとするから、悶々とする。これは、子どもと一緒に活動をしている教師と子どもにしかできない哲学だ。」というお話をいただきました。
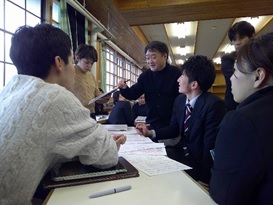
「参観した授業での子どもの姿をきっかけに、その子の成長のストーリーを語り合う場」という趣旨を共有しての授業研究会では、長いスパンでの子どもの成長について語り合われました。他教科の同僚と語り合うことで、自分一人では気づいていなかったその子の成長エピソードを知ることができ、ある先生は「結果や点数による自分と友達の比較ではなく、頑張っていることを先生も友達も認めてくれていることの実感そのものが、その子の成功体験となっているのではないか」と語られていました。「教育実践の生成過程を振り返る今日のような授業研究会を通して、教師が成長し、子どもが成長していく」という岩川先生の言葉で授業研究会が締めくくられました。
全校研究テーマ「表現力が育つ~すべての活動を通して~」の具現を支える「教師と子ども、子どもと子どもの温かな接点」について見つめ直す一日となりました。

リーディングスクール・アソシエイト校 島立小学校
対話で振り返る「1年目の挑戦」
「学びのスタイルのアップデート」をテーマに全校で「単元内自由進度学習」に挑戦してきた島立小学校では、2月10日に「研究まとめの会」を行いました。
例年、この会は先生たちの「実践発表」を主な内容として行ってきましたが、今回は数名のグループで、実践してみた手応えや成果、困ったことや課題など、それぞれの「思い」を交流する「対話の場」となることを願い、「ラウンド・スタディ」形式で実施しました。

「自分に学び方が任されると子どもたちはこんなに動く、という発見があった」「すべての子どもの学びを予想し教材研究するのは大変」など、自身の実践を振り返りながら「思い」を熱心に語り合う先生方。とても豊かな本音の対話の場が実現し、先生たちが囲んだ模造紙には、多くの対話の「記録」が記されました。
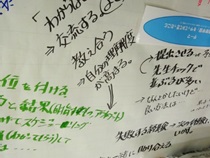
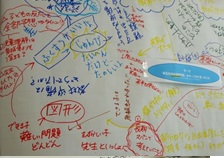
島立小では、ここを出発点として次年度の学校の「挑戦」のあり方を模索していきます。「対話」を通して学校づくりの「主体者・当事者」として、まなざしを共有していく島立小の先生方です。
学びの改革パイオニア校 波田中学校
~ 「全員が主役となる学校」を生徒と共に創る ~
波田中学校では「『全員が主役となる学校』を生徒と共に創る」を目指し、生徒一人一人が主人公となる学びに向けて歩みを進めています。美術科の横山先生は、この実現に向けて、生徒が主体的に学べるピクトグラム制作の授業を公開しました。この授業では、「伝わる絵の選択・大きさ・単純化」に着目し、どのようなピクトグラムが波田中に必要かを一人一人が再検討しました。
横山先生は、ピクトグラム制作をより効果的にサポートするために「ピクトくん」と呼ばれる模型を作成しました。ピクトくんは、手足を自由に動かせる人型の教材で、動きやポーズを連想しながらデザインを考える手助けになります。また、友達同士が意見交換できるように付箋を使ってアドバイスを伝える場も設けました。このように、生徒一人一人が主体的に学べる環境を整えています。
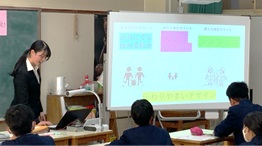
「休み時間終了時に廊下を走ると危険なことを伝えたい」というテーマでピクトグラムをデザインしたAさん。最初に「どっちの方が走っているように見えるかな?」と悩みながら、ピクトくんを動かしてデザインを再考しました。その後、友達からのアドバイスを参考にし、時計を加えて「休み時間終了の時間(10時30分)」を示すことで、さらに伝わりやすくするアイディアを取り入れました。授業終了時には、「友達からのアドバイスを活用して、よりよいピクトグラムがつくれた」と振り返り、手応えを感じていました。

波田中学校では、「一人一人が主人公となる学び」を実現するために、横山先生のように主体的に授業を公開する雰囲気が広がっています。今後もこうした主体的な学びの場がさらに広がり、多くの生徒が自分の力で学びを深めていくことが期待されています。
令和7年2月3日 更新
リーディングスクール 筑摩野中学校
聴き合い、考え合う授業へ
「協働の学び~対話を基盤とした授業づくり~」という全校研究テーマのもと、筑摩野中学校では、4人1グループを基本とした学びを昨年度より継続して行っています。
今回は理科の授業の一場面を紹介します。1年生の授業では「はかりにばねが使われている理由は何だろう」という問いのもと、ばねの伸びの実験を行い、グラフ化していました。ある生徒がグラフ化に苦心していて、先生も声をかけますが、その生徒はなかなか進みません。同じグループのメンバーが自分たちのデータをもとに「軸をこういう風にしたらどう?」「私はこうしてみたよ」と話し出します。それを聴きながらヒントを得たようです。また、2年生の授業では並列回路での電流の流れ方を実験で調べていましたが、予想と違った様子で何度も4人で繰り返し話し合って測っていました。理科の授業は理科室の構造上4人グループが基本ですが、誰かが教えたり、仕切ったりするのではなく、級友との関わり方がごく自然で自分たちで聴き合い、考え合いの姿が印象的でした。日頃から4人1グループでの学びの機会が多いことがもたらした結果だと感じました。


先生方の意識も変わってきました。先生方の声を紹介します。「グループワークを活発に行うことで、授業内で自身が話す時間が短縮したと感じます。生徒自らで学びを得ようとする姿が見られ、さらに自分でもそれを狙った授業展開をつくるようになりました。」「生徒が気軽に『なぜ』『どうして』といった言葉を交わす環境に、教育現場としての充実感を感じています。」「生徒が協働して、又は自分の力で学んだことを最終的に一つのゴールにはめ込まないように割り切ることができるようになりました。」「生徒が必要感をもって学び合いをするために、学習問題や授業中の問いかけを考えるようになりました。」対話を基盤とした授業に取り組んで、先生方にも変化や学びがあったようです。
2月12日には麻布教育研究所の村瀬公胤先生を招き、授業クリニックを予定しています。さらなる協働の学びの進化を続けます。
リーディングスクール 開成中学校
2学年 総合的な学習 発表会
1月31日、2学年の「『総合的な学習(開成タイム)』発表会」が行われました。「(1)地域の防災、(2)ナゼそこ!?ポツンと開成中、(3)伝統工芸、(4)郷土食」の4つに分かれて探究してきた成果をアウトプットする時がやってきたのです。
私は発表が始まる前に、「今日の発表会は素晴らしいものになる!」と確信しました。なぜなら、発表会のスタートが近づく中、教室・廊下を準備に飛び回る2年生の表情が「早く発表したい!」という気持ちに満ち溢れていたからです。それはまさに、この数か月取り組んできた自分の探究に対して自信を持っている表れでしょう。
また、この発表会はただの発表会ではなく、2つの要素がプラスされています。1つは「参観日」、そしてもう1つは「新入生の中学校見学」。そのため、オーディエンスには「保護者」も「小学6年生」も混ざり、各会場はまさにカオス!特に、新入生が入学前に「開成タイム」を体感できるのは中1ギャップ解消に一役買うであろう、意味ある取り組みだと思います。
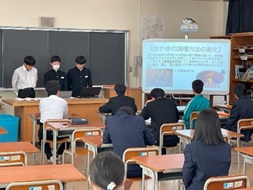
ちなみに、発表会では各グループが3回ずつ発表し、オーディエンスは興味のあるグループの発表を3つ選んで聞くことができます。全ての会場に足を運んでみると、どの会場も熱気にあふれていました。発表の仕方はプレゼン発表が中心にあるのはどのグループも共通でしたが、プラスして体験あり、クイズありと様々な工夫が見られました。そうした発表に、小学生から保護者まで、発表に引き込まれていました。

発表後、オーディエンスは色分けされた付箋を通してフィードバックを残していきます。色分けされた付箋が並んでいる光景はまさに壮観でした。新入生も含めて「探究のたすき」が繋がっている、そのように感じられました。開成中学校の2年間にわたるリーディングスクール事業を通した取り組み。その1つの区切りの姿として、大変印象深い光景でした。
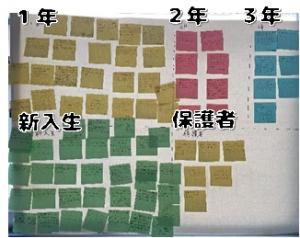
リーディングスクール・アソシエイト校 開明小学校
先生たちが紡ぐ「学びの物語」
1月28日 リーディングスクール・フェス当日。開明小学校では学校づくりの合言葉「『いってみよう』『きいてみよう』『やってみよう』○○たい!」から生まれたキャラクター「たい」にちなんで、たい焼き屋台を模したブースを開設しました。今年、研究推進づくりで大切にしてきた「楽しさ」が、びんびんと伝わります。

今回のアウトプットの中で、研究主任の横澤先生が真ん中においたのは、先生たちひとり一人の「学びの物語」です。先生たちが一年間の自己課題をベースとした自身の歩みを振り返り、綴った「わたしのたい焼き」シートを通して、先生たち一人一人の学びの足跡と手応えを紹介いただきました。
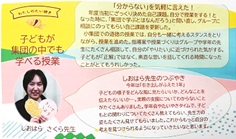
先生たちのシートにはグループの先生たちの親身なかかわりへの感謝が多くつづられており、開明小の研究が豊かな「協働」の上に立っていることが改めて感じられます。このシートは「ジャーナル」としてこれまで同様、職員室の壁に掲示され、先生たちで共有されます。
2月には、先生たちがそれぞれの「学びの歩み」を、地域・保護者・教職員向けにアウトプットする機会を持ちます。先生方が紡ぐ物語の糸が様々な「ひと」とつながり合い、織りなされていく開明小の学校づくりです。
令和7年1月27日 更新
リーディングスクール 明善小学校
「子どもにゆだねる」
子ども達に「主体的な学習者となってほしい」と願う理科専科の先生。従来の教授型の学習から、子ども一人一人が自分の学習として取り組むことができるような授業緒の在り方を模索しています。
単元の第1時に、単元のめあて、学習のポイント、日程などを子ども達に示し、単元全体の見通しを持ってもらいます。子どもたちは、どの学習をいつやるのか学習計画を立てます。第2時からは教科書と理科学習帳を手がかりに、一人または友だちと各自学習を進めます。単元の終末には、グーグルスライドを使って一人一人まとめを作成し、発表します。必ず押さえておきたい用語や学習の定着具合は、グーグルクラスルームで先生から共有され、一人一人確かめられるようになっています。
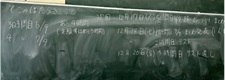
写真は「てこのはたらき」の単元で、各々教科書を参考に実験をしたり、てこのはたらきを使った作品を作ってみたりするなど思い思いに学習している様子です。「今日はこの学習をする」ということが一人一人明確であり、どの子も前向きに取り組んでいる様子がうかがえました。



リーディングスクール・アソシエイト校 旭町中学校
教師の手から生徒の手へ
学びの転換期と言われる今。これまでの教師のあり方を問い直し、子どもが主体的に学ぶにはどうしたらいいかと試行錯誤している先生方がたくさんいます。旭町中学校の先生方も、今まで先生の手の中にあった学びの主導権を、少しずつ子どもたちに預けていく、そんな実践にチャレンジしています。
柴先生は、3年生の国語の授業で、生徒それぞれが課題を決め、タブレットなどを使いながら自由に調べ学習をし、最後に評論にまとめるという実践に挑戦しました。これは、生徒の主体性を重視した試みでしたが、一方で先生は、生徒全員が主体的に取り組む難しさや、生徒の自主性に任せることへの不安、個別のサポート不足といった課題も感じていました。
柴先生のチャレンジに対して、教頭先生と篠田先生は、生徒の中に見られた良さについて語り合いました。そして「生徒に任せることで、生徒たちは主体的に学び、成長していく」「生徒同士が教え合うことで、理解が深まり、新たな発見が生まれる。」と、柴先生のチャレンジの価値を柴先生にフィードバックしていました。
柴先生も、生徒から「先生、ここにあることはこう思うんですが、これってどういうことですか?」と質問されたり、生徒同士で議論が始まったりする場面が見られたと、生徒たちの主体的な学びの変化の気づきを語られました。

子どもたちに任せる授業の難しさを感じながらも、その可能性に期待し、より良い授業を目指して試行錯誤している旭町中学校の先生方です。
学びの改革パイオニア校 波田小学校
~ 子どもたちがもっとのびのびとやりたいことにトライできる学校にしたい! ~
子どもも先生も「やってみたいことに挑戦できる学校に!」と歩みを進めている波田小学校。先生方も「まずやってみよう、挑戦しよう」ということで、放課後の時間を利用し、自主的な職員研修会を開催してきました。
県のパイオニア校の視察として、軽井沢風越学園のアウトプットディに参加した3名の先生方が、11月末の職員会でその様子を報告しました。しかし、職員会では十分に話を聴いたり語り合ったりする時間がなかったので、12月末に「風越学園自主研修報告会」を実施することにしました。
研修報告会当日は、22名もの先生方が参加され、はじめにアウトプットディを参観した3名の先生方が、それぞれ作成した資料などを用い、風越学園の子どもたち・スタッフの様子や校舎環境などについて発表しました。その後、3人の発表者を囲み、3つのグループに分かれ、風越学園の様子や校舎環境などに対する質問や、自分たちが感じたモヤモヤ感などについて語り合いました。

「本当に自由に過ごす子どもたちが大人になっていくときに社会の中でうまく適応できるのか?」などの疑問の声や、「その子の個性が認められ、子どもたちがいきいき・わくわく・にこにこしている事実は素直に“いいなあ”と思える」などの声もありました。波田小のように人数も多く、校舎改築で制約もある中で、どのようにしていけば子どもたちが、さらにのびのびと過ごせるか悩みや困り感を語り合う姿もみられました。

改めて、目の前の子どもたちへの対応・言葉がけや授業づくりなどを問い直す貴重な機会になりました。
令和7年1月20日 更新
リーディングスクール 寿小学校
「寿小学校公開授業研究会」
寿小学校では、令和6年12月13日に公開授業研究会を実施しました。50名以上の参加者が子どもたちの学びの様子を参観し、単元内自由進度学習について深く議論しました。
公開授業では、1年生が算数「かたちづくり」と生活「リースづくり」、3年生が算数「円と球」と理科「豆電球に明かりをつけよう」に取り組みました。子どもたちはそれぞれのペースで学び、試行錯誤を重ねながら自己解決力を高めている姿が見られました。
研究会後には、上智大学の奈須正裕先生による講演が行われ、「教師としての姿勢」について深く考えさせられる内容でした。参加者は自身の授業観を改めて見直し、より良い学びの環境づくりに向けて新たな意識を持つことができました。
なお、2月には寿小学校において研究まとめの会を実施し、この1年間で子どもたちが見せた自己調整力や自律的な学びの姿を共有する予定です。



リーディングスクール・アソシエイト校 女鳥羽中学校
「アウトプット」に初挑戦
12月、2年生が4月以降の総合的な学習の時間に取組んだ「学びの歩み」を報告する「アウトプット・デー」を実施しました。体育館にいくつもの発表用のブースを設定し、生徒たちが発表用にまとめたシートを示しながら、2年生の仲間、1年生、先生たちに向けて発表し、参加者と質疑や感想を交流しました。
発表では、2年生で取組んできた「職場体験」、「高山旅行」などの学習活動を「キャリア学習」の一環として、自分の将来の夢や、興味・関心に関連付けながら、学びや成長を振り返り語ります。
このような形での「アウトプット」は初めての生徒たち。初めはとても緊張した面持ちでしたが、時に笑顔で、時に熱く語るなど、気持ちを高揚させながら表現の場を楽しむ姿がありました。

参観した1年生は、とても熱心に2年生の発表に聞き入り、先輩の姿を胸に刻んでいる様子でした。
授業後、「車座」による先生方の感想交流が行われました。先生たちから一人一人の生徒に寄せた「学びのよさ」「成長の姿」が豊かに語られました。
「本当に自由に学べる学校」をみんなで目指してきた女鳥羽中学校。「主体的に学ぶことの楽しさ」の実感を生徒たち、先生たちが深めています。
学びの改革パイオニア校 田川小学校
「任せること・任されることから生まれる変化~田川小学校の研究~」
パイオニア校として探究的な学びに取り組んできた田川小学校は、二人の研究主任を置いて実践に取り組んできました。これまで子ども中心の学びについて紹介してきましたが、今回は研究を進めている立場として、この一年間どのようなことを大切に取り組んできたか、小林先生にインタビューしてみました。
小林先生は、「今年は研究副主任として、自分の意識改革に挑戦しました。本校の研究は『自己肯定感のもてる子の育成』という目的を重視しています。この目的を達成するために、昨年は先生たちに『こうするといい』という手段を提示することを重視した関わりをしてきたのですが、うまくいきませんでした。そこで今年度は、先生たち自身の経験とアイディアを尊重することに心掛けました。以前は、相談されると解決策を提示していましたが、今は先生方のやり方をじっくり聞き、困り感に対して改善の方法を一緒に考えることを大切にしています。今までの自分で何とかしなければという考え方から解放され、先生たちに頼れるようになったことで、私自身の視野が広がりました。」と話してくれました。
木村校長先生も、「先生たちがより主体的に研究に取り組み、互いに協力し合い、学校全体の活気が高まりました。小林先生の研究副主任としてのあり方の変化は、校内研究を活性化させ、より良い教育の実現へとつながっていると感じています。」と話されました。
田川小学校の先生方は、子どもたちの「自己肯定感のもてる子の育成」という共通の目的のもと、先生方が経験とアイディアを活かし、主体的に研究活動に取り組んでいる様子がうかがえました。2月の参観日では、それぞれのクラスがこれまでの学びをアウトプットします。どのような歩みが表現されるのか、とても楽しみです。
 リーディングラボで田川小学校の研究をアウトプットする小林先生
リーディングラボで田川小学校の研究をアウトプットする小林先生
令和6年12月23日 更新
リーディングスクール 筑摩小学校
2時間連続の単元内自由進度学習に挑戦!
「どの学年も学期に1回は自由進度学習を」と歩みを進めている筑摩小学校。11月25日、信州大学教育学部伏木久始教授をお呼びし、全職員で6年生の授業を参観後、研究会と講演会を実施しました。6年生2クラスが、算数「データの整理と活用」と社会「町人の文化と新しい学問」の2教科を組み合わせた単元内自由進度学習に取組みました。今回は、2時間連続の単元内自由進度学習に初めて挑戦しました。
授業が始まると、子どもたちは思い思いに自分が学びたい場所へ移動し、問題に取組んでいきます。A児がデータから最頻値を求めていると、近くで学習していたB児から「蘭学ってどんな学問だったっけ?」と聞かれて自分のやっていることを一旦止めて快く答えていました。C児は1時間目の終了チャイムが鳴っても「俺はやりたかいから休まない」とつぶやき、黙々と問題に取組み、D児は教師の所に行きチェック問題をクリアし、「ヤッター、俺、難しいのもできるようになったじゃん」と自らの成長を喜びました。2時間連続にしたことで、じっくり時間をかけ取り組んだり途中で教科を変えたりする姿が見られ、自分のペースで自分でやることを決める「自己調整力」の育成につながったのではないでしょうか。

研究会は、職員が4人グループになり「自分で考えて、自分で答えを出し、自分でわかったと感じる姿は格別だよね。自由進度学習のよさですね」など、子どもの姿から自分たちが学んだことなどを語り合いました。研究会後、伏木先生から「自由進度学習における学びの質を高める ~教師の直接指導と評価のあり方~」についてお話を聴きました。伏木先生からは、単元内自由進度学習を通してやりがいや達成感を感じている筑摩小の子どもの姿や日常生活に関わる導入問題の工夫や子どもを引き込むガイダンスの重要性などについて示唆をいただきました。

研修会を通して、筑摩小の研究の歩みを振り返り、さらなる一歩へと踏み出す機会になりました。
リーディングスクール・アソシエイト校 菅野中学校
次の一歩へ
11月に「協働的な学び」の環境づくりを目指して「コの字型の座席配置」による授業実践に全校で取組んだ菅野中学校。12月、「コの字型の座席配置」で授業をしてみた手応えや課題を先生たちが振り返り、交流する機会を持ちました。
振り返りの会では、先生たちが4人ほどのグループで、「コの字型の座席配置」で感じた手応えを語り合い、「成果」と「課題」の観点から、ホワイトボードに整理していきました。各グループでは和やかな雰囲気の中、率直な対話が交わされました。
グループ対話のシェアリングでは、「子どもたちから自然に話し合いが始まる。」「距離が縮まり雰囲気が変わった」「生徒の様子がわかりやすくなった」といった「手応え」があげられる一方、「おしゃべり、わちゃわちゃになりやすい」「学習活動によっては合わないものある」といった悩みや課題、「互いの顔がいつも見えることがしんどい生徒もいるのでは?」という子どもへ寄り添いも共有されました。話し合い後、次回は様々な課題を克服し、「コの字型」のよさを活かす工夫をみんなで出し合うこととなりました。


菅野中学校では年明けの三学期、探究的な学びに取組んだ生徒たちが、参観日の機会に自分たちの学びを保護者や友だちに向けてアウトプットする初めての機会を予定しています。
生徒たち、先生たちが協働的に学びながら「次の一歩」に挑戦している菅野中学校です。
学びの改革パイオニア校 開智小学校
伝えたい!これまでの私たちの歩み~アウトプット会~
今年度、開智小学校の新たな取り組みとして行ってきた4年生・6年生の異年齢による総合的な学習の時間。これまでの学びの歩みを全校児童と保護者・地域の方に向けてアウトプットしました。9月に中間アウトプット会として、前半と後半に分かれて、互いの探究を見合った児童たちは、11月に丸ノ内中学校で行われた丸中Jr.学会(中学校で行われる探究学習発表会)に参加し、そこでアウトプットの様子やフィードバックのあり方を学んできました。その後、さらに自分たちの探究を深めるため様々な体験活動を通して、タブレットや模造紙にまとめたり、劇や作品を制作したりしてきました。
12月18日に行われたアウトプット会では、自分たちがこれまでどんなことに課題意識を持ち、どんな取り組みをし、そこで感じた驚きや大変さを語りました。来てくれた人に丁寧に伝えたいという思いから原稿にまとめ読み上げる姿もありましたが、質問されると自分の言葉で語れる児童が多く、これまでの活動が自分事になっていました。また、今回はフィードバックを大切にと考えていることから、感想だけでなく、もっと良くするためのアイディアをもらおうと、発表の最後にはフィードバックの時間を設けてやり取りしていました。

ここまでの活動に開智小学校の先生方は、どのように伴走すればよいか、とても悩んだそうです。しかし、「子どもに委ねる」を合言葉に、児童たちがやりたいことを実現できるように子どもとの対話を大事にし、伴走してきました。その一つの成果がこのアウトプットでの児童たちの堂々とした姿だったと思います。
今回のフィードバックをもとに、さらに進化していく子どもたちの姿が楽しみです。
令和6年12月16日 更新
リーディングスクール 中山小学校
新たな取組み「中山っ子発表会」大成功!
12月6日(金曜日)には生活科・総合的な学習の時間での学びを、保護者や地域の方に向けて発信する「中山っ子発表会」が行われました。昨年度までは、各学年での参観日に合わせて「学習発表会」という形をとっていましたが、今年は全校で一斉に、しかも、子ども自身が他の学年の発表を見ることができるようするという新しい取組みを先生方は模索してきました。発表はもちろん、子どもたちの手作りです。
当日は大盛況。1、2年生は自分たちの活動を、タブレット端末を上手に活用して、クイズも交えて発表しました。学年によっては、発表を聞いての感想を付箋に書いてもらい、新たな課題発見につなげていこうとする動きもありました。
 【1年生】季節ごとの活動を6つのブースで紹介。中山保育園の年長さんに説明する
【1年生】季節ごとの活動を6つのブースで紹介。中山保育園の年長さんに説明する
 【5年生】自分たちで育てた「5年米」の販売。おはぎ、おもちも販売した。
【5年生】自分たちで育てた「5年米」の販売。おはぎ、おもちも販売した。
発表会を終え、子どもたちからは、「他学年の活動は、いつもは見れませんが、学年によってクラスの個性が出ていて面白かった」、「たくさんの意見が聞けてよかったです。『よかった』や『◎』の付箋が50枚以上あって、とってもうれしくなりました。」などの感想が聞かれました。今日の手応えをもとに、さらなる課題解決に向けて歩き出す中山小学校の子どもと先生たちです。
リーディングスクール 鎌田中学校
味噌の生産日本一、長野県
総合的な学習の時間「KMDタイム」では、「私たちはこの地域のために何ができるか」を問いの出発点として学びを深めていきます。2年生のある学級では、松本の魅力について調べています。「松本の魅力について多くのことを知っているのは誰だろう」と考え、施設にいる高齢者のもとを訪れました。「松本のいいところ、誇れるものや好きなところ」を尋ねたところ、信州味噌が挙げられました。調査を進めたところ、なんと長野県は「味噌の生産日本一」。海外では、一般的に、熱を加えて発酵を促進する「速醸法」が取り入れられ、短期間で味噌が作られます。一方で、伝統的な天然醸造では、製造までに時間はかかりますが、豊かな風味のあるおいしい味噌になることがわかりました。「調べたことは、他の中学生にも見てもらいたい。鎌田中の取り組み、自分たちが、何をしているのかを他の学校に知ってもらいたいし、お互いの学校が交流することで、色々な(知識や経験の)引き出しを増やしたい」。学びに主体性を帯びた時、生徒の学びの歯車は力強く回り始めています。
 調べことを模造紙にまとめました
調べことを模造紙にまとめました
 調査した内容をメモしたノート
調査した内容をメモしたノート
リーディングスクール・アソシエイト校 梓川中学校
~ 地域の後輩に中学校の様子を紹介しよう! ~
総合的な学習の時間を使い「SDGsを知ろう・気づこう・楽しもう」と活動を続けている1年生。SDGsの達成目標である17項目を意識しながらも、1年生の間は、ともかく活動を楽しむことに力点をおき進めています。そして、2年生後半から3年生にかけて達成目標「11住み続けられるまちづくりを」などを中心に「私の住む梓川」について一人一人が考え探究していけるようになればと構想しています。
今回は、達成目標「4 質の高い教育をみんなに」「11住み続けられるまちづくりを」などを意識しながら、1月に実施する「地域の学校梓川小6年生の中学校参観」に向けて、各クラスが中学校の様子を紹介する動画づくりを行っています。
1年生のあるクラスでは、「6年生が中学校っていいな~と思える動画をつくろう」を合言葉に、グループごとどんなことを紹介したらよいかアイディアを出し合いました。まずは各自で「初めての人との出会い」「中学校には面白い先生(担任)がいる」「小学校に比べ委員会の数が多い」などと小学校との違いを近くの友と談笑しながら付箋に書き出しました。その後グループになり、各自の付箋を貼りながら「グループでまとめてベストなものを提案しよう」とアイディアをまとめていきました。どのグループも和気あいあい楽しそうに語り合いまとめている姿が印象的でした。


令和6年12月9日 更新
リーディングスクール 清水中学校
教科指導を通して「表現力」を育む
全校研究テーマ「表現力が育つ~すべての活動を通して~」の具現に向け、長野県教育委員会の指導主事を講師に招聘しての研究授業を全教科で行い、授業改善・充実を図っています。
このほど参観をした保健体育、音楽、国語の授業では、生徒が自分の考えを形成したり、判断の根拠を添えて表現したりすることができるように、各教科等の見方・考え方を働かせる授業デザインがなされていました。また、互いの意見を尊重して聴き合う関係性や、互いの成長を認め合う心理的安全性の高さが各学級の土台にあることが感じられました。


リーディングスクール・アソシエイト校 島立小学校
実践をみんなの共有財産にする
1学期末の「一日職員研修」ですべての先生が「単元内自由進度学習」の実施に向け準備をした島立小学校。2学期以降、先生たちの実践への挑戦が続いています。
先生たちの貴重な実践からの学びを共有し、島立小みんなの財産にしたい!と考えた研究主任の平本先生は、職員Class Room内にスライドファイルを作成し、授業者の振り返りや、参観者のフィードバック、授業の写真や動画などを書き込んでもらう取組みを進めています。
スライドにはそれぞれの先生の工夫点や課題、また、具体的な子どもの様子や環境設定が写真とともに掲載され、先生たちが新たに授業実践を考える際に、大きな参考になっています。
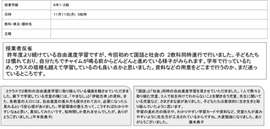

初めて「単元内自由進度学習」の実践に挑んだ先生たちからは、「子どもたちの食いつきが違う」「一人一人の学びの様子がよくわかるようになった」といった手応えが寄せられる一方、自由進度学習の準備には、それなりの時間が必要です。
このように、島立小学校では実践をみんなの共有財産にすることで、すべての教室で「子ども主体の学び」へのアップデートが行われることを目指していきます。
学びの改革パイオニア校 丸ノ内中学校
丸中Jr.学会~これまでの「忠恕」の時間をアウトプット~
丸ノ内中学校では、「忠恕」の時間(総合的な学習の時間)のアウトプットの場として、生徒が探究学習の学びを発表する「丸中Jr.学会」を実施しています。この丸中Jr.学会は、生徒が自身の探究内容をポスターセッション形式で発表し、学校以外の人からも意見を取り入れることで学びを深め、次のステップへと繋げることを目的としています。
今回は3年生のジュニア学会でした。2年間の探究活動の集大成として、丸中Jr.学会を最終発表の場と捉え、これまでの学びを振り返りました。生徒たちは、自身の学びの歩みを堂々とした姿で、自分の言葉で伝えていました。昨年度は原稿を読んでいた生徒もいましたが、今年は原稿を読む生徒はほとんどいませんでした。これは、生徒自身が体験を通して学んできたこと、そしてラーニングジャーナル(デジタル・ポートフォリオ)で日々の学びの蓄積と振り返りを繰り返し、学習を調整してきた成果といえるでしょう。また、Ppdacメソッドを活用し、複数の事例やデータを組み合わせて結論を導く、論理的思考力が身に付いてきました。ここに至るまでの教師の丁寧な伴走支援も、生徒の自信へと繋がっていたと考えられます。

丸中Jr.学会を終えた生徒からは「外部の方から学ぶことによって、知識を学んで伝えるだけでなく、そこにいる人の思いも一緒に伝えることが大事だと感じた。」という感想がありました。丸ノ内中学校が大切にしてきた人とのかかわりや体験の中でしかわからないことの大切さを、ポスターセッションを通して改めて感じていたようです。
3年生は、これから進路を決める大切な時期に入っていきます。しかし、これまで進めてきた探究を丸中Jr.学会で終わらせるのではなく、続けていきたいというグループもあります。そのために教師は、毎週ある「忠恕」の時間を活用し、生徒と共に考えながら、さらに学習が深まるよう支援しています。生徒の学びたいことに伴走し続ける丸ノ内中学校です。
学びの改革パイオニア校 波田中学校
~ クラウドを活用した自由進度学習への挑戦!~
「『全員が主役となる学校』を生徒と共に創る」を合言葉に、授業では「一人一人が主人公となる学び」を目指し研究を進めている波田中学校。音楽科のA先生は、参観した他校の授業を参考に、3年の題材「アルトリコーダーの響きを楽しもう(9時間)」で自由進度学習に挑戦しています。
ガイダンスで、「ソロ演奏または友達とアンサンブル演奏をする」などの4点の目標を示し、学習の流れを説明し、学習計画を立て単元がスタートしました。ゴールとなる第9時では、ソロ演奏またはアンサンブル演奏をタブレットで録画し、Googleクラスルーム「音楽」に提出するようにしました。
A先生は、事前にクラスルームの「音楽」の中に、楽譜や練習のフレーズ、A先生が演奏した「参考演奏」録画(13曲)などのデータを入れておきました。生徒たちは、最初にアンサンブル演奏かソロ演奏かを決め、A先生が参考演奏として示した曲の中から自分が演奏したい曲を決め、練習を始めました。


生徒たちは、一人または友達と演奏しながも、練習の途中で自分が必要だと思うデータを選び、視聴し参考にして練習を続けています。学習はまだ始まったばかりですが、A先生は次のように手応えを感じています。
「自分たちで運指を覚えようとしたり、タンギングについて自分たちで調べようとしています。一人で黙々とやったり友達に相談したりいろいろな姿が見られますが、自分たちでやろうとする意欲が通常の授業より伝わってきます。」
ゴールの演奏を楽しみに、音楽科では、自らが学び取る「自由進度学習」の実現に向けて挑戦を続けていきます。A先生ご自身から沸き上がった自律的で主体的な挑戦は、授業づくりへの「探究」そのもの。その営みは今、静かに波田中に広がっています。
令和6年12月2日 更新
リーディングスクール 筑摩野中学校
4人1グループの学びを重ねて変わってきたこと
「協働の学び~対話を基盤とした授業づくり~」という全校研究テーマのもと、筑摩野中学校では、4人1グループを基本とした学びを昨年度より継続して行っています。この学習形態を重ねる中で、生徒たちの学びの姿に大きな変化が生まれているようです。例えば、教師がグループで話し合うように指示を出さなくても、自然と対話が生まれ、質問したり、自分の考えを伝えたりする姿が多くのクラスで見られています。4人1グループのメンバーだけでなく、他のグループの生徒の説明を真剣に聴き入ったり、自ら納得する答えを求めて友人のもとへ行って考え合ったりしている姿もあります。また、教師が「聴き合っていいんだよ。」と何度となく声をかけることで、生徒たちが安心して、自分の学びを深めるために級友と対話を重ねられているようです。




聴き合うこと(=対話)を大事に今後も授業づくりをしていきます。
リーディングスクール 開成中学校
「鮮やかにバトンが渡されました!」
前回のWebページで予告した、3年生の「『総合的な学習(開成タイム)』発表会」が終了しました。発表を見学した1,2年生は、その感想を付箋に書いて残しました。感想がしたためられた付箋は3年生の各グループに届けられ、3年生はあらためて自分たちの発表を振り返っていました。
1,2年生にとって、3年生の発表はかなりインパクトがあったようで、感想はどれも高評価!ただ、感想の内容が「良かった」「面白かった」に留まらないことに驚きました。「追究心がすごい」「メリットとデメリットがわかりやすくまとめられている」「字の色の使い方も工夫」「パンフレットがよく作り込まれている」「ただ長文を書くだけではなく、イラストを使うことによってわかりやすくなっていた」等々…、実に細かなところまで感じている感想に思わず唸ってしまいました。活動を始めたばかりの1,2年生は、3年生の発表を通して、自分たちのテーマにどのように関わり、どのように発信していけばいいのか、具体的にイメージすることができたと思います。
手つかずの山を切り開き、1本の道を通した3年生。ゼロから「1」を生み出すことは本当に大変だったと思います。後輩たちはその道を利用して、道を整えたり、別の道を作ったり、さらにその先まで進んだりと、学びをどんどん進めていくことでしょう。今、鮮やかに、そして確かに「探究のバトン」が託されました!
この日、1,2年生は自分たちの活動を始めていました。ある班は、学校が建っていることには、防災の役割もあると知り、校庭の土がどのくらい固いのか調べていました。まさに、探究する姿!どんな道を整備していくのか、そしてどこまで進んでいくのか、今後の1,2年生の学びに注目していきたいと思います!
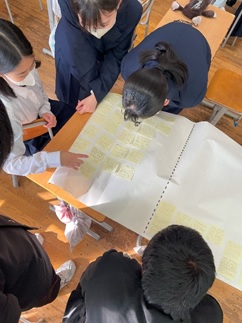

リーディングスクール・アソシエイト校 開明小学校
「みんなが前を向いていかれる授業公開」
「「子どもの〇〇たい」から始まる学校づくり」に取り組んでいる開明小学校では、この秋4回目の校内公開授業研究会「たい焼きデー」を実施しました。今回も4人の先生が授業者として立候補、信州大学の谷内教授を助言者として公開授業と研究会を実施しました。
公開授業の一つ、「楽器でお話ししよう」(音楽2年生)では、子どもたちがペアの友達と楽器で会話をするようにリズム遊びを楽しみました。子どもたちが「やりたい」という思いを高めながら見通しを持って取り組めるよう、「リズムカード」から好きなリズムを選べるようにしたり、ティンパニからクラベスまで様々な楽器に挑戦できるように環境設定したりなど、先生は細やかな工夫をされました。
様々な楽器の音を味わいながら自分の選んだリズムを友だちと時間いっぱい楽しむ子ども達でした。

放課後は研究グループの先生方による振り返りの会。
授業者と一緒に授業を作ってきた先生たちは、子どもの学びの姿を自分ごとのように語り合い、とても和やかに盛り上がった会となりました。
助言者の谷内先生は「学びを楽しむ子ども」として、この日の授業で見られた子どもの学びの素敵な姿、そしてそれを引き出している先生たちの細やかな工夫を紹介されました。さらに「発問の工夫」など、さらに学びを充実していくためのヒントを示唆されました。谷内先生は最後に「次に、またチャレンジするぞ!という意欲に満ちた先生方の様子でした。みんなが前を向いていける公開研究会だ、と強く感じました。」と結ばれました。

まさに開明小の「現在地」を評された言葉でした。
学びの改革パイオニア校 田川小学校
探究@田川小 公開授業(11月22日)
公開授業を終えた小嶋研究主任にインタビューしました。
「今回の一番の目的は、外部の方を田川小学校にお呼びして、田川小学校で大切にしてきた『子どもをよく見ていく』ということを一緒に考えてもらうということです。単に発表のための公開授業ではなく、先生方や参観者の方々に子どもたちの行動の意味を考えてもらい、様々な見方から次の授業につなげていく授業研究会にしたいと思っていました。」
「他市から参加されたA小学校の研究主任の先生は、ある子どもがゴミを丁寧に広げて観察している様子を写真で見せながら、子どもがゴミ拾いをする理由についても、『綺麗にするためだけではない』『宝探しのような面白さがあるのではないか』など、子どもが夢中になって探究する意味について語ってくれました。子どもたちがゴミ拾いを通して、ゴミに対する意識を変え、楽しみながら探究していく姿は、大人にとっては見失いがちな視点(子どもの中にある楽しさ)であり、子どもの行為の中にある学びの本質について考えることができました。」

「また、信州大学の安達先生を講師に招いての研修では、『探究し続けた子どもが35歳になった時どんな力が身についているか』というワークショップを行い、先生方の探究観を語り合いました。その瞬間では見えない力ですが、継続することで身についていくだろう力を語り合うことで、探究の可能性や面白さを感じることができました。」

田川小学校では、2月に全校がアウトプットをする予定です。今回の途中経過がどのような形になっていくのか、楽しみです。
令和6年11月25日 更新
リーディングスクール 明善小学校
「未来につなぐ工芸品」
国語「未来につなぐ工芸品」の学習を通して日本には様々な伝統工芸があることを知り、その魅力に触れた4年生。自分が『ステキだな』と思った伝統工芸について友だちに伝えるため、タブレットや図鑑を用いて調べ、「わたしが伝えたい〇〇のみりょく」と題して文章にまとめています。先生は一人一人の学習ペースを大切に考え、この学習のゴールを明確にして進め方を簡潔に示し、あとは子どもに委ね、必要に応じて助言をしています。子どもたちは一人で調べたり友だちと相談したりしながら、自分のペースで学習を進めていきます。時間を持て余している子はおらず、どの子も自分のやり方で時間いっぱい取り組む姿が印象的です。
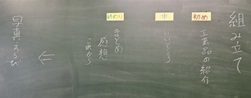
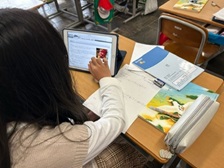
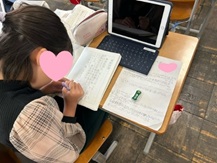
学びの改革パイオニア校 波田小学校
5年生が中学校の生徒会へ参加!
子どもたちの願いをベースにした小中連携に取り組んでいる波田小・中学校。11月11日、5年生が「児童会の引継ぎに向け、中学校の生徒会に参加し中学生と交流することで、今後の児童会活動の参考にしたい」と波田中学校の生徒会に参加しました。
所属する園芸委員会と同じような委員会に参加した5年生のAさんは「緑化委員会の活動を見て思ったことは、小学校のように花を育てる仕事をしていると知って驚きました」と感想をもちました。
体育委員会では、「体育館でのボールの使用方法」を呼び掛けるポスターをCanvaで作成し、小中学生が交じり「どのイラストがいいと思う?」と相談しながら進めていました。他の委員会でも、5年生が生徒会活動の様子を真剣に見聞きする姿が印象的でした。
最後の5分間には、「5年生との対話の時間」が設けられ、5年生から「中学校で大切にしている活動は何ですか?」などの質問が寄せられ、誠実に応える中学生の姿が見られました。
5年生のBさん「とても大変な活動をしていてびっくりしました。そして、がんばっている姿がかっこよかったです。中学生のように真剣に児童会に取り組みたいし、大変なことにもチャレンジしたいです」。
中学3年生のCさん「町キレあいさつ運動などでしか会ったことがなかったけれど、自分たちが考えている生徒会像と、5年生が目指している児童会像に共通点があることが分かりました。機会があったらまたやってみたいと思いました」。
生徒会活動に参加した5年生が、今後どのように児童会を引き継いでいくのか楽しみです。


リーディングスクール・アソシエイト校 旭町中学校
教師と子どもが創る学校を目指して
旭町中学校では、「子どもと共に創る学校」を目指し、動き出しています。その第一歩として、MIH(妄想いっぱい話し合う)会が開かれました。この会のテーマは「魅力ある学びの環境づくりに向けて」です。まず教職員がグループに分かれ、一人一人の妄想(夢や理想、アイディア)を出し合いました。「勤務時間内に仕事が終わるような時間の確保」「大学の授業のように必修科目と選択科目を設ける」「5時間授業を増やす」「タブレットは3年間リース方式にし、卒業時に返すか買い取るか選択。破損は個人負担」などのように、教師自身の働き方や仕組みについての妄想が出されたり、「学年行事の計画・準備を生徒中心で実施」「2時間目と3時間目の間に休み時間がほしい」「1週間に1コマ、自分で好きな教科を決めて勉強する」「制服を廃止する」「昼休みは睡眠時間を設ける」「教室にこたつとソファーを置く」など、子ども視点に立ったアイディアが出されたりしました。
このように教職員がアイディアを出し、来年度の学校運営を決めていくことは、多くの学校で行っていることだと思いますが、旭町中学校ではさらに一歩踏み出しています。教職員の出し合った妄想を廊下に貼り出し、生徒からも意見をもらうのです。職員室前には「生徒の皆さんの考えを聞かせてください」と鉛筆と付箋が置かれ、自由に考えを書き込めるようになっています。「毎日5時間授業」「授業中に休憩が欲しい」「お昼寝の時間」「この前の道徳のようにクラスを超えての授業があったらうれしい」「タブレットを使える時間がほしい」「掃除なし」などと、生徒の本音がそこに書かれていました。
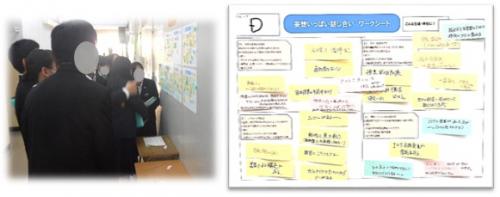
何かを急に変えていくことは難しいかもしれません。しかし、旭町中学校の大人と子どもがアイディアを出し合い、合意の上で決めたことは、きっと変えていくことができるでしょう。共に創る学校を目指す旭町中学校のシンカが楽しみです。
令和6年11月18日 更新
リーディングスクール 寿小学校
「子どもの自律性と学びの意欲を引き出す授業づくり」
12月13日(金曜日)に寿小学校で予定されている公開研究会に向け、各部会で授業準備が進められています。
この日の低学年部会では、生活科の授業で子どもたちの自律性を引き出すための学習環境について話し合いました。秋の遠足で子どもたちが集めた「どんぐり」や「松ぼっくり」などを活用し、「自分でやってみたい」「こうしてみたい」という意欲が自然に湧くよう、自由に試せる材料コーナーや、夢中になって学びに取り組める空間づくりが進められています。
高学年部会では、教室環境や学習カードが、児童一人一人の興味や学習ペースに適しているかを検討しました。
どちらの部会でも、設計された学習環境が児童の育成したい資質・能力へのアプローチとして有効であるか、また、子どもたちの「学びたい」という気持ちに火をつけられるかについて、活発な意見交換が行われました。
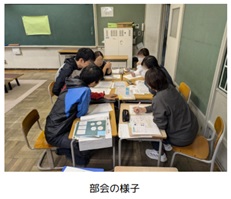

リーディングスクール・アソシエイト校 女鳥羽中学校
「探究」から生まれる新たな学校文化
「プロジェクトM」として「地域を題材とした探究の学び」に踏み出した女鳥羽中学校の3年生。文化祭では、一人一人が、初めての探究に取組んだ道筋と成果をまとめ、発表の機会を持ちました。
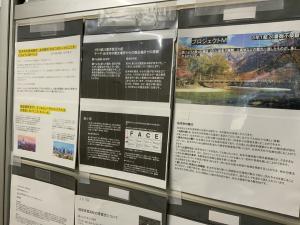
「『地域』に目を向けた学びの成果が様々なところに現れてきました。」と普明校長先生は話されます。
「岡田地区が開催する文化祭の運営ボランティアを学校で募集したところ、3年生が19人集まり、地域の皆さんとともに運営に携わりました。また、本郷地区からの募集に対して、1年生が自主的に応募し、活躍する動きも生まれました。多くの生徒が地区の文化祭に参加したということです。」
「さらに、生徒会会長選挙の際、候補者の多くが『地域とのかかわりを深めたい』という願いを訴えました。これまではなかっただけに、嬉しい驚きでした。」

「地域」に目を向けた学びから「当事者意識」が生まれ、それが引き継がれていく…「探究」から新たな女鳥羽中学校の学校文化が育っていきます。
令和6年11月11日 更新
リーディングスクール 筑摩小学校
自分のやりたいことをもっと追究したい!
4~6年生の子どもたちが、自分の好きなことをもとに取り組みたいことを決め、計画し活動を重ねてきたフリースタイルプロジェクト。10月23日(水曜日)の発表会に向けて、多くの子どもたちは、Canvaを使い、写真や動画などを入れ発表資料を作成しました。
発表会当日は、3部構成で「発表する時間」と「友の発表を見る時間」を設け、3年生も参加しました。「Canvaを使い発表する・実際に作ったものを紹介する・ダンスやけん玉など実演する」など、それぞれのやり方で堂々と発表する姿から、自分が取り組んできたことへの自信を感じました。また、これまでの国語の学習を生かして「きっかけ」「作り方」「工夫したこと」「結果」など項目立てをしたり、相手意識に立って分かりやすいように写真や動画・クイズなどを取り入れたりなど、教科で学習したことを自分の発表につなげている姿も見られました。このような経験が、これからの教科学習を学ぶさらなる意欲につながっていくことになると思います。さらに、発表会を通して友だちの取り組みや自分の活動を振り返ったことで、友だちのよさ・自分のがんばりを認めることもできました。




今年度、筑摩小の目指す姿の合い言葉は「チャレンジ! 始める一歩・続ける一歩」です。フリースタイルプロジェクトは、今年度初めての「チャレンジ!」でした。試行錯誤をしながら「始めの一歩」を踏み出しました。今年度の取り組みを子どもと職員で共有し、来年度へ向け「続ける一歩」を踏み出していきます。
リーディングスクール・アソシエイト校 菅野中学校
「ともに伝え合い、学び合う風土をつくる」
「協働」をテーマに、豊かな対話をベースとした授業・活動を通して、生徒の思考力・表現力、関係性の高まりを目指してきた菅野中学校。生徒たちが日常的に「思い・考え」を伝え合う環境づくりを目指し、この11月から全校で「コの字型の座席配置」を実施することに踏み出しました。

実施に先立って、先生たちがその意義を協議し、さらに全校集会で校長先生から提案、生徒たちとも「コの字型」での学びの意味・目的を共有するなど、準備を重ねてきました。

実施後「授業で向かい合っているのでみんなの顔や授業中の反応・動きがよく見えて、自分にとってはこの席の方がいいと思った」といった生徒の感想や、「子どもが『ぜひ見に来て』というので、参観しました。子どもたちがかかわりあって学んでいてよかったです」という保護者のアンケートなど、まずは前向きなフィードバックを得ることができました。

一方で、今後の課題も明確に。「これまでとは異なる生徒の動きが生まれ、先生が戸惑うケースありました。10月の職員研修で畔上一康先生(長野短大学長)から『〈問い〉と〈場〉の工夫があればよりよく学べる生徒たち』という示唆をいただきましたが、『コの字』を活かした授業づくりにみんなで挑戦したいと思います。まずは先生たちみんなで、『コの字型』の手応えを交流したいと思います。」(研究主任 飯森先生)
「共に伝え合い、学び合う風土」を目指した菅野中学校の先生方の挑戦が続きます。
学びの改革パイオニア校 開智小学校
開智探究の日 ~学びの改革パイオニア校 授業公開~
11月6日(水曜日)、開智小学校では『開智探究の日』として、各クラスで行っている探究活動の公開授業を行いました。
今年度の開智小学校の学校づくりテーマ「自分をとりまく『人・もの・こと』とつながり、自らもとめて学び続けるこどもを育てる~『子どもが主人公』自他を認め合い、自分らしく学び続ける学校~」のもと、子どもたちは各クラスで生き生きと探究活動を進めています。
これまでWebページでも紹介している4年生と6年生の異学年探究では、子どもたちのかかわりがより一層深まりました。あるグループは、松本城の歴史や方言を題材としたタイムトラベル劇を制作していました。4年生はタイムマシンベルトやタイムスリップ音(Canvaとスクラッチを活用)を作ったり、6年生は原稿用紙に書かれた台本を付箋を使って修正したりするなど、それぞれが自分の得意なことを生かしながら、一つのものを創っていました。
子どもたちに質問すると、これまでの探究活動を嬉しそうに語る姿が見られ、子どもたちの探究が「自分のもの」になっていることを実感しました。

このような子どもたちの頼もしい姿を見る一方で、教師としてどのように伴走していったらいいのかと問い続けている開智小学校の先生方。10月30日(水曜日)には、長野短期大学学長 畔上先生をお招きし、「人間的営みとしての学び ~自ら探究する子どもを育てる~」とのテーマで職員研修を行い、教師のあり方について学びを深めましたが、今回の開智探究の日は改めて教師のあり方について考える機会となりました。「子どもが主人公」として自分らしく学び続ける学校を目指し、開智小学校の先生方の学びはこれからも続きます。
令和6年11月5日 更新
リーディングスクール 中山小学校
やわらかい雰囲気に包まれる中山小学校
この日、3・4年生の子どもたちは、松本大学から講師を招いて「走り方講座」を受講していました。講師の先生から、運動に必要な3つの要素は「フォーム」「力の入れ方とタイミング」「リズム」であることを教わった子どもたちは、大学生とともに音楽に合わせてラインを左右に飛び越える運動に取組みました。初めて出会ったお兄さん、お姉さんを相手に、あっという間に打ち解け、笑顔を交わしながら身体を動かしていました。

5年生はALTが発するいくつかの単語の発音を聞き、ある単語が出たら目の前の消しゴムをとるというゲームの中で、言葉を聞き分ける力を高めていました。和気あいあいと課題に取り組む子どもたちの姿がありました。また、廊下には、今年学級で収穫したコメについて、今後の活動への子どもたちの願いが書かれていました。子どもたちは12月上旬に実施予定の学校のお祭りで、収穫したコメで作った料理などを来校者にふるまう予定だそうです。

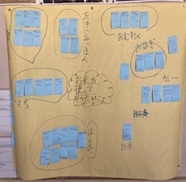
今回の訪問で感じたことは、どのクラスも雰囲気にやわらかさがあることでした。各学級で取り組んでいる生活科や総合的な学習の時間の中では、子どもの中でやりたいことがぶつかることが何度もあったでしょう。また、願いの実現に向け、地域の大人や他の学年の子どもたちに協力を求めることもあったかもしれません。そのような人と人との関わりの中で、他者を受け入れる寛容さや折り合いをつけ、みんなが楽しめる新しい考えを生み出したりする取り組みを経て、このようなやわらかな雰囲気が形作られるのではないかと感じました。
リーディングスクール 鎌田中学校
廃棄果実からバイオエタノール作りに挑戦! ~続報~
2学年のある学級は、総合的な学習の時間「Kmdタイム」の授業で、廃棄される果物を原料に、バイオエタノール作りに挑戦しています。
バーナーで煮詰めたぶどう果汁がフラスコの中でグツグツと弾け、甘い匂いが広がっています。このぶどう果汁は、廃棄予定のぶどうを回収してつぶし、酵母を加えて発酵させたものです。ぶどう果汁を加熱して気化したアルコールは、周囲を水で冷却した試験管内に、液体として取り出されます(写真参照)。蒸留と呼ばれるこの過程で抽出できるアルコールの量は、果物によって異なることが実験を通じて明らかになりました。スイカ<りんご<ぶどうの順に、多いアルコール量を得られます。1度の蒸留でアルコール濃度は低くても、2次蒸留によって60~70%の高い濃度になるものの、少量しか抽出されないことも確認されました。


「捨てられてしまうものを使い回せるのはよいことだが、廃棄される果物からエタノールを抽出するまでに、人や時間的な負担がかかることが今回の授業でわかった。量産する方法を考えなくては」。年度当初、「本当にバイオエタノールを作り出せるのか」と思案していた生徒たちの学びのまなざしは、量産方法を検討するフェーズへと向いています。
リーディングスクール・アソシエイト校 梓川中学校
私たちの梓川
「地域とともに歩む」ことを大切に考え高齢者宅を訪問した3年生。高齢者の方々が訪問を大変歓迎し喜んでくださったことに感謝しつつ、一人一人が感じた「梓川」の課題について追究を進め、「探究のあゆみ」としてまとめています。
高齢者から「一人なので大雨が降った時の避難が不安」という声を聴いたAさん。「大雨が降った時、梓川はどうなるのだろう?」という課題をもち、調べ始めました。以前、梓川地区では毎年にように水害に見舞われたがダムの完成により水害が減ったこと、またハザードマップからどの地区が水害を受けやすいかや氾濫した場合の避難方法等についても調べました。今後は、「避難所の安全性や水害災害に対しての松本市の取組」について追究していく予定です。

高齢者から「買い物などにでかける時に行く手段がない」という悩みを聴いたBさん。「のるーと松本」の梓川地区の利用率が低下し要望書を提出したことや、高齢者だけでなく高校生も家から近い駅がなく通学が大変なことを知りました。今後は「のるーと松本以外での高齢者の外出方法や高校生の通学状況(時間、距離)」などについて追究していく予定です。

高齢者の方の声より、自分たちが暮らす「梓川」について様々な課題に気づいた生徒たち。これから、それぞれが調べていることを発表し合い、友が気づいていない視点を出し合う機会をもつなど、互いに関わり合い学びを深め、それぞれの「探究のあゆみ」を進めていきます。
学びの改革パイオニア校 丸ノ内中学校
生成AIの可能性を探る 丸ノ内中DX
丸ノ内中学校では、年暦を作成する段階で、校内の研究や研修等を検討する「学びの戦略会議」と、職員研修の日を計画的に設定しています。学びの戦略会議では、職員のニーズに応じて、DXや探究に関する研修を企画していますが、今回DX担当チームから、「生成AIを活用した研修」が提案されました。
これからの時代、生成AIは教師の働き方や生徒の学び方を大きく変えていく可能性があります。生成AIをまず教師が使ってみることで、その可能性を体験的に学ぶということが、今回の研修の目的の一つでした。生成AIでは、求める結果を得るために入力する指示文や質問文である「プロンプト」が重要です。実際に使ってみると、「正確に物事を伝えないと、正しい答えが返ってこないので、国語の勉強になる。」「プロンプトの書き方で、回答が変わってくる。」など、指示や質問の重要性に気づくことができたようです。
丸ノ内中学校では、探究で重視している批判的思考力についても、生成AIを活用することで育むことができるのではないかと考えています。「生徒が探究で得たデータを生成AIに分析させ、その結果を考察することで、生徒は情報や分析の妥当性について批判的に考えることができます。教師も生徒の探究テーマについて、常に専門的な知識を持っているとは限りません。生成AIを活用することで、教師は生徒と共に学び、探究を深めることができるのではないか。」と、学びの戦略会議では、生成AIの活用の可能性に期待を寄せています。

今回の研修を通して、丸ノ内中学校の先生たちは、これまでの実践に加え、新たな働き方・学びのあり方を模索しています。パイオニア校としての挑戦は続きます。
令和6年10月28日 更新
リーディングスクール 清水中学校
学習オリエンテーション(2)を開催 ~表現力の育成に向けて、上半期をふりかえる~
全校研究テーマ「表現力が育つ~すべての活動を通して~」を、教師はもちろん、生徒も日々の活動で意識している清水中学校。10月3日に、第2回学習オリエンテーションが開催されました。前半は、全校が一堂に会して、事前にとったアンケート結果を共有しながら上半期の取組みをふりかえりました。その中で、ある生徒の回答(写真)が読みあげられた際に、多くの生徒がうなずきながら聞いているのが印象的でした。
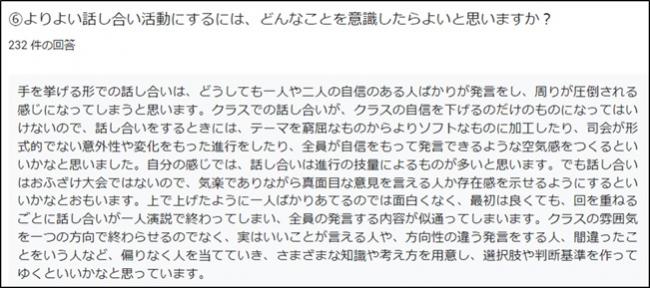
特に最後の一文から、「集団としての最適解・納得解を得るには、多様な他者との対話を通して合意形成をしていくことが大切だ」という思いを読み取ることができます。表現することへの気づきの深まりを感じられた学習オリエンテーションでした。
リーディングスクール・アソシエイト校 島立小学校
「やってよかった!」単元内自由進度学習
「学びのアップデート」を目指し、先生たちみんなで単元内自由進度学習の実践に取組んでいる島立小学校。高学年で専科(6年算数・5年社会)を担当されているM先生が、初めてこのスタイルの学習に挑戦されたと伺い、お話をお聴きしました。
実践は社会科の1単元(5年「暮らしを支える工業」)。昨年の5年の先生の実践を参考に、夏休み中に学習資料を作成されたそうです。実施にあたっては、子どもたちが新しい学び方に戸惑わないように、前単元で同様の学習資料を作り、一斉の授業の中で「学び方の練習」をするなど、丁寧に準備を進めてきました。
実践を終えてM先生は「実際にやってみてよかった!」と話されます。
「初めはなかなか進められない児童も、次第に自分で資料を見つけ書き込むなど、学び方に慣れていく様子でした。早めに進んだ児童は、それぞれ『発展課題』に挑戦していました。普段の授業ではあまり積極的ではなかった子どもが熱心に調べ学習カードに記述するなど、新たな子どもたちの姿に出会えました。また、子どもたちが書き込んだ一人ひとりの学習カードを見るのも楽しみでした。」


単元終了後、テストをしてみると、知識・理解が88%、思考・判断・表現が93%の到達度。「『見るだけ、聴くだけ』から、『自分で調べる・まとめる』に変わったことで定着度が高まったのではと思います」「みんなで確認したい動画等の資料の扱い方や、協同的な学びの場の位置づけなど、改善したい点も明らかになりました」とM先生はにこやかに話されました。
挑戦・練習・修正し、さらに挑戦…という成長のサイクルが先生たちにも子どもたちにも生まれている島立小学校です。
学びの改革パイオニア校 波田小学校
迎え入れて、みんなで関心を向けていく
「多様性を受容する学校づくり」に向けて歩んでいる波田小学校。
10月22日、岩川直樹先生(埼玉大学教育学部教授)が来校されました。4~6校時にすべての学級の子どもたちの姿を参観され、放課後には「多様な学びを考えるときに大切にしたいこと」をテーマに全職員で研修を深めました。

研修会は、子どもとの関係づくりに悩みながら取組む先生方が日々感じている思いを語り、岩川先生がそこにコメントを寄せるという対話形式で行われました。学びのペースがつかめない子どもへの対応に悩む担任を支える先生方の迷いや思い。先生方に支えてもらっている自分に葛藤しながらも、日々誠実に子どもに向き合おうとしている担任の迷いや思い。先生方が悩みや苦しみを開示し、それを受け止め支え合う温かくステキな会になりました。

【岩川先生のお話より】後悔はいっぱいありますよね。こうやればうまくいく、何かやればうまくいくとはならない。一喜一憂すること、それが大事ですよね。悪戦苦闘(子ども一人一人に誠実に向き合う努力)することが尊く大切なこと。教室に入れなかった子がちょっと入れるようになる、子どもが変わるときその傍らには悪戦苦闘がある。どんな子ども「よく来たね。どこでも学べるよ」と迎え入れることが何よりも大切ですよね。迎え入れて、その子にみんなで関心を向けている4人の先生方の姿に感動します。
全職員が「多様性を迎え入れる」意味を改めて問い直す機会になりました。
令和6年10月21日 更新
リーディングスクール 開成中学校
大きな節目を迎えました!
開成中学校の「『総合的な学習(開成タイム)』改革」も大きな節目を迎えています。先行して始めている3年生に続き、いよいよそれを1,2年生の総合にも広げていく時期がやってきたのです。
1年生は「進路コンパス」で取材してきた内容をグループで共有していました。来年度の職場体験に繋がる大事な場面で、取材内容を聞いていると「職業」を捉える根幹を成す内容も多く、大変興味深いものでした。
2年生は全体会で、今後の活動について説明を受けました。学年を「(1)地域の防災、(2)ナゼそこ!?ポツンと開成中、(3)伝統工芸、(4)郷土食」の4つに分けて探究をスタートする予定です。既に「コレ!」と決まっている生徒もいるように見えましたが、迷っている生徒もおり、あらためてタブレットで希望を募ることになります。

3年生はここまでやってきたことをまとめ、次の参観日に発表します。現在その準備も佳境に入っています。1学期から続けてきた活動がいよいよ形を成してきており、発表会が楽しみです。一部ですが、今回写真にて紹介させていただきます。

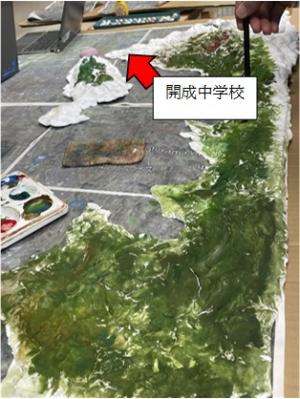 中山から開成中の地形模型
中山から開成中の地形模型
この発表を1,2年生は見に行きます。説明を受けただけでは今一つイメージできない生徒も、実際に活動してきた3年生の発表を見ることにより、これから自分たちが進めていく活動のイメージができることでしょう。
3年生は受験に向けて、開成タイムは一区切りとなります。探究の森が闇に包まれていた中、新たな道を切り開いた3年生。その背中を1,2年生は追って探究の森に入っていきます。大きな節目を迎えた開成中学校のこれからに注目です!
リーディングスクール 筑摩野中学校
学びを支える「問い」を協働的に学ぶ
「対話をベースとした協働的な学び」づくりに取組んでいる筑摩野中学校では、今年度、生徒の学びを支える「問い」と「振り返り」のあり方について、全職員が参加するLg(ラーニンググループ)研究会で考えを深め、実践を行っています。
8月22日に行われた第2回Lg研究会では、中心講師の村瀬公胤先生から学んだ「Let’s型の問い(~しよう!という形の問い)」と「W型の問い(なに?いつ?どれ?という形の問い)」の2種の「問い」を実際に作り、それぞれの「問い」によって生じる思考の過程を体験するワークショップを行いました。
先生たちが考えた「問い」をいくつかご紹介します。
★Let’s型の問い
「このクラスの全員が笑顔になるためにできることを考えよう。」
「学校でしてはいけないことを考えよう」
★W型の問い
「あなたが安心して過ごせない姿はどれ?」
「最も危険なのはどの子?」
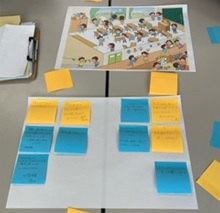
このワークショップを通して、先生方は様々な気づきを交流しました。
「いろいろな視点で物事を見ることで、たくさんの問いを作ることができると思った。」
「生徒の立場で答えると、W型の問いの方が答えやすく、書きやすいと感じた。」
「子どもに気づいてほしいことや考えてほしいことを明確にして問いを考えることが必要だと感じた。」

協働的な学びを支える、大切な「問い」。
先生たちも、協働的に学びを深めます。
リーディングスクール・アソシエイト校 開明小学校
個々の課題を協働的に学び合う先生たち
「クリーム・あんこ」「チーズ」「ブルーベリーアイス」「カスタード」「チョコ」「さつまいも」…開明小の研究グループのなんともおいしそうな名前です。「『~たい』から始める授業づくり」に取り組んでいる開明小の「重点研究会=たい焼きタイム」から、たい焼きの中身にちなんで名付けられました。

2学期の「たい焼きタイム」では先生たち一人ひとりの「自己課題」に挑戦する授業づくりをグループの先生たちと相談しながら進め、授業公開し、学び合います。
授業公開は信州大の谷内教授や中信教育事務所の担当指導主事を招いて、2学期だけで4回実施。授業者は手上げ方式で、今回(10月17日)の4人もあっという間に決まったといいます。先生たちが「~たい」に満ちているのが感じられます。
授業後の研究会では授業の具体的な子ども姿について、活発で和やかな語り合いが続きます。授業者の先生と一緒に授業を作ってきたことで、グループの先生たちにとって公開授業が「自分事」なっているのでしょう。先生たちが子どもたちの「内面」にまで思いを寄せて語り合う様子が印象的でした。

助言者の吉沢寛之先生(中信教事指導主事)からは「子どもたちの姿を通して先生たちがエネルギーを高める素敵な時間ですね」と励ましのメッセージが贈られました。
個々の課題を協働的に学び、同僚性をますます深める開明小の先生たちです。
令和6年10月15日 更新
リーディングスクール 明善小学校
「きもちにあうおと、みっけ!」
「天までとどけ、1、2、3!」みんなで声を合わせて、くじらぐもにとびのった1年1組の子どもたち。

くじらぐもにのったときの気持ちを『学びノート』に記しました。
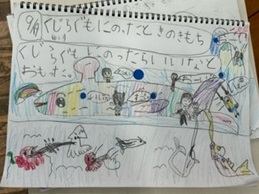
さらに、音遊びで親しんだ打楽器でいろいろな演奏の仕方を試しながら、くじらぐもにのった時の気持ちに合った音さがしをしました。

「ふわふわ」「きもち~!」「楽しいんですけど~!」など、どのように鳴らせば自分の気持ちを表すことができるのか考えました。
リーディングスクール・アソシエイト校 旭町中学校
Canvaを活用した子ども観の捉えなおし
「先生たちがまず使ってみる経験を広げていきたい」と願う篠田研究主任。夏休みの研修に引き続き、先日行われた教育課程研究協議会においても、Canvaを活用した授業研究会を実施しました。
この授業研究会でCanvaを使うには、3つのねらいがありました。
1 参観者が生徒の学びの姿をCanvaでまとめることで、後日生徒が自分の学びを客観的に見ることができる。(まとめられたプリントを廊下に掲示)
2 授業者が、一人では見きれない生徒の姿を、実際の姿(写真とコメント)で参観者からフィードバックがもらえる。
3 参観者が、主体的に生徒の学びを見つめ、生徒の学びに起こっていることを丁寧に考察し、表現できる。
授業研究会では、それぞれの作ったプリントを真ん中に置き、生徒の学びを語り合いました。「Canvaでまとめる際に写真を使うため、今まで以上に生徒の表情に注目したり、生徒の声にもしっかり耳を傾けたくなります。」と教頭先生が語るように、参加した先生方からも積極的な授業参加が見られました。そこで、旭町中学校では、参加した先生方一人一人がCanvaを使えるように、Canvaの研修を行いました。そのあとに授業を参観して、生徒の学びをCanvaでまとめました。

子どもの姿で語り合うことで子ども観を捉えなおし、そこから授業のあり方を考え直していくことにつながっていきます。 旭町中学校では、Kjk(気軽に授業を公開しよう)の会があります。Canvaを一つのツールとして子どもの姿を語り合っていく旭町中学校。生徒の「学びたい」を大切にした授業が、多くのクラスで広がっていきそうです。
学びの改革パイオニア校 波田中学校
6年生が中学校で授業体験!
「中1ギャップ」の軽減を目指し、児童・生徒の願いをベースにした小中連携に取り組んでいる波田中学校・波田小学校。6年生に「中学校生活について知りたいこと・不安なこと」についてアンケートを取ったところ、「授業」がもっとも多く出てきたものの一つでした。そこで、小学校で学習した内容を踏まえ、「中学校で、中学校の先生による、少し発展的な授業を体験しよう!」と計画しました。
事前に、中学校の理科の先生たちが小学校に赴き、理科専科の先生と体験授業のねらいと方法を共有し、6年生が学習した理科の小単元「生物と食べ物のつながり」について、中学校で学習する「食物連鎖」との系統性を踏まえて、内容を検討しました。ちょうど6学年4学級に対して、中学校の理科教員も4名であったため、各クラスを1名ずつが担当して、1時間の授業を実施することにしました。学習指導案と教材を作成し、理科教科会で共有して互いに授業を見合うなど、日常の授業改善を図る機会ともなりました。

本時は「ライオンとシマウマの数の関係は、どうなっているのだろうか?」という学習問題をたて、既習事項をもとに予想し、疑似的な観察・実験を通して追究します。
子どもたちは、夢中になってこの疑似的な観察・実験に浸り込み、記録していきました。授業の終盤には、ライオンとシマウマの数を表とグラフにまとめ、増減の関係を考察しました。
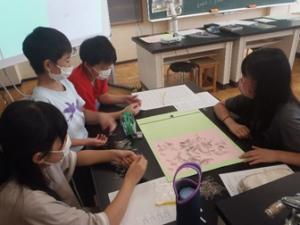
子どもの感想より
「まだ1回も行ったこともない見たこともないところ(中学)で理科をするという初めての体験でしたが、楽しかったです。食べる・食べられる関係を実際にやってみるとより深くわかりました」
柔らかな表情で小学校へ戻っていく子どもたち。波田中学校では、今後も子どもと教員の願いをベースにした小中連携を進めていきたいと考えています。
令和6年10月7日 更新
リーディングスクール 寿小学校
単元内自由進度学習の授業公開のその後
6月25日(火曜日)の授業公開後、授業者であったA先生は、別の単元でも自由進度学習を実践しました。子どもたちは「やった!また自分のペースでできる!あれ、楽しいんだよ」と前向きに捉え、熱心に取り組んでいました。さらに、全員が最後までやり遂げようとする姿に、子どもたちの大きな成長を感じました。

A先生と部会主任のB先生は、そんな子どもたちの成長を深く実感すると同時に、授業計画を立てる際に、自分たちの意識も変わってきたことを次のように語られました。
(A先生)授業用の自作プリントを作成する際、子どもたちが1枚でこなせる量を考慮するようになりました。また、口頭での説明をプリントにも明示し、子どもたちが自己解決できる方法や工夫を意識するようになりました。今後は、小さなことでも子どもたちが「これやりたい!」と自発的に動ける姿を目指したいと思っています。
(B先生)授業で育てたい力を明確にし、そのゴールに向けて単元を構想するようになりました。これまでも続けてきたことですが、改めて単元全体を見通して授業を組み立てることの重要性を実感しています。
リーディングスクール・アソシエイト校 女鳥羽中学校
教科で探究的な学びに挑戦
2年生理科「電流の性質」の授業です。電流計や電圧計を用いて、回路を流れる「電流」の規則性を見出す単元ですが、授業者の北原先生は「『やらされ感』がある授業から、生徒が『問い』をもって探究的に学ぶ授業へ挑戦したい!」という願いをもって単元を構想しました。
授業に先立って、生徒たちが「自分ごと」として予想を立て実験に臨めるよう、実験器具を2人に1セット準備、また、生徒が「電流の大きさ」を直に感じられるよう、通常は「抵抗器」を使うところに「豆電球」をおくなど、生徒の思考を予想して準備をしてきました。
本時は、今まで1つだった「豆電球」を二つ直列でつないだ様子をみんなで見るところからスタート。予想したよりもずっと暗い電球の光り方を観察した生徒たちは、「電流値」について、様々な予想を立てました。続く追究場面では、繰り返し測定できる実験器具を使い、心行くまで測定を進める生徒たち。測定結果はタブレットを用いてリアルタイムに共有されます。「電流の減り方と光り方が違うぞ」「並列にするとどうなるのだろう」といった気づきや新たな問いが生まれ、時間いっぱい「探究」を続けました。


北原先生は「生徒たち一人ひとりが自分の課題をもち、考察を書きました。生徒たちがこうしたら、こうしよう、とすごく考えたのですが、考え抜いて授業に臨むと、子どもたちは「学ぶ姿」で応えてくれることを実感しました。」と授業を振り返られました。
放課後、授業を参観した女鳥羽中の先生たちが集まり、恒例の「座談会」で子どもたちの学びの様子を語り合います。助言者の中村真由子先生(大東文化大)は「授業参観している先生たちの表情がよかった」と話されました。
先生方の「挑戦」と「温かいまなざし」の中で、女鳥羽中の生徒たちは、さらに「自由に」学んでいきます。
学びの改革パイオニア校 田川小学校
授業をみんなで考える「チューニング」
11月22日に行う探究にかかわる授業公開に向け、今後の活動のねらいや子どもたちの育ちの見通しがもてるようにと、「チューニング」※1を行いました。
昨年度から何度か行っていることもあり、チューニングが始まると提案者の考えや問いに対して、グループメンバーの先生方(アドバイザー)は親身になって授業の展開や子どもの可能性を語っていました。
チューニングを終えて、提案者の先生は「自分の疑問がいろんな先生がお話ししていただいたことによって、やっぱりなんかクリアになる部分が多かったな。授業の内容を1つに決めなくてもいいのかも。色々あってもいいかなって思いました。」(笠原先生)「一つの狭いところに絞るのではなく、もっと広がるような、一人一人の追究があるような、子どもたちが『こうしたい』って言うことに乗っかっていくのもいいかなと思いました。」(竹内先生)と、今後の授業に対して前向きになった気持ちを語られました。

このように先生たちが、一つの授業に対してアイディアを出し合っていくことで、一人一人に当事者意識が生まれ、貢献意欲も高まってきます。チューニングを終えた後も、その先生の授業について話している田川小の先生方の姿が素敵でした。普段の職員室でも、子どもを真ん中に授業の様子を語り合っている姿がたくさんあるといいます。
田川小学校の先生方が、子どもの学びのために一緒に作っていく授業の歩み。公開授業だけでなく、日々の授業にどんなドラマが生まれてくるのか楽しみです。
※1チューニングとは、軽井沢風越学園で行っているディスカッションの手法で、単元の設計段階や進行中に、建設的なフィードバックや担任が考えつかなかったアイディアを得たり、想定していなかった問題点に気づいたりするためのものです。
令和6年9月30日 更新
リーディングスクール 筑摩小学校
2学期もスタート 単元内自由進度学習!
「学期に1回は自由進度学習をやろう」を合言葉に歩みを進めている筑摩小学校。9月中旬には、6年生2クラスが、算数「場合を順序よく整理して」と社会「今に伝わる室町文化」の2教科を組み合わせた単元内自由進度学習(12時間)を実施しました。授業が始まると、子どもたちは自分が学びたい場所へ移動し、問題に取組んでいきます。

「赤、青、黄、緑、白、黒の6種類の色紙から4種類をえらんで組にします。組み合わせは全部で何とおりありますか」という問題を追究し始めたAさん。6種類の色を書き、白と黒に×をつけた後、どのように表をつくればよいか困っていると、先生が来て「前時のように、選ばない色に×をつけたら」と助言します。Aさんは、選ばない2種類に順序よく×をつけながら表をつくり「15通り」と導き出し、「めちゃ楽じゃん」とつぶやきました。さらにAさんは、困っているBさんに「俺、教えてあげるよ」と自分のやり方を説明しました。Bさんは、助言をもとに表に順序よく2個ずつ×をつけながら求めると「このやり方、楽だね」と言いました。

Aさんの困り感に寄り添った先生の適時の支援が拓いた学びの姿。子ども一人一人の学びを把握しながら先生が支援に注力できる自由進度学習のよさが光った場面でした。
リーディングスクール・アソシエイト校 菅野中学校
「自分ごとの学び」へのステップアップ
菅野中学校の2年生は「総合的な学習の時間」で5つの講座に分かれて探究活動を行っています。そのうち「防災」を選択している45名の生徒たちの学びの一コマを紹介します。
これまで、「マインクラフト」で菅野地域の3Dマップを作成し、「バーチャル洪水」を体験するなどの活動をしてきた生徒たちが、この時間「本当に水害が起きたら自分たちの生活はどうなる?」という問いに取組みました。
冒頭、8月14日に実際に菅野地域で起きた局地的な大雨によるアンダーパス水没のニュースを食い入るように見た生徒たち。その後のグループ活動の中で、活発に対話しながら、自分の考えを「イメージマップ」に豊かに記述していきました。

あるグループでは、具体的な生活場面を想定して、避難所での生活に必要なもの、持って行かれないもの等について意見を出し合い、深め合っていました。
これまで、どこか「他人事」だった「水害」が、生徒たちにとって「自分ごと」に変わっていく学びの時間となりました。この「必要感」をベースに、生徒たちは水害への備えについて、「自分たちにできること」を考え、共有していきます。
学びの改革パイオニア校 開智小学校
ミニアウトプット会~総合的な学習の時間中間発表会~
開智小学校の4年生と6年生による、総合的な学習の時間の中間発表会「ミニアウトプット会」が開催されました。この会は、異学年が協働する新たな試みの中で、子どもたちが互いの活動に興味を持ち、「他のグループはどんなことをしているのだろう?」という声に応える形で企画されました。
この会の目的は、子どもたちが発表を通して、
〇相手からフィードバックをもらう
〇聞いている人とともに、今後の活動の方向を考える
ことでした。初めての試みということもあり、先生方が6年生の発表に対してフィードバックの手本を示しました。フィードバックでは、発表者の考えを受け入れ、積極的に質問したり、新たなアイデアを提示したりすることで、発表者が勇気づけられるような雰囲気作りを心がけました。

中間発表では、すでに調査を終え、まとめの段階に入っているグループや、今後の活動の方向性に悩んでいるグループなど、様々な段階の子どもたちがいました。しかし、発表を通して、
〇他者からの素朴な疑問やアイデアが、新たな探究のヒントになる
〇互いの活動を知り、刺激し合うことで、探究意欲を高める
といった効果がありそうです。

6年生は、丸ノ内中学校で行われる総合的な学習の時間のアウトプットデイにも参加して、アウトプットの仕方やフィードバックの仕方について、更に学び深め、自分の探究に生かしていく予定です。自分たちも経験したからこそ得られる学びがきっとあると思います。
令和6年9月24日 更新
リーディングスクール 鎌田中学校
廃棄果実からバイオエタノール作りに挑戦!
総合的な学習の時間「Kmdタイム」では、「私たちはこの地域のために何ができるか」を問いの出発点として学びを深めていきます。
2年のある学級では、「バイオエタノールの可能性~松本市の廃棄果実から~」をテーマに、廃棄される果物からバイオエタノールを作ることに挑戦しています。バイオエタノールは、生ごみや木くず、作物などから製造するエタノールのことです。県内のガソリン価格の高騰と松本市で廃棄される果物に着目して、バイオエタノール作りの着想を得ました。
日本では馴染みの薄いものですが、「アメリカはトウモロコシ、ブラジルはサトウキビを使ってバイオエタノールを製造し、アメリカとブラジルで世界の70%のシェアを占めている」という現状があるようです。
生徒は、廃棄されるスイカから果汁を取り出し、この果汁に酵母を加えて発酵させます。スイカ果汁とともに、酵母量を変えた砂糖水も準備しました。2週間後、これらの水溶液のアルコール濃度はどのように変化するかを実験しています。


生徒たちは、「もし、本当にバイオエタノールができれば、(化石燃料に代わることから)地球温暖化対策になると思う」「地球温暖化のことを考えると、まず動いてみることで変えられる世界がある」と述べ、私たちの住む環境を自分たちの手で変えようとしています。
リーディングスクール・アソシエイト校 島立小学校
2学期、「学びのアップデート」に歩み出す
1学期末の「一日研修」で全ての先生が2学期の「自由進度学習」の構想を立てた島立小学校。9月を迎えいよいよ実践がスタートしました。
全校に先駆けて授業を公開したのは2年生の先生たちです。学年の2人の先生が協力し、算数の自由進度学習の単元づくりに挑戦しました。
初めて経験する学び方に触れた子どもたちからは「自分のペースでできてうれしい」「友だちへの説明が上手にできてうれしい。」「途中、レッスンコーナー(やり方を確認したり、進め方が分からない子への支援をしたりする全体指導の場)があってよかった。」といった声が寄せられました。
実践された先生からも「一斉授業では生まれなかった子どもたち同士の関わり合いがあり、自分から進んで取り組む姿がみられたことが新鮮。」「一人一人の児童の様子がわかり、必要な支援ができた」といったメリットや「教材の吟味の必要性」「評価のあり方」といった課題が振り返られました。
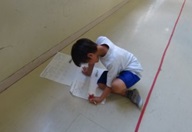 一人で学ぶ
一人で学ぶ
 みんなと学ぶ
みんなと学ぶ
このような子どもの姿や先生たちの振り返りを共有し、島立小学校では、「学びのアップデート」をみんなで進めていきます。
リーディングスクール・アソシエイト校 梓川中学校
~ もっと関われるようにしたい! ~
「地域とともに歩む」ことを目指している梓川中学校。3年生は、地域の方の要望に応え、卒業した3年生が行った「高齢者のお宅を訪問し、地域のことを学んだり困りごとを聞いたりする活動」を引き継ぐこととし、グループに分かれ訪問しました(リーディングスクール通信No28参照)。

【生徒の感想より】
〇訪問したAさんは、すごく姿勢がよくてすごく若く見えました。…旦那さんも亡くなられて一人で寂しいと言っていました。また、通りかかったときにでも来てほしいと言っていたので、また行きたいと思います。中庭の草むしりなどできることをやったり、もっと関われるようにしたいです。
〇小豆をとる作業をしながらお話をするのはとても楽しかったし、1時間がとても短く感じました。一人暮らしだったので、私たちが来たことをとても喜んでくださったので、私もうれしかったです。梓川や三郷あたりの戦時中のお話を聞く貴重な機会になりました。

生徒たちは、高齢者宅の訪問を通して、昔の梓川の様子について聞いたり、高齢者の方が普段どんな生活をしているのか知ったりする機会になり、「また会いに行きたい、できることを手伝いたい」という思いを強くしました。今後は、お話をする中で知った「困りごとや地域の課題」について、どんなことができそうかアイディアを出し合う予定です。
梓川地区のお年寄りに笑顔と元気を届けられるよう3年生の活動は続きます。
令和6年9月17日 更新
リーディングスクール 清水中学校
一人ひとりが活躍できる=多様な考えを受け入れる(表現力の育成)
2学期が始まって間もない8月下旬、清流総合発表会に向けた生徒集会が開催されました。「一人ひとりが活躍できる生徒会にしたい」という生徒会長の願いを受け、生徒会総務や各委員会から告知がなされました。総務からは、生徒会企画の有志発表に数学や自作プログラムの探究成果、英語劇など計6組が出演予定であり、さらにMcや小道具づくりの希望者を募集していることが伝えられました。整美委員会・生活委員会からは、校歌のミュージックビデオ作りを各クラスで分担して行うので、積極的に制作に関わってほしいという呼びかけがなされました。
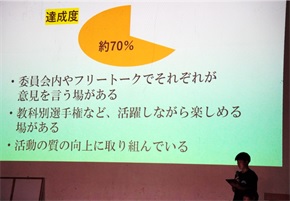
このように、生徒が自分の取り組んできたことを表現したり、その取組みや各グループの考えなどを周りの生徒が受け入れたりする経験を重ねていくことは、お互いを認め合うことになり、一人ひとりが活躍できることにつながっていくものです。清流総合発表会に向けた生徒の熱い思いを、教師も同じ熱量で支えていることで、全校研究テーマ「表現力が育つ~すべての活動を通して~」が具現されている清水中学校です。
学びの改革パイオニア校 波田小学校
園児に本の読み聞かせをしたい!
「やってみたいこと・挑戦したいことを実現できる学校」に歩みを進めている波田小学校。
2年5組の子どもたちは、4月に学習した国語の「ふきのとう」の音読に自信を深め、学年で音読発表会をした経験から「保育園の子(以下園児)に本の読み聞かせをしたい」という願いをもちました。さらに地区探検の学習をきっかけに、波田地区には保育園がいくつかあることを知り、保育園の頃の思い出話をする中で、保育園の子どもたちと交流したいという思いを強くしました。
そこで、波田中央保育園の年長園児と交流会を開くことにしました。「園児に楽しんでもらいたい」という願いを実現するために、読み聞かせに加え、「じゃんけん列車」や「股くぐりリレー」など、年下の子と一緒に楽しめる内容を考え、やり方や伝え方の練習をして当日に臨みました。
本の読み聞かせでは、園児が集中してお話を聞いてくれました。早く読み終わったグループの子たちは、自主的に園児に話しかけ、名前や好きなものを伝え合う姿も見られました。

「じゃんけん列車」や「股くぐりリレー」は園児と一緒になって楽しみました。じゃんけん列車は「園児との交流」を意識し、進んで園児とじゃんけんをして列になっていました。最後の一列になるときには大盛り上がりでした。初めての園児との交流会は、大変楽しい時間となり、「また交流したい」という思いをもちました。

2年生では、全クラスで交流会を実施し、「園児と交流したい」という願いを実現させていきます。
リーディングスクール・アソシエイト校 開明小学校
先生たちが地域の魅力を探索「地域たいやき研修」
「たいやき」をメインキャラクターに、子どもの「~たい」から始まる授業づくり・学校づくりに取り組んでいる開明小学校では、夏休みの一日、「地域たいやき研修」を実施しました。
この研修の目的は「先生たち自身が地域を知り、地域とつながりを深めるきっかけを作ること」。
当日、先生たちは特製の名刺を一人10枚(!)もち、地域へ出かけていきました。
地域の方々は「飛び込み」で訪問した先生たちを温かく迎え入れ、それは熱心にお話をしてくださったそうです。
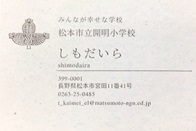
職員室の住宅地図には、先生たちが「つながった」地域の「ひと・もの・こと」が書き込まれていきました。

先生たちの、この「学び」は子どもたちの「~たい」の学びに、必ずつながっていくことでしょう。
令和6年9月9日 更新
リーディングスクール 開成中学校
「広がりと、深まり」~夏休み職員研修会より~
本年度、探究的な学びの本丸「総合的な学習」の改革を進めている開成中学校。前回のWebページでもご紹介したように、1学期は3年生の「総合的な学習(=開成タイム)」を大きく変えて実施しました。2学期はこれを1,2年生の総合にも広げていくことになります。昨年度から丁寧に進めてきた改革の最終段階となります。そして、開成中ではもはや恒例となりつつある「夏休み研修会」にて、教育研修センター堀内指導主事を招いて学習会を開き、最終段階に向けた意識合わせを図りました。
前半は、先行してスタートしている3年生の成果や課題を共有し、1,2年生も含めた2学期以降の開成タイムをどう進めていくのか、具体的なイメージを持ちました。
後半は研究主任が用意したチョコレートを題材に、堀内主導主事がファシリテーターとなり、わずかな時間ではありますが職員一人ひとりが「探究」しました。体験して考えながら説明を受けたので腑に落ちる部分が多かったと思います。「チョコレート」という1つの題材にも、様々な探求の芽があること、他者と適切な場面で話すことで、自分自身が持っている「これを調べてみたい」というものがより明確になってくること等々を体感できたことは貴重な経験になりました。


もちろん、これで全てがクリアになって2学期を迎えられるという訳ではありませんが、「開成タイムが向かう先に一筋の光が見えた!」そんな気持ちになる研修会でした。
リーディングスクール 筑摩野中学校
7月の村瀬先生の授業クリニック
筑摩野中学校では7月17日に麻布教育ラボの所長村瀬公胤先生を招き、授業クリニックを行いました。教室訪問で参観した授業について村瀬先生からアドバイスをいただいたり、2年生の国語の短歌の授業を全職員で共同参観し、授業懇談会を開き、村瀬先生のお話を聞いたりしました。その中で、協働の学びの妨げになる避けた方がいいことを教えていただきました。
(1)ぼんやりとした問い
「どのような」という問いはぼんやりしていて答えにくい。また、前時の振り返りが長すぎる(すべて説明してしまう)と大事なところがぼんやりしてしまう。
(2)Let’s型(~しよう)の課題
子どもが何についてどうするのかわかるまで時間がかかる。「どちら・どれ」や「どこ」のW型の課題の方が学び合い、協働的な学びにはつながりやすい。ある子どもが「こっちかな」というと、「え、そっちなの?」と突っ込みが入る、これが学びの出発点になる。
(3)班で1つに決める
親しむ前にいきなり短歌を選ぶのは難しい。全員で1つの歌、1人1つの歌でも良い。個人の学びの保障をする。
(4)1班に1つのホワイトボード
班に1つだと誰かの考えになってしまいがち。全員がペンを持つだけでも違う。1人1枚のシートで4枚のシートを1枚にする等、4人グループの学びをすることも可能。


村瀬先生は「教育実践に100%の正解もないし、100%の間違いもない、ただ、子どもにとってこの1時間はどんな学びがあったのかをみること、そして、授業者が挑戦し続けることが大事である」と話されました。また、「協働的で探究的な学習とは、学び手が選び、考え、表現する学習」であることを、具体例を示しながら、あらためて示唆されました。定義・事実は1つでも、それをどのように納得するか、意味づけるかは子どもの数だけあります。クリニックを活かし、2学期も「教科書スタート、子どもの表現がゴールになるような授業」を目指して取り組んでいきます。
令和6年9月2日 更新
リーディングスクール 明善小学校
4年生「こども先生 登場!」
「こども授業グループ」の児童が『先生』になって算数の授業をしました。教科書にはない「色々なグラフについて」という内容です。自分たちで調べ、進め方を工夫し、電子黒板やタブレットを効果的に用いながら、『こども先生』も子どもたちも、生き生きと共に1時間をつくる姿が印象的でした。
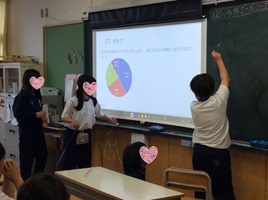
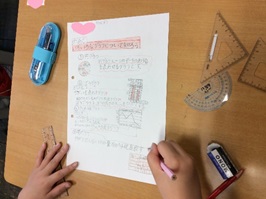

リーディングスクール・アソシエイト校 旭町中学校
自分でやってみるから見えてくること(大人学びは子どもの学びの相似形)
旭町中学校では、教師が自ら「探究」を体験する取り組みを行っています。夏休みの初めにミニ探究やCanvaの使い方を学んだ先生方。夏休み中には“「自分の好きなこと」をテーマに、Canvaを使って表現しよう”という課題が出されました。
あるラーメン好きの先生は、こだわりのラーメン店を紹介するポスターを作成。同僚と実際に店を訪れる計画を立て、探究は授業にとどまらず、私生活にも広がりました。また、松本上土通りを紹介した教員は、他の教員の地図を見て、自身のポスターを改良しました。教職員同士で作品を共有し、意見交換することで、表現方法や伝え方の工夫を学びました。この経験を通して、「探究は、新たな知識や疑問を生み出す面白い活動だ」と感じた教員が多くいました。
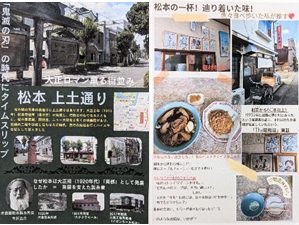
今回の取り組みで、教職員は、探究活動が単なる課題ではなく、自ら学び、成長する機会であることを実感しました。生徒にも、このような主体的な学びの機会を提供することで、探究心を育み、自ら課題を見つけ解決する力を養いたいと考えています。
学びの改革パイオニア校 波田中学校
波田中学校 ~「ブレーキことば」をゆるめる3ステップ!~
波田中の1年生は「自己肯定感の醸成」を目指して、昨年度から信州大学学術研究院教育学系准教授高橋史先生が提案されている「ライフスキルアップ授業(全6時間)」に取組んでいます。
8月28日には第三回「ブレーキをゆるめてみよう」を道徳の時間に実施しました。
「結果ばかりに意識を向けると、『みんなからどう思われるだろう』『やってもムダ』などというブレーキことばが出てきやすい」ことを身近な事例から学んだ生徒たちは、その後、「(1)ブレーキことばを見つける、(2)ブレーキことばに優しく(優しい言葉かけをする)、(3)自分(または相手)を元気づける言葉かけをする」という「ブレーキことばをゆるめる3ステップ」について、具体的な事例を通して学び合いました。

授業後、ある生徒は「ブレーキことばを使わないようにして、落ち込んでいる友達を励ましていきたい。ブレーキことばを意識していくと、もう1回やってみようという気持ちになると思う」と語っていました。「ブレーキことば」をかけやすい日頃の自分の姿に気づき、自分や友達を勇気づけていくステップを学ぶ機会となりました。
「自分のよさに気づき認める」ことを願い、ライフスキルアップ授業は続きます。
令和6年8月26日 更新
リーディングスクール 寿小学校
リーデングスクール校の実践を各校へ
6月25日(火曜日)に松本市教育研修センターの研修講座『実践校に学ぶ 単元内自由進度学習』が寿小学校で行われ、大変多くの先生方が参加されました。2年生、4年生の公開授業後に開催された「語り合いの会」では、寿小が重視する「子どもに委ねる学び」「学習の進め方を自ら調整する力の育成」「多様な学習の進め方を実践できる環境整備」などについて、主体的に活動する子どもたちの姿を見た先生方からたくさんの質問が寄せられました。


参加者から寄せられたリフレクションシートには、「45分間、目を輝かせながら学習に向かう子どもの姿を目の当たりにした。子どもに委ねることは勇気がいるが、本研修で得たことをもとに学年で連携して実践したい」「子どもが主体的に目標に向かい、自己調整しながら進める単元内自由進度学習は、個別最適な学びを実現する学習方法として非常に優れていると実感した」という声が寄せられました。

リーディングスクール・アソシエイト校 女鳥羽中学校
生徒主体の学習にチャレンジ
「ほんとうに自由に学べる教室」をテーマに、学校づくり・授業づくりに取り組んでいる女鳥羽中学校。今年度、様々な場面で先生たちが「生徒の個の学びの成立」と「豊かな関係性の醸成」を目指してチャレンジを続けています。
7月には初任の先生が「単元内自由進度学習」(社会科)に挑戦し、全校の先生方に授業公開しました。九州地方について、各生徒が着目した「自然の特色を生かした営み」について、考えをまとめ表現する一連の単元の最後の授業。どの生徒も自分の「まとめ」にこだわりを持ち、粘り強く向き合う学びの姿がありました。

3年生は探究的な学習「プロジェクトM」に取組んでいます。「地域を知ろう!」というテーマのもと、「自然」「観光」「芸術」「産業」などの観点から「地域」を見つめなおし、生徒たち一人一人が「問い」を立てて学んでいます。
「まだまだ、ネットで調べを進める段階ですが、『地域のこと、知っているようで知らなかった』と振り返りながら、生徒たちは興味をもって学んでいます。今までにはなかった姿だと感じています。これから、どのように活動を展開していくか、私たちも悩みながら進めています。」と、総合的な学習主任のA先生。
生徒たちも、先生たちも、試行錯誤しながらともに「学び」にチャレンジを続ける女鳥羽中学校です。
学びの改革パイオニア校 田川小学校
6年生「交流」活動の今 ~続けるからこそ育まれてくること~
田川小学校6年生は、昨年から「交流」をテーマに探究活動を行っています。5年生の活動の様子は、市教育委員会のウェブサイトでも紹介されています。
6年生になった子どもたちは、これまでお世話になっている地域の方々との交流を深めたいと考え、学校への招待を計画していました。しかし、天候やタイミングが合わず、なかなか実現できずにいました。そんな中、国語の授業でインタビュー活動を行った際、地域の方から「学校に行くより来てほしい」との言葉を聞き、子どもたちは自分たちから福祉ひろばを訪れることを決意しました。
交流会では、子どもたちは校歌を歌ったり、リコーダーを演奏したりと披露しました。地域の方々とも一緒に大きなトランプで遊び、楽しい時間を過ごしました。最初は緊張していた子どもたちも、次第に笑顔が増え、会話も弾むようになりました。

5年生の頃は、自分たちが楽しいと思うことを中心に考えていた子どもたちですが、回を重ねるごとに、1年生との関わり方や地域の方への配慮など、相手への意識が高まってきました。また、子どもたちの活動がきっかけとなり、地域の方から学校への関心が高まり、新たなつながりが生まれています。
この取り組みを通して、子どもたちは、地域の一員として、地域の人々との関わりの中で相手を大切にすることを学んでいます。地域の方も、子どもたちの成長を温かく見守り、学校を支える存在となっています。

田川小学校では、今後も地域との連携を深め、子どもたちの学びを豊かにする様々な取り組みを進めていきます。
令和6年8月5日 更新
リーディングスクール 筑摩小学校
自分のペースで学びをデザインする!
「どの学年も1学期に1回は自由進度学習をやろう」を目標に研究を進めている筑摩小学校。7月中旬には、5年生が、算数「合同な図形」と保健「けがの防止」の2教科を組みわせた単元内自由進度学習(15時間)を実施しました。
算数では、子どもたちが自分のペースで問題に取組み、指定された所まで進むと、先生の所へ行きます。先生は、内容が理解できているか、その子に合わせた問題を出し、どうしてそうなるかを説明するよう問いかけます。子どもたちは「平行四辺形の4つの角をたすと360°で、平行四辺形の反対側の角(向かい合う角)の大きさは同じだから、360°から50°の2つの角を引く。260°になるから、それを2で割ると㋐の角(平行四辺形のもう一つの角)がわかる」のように自分の言葉で説明します。
保健では、タブレット内にある動画を適宜視聴しながら、問題を解いていました。
 先生の所に説明にいく子どもたち
先生の所に説明にいく子どもたち
 タブレットで動画を視聴する子どもたち
タブレットで動画を視聴する子どもたち
担任のF先生は「自由進度学習をやると、全員が説明にくるので、すべての子どもの理解の様子がわかるところがよい。頭で360°とわかっているつもりでも、口に出して説明していくことで360°の意味がさらにはっきりわかると思う」と語っていました。
子どもたち一人一人が、自分の学びをデザインしていくことを願い、筑摩小の歩みは続きます。
リーディングスクール 中山小学校
子どもたちの思いを醸成する ~4学年 地域を知る~
昨年度まで水辺の生き物との関係を深めてきた子どもたちは、4年生になっても水辺の生き物と継続してかかわっていきたいと考えていました。そんな子どもたちとの生活が始まる中で、担任の先生は、子どもたちの学びの視野を学校内から、学校を取り巻く地域へと広げることで、さらに豊かな学びを子どもたちと味わいたいと考えるようになりました。
そこで、担任の先生は地域の民話『泉小太郎』を子どもたちに紹介しました。「知ってる」「ちょっと知っている」など、子どもたちの反応は意外にもバラバラでした。昨年度の先輩が『泉小太郎』の劇を披露してくれたにも関わらず、です。そこで先生は泉小太郎の本を何種類か用意し、時間をかけて読み比べる場を設けました。子どもたちからは、「泉小太郎って〇〇な人なんだね」などと、地域の民話への理解を深めたり、関心を高めたりする姿がありました。

少しずつ、子どもたちの視野は地域へ向き始めました。一方、教室には水辺の生き物が水槽で飼育されています。子どものやりたい、かかわりたいが、4年生の教室には保証されています。
リーディングスクール・アソシエイト校 菅野中学校
「体験」に浸りこむ学び
菅野中学校では、学びのテーマ「協働」を生徒と共有し、生徒主体の学びづくりに挑戦しています。その取組の一つとして、今年度、「総合的な学習の時間」のあり方を大きく見直し、生徒たちが自分が選んだテーマについて、心行くまで学ぶことができる「探究の学び」の実現を目指します。
1・2年生は「防災」「福祉」等のテーマ別講座に分かれ、探究活動を進めてきましたが、7月18日(木曜日)、「総合的な学習の日」として、それぞれの計画に基づき、「一日探究」に挑戦しました。
校区の公民館で大学の先生の支援を受けながら地域の防災3Dマップ作りに取組む生徒、運動公園でスポーツ活動を思い切り楽しむ生徒、地域の用水路を足を使って探索する生徒…。仲間とともに体験に思い切り浸る時間が実現しました。


心行くまで取組んだ「共通体験」を振り返る中で、生徒たちがどのように「問い」を育んでいくのか、これからが楽しみです。
令和6年7月26日 更新
リーディングスクール 鎌田中学校
長野県のリサイクル率を松本市から改善したい
総合的な学習の時間「Kmdタイム」では、「私たちはこの地域のために何ができるか」を問いの出発点として学びを深めていきます。
2年生のある学級では、興味関心のあるテーマごとにグループを作り学習を深めています。そのグループの1つは、リサイクル問題に興味をもっています。
「長野県のリサイクル率は、全国が20.3%であることに対して、17.5%と低い。リサイクルへの関心を高めるための動画を作りたい。またリサイクルの重要性を伝えるだけでは忘れてしまうため、パンフレット作りを目指したい。自分たちが頑張って、長野県のリサイクル率を松本市から改善し、環境問題の改善につなげられればと思う」。
生徒の学びはどのように展開されるのか、これからの学びに期待が増します。
 フードロスについて調べる生徒たち
フードロスについて調べる生徒たち
 農産物直売所でインタビュー
農産物直売所でインタビュー
リーディングスクール・アソシエイト校 梓川中学校
~ 梓川地区の方々の思いとは! ~
昨年の3年生のように「地域の必要感から、自分たちができることを考え、地域に関する活動をしたい」と考えている3年生。先日、学年集会を開き、地域連携主任のK先生が、梓川地区で「何を学びたいか」のアンケート結果を報告しました。
3年生のアンケート結果は次の通りです。
・梓川地区の歴史を学びたい ・地域の特産物リンゴについて知りたい ・過去の地区の様子を知りたい ・災害時などのボランティア活動について自分でできることを調べたい など
その後、地域の公民館活動をされているAさんが、「地域の方々の思い」として、3年生に次のように語りました。
「今、梓川地区では高齢者が増えています。昨年の3年生が高齢者宅を回り、高齢者の困りごとを聞いてくれました。高齢者の方々は、そのことがとても嬉しく『3年生が卒業すると寂しくなる』などと話していました。できるなら、その活動を継続してもらえると嬉しいです。ぜひ、皆さんの力を貸してください!」
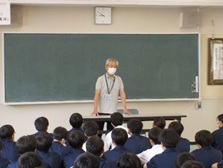
この声を聴き、生徒たちは「草取りならすぐできる」「訪問して困っていることのお手伝いをしながら昔の話を聞いてみたい」「僕たちが知らない梓川地区のおすすめの場所を教えてもらいたい」などの感想を持ちました。夏休み明けの9月には早速高齢者宅を訪問し、交流活動をする予定です。
梓川中では、昨年の3年生の意志を引き継ぎ、地域の多くの高齢者の困りごと解決に向け、地域とともに歩んでいきます。
令和7年7月22日 更新
リーディングスクール 清水中学校
清流総合発表会に向けたフリートーク
全校研究テーマ「表現力が育つ~すべての活動を通して~」の具現に向け、生徒会活動の充実に重点を置いている清水中学校。先日の生徒集会では、清流総合発表会(9月開催)にむけてフリートークの場が持たれました。
「全校のみんなが納得して気持ちよく有志発表をするために」をテーマに、縦割りグループごとに意見交換がなされました。運営側や発表側のハードルやそれを超えていく工夫が語り合われることはもちろんのこと、なぜ有志発表をするのかという目的をあらためて問い直すグループもありました。清流総合発表会を創り上げる当事者として意見を伝え合う姿が、あちらこちらで見られました。


生徒集会後、先生方にインタビューすると、「今回のように自分事として意見を出し合いながら創り上げていくことを大事にしていきたい」や「多様な意見を共有できるように、ファシリテーターを育てていくことが『表現力が育つ』ことにつながると思う」といったふりかえりをお聞きすることができました。
すべての活動を通して表現力が育つことに向かっている清水中学校です。
リーディングスクール・アソシエイト校 島立小学校
「単元内自由進度学習」に、みんなでチャレンジ
「自由進度学習と端末活用による学びのスタイルのアップデート」をテーマに全校で授業改善に取り組んでいる島立小学校では、7月5日(金曜日)、計画休業日に「学び合おうDay『やってみよう!授業づくり』」と題して一日教職員研修を実施しました。
この日のゴールは「自由進度学習をどの教科・単元・期日で行うかを決め、その計画表・学習カードを作成し、できれば学習資料をいくつか準備する」。
はじめに、東京都の中目黒小学校(奈須正裕先生の監修のもと、単元内自由進度学習を実践)への視察研修の報告、続いて教頭先生より「単元内自由進度学習」の基本的な考え方について、資料を使いながら説明がありました。
そして、その後、小グループに分かれ、先行して単元内自由進度学習に取組んでいる先生から実際に使った資料を示しながら、授業づくりの工夫、子どもの学びの様子等について、具体的に学ぶ機会を持ちました。先生たちは、様々に質問をしながら、単元内自由進度学習の実施に向けて、少しずつイメージを明確にしていきました。
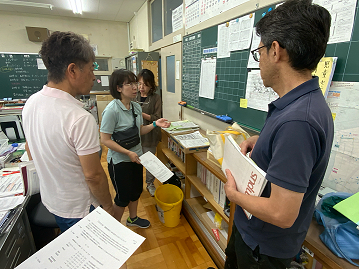
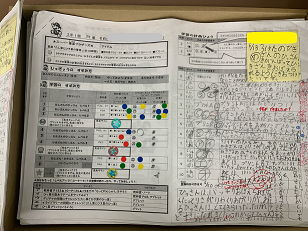
その後、午後にかけて、先生方は相談し合いながら、教材研究や単元構想にじっくり向き合いました。
こうして、一日の終わりには、「いつ、どの教科・単元で行う」一覧表が完成し、すべての先生方が単元内自由進度学習の実践について、具体的な見通しを持つことができました。
2学期、「自ら学ぶ」を目指した島立小の実践が花開きます。
リーディングスクール・アソシエイト校 旭町中学校
旭町中学校 Kjkの会~気軽(K)に授業(J)を公開(K)しよう!~
学校目標「剛愛聡」の“聡”は、「探究的な姿勢で多様な考えに耳を傾け、自分で考え、他者や世界に向けて自分で表現し、自ら行動する生徒」を掲げています。このような生徒を育むために、まずは教師自らが行動し、表現することが大事だと考え、普段の授業を見合う会『Kjkの会』を立ち上げました。先生たちが気軽に参加できるようにと「この日に授業を公開します!」と自分のやりたいタイミングで授業を公開し、放課後は授業について語り合っています。
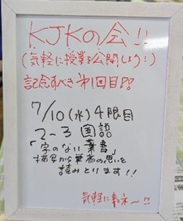
また、終業式の午後には授業を考える会を設け、探究的な学びについてのワークショップを行いました。学習者の立場でミニ探究を行い、そこで起こる感情の変化や生まれてくる問いなどを、体験を通して学びました。その後、そのワークショップがどのようなプロセスで構成されていたか考え、実践者としてこれからの探究的な学びで何ができそうか話し合いました。「『子供の学びは大人の相似形』と、教師が主体的に学ぶことがこれからの旭町の生徒の学びにつながる」と、研究主任の篠田先生が以前語っていたように、旭町中学校の先生たちも自ら動き出しています。

学びの改革パイオニア校 波田小学校
~ 次は、私たちでやってみようかな! ~
今年度、「やってみたいこと・挑戦したいことを実現できる学校」を目指している波田小学校。3月に実施した「6年生ありがとうミニコンサート」に続き、7月に5・6年生の有志を中心に、「七夕コンサート」を行いました。今回は、波田小学校の象徴である正面玄関前の松林で休み時間に開催すると、大勢の子どもたちが演奏を聴きに集まりました。
1曲目は、「おり姫とひこ星が会えることを願って演奏します」というアナウンスに続き、ヴァイオリンによる「キラキラ星変奏曲」が演奏されました。

松林に吹き抜ける風にのり、ヴァイオリンの爽やかな音色が届きました。
2曲目は、ヴァイオリンの伴奏にのり、2年生から6年生までの有志合唱隊16名による「少年時代~パッヘルベルのカノン風~」の演奏でした。本日の演奏のためにアレンジした美しいハーモニーが松林に響きわたりました。

合唱隊で参加した5年生のAさんは、「歌だけでもやっていいのかな。次は私たちでやってみようかな」と話していました。
自分たちの「やってみたいこと」の輪が広がりつつある波田小の子どもたちの次なる挑戦が楽しみです。
学びの改革パイオニア校 丸ノ内中学校
教師自ら探究する職員集団
丸ノ内中学校の実践は、生徒が行う総合的な学習の時間だけではありません。教師が常に生徒の半歩前を歩き、探究するとはどういうことなのかと探究しています。
月に1回程度、教師の探究の時間が設けられ、グループに分かれて探究活動をしています。おいしいお米を求めて米について追究しているグループ、松本市にご当地ラーメンがないなら自分たちで作ってしまおうと考えるラーメン部など、それぞれのテーマで調べたり体験したり、作ったりしています。この教師の探究は今後も続き、10月頃にはポスターセッションを行う予定です。

また、丸ノ内中学校は探究を通して高校とのつながりも考えています。7月15日に行われた「学校と社会をつなぐ~探究的な学びをデザインする対話会~」には、宮下校長先生が出席し、高校や企業、行政や大学生などと交流し、さらに探究の幅を広げようと動いていました。教師も管理職も、子どもたちが探究するにはどのような環境がいいのか、半歩どころでなく歩き回っている丸ノ内中学校です。

令和6年7月16日 更新
リーディングスクール 開成中学校
「地域の魅力」を探究する生徒の姿
本年度、開成中学校はいよいよ探究的な学びの本丸「総合的な学習」の改革を進めています。これまでの開成中の「総合的な学習」は「行事総合」が中心でしたが、そこを大きく変えて、3年生は4クラスを、「観光」「自然」「松本の食」「防災」「魅力発信」「歴史」「伝統文化」の7つのテーマに分けて探究学習を展開しています。去る7月5日、本年度3回目のテーマ別探究活動が実施されました。
校外に出ている1グループを除く6グループの活動を観て感じたのは生徒の「探究する姿」はもちろんのこと、「地域」と共に育っていく姿でした。「地域を学ぶ」だけでなく、「地域と学ぶ」生徒の姿が印象的でした。この日の活動7グループ中、地域の方を講師に招いたり、地域の方にお話を伺ったりというグループが4グループありました。
地域の方々から学ぶ事柄はまさに「地域の生の姿」であり、それに触れた生徒の探究する姿には思わずカメラを向けたくなりました。紙面の都合上、選りすぐりの2枚を掲載させていただきます。
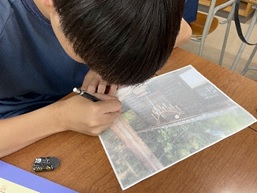

また地域の方々も、今回中学生とやり取りする中で、「もう今の中学生は知らないだろう」と思っていた文化がまだ残っている事実に驚く姿もありました。地域と共に育っていくというのはこういうことなのかもしれないと思った瞬間でした。
リーディングスクール 筑摩野中学校
毎時間の積み重ねを感じることのできる振り返り
筑摩野中学校では、「協働の学び~対話を基盤とした授業づくり~」の全校研究テーマのもと、今年度は4人1組のグループの学びを継続しながら、より充実した協働の学びにつながる魅力的な「学習問題」の設定、そして、生徒の学び(頑張り)を評価する「振り返り」に力を入れて研究を推進しています。

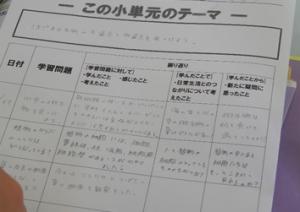
写真はある理科の授業の振り返りシートです。小単元ごとの1枚ポートフォリオになっています。日付と学習問題の隣には、(学習問題に対して)学んだこと・感じたこと・考えたこと、(学んだことで)日常生活とのつながりについて考えたこと、(学んだことから)新たに疑問に思ったことという項目の欄があります。生徒が自分の言葉で表現(アウトプット)し、毎時間の積み重ねを実感できるようになっています。「教科書の内容」ではなく「生徒自身の振り返りの言葉」を「学び」のゴールにおきたい、という願いがここにはあります。
「生徒自身の生徒自身が自分の学び(頑張り)をふり返り、そして、教師がそれをいかに評価し、次の授業につなげていくか、全職員、全教科で考えていきます。
リーディングスクール・アソシエイト校 開明小学校
「挑戦の気風」が盛り上がる!
開明小学校では「『学び』を楽しむ子ども」を願い、「いってみよう!きいてみよう!やってみよう!」を合言葉に、子どもの「願い」「問い」から始まる授業づくりに全校で取り組んでいます。
6月25日(火曜日)には、外部から指導者を迎え、3つの公開授業から学び合う研究会を行いました。
 1年図工「カラフルいろみず」お気に入りの色をつくろう!
1年図工「カラフルいろみず」お気に入りの色をつくろう!
 3年総合的な学習「開明小のヒミツをあばきたい」年表にまとめよう
3年総合的な学習「開明小のヒミツをあばきたい」年表にまとめよう
 2年生活「ミニトマトを育てよう」かんさつ大さくせん!
2年生活「ミニトマトを育てよう」かんさつ大さくせん!
いずれの授業でも、子どもたちが「自分の願い」をもって、生き生きと学習活動に取組み、友達と豊かに対話する姿がありました。
これらの授業づくりに当たっては、校内重点研究会「たいやきタイム」で、全校の先生たちが一緒に授業づくりをサポートしてきました。それにより、授業者の先生方は自信をもって子どもたちと単元の学びを重ねることができました。
授業後の研修会では、先生方がグループで円卓を囲み、授業での子ども達のすがたから、それぞれの子どもの行為の意味や授業づくりについて考え合いました。

子どもたちの「やってみたい」という気持ちをさらに引き出す授業づくりをめざす開明小。先生たちの「やってみたい」挑戦の気風も盛り上がっています。
令和6年7月8日 更新
リーディングスクール 明善小学校
「自分たちのやりたいことをやりたい!!」
明善小学校で低学年期に「学びノート」を使い、生活科を中心に自分たちのやりたいことを実現してきた経験をもつ子どもたちが、4年生になりました。担任の先生方には総合的な学習の時間に学年として取り組もうとしている題材の構想があり、子どもたちに伝えたそうです。すると、子どもたちから「グループ学習やりたい!」「なんで総合なのにグループでやりたいことやらないの?」と次々と声が上がりました。そこで4年1組では、やりたいこと別に8つのグループに分かれ、学年の題材と並行して取り組むことにしました。
「こども授業グループ」では、自分たちが先生になって国語の学習をする準備をしていました。先生と相談して「新聞を作ろう」の単元をどのように進めるかA4用紙にメモしたり、実際の新聞を広げて作成の工夫を考えたり、友だちと相談しながら活動していました。


低学年期の「学びノート」から、A4用紙に大きさや形が替わっても、自分の思いを記す、メモを取る、まとめるなど、書くことに迷いがない子どもたちの姿がありました。
学びの改革パイオニア校 波田小学校
~ 自分の強みを活かそう!~
「中1ギャップ」を軽減し「自己肯定感の醸成」を目指している波田中学校。昨年度から1年生の道徳の時間を利用し、信州大学学術研究院教育学系准教授高橋史先生が提案されている「ライフスキルアップ授業(全6時間)」に取組んでいます。
第1時「自分の行動は自分で選んでみよう」の授業後、学年会の時間を使い、高橋先生と「第1時の様子と次回の授業の向けてのポイント」等について、Zoomを用い話し合いました。

先生方からは、次のような率直な意見が出されました。
・人生すごろくは、大変盛り上がり、選べない人生より自分で選べる人生の方がいいなどポジティブにとらえる生徒が多かった。
・全体的に楽しい雰囲気の授業となったが、この授業の最後はどうなればいいのかなと迷う面があった。
高橋先生からは、「締めの言葉、確かに大切ですね。指導案にここを押さえておけばよいと示されると、先生方も進めやすいですね」と改善点が出されました。
次回は、「~強みを『活かす』『伸ばす』~」をテーマに、「自分の強み」について考える予定です。高橋先生からは、「自分の強みがどうしても言えない子には、先生や友達同士が強みを言ってもいいです」と助言がありました。
「自分の強み・よさ」に気付き、困っていることを素直に言える人間関係を目指し、ライフスキルアップ授業は続きます。
令和6年7月1日 更新
リーディングスクール 寿小学校
新たな挑戦
昨年度より取り組みを開始した寿小学校の単元内自由進度学習。1年生は単一教科(算数)でスタートしました。単元終了後には、「ほかの教科もやりたかった」という声が多く聞かれたため、今年度6月の公開授業では子どもたちが選択できる範囲を広げ、算数と国語の2教科同時進行の単元内自由進度学習に挑戦します。
4年生では、算数と図工の2教科同時進行の単元内自由進度学習に挑戦します。図工は、研究部会にとって初挑戦となるため、子どもたちが教科の目標に向かい、自律的な学びができるような学習環境のあり方について教材研究を重ねています。
今もっている力を存分に発揮し、目を輝かせながら自ら進んでいく子どもたちの姿を想像しながら、寿小学校の挑戦は続きます。


リーディングスクール・アソシエイト校 女鳥羽中学校
「プロジェクトM」始動!
「ほんとうに自由に学べる教室」をテーマに、学校づくり・授業づくりに取り組んでいる女鳥羽中学校。今年度、学校を挙げて「探究の学び」にチャレンジします。
これまでの女鳥羽中学校の「総合的な学習」は、ある程度テーマや枠組みが決められた中で、用意された活動に取り組む形を中心に行われてきましたが、先生方が「願う生徒の学びの姿」を話し合い、「生徒自身が身近な環境の中から追究したい『問い』を見出し、学び方も自ら考え、学んだ結果を様々な方法で表現する『探究的な学び』」に踏み出すことにしました。名付けて「プロジェクトM」。
6月11日、3年生は、学習オリエンテーションを実施し、新たに挑戦する学びのイメージを共有しました。先生方は生徒たちに先行し、地域でどのような「学び」が成立できそうか、教材研究をスタートさせました。今後、地域の方へのインタビュー活動等フィールドワークが予定されています。


女鳥羽中学校の先生たち、生徒たちが一緒になって、あらたな「学びのステージ」を拓いていきます。
令和6年6月24日 更新
リーディングスクール 筑摩小学校
自分に合った学習が自分でできる!
「子どもの“学びデザイン力”を育てる学校づくり」を目指している筑摩小学校。「どの学年も1学期に1回は自由進度学習を実施しよう」を目標に取組みを進めています。先日、4年生が、算数の単元「角とその大きさ」で単元内自由進度学習(10時間)を実施しました。授業では、子どもたちが「一人で集中して学習したい・先生に聞きながら学習したい・友達と相談しながら学習したい」の3つの中から学び方を選択し学んでいきます。授業の途中でも「友達と相談しながら学習したい」と思ったら変更することができます。
授業後の子どものたちのふりかえりです。
・友だちと相談して分からなかったら聞いて、それでも分からなかったら先生に聞くというやり方が一番自分に合うやり方だとわかった。…
・チェック2までいけた。先生にわからないところを聞けた。ペースが遅くなってチェック3までいけなかった。だから次はペースをもう少し上げたい。一人でやる時間を増やしてペースをあげたい。
 友と相談しながら取組む子どもたち
友と相談しながら取組む子どもたち
 一人一人もくもくと取組む子どもたち
一人一人もくもくと取組む子どもたち
「できた・できなかった」という振り返りにとどまらず「自分にはどの学習の仕方がいいのか気づき、自分で学習を進める楽しさ、よさを感じている」子どもたちです。筑摩小のシンカは続きます。
リーディングスクール・アソシエイト校 菅野中学校
「協働のよさ」を味わいながら学ぶ子どもたち
学びのテーマ「協働」を子どもたちと共有し、「対話」を大切にした授業づくりを進めている菅野中学校。6月の実践の一コマです。
【日常の無意識の中にある差別意識に気づく(3年道徳)】
3学年全員が体育館で、「マイクロ・アグレッション*」について学ぶ場面です。(*無意識の偏見や思い込みによる否定的なメッセージにより、意図せず誰かを傷つけてしまう言動)
「『やっぱり日本人ってマナーがいいね』という言葉には、問題があると思いますか?」という先生の問いかけに対して、生徒たちはグループで対話し、お互いの考えを確認し合い、さらに「日本人がごみを片付けている場面の事実だから問題はないと思う」「日本人以外の人が聞いたらいやな気持がすると思う。」といった根拠を豊かに語り合いました。様々な「言葉」について、問い直しと対話を繰り返す中で、生徒たちは「何気なく使っている言葉が誰かを傷つけるメッセージになりうること」への気づきを深めていきました。

【熱帯の気候を「自分ごと」として学ぶ(1年社会)】
「世界の気候の特徴」を学ぶ場面、「アピア(サモア)に2泊3日の旅行に行くために必要なものリストを作ろう」という学習問題のもと、生徒たちは相談しながら教科書の本文、写真、雨温図等から現地の「衣・食・住」を読み取り始めました。そのうえで「半袖Tシャツ3枚あればいいかな」「日焼け止めもいるよね」「あ、そうか」と、時間いっぱい、対話を重ねながら楽しそうに持ち物リストを埋めていきました。

「問い」をもとに考え、対話し、「新たな考えに触れる」「自分の考えを承認してもらう」よろこびを味わう生徒たち。このような学びの経験を積み重ねることで、生徒が一層主体的になっていくことを実感しながら、先生方は授業づくりの挑戦をすすめています。
授業後、参観された先生方はこのように(↓)フィードバックを交流しあいました。先生方自身の「協働的な学び」の一コマです。
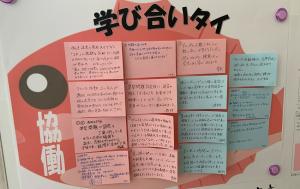
学びの改革パイオニア校 開智小学校
探究の時間の工夫~時間を合わせるからできること~
開智小学校では、新たに水曜日の午後を「探究の時間」として設けています。この時間は専科授業がないため、専科の先生方も探究活動に参加できます。4年生と6年生は、同じ「材(市立博物館)」からスタートし、異年齢での探究活動を展開しています。子どもたちは自分の問いを出し合い、共有しながら追究しています。先生方も伴走し、7人の先生が協力して学びの環境を広げています。
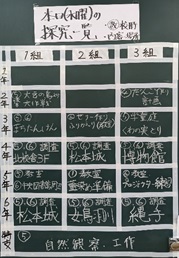

(問いをもった子どもは、端末を使って調べています。そのほかの子どもたちは、松本城や市立博物館など、調査活動に出かけています)
「子どもたちに委ねる探究」をテーマにしている開智小学校。子どもたちの学びの環境をどのように構成していくかについても探究中です。授業設計研修後、ある先生は「伴走者である私たちは、環境設定(子どもが自己決定できるような場の設定)、教材研究(子ども達は、どんなことに引っかかりをもち、どのようなことを悩むのか)、授業設計(どんな力をつけさせるか、そのために何が必要か【人・もの・こと】)をしっかり考える必要がある。」と振り返っていました。子どもの学びを支える先生方の思いが伝わってきます。
令和6年6月17日 更新
リーディングスクール 中山小学校
一人ひとりの子どもの学びの道筋が保障される
梅雨入り間近のある日、中山小学校のすべての教室を参観させていただきました。新1年生の子どもたちは、はさみの使い方を学んでいましたが、はさみの使い方に慣れない友達を応援したり、無事に紙型を切り抜き終わった友達に「頑張ったね」と声をかけたりするなど、学び合う学級の土台が作られていました。また、体育館では5・6年生が合同で「シャトルラン」に取り組んでいました。「頑張れー」という仲間を応援する声が絶えず、体育館に響いていました。

次の時間で、6年生は算数の課題に取り組んでいました。教室は大きく3カ所の子どもたちのまとまりで分かれていました。子どもたちに尋ねると、「『塾コース(電子黒板前のグループ)』の方がわかりやすい人と、ぼくたちにみたいに友達と相談しながら自分たちのペースで進みたい人と、一人で黙々やりたい人で分かれたんです」と教えてくれました。さらに「自分で選ぶってどう?」と尋ねると、「自分で選んだやり方の方が身につく」と教えてくれました。

「すべての子どもがいきいきと自分らしく学ぶ中山小学校を作り上げたい」という年度当初に校長先生から伺った学校への思いが、また一つ新しい取り組みとして具現化されています。
リーディングスクール 鎌田中学校
学習を自らマネジメントする
鎌田中学校の総合的な学習の時間「Kmdタイム」では、「私たちはこの地域のために何ができるか」を問いの出発点として学びを深めていきます。生徒が学びの主体者となり、自らの学びをマネジメントしていく力を培ってほしいと考えています。そして、Kmdタイムで培った探究的な学びを、教科学習でも実現していくことを目指します。
年度当初には、教科学習のオリエンテーションを開きました。その中で、学習の進め方を自ら調整する力を培うために、学習の目的や進め方などについて自ら見通しをもって、日々の学習に取り組むことの大切さを共有しました。たとえば、ともすれば「こなすだけ」になりがちな漢字練習を、生徒自らが表現したい文脈に応じて習得していく学びに変えていくことをきたしています。このように今年度の鎌田中学校では、あらゆる機会を通して生徒が自身の学習をマネジメントする力を高めることを大切にしていきます。
 興味に応じて学びを進める生徒たち
興味に応じて学びを進める生徒たち
リーディングスクール・アソシエイト校 梓川中学校
「私たちの梓川」の学びをめざして
梓川中学校では、「地域の切実な課題を受け止め、自分たちができることを考え、仲間と協働して解決方法を見出だす探究的な学び」を実現したいと考えています。その構想にあたり、研究主任と副主任(地域連携担当)が梓川地区地域づくりセンター長や公民館長に、地域の課題や願いについてお話をきく機会を持ちました。
地域の方からは、高齢化の進行によって生じている様々な切実な困りごとや、それを解決するための人手不足、さらに地域の大切な資源である「梓川」の環境保全など、様々な課題をお話しいただきました。また、地域の将来の担い手である中学生に梓川地区の魅力を知ってもらい、将来「梓川地区に住みたい、戻りたいとの思いを抱いてほしい」という期待があることを共有しました。

先生方は、今後、地域の方々との出会いと対話を通して、「私たちの梓川」という思いを深め、地域の課題解決に向け主体的に取組もうとする子どもたちの学びを実現したいと考えています。
「地域を深く知り、地域への思いを深める学び」に向けた梓川中の挑戦が始まりました。
令和6年6月10日 更新
リーディングスクール 清水中学校
生徒会活動を通して表現力が育つ
第1回生徒総会にて、今年度の生徒会スローガンが「Say! ~生徒の声が導く成功~」に決まりました。このスローガンを受けて、翌週の職員連絡会で生徒会顧問から全職員に、「次回の委員会は、生徒会役員からトップダウンで提案をするのではなく、所属する委員一人ひとりの声を聴き、その声を活動の充実につなげられる場にしたい」という願いが伝えられました。全校研究テーマ「表現力が育つ~すべての活動を通して~」の具現に向け、これまで以上に多様な声を聴き合う集団づくりに向かう機運が高まりました。
生徒会役員と担当職員との事前打合せ会で、Y先生は「いま話題になったことを見える化してごらん」、「この目的を実現するためには、あなたたちはこの視点で議論することが大切だと思っているんだよね」と生徒と関わっていました。Y先生は、「今年のスローガンを実現するためには、生徒会役員のファシリテーターとしての役割が重要となる。今日の事前打合せでは、ファシリテーターとしての見本を意図的に示しました。」と語られました。

 事前打合せをする生徒会役員と担当職員
事前打合せをする生徒会役員と担当職員
今回の事前打合せ会を経て行われた各委員会における生徒の姿については、次号のリーディングスクール通信「学びの風便り」にて紹介します。
リーディングスクール・アソシエイト校 島立小学校
先生たちが学びを楽しむ
島立小学校の先生方がチャレンジしている取組の一つに、自主研修会「Enjoy!島立」があります。この研修会では、先生方が教室で実践されている様々な工夫や知見(これらを教務主任の野村先生は「宝物」と呼ばれます)を持ち寄り、楽しく学び合うことを目指します。
6月7日には、研究主任の平本先生を講師に、全ての子どもたちの学びへの参加を保証するGoogle Meetの効果的な活用について、学び合いました。先生方は実際に授業で使った資料を子ども(学習者)と授業者、双方の立場から体験し、そのよさを実感するとともに、自身の実践に向けて様々な質問・意見を活発に交流されました。

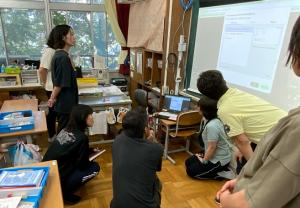
「自由進度学習と端末活用による学びのスタイルのアップデート」をテーマに、「子ども主体の学び」づくりに取組む島立小。先生方自身がコミュニケーションを深めながら学びを楽しむことにチャレンジしています。
学びの改革パイオニア校 波田小学校
~やってみたいこと・挑戦したいことを実現できる学校!~
パイオニア校として「多様性を受容する学校づくり」に取組み、2年目を迎える波田小学校。今年度は、「多様性を受容し、やってみたいこと・挑戦したいことを実現できる学校」を目指しています。
その実現に向け、今年度の職員の研究グループは、「健康教育(教育課程)」「国語(自分の言葉を伝える)」「単元内自由進度学習(算数)」の3つの部会に分かれ取組みます。所属する研究部会を決める前に、先生方一人一人が今年度取り組みたい「自己課題」を提出し、それをもとに研究主任が中心となって、研究グループを決めました。
研究主任のK先生は「なるべく自己課題に合わせグループを編成し、一人一人が主体となってやる研究に、少人数で対話する機会を多くしたいと考えました。教師自身も主人公となり、やってみたい授業をつくる研究会にしたいです。そのため算数部会では、全員が授業をやる予定です」と語りました。

職員室の黒板には、先生方一人一人の自己課題が掲示されています。子どもだけでなく、先生方も「やってみたい・挑戦したい自己課題」の実現に向けて、授業づくりにトライしていきます。
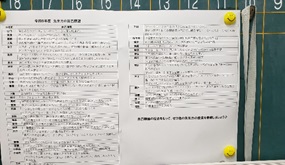 先生方の自己課題
先生方の自己課題
学びの改革パイオニア校 丸ノ内中学校
実践校に学ぶ「探究の学びの研修」@丸ノ内中学校
5月28日(火曜日)に、丸ノ内中学校で「探究の学びの研修」が行われました。探究の学びに関心のある先生方が集まり、丸ノ内中学校の総合的な学習の時間(忠恕の時間)を参観し、その後探究コーディネーターの上條先生から丸ノ内中学校の考える探究学習について説明がありました。
授業を参観した先生は「(生徒に尋ねたところ)高山の醤油について実際に現地で見たり味わったりして特徴を確かめたい。そして、松本の醤油と比べてみたいし、新たな醤油づくりも考えている。」という言葉から、「生徒の探究する姿や声から、探究することの楽しさを感じていることに気づきました。」との感想がありました。
また、上條先生の説明を聞いて、次のように考えている先生がいました。
「子どもの興味・関心に基づいた授業を構築するため、先生方が研修を重ね、全体で探究学習を重視していることがわかりました。」
「学校全体として探究の学びとしての総合を位置づけていくための学校内での取り組み(組織づくりや合言葉など)も非常に勉強になりました。」
参加した先生方は、自校での探究的な学びを進めていくうえで校内研修の大切さを感じているようでした。


令和6年6月3日 更新
リーディングスクール 開成中学校
子どもの姿から出発するために…「Nrt」と「Nino」の活用
どんな素晴らしい取り組みも、目の前の生徒に合っていなければ意味がありません。今年度、開成中では新たなスケールを用い、「生徒の姿」を多角的に捉えようと試みています。
3年生が修学旅行に出掛けている裏で、1,2年生全員に「Nrt(標準学力検査)」と「Nino(認知能力検査)」を実施しました。この2つの検査結果をクロス集計することにより「認知能力相応の学力がついているか」を把握することができます。
22日に行われた第2回職員研修では、1,2年のクラス毎にグループとなり、学級担任と教科担任が生徒について意見交換をしました。前回の職員研修同様、どのグループも和気あいあいと生徒の姿を語り合っていました。「こんなところで困っている」に留まらず、「どうして困っているのだろう」というところまで話し合うグループが多く、これは間違いなく今後の授業改善に繋がっていきそうだと感じました。
より精度の高い実態把握を経て、本年度はいよいよ本丸「総合的な学習の時間」の改革に着手します。総合も含めた「令和6年度 開成中学校下『学びのデザイン』計画表」は下図のとおりです(※詳しい内容を確認したい方は下のリンクをクリックしてください。pdfがダウンロードできます)。
「こういうことをやりたい」「「こういう自分になりたい」が実現する学校を目指し、令和6年度開成丸は出港しました。
リーディングスクール 筑摩野中学校
よりよい協働の学びを目指して
令和6年度の筑摩野中学校の全校研究テーマは「協働の学び~対話を基盤とした授業づくり~」です。昨年度から始まった4人1グループの学びでは、対話が生まれる学習問題の工夫という成果や対話の中から学びを生み出す方法について課題が見えてきました。今年度は、(1)より充実した協働の学びにつながる魅力的で考えがいのある学習問題の設定、(2)学習問題を受けて生徒が学んだこと、見い出したことを自分の言葉でアウトプットできる振り返りのあり方、その振り返りを教師はどのように評価するかという「学習問題」と「振り返り」の2点に力を入れていきます。

5月8日より、全校で4人1グループの学びが始まりました。1年生の社会の授業では「日本はどこからどこまで?」という問いで授業が展開されていました。教科書がゴールではなく、生徒がその日の学びを振り返り、表現した言葉がゴールになるように、今年度も職員が一丸となって、よりよい協働の学びを研究していきます。
リーディングスクール・アソシエイト校 開明小学校
「学び」を楽しむ子ども、そして先生
開明小学校の学校づくりのテーマは「みんなが幸せな学校~「学び」を楽しむ子ども」。そして「いってみよう!きいてみよう!やってみよう!」という合言葉と「~たい!」のシンボルマーク「たい焼き」を子どもたち、先生たちと共有し、あらゆる機会にみんなの「~たい」を実現する学びを目指しています。
 校内に掲示される「合言葉」
校内に掲示される「合言葉」
4月30日には、「一日研修日」を実施。学校を計画休業とし、朝から、係の先生方が企画する研修に全職員が参加しました。その中で、一人一人の先生方が自己課題「実現したい授業」を決めだし、それに寄せる思いを語り合う機会をもちました。午後は、市の実施する「学級づくりワークショップ」に全職員で参加し「すべての子どもたちが安心して互いの思いを受け止め合える学級づくり」について、楽しく学びました。
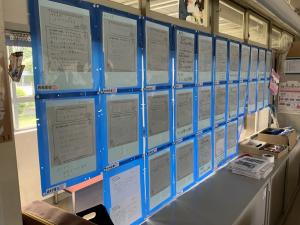 先生方の「自己課題」
先生方の「自己課題」
学校づくりを推進する校内研修を「たい焼きタイム」と名付けて、楽しみながら学ぶことを目指す先生方。学校を挙げて「エージェンシー」の向上に取り組む開明小の挑戦がスタートしました。
令和6年5月27日 更新
リーディングスクール 明善小学校
「自分たちで考える。自分でやってみる。」
6月に行われる音楽会で、どんなことを発表しようか2学年みんなで相談しています。昨年度、自分たちの「やってみたい!」を形にしてきた2年生が、どんなアイデアを出し合うのか楽しみです。
 【音楽会でどんなことを発表しようか話し合い】
【音楽会でどんなことを発表しようか話し合い】
学びノートに様々な思いや事象を記入してきた子どもたち。自主学習も思い思いに行っています。自主学習ノートも充実しています。
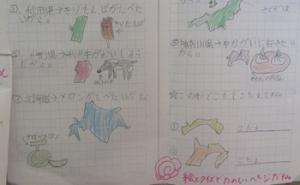 【2年生の自主学習ノートより】
【2年生の自主学習ノートより】
リーディングスクール・アソシエイト校 旭町中学校
「問い」を中心とした総合的な学習の時間を目指して
旭町中学校では中核となる学習として “平和学習”が行われています。これまでは教材研究によってていねいに作られたカリキュラムにそって、総合的な学習を進めてきました。しかし先生方は「これでは教師が示した学習内容を、生徒がそれに沿って進めていくこととなり、探究の学びになっていないのではないか」と問い返し、生徒の「問い」を中心とした総合的な学習の時間ができないかと考え始めました。
1学年では、学年一斉の授業の中で総合的な学習の時間の立ち上げを行いました。“生徒自らが考えを出し合い、お互いの考えを認め合える場づくり”を大切にしたいと考え、先生から「生きるためには何が必要か?」と問いかけられると、生徒たちは「生きるために必要なもの・こと」について一人一人で考え、その後グループで考えを共有しました。

生徒からは、「お金・健康・人とのかかわり・知識・衣服・考える力・支えてくれる人・・・」などと意見が出ました。その中で家・地域というワードから赤堀先生が「地域を大きくくくると松本になります。松本は3ガク都と呼ばれるけれど、松本の魅力とはなんだろう?」と再び問いかけられると、生徒たちは改めて松本について考え始めました。
これまで丁寧に作り上げられてきたカリキュラムを大切にしながら、生徒の「問い」を大切にした総合的な学習の時間に変えていく。先生方にとっても新たなチャレンジが始まりました。
学びの改革パイオニア校 波田中学校
「対話を重視した学びの充実!」
今年度の研究のスタートにあたり、研究主任のF先生が数学の授業を公開しました。「カレンダーの秘密を探ろう」と、カレンダー上の縦に並ぶ3つの数字を選びました。「8、15、22」「2,9、16」のようにいつも差が7になる理由について4人グループになり考えると、「1週間は7日だから差が7になる」ことに気付いた生徒たち。

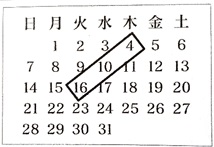
次に右上から左下ななめに並んだ3つの数について考えました。「4、10、16」「6、12、18」のようにいつも差が6になることに生徒が気付くと、F先生は「真ん中の数の2乗から他の2つの数の積をひいてみよう」と問いかけます。「10×10−16×4=36、12×12−18×6=36、あれ、いつも36になる」という声があちこちから起こると、「その理由を説明しよう」と文字式を利用し解決する学習に入りました。
「n×n−(n+6)(n−6)とできたけど、この後が難しい」「計算していくとnが消えて、36だけになる」「式はできたけど、どう説明を書いたらいいのかな」など友と考え合う姿があちこちで見られました。

「明日も学びに行きたくなる学校」を合言葉に、「授業の充実」に向け、「対話が広がる授業の工夫」について学び合う機会となりました。
令和6年5月20日 更新
リーディングスクール 寿小学校
子どもに委ねる授業づくりとは
寿小学校では、昨年度に引き続き、子どもの主体性をいっそう伸ばそうと「さあ やってみよう」を合言葉に教育活動を展開しています。そして、昨年度の取組をもとに、令和6年度 全校研究テーマを『さあ やってみよう と自ら動き出す子ども~子どもに委ねる(・・・)授業づくりを通して~』と決め、全ての学年で単元内自由進度学習に挑戦します。
4月の職員研修では、子どもに委ねる授業づくりについて、互いの考えを語り合うことをとおして、職員の「さあやってみよう」の意識を高めました。その後、各研究部会が開かれ、自校の子どもたちを想像しながら熱心な話し合いがなされました。
6月25日(火曜日)には、松本市教育研修センターの研修講座「実践校に学ぶ 単元内自由進度学習」で授業公開を予定しています。
 高学年部会の様子
高学年部会の様子
 低学年部会の様子
低学年部会の様子
リーディングスクール・アソシエイト校 女鳥羽中学校
「わかってほしい、聴いてほしい私の気持ち」
女鳥羽中学校の今年度の学校づくりのテーマは「ほんとうに自由に学べる教室」。子どもたちが互いの思いを受け止め認め合う関係性の中で、自分らしく個性を輝かせる学びが、すべての教室・場で実現することを目指します。
5月8日、今年度初めての全校生徒集会「相互理解集会」が行われました。全校の生徒たちが事前にアンケートに記入し、生徒会の役員が事前に発言の依頼をする等、誰もが安心して思いを発表できるよう、配慮しながら準備を進めてきました。
集会の前半は、「されて嫌な思いをしたこと」を語り合います。控えめだけれどしっかりした言葉で「思い」を開示する生徒たち。その一つ一つの言葉に全校のみんなが耳を傾け、向きあっている様子が伝わってきました。
 【友の言葉に耳を傾ける生徒たち】
【友の言葉に耳を傾ける生徒たち】
後半は「してもらってうれしかったこと」の語り合いです。「つらい思いをしていた時、共感してくれた」など、友のさりげない思いやりに触れたうれしさを交流し合いました。役員さんたちは「誰にしてもらったのですか?」「(名前を言われた人に)どう思いますか?」と、さらに思いをつないでいきます。
一人一人の「苦しさ」「うれしさ」を全校で受け止め合う、温かさに満ちた集会となりました。
その放課後、今度は先生たちが「車座」になって、今日の集会で感じたことを語り合いました。個々の生徒の「背景」にも関心を向けながら話し、受け止め合う先生方の姿は、生徒たちのそれと重なりました。
 【車座で思いを語り合う先生たち】
【車座で思いを語り合う先生たち】
「相互承認と受容の中で私の学びを実感できる学習指導と支援」の実現にむけ、女鳥羽中学校は大きな一歩を歩み出しました。
学びの改革パイオニア校 田川小学校
子どもの行為の意味を考える
4月5日の3校合同研修(田川小・開智小・丸ノ内中)を体験した先生方が、そこで感じたことを語り合いました。探究活動をしてみて、どうしたらいいか困った経験をした人もいれば、自由に外に出られる雰囲気がいいと感じる人もいました。同じ体験をしたからこそ出し合える素直な感想から「子どもたちもきっとそんな風に思うんだろうな。」と学習者の気持ちを実践者視点から捉え直しました。“子どもの行為には意味がある”という田川小学校の大切にしている考えを、体験を通じ感じられたようです。
研究主任の小嶋先生は「子どもたちも私たち教師も迷いながら、失敗しながら、試行錯誤して納得解を導き出していく探究的な学びを通して、子どもたちの『楽しかった』をつくることができれば」と考えています。そのような考えから田川小学校では、1学期の研修の中でグループごとに地域素材を教材化するために、教師自らが探究活動をしています。7月24日には、研究グループごとでアウトプットするという一つのゴールをつくり、そこに向け動いています。“子どもの学びは大人の学びと相似形”を実践する田川小学校。どんな伴走支援が子どもの学びの自走につながるか、新たな視点が見つかりそうです。

※4年生の総合的な学習の時間の立ち上げに向け、先生方の体験を語り合っています。そこから次回の部会では実際に田川を歩いたり入ったりしながら、見たり、聞いたり、感じたことから、子どもとどんな学びが生まれそうか考えていきます。
令和6年5月13日 更新
リーディングスクール 筑摩小学校
ワクワクしながら授業づくりを!
リーディングスクール校として、昨年度全校で「自由進度学習」の実践の歩みを進めてきた筑摩小学校。今年度も昨年度に続き、研究部会は「低・中・高学年の自由進度学習」の3部会で推進します。研究のスタートにあたり、全職員で「自由進度学習」について学び合う会を開きました。

研究主任が「けテぶれ学習・自由進度学習」の実践から学び合ってきたことを紹介し、最後に「いろんな先生を巻き込みながら、たくさん話をするのが大事。私たちが前向きにならないと子どもも前向きにならないので、そんな気持ちでやりましょう」と語りかけました。その後、連学年で、1学期を見通して自由進度学習に適している単元について検討し合いました。
算数の角度の単元では、分度器の使い方について最初一斉に学習した方がよいかという話題になりました。「昨年やってみて、算数は最初の1時間全体でやりポイントを押さえ、その後自由進度学習でやるのがよいと思った」と経験を踏まえた助言が出るなど、単元構成の工夫について語り合いました。

今年度も、全校で自由進度学習を実践し、「子どもがどんな反応をするかワクワクしながら授業をつくろう」と決意を新たに、筑摩小の2年目の挑戦は続きます。
リーディングスクール・アソシエイト校 菅野中学校
「協働」のよさを共有する
菅野中学校では今年度、「協働し主体的に学び続ける生徒の育成」をテーマに、リーディングスクール・アソシエイト校として、「対話」を大切にした生徒主体の学びづくりに挑戦します。そして生徒たちと共有して実現を目指す「学びのテーマ」を「協働」と決めだしました。
実践のスタートは、まずは先生たちが「対話」のよさを味わうことから。4月の職員研修で、「協働することのよさや価値」を先生方みんなで考え、語り合う機会を持ちました。「予想外に盛り上がった(校長先生)」話し合いは「協働」を先生方が具体的に考えるきっかけとなりました。
さらに全校で学習オリエンテーションを実施、「協働」のよさや価値を生徒たちが体験する機会づくりに挑戦しました。オリエンテーションは進行を務める研究主任の先生の「協働」についての説明の後、全校生徒が学年・学級を超えた小グループをその場でつくり、「菅野地区のよさって何だろう?」という問いについて考えを交流する、という形で行われました。
すべてが「初めて尽くし」の試みでしたが、3年生のリーダーシップのもと、グループ作りがスムーズに行われ、生徒たちははにかみながらも「自然がたくさんあること」「地区の誰もがあいさつを交わし合うこと」といった「菅野のよさ」について考えを交流することができました。

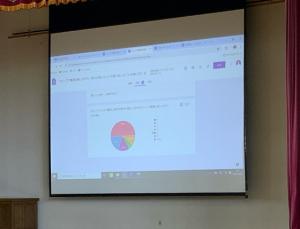
生徒たちの感想は、その場でタブレット端末を通して集計され、共有されました。
先生の「このようにみんなで対話しながら一緒に創っていく学びを目指したい」という言葉に、深くうなずく生徒たちの姿が心に残りました。
菅野中学校の大きな挑戦が、確実にスタートしました。
学びの改革パイオニア校 開智小学校
子どもに“ゆだねる”とは?
「もっと子どもに任せられる探究にしたい!」と願う探究コーディネーターの江口先生。そのような思いをもつきっかけとなったのは、昨年度の“子どもにゆだねられない”という反省からでした。子どもに“ゆだねる”とはどういうことなのでしょうか?
開智小学校では、全職員との会議の前に校長先生・教頭先生・研究主任・探究コーディネーター・部会主任でミーティングを行いました。“ゆだねる”という言葉一つとっても、一人一人のイメージが違います。そのイメージの違いを話すことで、開智小学校が願う“ゆだねる”が見えてきそうだということがわかってきました。

子どもが主体の探究活動をしていくために、教師はどのような伴走をしたらいいのでしょう。子どもが問いをたて、自ら課題を設定し、計画を立て進めていく。そのような開智小学校が目指す学びをまずは教師自らが体験してみる。自らの体験から、子どもの姿をイメージし、子どもの学びを見守り、支える。パイオニア校2年目の開智小学校が、新たな問いをもって動き出しました。
令和6年4月30日 更新
リーディングスクール 中山小学校
リーディングスクール2年目 今年は「質」にこだわりたい
令和6年度が明け、入学式翌日の4月5日(金曜日)。中山小学校の先生方の姿は丸ノ内中学校にありました。県指定の学びの改革パイオニア校である開智小、田川小、丸ノ内中の先生方とともに、風越学園の岩瀬先生によるワークショップに加わり、プロジェクト型の学びについて理解を深め、また、探究を核とした学校づくりを進める市内の仲間との親睦を深めていました。
後日、宮田校長先生から本年度の取組みの方向についてお話をお聞きすることができました。今年は次の3つを核に据え、学びの「質」を高める取組みを進めていきたいと思いを語ってくださりました。
・(異年齢の集団を活用した)対話の中で、どうやって「質」を高めるか。
・振り返りの視点をどうもつかによって、どのように学びが深まるか。
・基礎的な学びをどのようにして確実に定着させるか。
これら3つの核は中山小の先生方の実践の中から焦点化したものであるそうです。
基礎的な学びの充実が、探究を下支えする素地となり、それにより対話の内容が充実し、対話によって生み出されるものの価値がより高まる。そして、それらの過程に含まれるよさを自覚の世界に引き起こす振り返りの在り方を模索する営みの先に、すべての子どもがいきいきと自分らしく学ぶ中山小学校を作り上げたいという校長先生の熱い思いが伝わりました。


リーディングスクール 鎌田中学校
ワクワク!を学びにする
リーディングスクールとして2年目を迎える鎌田中学校は、学びの重点を以下のように定め授業改善に取り組みます。まず心理的安全性の確保と学びのユニバーサルデザイン化です。生徒が安心して自分を表現でき、誰にとっても学びやすい授業を目指します。
次に、探究的な学びを一層充実していきます。総合的な学習の時間「Kmdタイム」では、「地域に生きる私」という視点から「私たちはこの地域のために何ができるか」を問いの出発点として、学びを深め具体的な行動を起こしていきます。この授業では、生徒が学びの主体者となり、自ら学びをマネジメントしていく力を培ってほしいと考えています。そしてKmdタイムで培った探究的な学びを、各教科学習でも実現していくことを目指します。
Kmdタイムは、学びの興味に沿って「何をやってもいい」からこそ魅力がいっぱいです。「なんかワクワクする!」をキーワードに、5月のオリエンテーションを皮切りに探究的な学びを進めていきます。
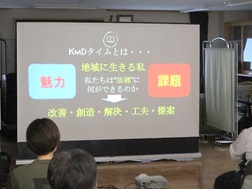

リーディングスクール・アソシエイト校 梓川中学校
「地域とともに歩む」実践を目指して!
今年度、学校づくりのテーマとして「地域とともにつくる探究的学習」を掲げている梓川中学校。
その礎となったのが、昨年度卒業した3学年の地域連携を核とした取組でした。1年時から「Sdgs」を中核に据え、3学年になり「住み続けられるまちづくりを」をテーマに、地域連携の学習に歩みだしました。そして、その学習を進めるにあたり大切にしたポイントは「地域の必要感に子どもの必要感を重ねる」ことでした。
最初は、3学年職員が梓川地区公民館・地域づくりセンターの方々と懇談し、「地域の高齢化が進んでいる」という地域課題(=地域の必要感)を把握しました。センターの方々と職員で「君たち(中学生)の力・協力が必要だ!」というメッセージ動画を作成し3学年に紹介することで、子どもたちの課題意識(=子どもの必要感)が自然と高めまるよう支援し、地域と子どもの必要感を重ねました。
センターからの依頼を受け、「地域のために自分たちができることはないか」と考え、実際に高齢者宅を訪問し、ニーズを調べることにした3年生。話を伺い、「交通手段がない」「一人暮らしで寂しい」などの困りごとを知り、解決策を考え、提案していきました。
 高齢者宅に訪問
高齢者宅に訪問
 自分たちが考えた解決策を伝え合う3年生
自分たちが考えた解決策を伝え合う3年生
今年度は、卒業生のこの取組を引き継ぎ、地域とともにつくる学習を構想していきます。
3月31日 更新
リーディングスクール 筑摩小学校
子どもの“学びデザイン力”を育てる学校づくり
筑摩小学校の令和5年度の取り組みが終わりました。
児童一人ひとりが自分に合った方法で主体的に学ぶ力を育むために、単元内自由進度学習を取り入れました。今年度がはじめての取組でしたが、全ての学年で1回以上実施することができました。
「自由進度学習ってどうやるんだろう」「何からはじめればいいんだろう」という手探りでのスタートでしたが、県内外の実践校を実際に視察してイメージをつかむことができました。視察の報告を兼ねた職員研修を経て、まずは7月に4学年と2学年で実施しました。これを皮切りに、低中高の連学年でつくる部会内で職員が連携しながら、専科の授業を含めて2月までに全学年が自由進度学習を行いました。
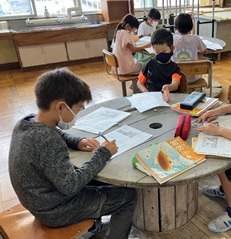

来年度は各学年での実践をさらに進めるとともに、一斉指導の形態での授業の充実も図っていきたいと考えています。
リーディングスクール 筑摩野中学校
今年度の取り組みをふり返って
今年度、筑摩野中学校全校をあげて取り組んできた「対話を基盤とした授業づくり」。職員一人ひとりが成果と課題をあげて振り返りました。
成果としては「生徒が気軽に話せるグループ活動を心がけ、どんな組み合わせでも自然体で話ができる雰囲気がつくられてきた。」「4人組で学ぶことが自然になり、問いに対して、一人で考えたい生徒も相談しながら考えたい生徒もそれぞれが選択しながら学習を進めていけるようになった。」「村瀬先生の授業クリニックを受けて、対話について学んだことが大きな成果だった。自然と子どもたちが対話すること、学習問題を考え、子どもの思考を促すものにするなどを意識できた。」などの意見がありました。


一方で、課題として「関係ない会話に脱線してしまう。」「人間関係に左右され、対話になりにくいことがある。」「一人で考えたい生徒もいる。逆に一人では考えられない、人任せ、人伺いな姿も見られた。」「より効果的で意味のあるグループ活動を考えたい。今のところ“わからなかったら相談する”レベルの授業がほとんどなので、生徒にとって対話する意味のある問いを投げかける授業にしたい。」などの意見がありました。
4人グループでの学習スタイルを進める中で生徒たち、先生たちともに授業に対する意識が確実に変わってきたように感じます。職員数50名を超える筑摩野中学校ですが、一人ひとりが率直に成果と課題を出し合い、共有できるのは本校の強みだと思います。出てきた課題を解決していけるよう職員が一丸となってよりよい授業のあり方を来年度も検討していきます。
学びの改革パイオニア校 波田小学校
6年生に「ありがとう」を伝えたい!
来年度に向けて「子どもがやりたいことができる学校」へと歩み始めた波田小学校。
3月11日の休み時間、5年生のSさん中心に声をかけ、3年・4年・5年・職員の有志11名による「6年生ありがとうミニコンサート」を開催しました。
当日に向け、Sさんたちは「ミニコンサート企画書」を校長先生に提出し、企画が通り、リハーサルを重ね本番を迎えました。曲目は、いきものがかりの「ありがとう」です。

演奏が終わると、6年生はSさんたちに駆け寄り「よかったよ」「ありがとう」などと感謝の言葉を口々に伝え、教室に戻っていきました。当日は、休み時間になると6年生を中心に音楽室へ訪れ、部屋に入りきれず廊下で聴く人がでるほどの盛況ぶりでした。5年生3名と職員2名によるヴァイオリンとピアノの演奏に合わせ、3年・4年・5年生6名が「ありがとう」を歌いました。

「多様性を受容する学校づくり」に取組んできたこの1年間。来年度は「子どもがやりたいことができる学校」の実現を目指すことにより、さらに「一人ひとりの子どもの多様性を受容する」ことにつながるのではないかと考え、歩みを進めていく予定です。
学びの改革パイオニア校 波田中学校
~ 自分の強みを知る機会になった! ~
「明日も学びに行きたくなる学校」を目指し、自己肯定感の醸成に努めてきた波田中学校。1年生では、信州大学の高橋史先生のご指導とご助言のもと、「ライフスキルアップ授業」を10月から月1回のペースで実施してきました。

6回の内容は、主に以下のようになります。
第1回 自分の行動は自分で選んでみよう
第2回 自分の強みを「活かす」「伸ばす」
第3回 ブレーキをゆるめてみよう
第4回 気分を測ることばとサインの使い方
第5回 体をゆるめて気もちもリラックス
第6回 行動を変えて気もちをリフレッシュ
6回の授業を通して、「自己肯定感を高められたと思いますか?」という質問に対し、「おおいに高められた」「まあまあ高められた」と答えた1年生は81.8%となり、多くの生徒が自己肯定感を高められたと感じたようです。

以下は、生徒たちの感想です。
- 自分の日々の生活の中で、「こんなことがあったらこう対処すればいいや」という方法を通して、自分を好きになることができたので、この授業は来年も続けてほしいなと思いました。
- ライフスキルアップを学んでことで、今まで知らなかった自分の強みを知ることができたり、リラクセーションやアクチベーションなど、色々と日々の生活に生かせるようなことを学べたりできたのでよかった。
波田中学校では、自己肯定感の醸成に向け、来年度も歩みを続けていきたいと思います。
3月25日 更新
リーディングスクール 寿小学校
『さあ、やってみよう』の学校づくりの成果
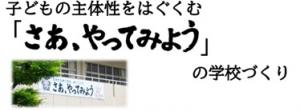
本年度、本校では「さあ、やってみよう」を全校のあいことばに、子どもの主体性をはぐくむ学校づくりに取り組んできました。そして、授業研究では、「子どもに委ねる学習」をキーワードに、子どもが主体的に取り組む授業づくりを目指してきました。
その取組の成果として2つの点が挙げられます。1点目は、児童の学びに向かう姿の変化についてです。4月、学習面でも生活面でも受け身だった子どもたちが、今では「先生、こんなことをしたいんですけど、いいですか。」と、自分の意思を示すようになりました。あるクラスでは、日々の宿題についても「自分たちで考えたり選んだりして取り組みたい」という思いを抱くようになり、話し合いの末に「マイプラン家庭学習」を行うようになりました。

2点目に挙げられるのは、教師自身の授業づくりへの考え方の変化です。ある先生は、「目の前の子どもたちが、自分たちの力だけで目標を達成できるには、どんな準備が必要か、一人一人の学び方の特性を考慮しながら準備をするようになった」と自らの変化を語っていました。
新年度に向けては、さらにICTを授業に溶け込ませながら、個別最適な学びの実現に向かう先生方の熱い気持ちを高めて、より一層「さあ、やってみよう」の精神で取り組んでいきます。
リーディングスクール 開成中学校
「光は本当に1点で集まるの?」 学びを深めていく生徒
前回に続き、1年生理科の授業です。本授業では「物体がレンズに近いとき、なぜスクリーンに像がうつらないのか?」という問いをもち、「光の道筋がどこで交わるのか探し出そう」と、一人一人が光の道筋を作図しながら探究を続けました。
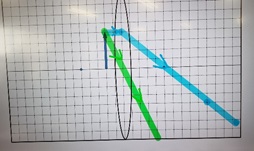
「1点に光が集まったという人もいるけど、光がどこかで交わることは本当にないのかな?」という教師の問いかけから、「本当に1点に集まるの?」「無理じゃないの?」「いやこうすればできるかも」などと、友と自分の考えを対話しながら学びを深めていきました。レンズに物体が近づくと「前みたいに作図ができない」「光が一つの所に集まらない」ことに気付き始めた生徒は、「光が一つに交わらないからぼやけるのかな」「うつるけど像じゃないのでぼやけるのかな」などと予想をたてました。

本授業は教師の問いかけから、「光は本当に1点に集まるのか」という探究が次時へと続きました。その流れはとても自然で、教科毎に探究のサイクルを意識して取り組んできたことが、成果として表れていると感じます。
『生徒が学ぶ学校』へ変わろうとしている開成中学校。この1年間でその土台はかなりしっかりとしたものになりました。さらに歩みを進める開成中学校の様子を、来年度もお伝えしていきたいと思います。
学びの改革パイオニア校 丸ノ内中学校
新年度を『教師の学び』でスタート!
丸ノ内中学校では学区の田川小学校、開智小学校と目指す学びのあり方を共有し、ともに「探究の学び」の実践に取組んできました。学びの改革パイオニア校として連携している軽井沢風越学園のスタッフも加わり、定期的に探究コーディネーター・ミーティングを開催し、各校の取組の現状、校内研修の進め方等の課題を協議、共有してきました。
その協議の中で「今年度の歩みを切れ目なく継続するために、教職員が入れ替わる4月の初めに、『学びの方向』を確かめ共有する合同研修会を開こう」というアイディアが生まれ、風越学園の連携・協力も得て実現することになりました。
3月の「ミーティング」では、「『探究』合同研修」の目的、内容や流れを検討しました。さらに、研修の中で行われる「ミニ探究活動『発見!丸ノ内中の〇〇』」をメンバーが実際に体験し、参加者の意識や活動の意義などを確認しました。

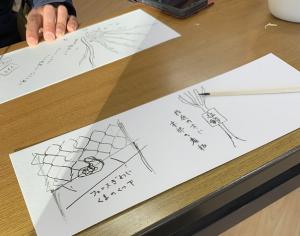
年度当初に、しかも学区の小・中学校が合同で「探究」について学び合うという画期的な「『探究』合同研修会」。1年の歩みをとおして「『学び』の大切さ・楽しさ」を子どもたちと深く実感してきた学校が、さらに新たな挑戦に踏み出そうとしています。
3月18日 更新
リーディングスクール 明善中学校

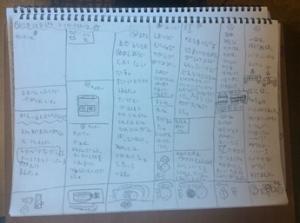
自由に思いのままかいたことが認められることで、安心して自分の感じたことを書いたり自分を少し開放できたりするなど、どの子も自信を持って表現できることにつながりました。
園小接続、接続期カリキュラム、生活科の充実、学びノートからの児童理解等、明善小学校が取り組んできた園小接続期における子ども理解と「学び」のあり方の研究は、子どもたちの主体的・対話的な学びや日常生活場面での課題解決力向上につながっていると感じます。今後は幼保小にとどまらず幼保小中のつながりや、高学年の学びの充実等についてさらに深まることが期待できそうです。
リーディングスクール 鎌田中学校
社会科教員としての私が「社会っておもしろい!」と思うから、子どもたちにもこのおもしろさを伝えたい、広めたい、知ってほしいと感じています。社会科のおもしろさを知った子どもたちは、「勉強をやろう!」「宿題はどうした!?」なんて教員が言わなくても、自ら学び始めると信じています。この学びに向かう原動力を育むことが、社会科教員が教える価値だと思います。
ある社会科の先生は、単元内の自由進度学習について、このように振り返りました。自由進度学習は、生徒自身が立てた問いの解決に向けて、自分で調べ、調べた知識のパーツをつなぎ合わせて全体的な学びを構成していく学習です。自分なりに出した答えを、根拠を持ってまとめ、他者に発信することも、鎌田中学校では大切にしてきました。
この学びを受けた生徒は「先生から教えられた」という講義型の授業では培うことができない学びの記述をしており、この学習形態に手ごたえを感じています。

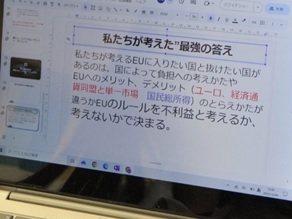
今後は、限られた授業時間数のなかで、頻出単語とその背景知識をおさえる講義型の授業と自由進度学習とのバランスを取りながら、生徒が生き生きと学ぶ授業となるよう取り組みたいと考えています。
学びの改革パイオニア校 開智小学校
「地域」をフィールドとして、全校で探究の学びに挑戦している開智小学校。
3年生は松本の商店街の見学をすすめる中で、「観光客のみなさんに、松本のよさを伝えたい」という願いをもち、チラシをつくって配付する活動を決めだし、挑戦しました。
チラシ作りに取り組む中で、新たな問いが生まれ、子どもたちは様々なことを深く調べていきました。土日を利用しておうちの方と一緒に調査にいったり、お店の方にインタビューしたりなど、自分で考えて取材する動きが生まれました。
3月。いよいよ、完成したチラシを街に出て配る日が来ました。
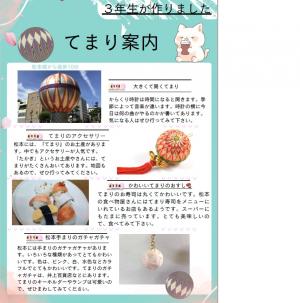
以下は、子どもたちの感想です。
★「初めは、はずかしくて声がかけられませんでした。思い切って声をかけた外国の方が、一生懸命に聞こうとしてくれたのがとてもうれしかったです。これがきっかけになって、どんどんチラシを配ることができました。」
★「お店に行ってチラシを見てもらったら、「3年生が作ったとは思えない」とほめてもらいました。すごくうれしくて、もっと頑張ろうと思いました。」
「思い」をかけとりくんできた「チラシ作り」や思いがけない「ひと」との出会いをとおして、「成長した自分」や「学びのよさ」を味わう子どもたち。「探究の学び」の力を実感する一コマでした。

3月15日、学校に1本の電話が入りました。松本城でチラシを受け取った方(県外の方)からでした。
「本当にうれしかった。子ども達は天使のようでした。松本てまりの話も良かった」とのお話でした。
子ども達のよさをお伝えいただいた言葉に、先生たちも幸せな気持ちいっぱいになりました。
3月11日 更新
リーディングスクール 中山小学校
中山小学校はこの1年間、「自ら探究的に学ぶ子どもを育む授業のあり方」をテーマに、生活科や総合的な学習の時間を核として実践を重ねてきました。
この1年間の歩みを、研究推進の中心となった佐藤先生にお尋ねしました。佐藤先生からは、「子どもたちは自分で考え、動くようになってきた。まずはやってみよう、失敗しても修正していけばよいと考えるようになった」と、子どもたちの成長の手応えが語られました。佐藤先生はさらに、「これからの予測困難な社会の中で、子どもたちはうまくいかないことがたくさん出てくると思う。そのような状況に恐れを抱くことは人間として当然あると思う。しかし、子どもたちには、人の力を上手に借りながら、自分がやろうとしていることに修正を加えながら逞しく生き抜いてほしい」と語られました。
子どもたちがこの1年間学んできたものは、「生き方」ではなかったか。そう感じました。

リーディングスクール 清水中学校
根拠を添えて自分の考えを表現できた場面の振り返りとして、生徒から「学年集会や生徒総会など、みんなが集まっている場面で、根拠を添えながら発言を多くすることができた」、「美術の時間に、自分がなぜこの作品にしたかの意見や根拠などをもとに授業に取り組めた」など様々なエピソードがアンケートに記述されました。また、自分の考えを表現するだけでなく、「自分の考えとそれに対する理由を持ちながら人の考えを聞く力」の大切さも生徒自身の気づきとして生まれました。表現力の土壌となる仲間との関係性を大切にしている思いも伝わってくる振り返りでした。
教師の振り返りには、「生徒を主語に据えて教材研究する時間が増えた。生徒が楽しく自己表現したくなる授業にするためにどうしたらよいかを常日頃から考えるようになった」や「生徒が『考えてみたい』と思えるかどうかをより考えるようになった」などが記述されました。確かな教材研究とあたたかな子ども研究から、子どもが主人公の授業づくりに手応えを感じられた1年間であったと思います。
 子どもや教材について語り、傾聴する職員集団
子どもや教材について語り、傾聴する職員集団
学びの改革パイオニア校 田川小学校
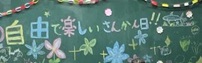
全校で「探究の学び」に取組んでいる田川小学校。3年生は、初めて挑戦する「総合的な学習の時間」で、自分たちで決めだした「探究したいこと」について、小グループで取り組んできました。時に、学級に投げかけて相談したり、みんなで同じ活動に取組んだりと、お互いにかかわりながら、それぞれの学びを続けてきた子どもたちは、2月20日、「自由でたのしいさんかん日」として、保護者の皆さんを招いてそれぞれの学びの成果を発表する会を企画・実施しました。


会の内容や構成、飾りつけや進行など、すべて子どもたちが考えて実施したこの会。グループごとに設置したブースでは、自分たちが取組んできた「藍染め」「野菜づくり」などの活動の足跡を、紙芝居にしたり、クイズにしたりなど、さまざまに工夫しながら発表しました。会場には、保護者の皆さんのほか、これまで3年生に様々なアドバイスをくれた5年生も訪れ、3年生の発表を見守りました。

実の「お客さん」を前に、元気・やる気いっぱいの子どもたち。「うれしかったこと、びっくりしたこと」など、その時々の「思い」を交えた「学びの物語」に、心からの温かな拍手が送られました。
3月4日 更新
リーディングスクール 筑摩小学校
4年生では、算数「直方体と立方体」の学習を自由進度で進めています。今年度のこれまでの取組から見出されたことをふまえて、学習環境の工夫を特に注力してきました。工夫の一つが写真のマグネットブロックです。実際の立体と展開図とのかかわりがイメージしやすいように用意しました。
ある日の授業でAさんは、展開図を組み立てたときに平行になる面はどれかを考える場面で、紙に図を描きながら考えていました。なかなか答えを導き出せないAさんを、隣で学んでいたBさんはじっと見ていました。しばらくすると、Bさんは廊下からマグネットブロックを持ってきて、Aさんに声をかけ一緒に組み立て始めました。「ここが持ち上がってこっちに来るから…」「あ、そうか!」Aさんは実物を操作する中で立体と展開図の関係をつかみ、問題の答えを導くことができました。

Bさんは以前に同じ問題でつまずいたときブロックを使って理解した経験を思い出して、Aさんに声をかけたそうです。自由進度学習の経験を重ね、当初は競争意識を持っていた子どもたちも、自分のペースで安心して学べるようになってきたことで、学びながら自然に他者と関わる機会が増えています。
今年度の取組をとおして、従来の教室での学びがほぐれてきていると感じています。
リーディングスクール 筑摩野中学校
筑摩野中学校が「対話を基盤とした授業づくり」とともに今年度力を入れたのが不登校生徒支援です。昨年度までは担任が中心の支援でしたが、今年度は、各学年に不登校生徒への支援担当職員を配置し、さらに、全校コーディネーターを新設しました。
学年担当や全校コーディネーターの先生がいることで、今まで以上に対象生徒を詳しく知り、学年会や職員全体で支援方法を考えることができました。全校コーディネーターの先生は、家庭訪問の回数を増やし、生徒や家庭との関係づくりを大事にしてきました。また、教育委員会の不登校アドバイザーとの懇談でも担当職員が積極的に質問したり相談したりして、いただいたアドバイスをダイレクトに学年会に伝えて共有し、支援につなげてきました。
その結果、あまり家から出ることのなかった生徒数名が教育支援センターに足を運ぶようになるなど前向きな変化が現れました。写真は、1月26日に視察に行った岡崎市立福岡中学校の教室の様子です。


一人ひとりの学びの機会の保障のため、今後も今の体制を強化し、継続していきます。
学びの改革パイオニア校 波田小学校
地域の方が子どもの登下校を見守って下さる等、日ごろから地域の方との結びつきが強い波田小学校。2月19日の「食育の日」、総合的な学習音時間にお米作りなどでお世話になった地域の生産者の方のお身を聴こうと、農家の方が栽培した野菜やお米を味わいながら一緒に給食を食べる「交流会」を実施しました。これまでも、家庭科や社会科。生活科や総合的な学習の時間の授業と食育を絡め、地産地消について学んできた子どもたちからは、たくさんの質問や感想が出されました。

5年生のある教室では、自分たちのお米作りの経験と重ね合わせ「お米作りで大変なことはどんなことですか」「おいしいお米を作るためにどんな工夫をしていますか」などの質問が次々にだされ、農家の方がお米作りに対するこだわりを熱く語ってくださいました。

地域の方のお米や野菜づくりの思いに触れ、もっと地域の方と触れ合う機会を大切にしたいという思いを強くしました。今後も、地域との連携を一層大切い考え、歩んでいく予定です。
学びの改革パイオニア校 波田中学校
「仏像の世界に秘められた魅力」を、「生徒が学びたいと思える授業に」と教材研究を重ねてきたY先生。「修学旅行を控える2年生が、仏像の魅力を感じとる」ことを目標に、美術の授業を公開しました。
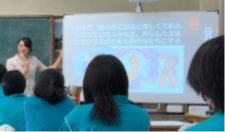
授業冒頭「修学旅行では何が楽しみですか?」というY先生の問いかけをきっかけに、生徒の意識は「仏像の世界」へと引き込まれていきました。
電子黒板を用いた「校長先生を如来・教頭先生を菩薩・担任を明王・教科担任を天部」とするユニークな提示やアニメ「呪術廻戦」の話を交えた服装・表情・髪型(アフロ)などの説明に、生徒は興味を引き立てられ、仏像の造形的な特徴をもとにグループ分けを行いました。
授業後、「仏像のイメージが変わった」「修学旅行に行くのが楽しみになった」などの声が生徒から寄せられました。

「生徒が学びたい」と思える授業づくりに向け「教材研究の大切さ」を再認識し、今後の課題として「対話が広がる授業の工夫」について職員で学ぶ機会となりました。
2月26日 更新
リーディングスクール 寿小学校
寿小学校職員3名は、2月に今年度3度目となる県外の先進校の取り組みを視察しました。先進校では、日常生活のあらゆる場面で子どもたちが自由に意見や考えを述べられる機会があり、学級の係活動、児童会活動、行事などが「子どもから始まる活動」になっていました。学校の主人公は、自分(子ども自身)であると自覚しながら活動する経験を重ねることにより、単元内自由進度学習においても、自らの学びを組み立てて進められる「主体的な学び」が実現し、そのことが「自律的な学習者の育成」につながると実感しました。
 県外視察の様子
県外視察の様子
 寿小研究まとめの会
寿小研究まとめの会
リーディングスクール 開成中学校
「『教師が教える学校』から『生徒が学ぶ学校』へ」を掲げ取組みを進めてきた開成中学校。教科毎に探究のサイクルを意識してきた取り組みの一区切りとして公開授業を行いました。
理科の1年生の授業では、「この地層から大地の歴史についてどのようなことがわかるだろうか」という教師の問いかけ後、今後どのように調査・実験・観察を行っていくか一人一人計画を立てました。

その後、提示された各層に含まれる岩石標本をもとに、「この岩石は何か」追究していく活動が始まりました。「これはチャートじゃないかな。釘で削ると釘が負けちゃうくらい固いから」「岩石を割って顕微鏡で見ると、鉱物が入っていないから深成岩ではないな」など、地層がどの岩石から構成されているか探究していく生徒たち。

教科毎に探究のサイクルを意識して取り組んできましたが、探究のサイクルを回しやすい教科もあれば、難しい教科もありました。ただ、探究のサイクルを意識しながら教科ごとに取り組んだことは、次年度より進めていく「総合的な学習」の改革にあたって確かな土台となるはずです。
学びの改革パイオニア校 丸ノ内中学校
丸ノ内中学校では総合的な学習の時間(忠恕の時間)に、学級を超えた小グループを編成し、それぞれが決めたテーマについて探究を進める「プロジェクト型探究」に取組んでいます。2月21日(水曜日)、1,2年生がポスターセッションで学びの歩みを発表・交流しあう「丸中Jr.学会」を開催しました。
1,2年生にとっては今回が初めてのポスターセッション。11月に参観した3年生の発表を一つのモデルに、準備を重ねてきました。セッションの前半は1年生、後半は2年生が、それぞれ15のブースを設置し、掲示物(ポスター)やタブレットの画像、実物等を示しながらこれまでの探究の歩みを発表しました。
当日は、丸ノ内中の生徒のほか、開智小、田川小の5,6年生、保護者の皆さん等、大勢の皆さんが参集され、それぞれのセッションに参加しました。発表者の熱意と参観者の期待感が響き合い、会場全体が高揚感に包まれていました。


やや緊張した面持ちで一生懸命語る1年生、取り組んできた題材への思いを熱く語る2年生…
参観したみなさんからも温かい感想や質問が寄せられ、各ブースで豊かな対話が行われました。

上級生、下級生、保護者、小学生、先生たち… 会場のみんなが「学ぶことのよさ・楽しさ」を分かち合う素敵な場になりました。
2月19日 更新
リーディングスクール 鎌田中学校
身近な地域にある疑問の解決を図る総合的な学習の時間「Kmdタイム」は、1年の振り返りの時期を迎えます。取り組む学級によってテーマは様々です。
ある学級は松本市の魅力の発信を課題とし、別の学級は松本の防災や避難場所に関心が向きました。さらにおやきや水まんじゅうなどを作る学級もありました。数十時間を費やして、実地調査したり地域の方や企業に問い合わせたりして知識を蓄えてきました。知りたいこと、取り組みたいことを、ありのままに自由に学ぶスタイルは、Kmdタイムのよさです。
とかくモノづくりや食べ物など、活動自体に目が向く傾向にあります。しかし鎌田中学校では、活動に繋がる学びの出発点を忘れてはいけないと考えています。身近な地域に寄せる素朴な関心や疑問を出発点として、その課題解決に向かう学びのプロセスを大切にしたいと思います。松本のことを知っていくことで新しい発見と価値を得られる授業となるよう、さらなる展開を目指していきます。
 1年 地域のごみ問題の解決に向けた取り組み
1年 地域のごみ問題の解決に向けた取り組み
 2年:信州大学生と土地の有効活用にしてディスカッション
2年:信州大学生と土地の有効活用にしてディスカッション
学びの改革パイオニア校 開智小学校
2月19日、開智小学校では1年間全校で取り組んできた「探究の学び」を全職員で振り返る「探究まとめの会」を持ちました。
全校の先生たちが3つのグループに分かれ、一人ずつ取組の成果や課題を発表し、グループの先生たちが「自分の実践に活かしたいこと」を中心にコメントを寄せ合う形で進められました。
会では「子どもたちに主体性と自信が育った」「自分で考えたことに熱中して取り組んでいた」等、先生たちが取組みの中で実感した子どもたちの学びの姿が活き活きと交流されました。

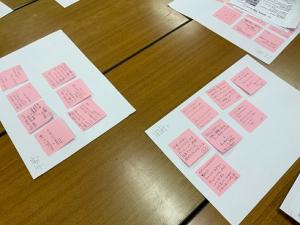
アドバイザーとして参加した中信教育事務所の指導主事の先生は「先生方が楽しそうに子どもの学びを語り合う関係性が素晴らしい。職員集団として『子どもってすごい!』と子ども観を更新されているのが大きな成果」と講評されました。
職員みんなで取り組んだ「探究の学び」の意味を確認し合う大切な刻みになりました。
2月13日 更新
リーディングスクール 中山小学校
1月24日(水曜日)には、この1年間の実践の共有と悩みの協議を、発表者と参加者に分かれてのポスターセッション形式で行いました。研究主任の先生のアイディアから生まれた新しい形の研修でした。先生方は自分の学級の歩みをスライドにまとめ、5分間のプレゼンの中に、子どもたちの探究的な姿と、そのような姿が生まれるための手立て、実践の悩みや困り感を語り、続く10分間で参加者の先生が意見や助言を行いました。

発表者からは、「外部の方や他の学年の仲間との関わりが増える中で、人へ進んで関わるようになった」、「知りたいことを調べるために本を利用する子どもが増え、本というものに対する意識が変わった」など、繰り返される探究の過程の中で、自身の生き方や身の回りのものへの見方が変容した姿が紹介されました。風越学園の岩瀬先生も参加され、中山小の先生方と一緒になって、子どもの成長を共に味わっておられました。

リーディングスクール 清水中学校
~「子ども同士の関係性」と「教師同士の関係性」は相似形~
1月26日には、埼玉大学の岩川直樹先生をお招きして、道徳(中1・中3)の授業研究が行われました。岩川先生からは、中1の学級には朗らかな雰囲気のなかに一人ひとりの言葉に関心を向けて引き受ける関係性があること、中3の学級には関心を寄せ合うあたたかな連鎖があることを、子どもの姿を通して意味づけていただきました。
また、職員室の雰囲気のよさも岩川先生が話題に挙げてくださいました。教師同士が日々の実践の構想や悩みを打ち明け、引き受けて語り合う職員集団であるからこそ、一人ひとりの教師が実践者として自立していることを価値づけていただきました。
全校研究テーマ「表現力が育つ~すべての活動を通して~」が、全ての学年で具現している清水中学校。その土壌として、子ども同士・教師同士のゆたかな関係性があることを実感する1日でした。
 資料を読んで感じたことを互いに伝え合う生徒
資料を読んで感じたことを互いに伝え合う生徒
 言葉を紡ぎだす生徒と、その言葉を受け取る生徒
言葉を紡ぎだす生徒と、その言葉を受け取る生徒
学びの改革パイオニア校 田川小学校
田川小学校の5年生の1クラスは総合的な学習の時間に「交流」をテーマに探究してきました。
1・2回目は校内の1年生と、いつも子どもたちを見守ってくださっている地域の「見守り隊」の方々との交流を重ねてきました。そして、3回目にはさらに交流の輪を広げ、就学前の幼児とその親御さんなど、様々な地域の皆さんを招いて交流会を実施しました。

地域のいろんなところにポスターを貼るなどして準備を重ねてきた子どもたち。当日は小さな幼児を含むたくさんの地域の皆さんが訪れ、運動遊び、折り紙、塗り絵等、子どもたちが用意した様々なブースでの交流を楽しんでいました。この交流会には田川小学校の1年生と3年生も加わり、とてもにぎやかな会になりましたが、5年生の子どもたちは、来場した人たちみんなが楽しめるよう、幼児に声をかけたり、地域の方をお茶に誘ったり、場所を整えたりと、自分で考え行動する姿が光っていました。

「疲れたけど、楽しかった!」とつぶやいた一人の5年生。「来てくれた人の笑顔が自分の楽しさ」という、シンカした「楽しさ」を味わっている姿と感じました。
2月5日 更新
リーディングスクール 筑摩小学校
1月22日に行われたリーディングスクール・フェスで「子どもの“学びデザイン力”を育てる学校づくり」をテーマに取組んだ今年度の筑摩小の歩みを発表しました。
はじめに、今年度の大きな柱となった「自由進度学習」の実践にあたって、子どもが自分の学び方を考えるための足場となっていた「けテぶれ学習」(計画・テスト・分析・練習のサイクル)を紹介しました。
その上で、自由進度学習の取組が子どもや教師の具体の姿を通して伝えられました。学ぶ場所や学ぶ順番の選択肢があることで、教科や単元に苦手意識を持っている子も安心して取組めたこと。普段の授業では受け身の子も、自分で考えて動く姿が見られたこと等が、成果として報告されました。
校内でこのような成果が共有され、自由進度学習を実践する学年がどんどん広がっていったこと。そして、授業公開には他校からも多くの先生方がご参観くださり、学校を越えて取組が広がりつつあることも大きな成果だと感じています。
筑摩小学校では、3学期も自由進度学習の取組を進めながら、子どもの“学びデザイン力”を育てていきます。
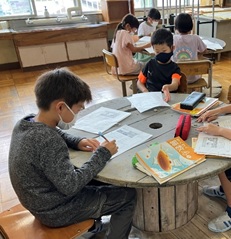

リーディングスクール 筑摩野中学校
筑摩野中学校では、「対話を基盤とした授業づくり」を全校研究テーマに掲げ、5月より「対話」を生み出すための4人組グループでの授業を行ってきました。今回は生徒や先生方の4人組グループの感想を紹介します。
3年生の生活記録には「今日は数学で円周角の定理をやりました。数学の授業では、話し合うことが多いです。4人班の机で授業をするようになり、『この問題ってこうやって解く?』などの会話がしやすくなりました。数学は、けっこう問題の答えが本当に合っているのか不安になりますが、目の前や横にクラスメイトがいることで確認がし合えるので自信がついたなと思っています。」と記されていました。近くに学んでいる級友がいるだけで安心感が生まれ、自然と対話する機会が増えているようです。

また、全学級を担当している家庭科の先生は、「4人グループに生徒が慣れてきていると思います。スムーズに授業に入っていきます。人間関係が柔らかく滑らかになってきていると感じます。」と話していました。

筑摩野中では2学期「聴き合う学級づくり」に力を入れてきました。4人グループが学びはもちろん人間関係の向上にもつながってきています。
学びの改革パイオニア校 波田小学校
「多様性を受容する授業づくり」を目指している波田小学校。職員研修の一環として研修係が、「信州大学伏木久始教授のお話を聞こう」と研修会を企画しました。
伏木先生からの提案で「気楽に語り合えるように」と、年代別にグループをつくり、グループごと教室に分かれ、オンラインで参加するスタイルを取りました。

演題は「単元内自由進度学習の実践で大切なこと ~教師の教育観が問い直される学習指導~」。
「学校に求められている教育の変化・自由進度学習を推奨する理由(自律的に学ぶ学習者を育てる)・自由進度学習の事例紹介」等のお話の後に、質問タイム・語らいタイムが設けられました。
自由進度学習に取組んだ先生方を中心に「学習計画を立てられない子へのアプローチの仕方」等、実践し困った点についての質問が出され、伏木先生が実践例をもとに質問に答えながらお話をまとめられました。

研修会後、「教師の教育観が問い直されている」と語り合う先生方の姿が印象的でした。
学びの改革パイオニア校 波田中学校
「ダンスは恥ずかしい」「踊ることは苦手」とダンス単元に苦手意識をもつ生徒に「ダンスの楽しさを実感してもらいたい」と教材研究を重ねてきたF先生。「今まで練習してきた成果を存分に発揮し、楽しみながら踊ることができる」を目的に保健体育の授業公開を行いました。
先生方に「見ていただきたい点(手立て)」として「(1)場の工夫は有効であったか(遮光カーテン・ スポットライト・音響)(2)タブレットの有効利用はできているか(音楽用・録画用)」を2点を明示。

生徒は、スポットライトと音響を有効に活用し、場の工夫を行い、普段の授業とはまったく違った雰囲気の中で迫力あるダンスを披露しました。音楽にのり楽しそうに踊る姿に、毎回の授業で練習を積み重ねてきた成果を感じました。


授業公開には10名以上の先生方が参観し、「生徒がやってみたい」と思える授業づくりに向け、「子ども理解・教材研究の大切さ」を改めて学び合いました。
1月29日 更新
リーディングスクール 寿小学校
11月20日(月曜日)の授業公開後の重点研究部会では、輝く子どもの姿の話題でもちきりでした。
1年生の「マイペース学習(算数)」では、単元終了後も「先生、自分でできたから楽しかった!もうおわっちゃうの?」「先生!家でもやってもいい?」という声が子どもたちから聞かれ、家庭でも主体的に学び続けようとする子どもの姿に出会うことができました。
5年生の「マイプラン学習(算数/保健)」の単元終末では、教師が設定したいくつかの発展学習の中から「保健 けがの防止」をプレゼンテーションソフトでまとめる活動を選択し、その活動に楽しさを感じながら時間をかけて取り組む子が多くいました。
自ら校内を歩き回って見つけたけがのおそれのある場所について、どのような危険がありそうか、どのように行動すればよいのかを考え、タブレット端末を用いて注意を呼びかけるポスターやプレゼンテーションを作成しました。
このように、授業をとおして、学習の根源的な価値である「楽しさ」「問題解決」「有用性」を実感する経験を積み重ねることは、子どもたちが生涯にわたり学び続けていく原動力につながっていくのかもしれません。
 休み時間もかたちづくりを楽しむ1年生
休み時間もかたちづくりを楽しむ1年生
リーディングスクール 開成中学校
夏休み以降、各教科1単元、探究のサイクルを回せそうな単元を選定し、授業を公開してきた開成中学校。全ての公開が終わり、来年度に向けて取り組みをまとめています。教科会で成果と課題を共有し、教科毎にまとめていますが、生徒が記入した学習カードやレポート等、生徒の姿がわかるようなものをまとめに入れて、生徒の姿を通してどうだったかを振り返るようにしています。この1年「生徒が学ぶ学校」を目指して取り組んできた開成中学校の姿勢がまとめ方にも表れています。
教科毎に探究のサイクルを意識してきた本年度の実践をベースに、来年度はいよいよ「総合的な学習」の改革に乗り出す予定です。そこに向けたプロジェクトもスタートしていますので、今後紹介していければと思います。

学びの改革パイオニア校 丸ノ内中学校
総合的な学習の時間「忠恕の時間」で「探究の学び」にチャレンジしてきた3年生の生徒たちが、軽井沢風越学園の9年生(中3相当)とオンラインで交流しました。
風越学園ではカリキュラムの中核に「探究の学び」を位置付けており、最終学年の9年生は「卒業探究」として、一人一人が各自が選んだテーマについて「探究の学び」を進めています。その「卒探」の中間発表会(アウトプットデー)の会場とオンラインでつなぎ、交流を行いました。
風越学園の生徒たちは、それぞれのブースでアウトプット(発表)を行います。そして、会場の保護者の皆さん、先生たち、児童生徒たちから質問や感想・アドバイス等のフィードバックを受けます。
丸ノ内中の生徒たちは、それぞれのブースをオンラインで訪れ、風越学園の生徒たちの発表を聴き、対話による交流をしました。

【生徒の感想より】
■探究が、個人それぞれの中でしっかりとプランの建てられているものばかりで聞いていてすごく関心を持つことができました。とても自分の身にもなるいい時間でした。
■どの講座も、失敗を繰り返しながら試行錯誤を重ねて作り上げたんだなと思える発表でした。私も、すぐに諦めるんじゃなくて失敗を重ねながら取り組める人になりたいと思いました。
■私たちがおこなっている探求と照らし合わせながら聞き自分たちの活動にも生かせそうなことを考えることができる機会になったのでよかった。
■様々な分野や活動から、それについて「行動」することで探究する姿がとても勉強になった。今後活動をしていくうえで、どのようにするのか、何のためにするのかなど、軸を持った探究にするためのことを学ぶことができた。
生徒たちの感想は、「学び方のよさ」に触れるものが多く、自身が「探究の学び」を体験したからこそ響いた「刺激」であることが感じられます。
初めての「他校」との交流。生徒たちにとって学びの「自信と可能性」を深める体験となりました。
1月22日 更新
リーディングスクール 明善小学校
1年生の生活科です。
「ぼくたちが保育園のときにおまつりに招待してもらったから、ぼくたちも招待したいな」と願いをもった子どもたち。「おまつりグループ」が中心になって準備し、寿東保育園の年長さんを招待しました。
自分たちの経験から年長さんが楽しめるものを考えて色々なコーナーを作ったり、2年生から接客についてアドバイスをもらったりして迎えた当日。屋台、お化け屋敷、ボーリング、射的…などたくさんのコーナーに年長さんは大興奮!おわりの会の感想発表では「楽しかった!」「また来たい!」の声がたくさん挙がり、保育園の先生からも「わかりやすくおまつりを進めてくれてありがとう。園にも遊びにきてね」と言ってもらい、大成功のおまつりでした。



リーディングスクール 鎌田中学校
3学年のある学級では、総合的な学習の時間「Kmdタイム」で「自分の大切なものを地震から守る」ためにできることを考えています。「防災ゲーム」を担当したグループは、楽しく防災の知識を学んでほしいという願いのもとカードゲームを作成しました。
「停電」「洪水」「津波」「家事」「地震」「土砂崩れ」という6つの災害に対して、「懐中電灯」「マッチ」「ハンカチ」「水」「傘」「タオル」「軍手」「ヘルメット」「スコップ」など、対応可能な最適なカードがそろえば手持ちカードを捨てることができるものです。
担当した生徒は、「様々ある災害に対して、ちょっとでも怪我が無く安全に避難するために、対応策を学ぶきっかけとして知識を身に付けてほしい」「小学生のような子どもだけでなく、大人にも必要な知識だと思う」と対策の必要性を意欲的に語っていました。


学びの改革パイオニア校 開智小学校
全校をあげて「探究の学び」に取組んできた開智小学校。
12月に実施した「学校評価アンケート」に、保護者の皆さんからの嬉しい声が届きました。
■創立150周年式典などがあり、総合的な学習の時間が多かった影響か、よりいろんな事に子どもの興味関心が増し、友達と協力して取り組む姿が以前より増えました。
■座学にとらわれない学習は刺激的らしく、家でも実験したり、調べ物をしたり、家族に質問するなど興味を持って学ぶ姿がありました。
■探究体験学習を通じて、社会の様々な事への関心が高まってきたのを感じます。
■「探究」というテーマが素晴らしいと思います。来年以降も開智小での学びに期待しています。
一番身近にいるおうちの方が、学校での学びの体験で育ちつつある子どもの「主体性」を感じ、応援メッセージとして学校へ届けてくださっていることに、先生たちは大きく勇気づけられています。
このようなフィードバックを子どもたち、保護者・地域の方々、先生たちで共有し、開智小学校ではさらに「子ども主体の学び」を目指していきます。


1月15日 更新
リーディングスクール 中山小学校
中山小学校では夏休みに風越学園の岩瀬直樹校長先生を招き、「子どもが探究的に学ぶこと」について職員研修を行いました。その際、岩瀬先生より「子どもと教師が一緒になって、学びの環境をつくりたいものです」というお話がありました。
中山小学校の先生方は、この言葉を受け止め、子ども主体的な学びが促される環境づくりにも取り組んできました。ある学級では、子どもたちが感じてきたこと、学んだことを先生と一緒になって整理し、掲示し続けてきました。この掲示は子どもたちが新たな課題に対峙した際に、解決に向けた取組みを作り出すよりどころとなっているそうです。
1月24日には再び岩瀬先生を招き、子どもと教師がともにつくる学習環境を見ていただく予定となっています。どのような感想をいただくことができるか楽しみです。


リーディングスクール 清水中学校
「そうだ 近畿、行こう。~地理的な見方・考え方を働かせて~」という魅力的な単元が、2年生社会科で展開されました。単元を貫く学習問題「なぜ近畿地方は旅行先として選ばれるのだろうか」を設定し、生徒は各自の仮説に基づいて視点を決めだし、産業振興の要因をワークシートに整理してきました。本時第5時は、友と情報共有することを通して産業振興を多面的・多角的に考察し、それを表現する授業場面でした。
ある生徒は、交通・通信の視点にこだわって情報共有をしていました。それは、前単元で学んだ交通網の整備と人々の生活とを関連付ける見方・考え方を働かせて考察しようとする姿でした。先生は机間支援を通してその生徒の姿を捉え、その生徒が追究しようとしていることのよさを価値づけていました。さらに、その生徒がこだわる交通・通信の視点からの追究が深まるように、グループ全員に旅行先に選ばれることの根拠となる交通・通信の資料を複数収集することを助言していました。生徒達は、収集した資料を共有するだけでなく、互いに「どうしてそれが旅行先を選ぶことにつながるのか」を問い返しながら、根拠の妥当性を検討しようとしていました。
清水中学校は全校研究テーマを「表現力が育つ~すべての活動を通して~」とし、各教科等の見方・考え方に基づく根拠を添えることを窓口として授業改善を図ってきました。本時の授業では単に根拠を添えるだけでなく、その根拠の妥当性も検討したうえで自分の考えを表現しようとする生徒の姿がありました。その背景には、確かな生徒理解と緻密な教材研究に基づき、上述のように意図をもって机間支援する先生の姿がありました。

↑ 地理的な見方・考え方を働かせながら友に問い返す生徒と、そのやりとりを見守る教師(左から2番目)

↑ 同じ視点で整理した友のワークシートと自分のワークシートを見比べながら、より深く考察しようとする生徒
全校研究テーマ「表現力が育つ~すべての活動を通して~」がより一層シンカして具現されている授業を参観することができました。
学びの改革パイオニア校 田川小学校
全校を挙げて「探究的な学び」に取組んでいる田川小学校。
2学期の振り返りとして、先生たちが、実践を語り合う会を持ちました。
先生たちは授業での子どもの作品や子どもの活動の写真など、思い思いに成果物を持ち寄り、小グループの中で、その時の子どもの様子、先生の思い、工夫点などを語り合い、聞き合いました。
嬉しそうに子どもの姿を語る先生。ニコニコしながらそれを聴き、時に問い返す先生。
楽しく和やかな会話が弾み、終了後も、職員室で話し足りないことを語り合うほどでした。


力を入れてきた実践のよさをお互いに確認し、3学期の実践に向けたモチベーションを高めあう、そんな素敵な時間になりました。
12月25日 更新
リーディングスクール 筑摩小学校
8月からスタートした2学期は、数多くの「はじめて」が詰まったものとなりました。はじめての高学年での自由進度学習の実践と公開では、他校の先生方にもご参観いただきました。2教科同時の自由進度学習にも挑戦しました。
写真は5年生がはじめてcanvaというデザインアプリで制作した本の紹介です。本のチョイスだけでなく色づかいやデザインに個性があらわれています。

子どもも教師も新しいことに挑戦しながら、締めくくりの3学期を迎えたいと思います。
リーディングスクール 筑摩野中学校
筑摩野中学校では、対話を基盤とした授業づくりに力を入れています。中学3年生のある生徒は、中学校での学びをふり返って「今年は4人1組での学習スタイルになり、楽しく学ぶことができている」と述べました。「対話」を生み出す4人組がよりよい学びにつながっていることを生徒自身が実感しているようです。
10月に発足した全職員参加のラーニンググループ(Lg)では、職員会議の中のLg学習会で授業づくりについて検討を重ねています。グループ内の話し合いを通して、「コミュニケーションがとりやすくなるエンカウンターとは?」「全ての子どもが前向きに取組める学習問題とは?」「問いで単元を構成する自由進度学習とは?」など新たな「問い」が生まれています。

1月16日には麻布教育研究所の村瀬公胤先生をお招きし、第2回授業クリニックを行います。「単元の核心に迫る今日のゴールの設定」「本質的な問いとなる魅力的な学習問題の工夫」などのご指導をいただく予定です。学校全体で授業づくり研修日として、授業者の先生の実践に自分の実践を重ね、学ぶ機会とします。
学びの改革パイオニア校 波田小学校
「運動が苦手な子も友と関わりながら楽しむことができる体育の授業」をめざし、5年生では「〇〇になりきろう!レッツムービング!」と題し、2クラスでダンスの授業を公開しました。
11月末の校内公開授業では、「イメージを広げて思いついたまま動いてみよう」をめあてに、二人組や三人組や四人組などになり、「ターザン」「ボーリング」など、子どもたちが考えたイメージカードに合わせて、思いつくままに自分たちなりの表現をし、クラスで見合いました。

12月1日の授業は、松本市体育同好会の公開研究授業として公開しました。「メリハリをつけた『海』を表現しよう」をめあてに、「陸にあがったカメ」「共食いをするピラニア」など引いたカードに合わせた表現をグループごとに行い、その後交流会でお互いに見合いました。

二つの授業とも、参加した全ての子どもたちが、友と関わりながら表現を楽しむ姿が見られ、笑顔と「ナイス」「すごい」の声が飛び交う時間となりました。
学びの改革パイオニア校 波田中学校
初任2年目のK先生は、「文法中心になりがちな授業から、生徒が必要感をもって、友と楽しみながら英語でコミュニケーションする授業へ」という願いを持ち、そのチャレンジを授業公開しました。
この単元では、K先生は生徒が表現への必要感を持てるよう、各自が事前にタブレットで家族や身の回りの写真をとり、その写真が何をやっているところか現在進行形を用いてクイズ形式で尋ね合う活動を工夫しました。
その対話の場面。生徒たちは「伝えたい」という思いにあふれ、時には思わず日本語も交えながら、生き生きと写真の内容を英語で表現しようとしました。英語での言い方がわからないところを友に気軽に相談し、自分の表現に取り入れる姿も多くみられました。


授業公開には他の教科の先生方も駆けつけ、子どもの姿から学び合いました。。
「明日も学びにきたくなる学校」を支える授業づくりへ向け、波田中学校の先生方はみんなで歩みを進めています。
12月18日 更新
リーディングスクール 寿小学校
11月20日(月曜日)に1年生と5年生で授業公開が行われ、市内から多くの先生方が参観に来られました。
1年生では、仲間と一緒に、自分の計画を自分のペースで進める学びを「マイペース学習」と名付け、算数「かたちづくり」で初めての自由進度学習に挑戦しました。第1時のガイダンスで学習の流れを丁寧に確認したことで、子どもたちは授業開始前にICT端末や、ファイル等の学習用具を自ら机上に揃え、自信に満ちた表情で学習に取り組んでいました。
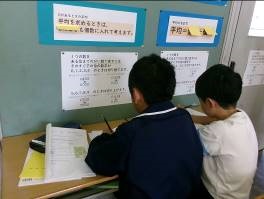
5年生は、算数「平均とその利用」、保健「けがの防止」の2教科同時進行の「マイプラン学習」を行いました。児童は、体験学習コーナーで「均す」言葉の意味を体感しながら、その意味を理解し、それぞれの計画に合った学習の場で学びを進めました。今年度二度目の単元内自由進度学習となる本学級は、問題や課題を解決する方法を自ら見つけて、さらに自律した学び手となって学習を進めていました。

リーディングスクール 開成中学校
夏休み以降は、各教科で探究的な学びを追究するため、各教科1単元、探究のサイクルを回せそうな単元を選定し、実践を積み上げている開成中学校ですが、並行して、来年度の教育課程について考える時期にもなってきました。全教育課程で「探究的な学び」の実現を図るには、「総合的な学習の時間」をどう「探究的」にしていくか、考えなければなりません。
そんな折、今年度継続してご示唆をいただいている、伊那市立伊那中学校長 有賀 稔先生をお招きして校内研修会が開かれました。探究学習「Inachu My Challenge」の実践からは学ぶことが多く、研修に参加した職員は大いに刺激を受けました。

ここまでの実践を経て、来年度の教育課程について本格的に来年度に向けた、開成中が向かう方向性については、次回以降随時ご紹介していきたいと思います。
学びの改革パイオニア校 丸ノ内中学校
学びの改革パイオニア校(探究)の3校では、風越学園との連携の一つとして「探究コーディネーター・ミーティング」を毎月開いています。3校のコーディネーターと風越学園スタッフを中心に、時に教頭先生も参加し、各校の研修・研究や、実践の状況、連携のあり方、悩みや課題等について情報交換・協議を行っています。これまでも、ここで共有されたアイディアのいくつかが各校で実践され、大きな成果をあげています。

12月8日に丸ノ内中学校で行われたミーティングでは、各校の来年度の研究・研修の見通しについて情報交換しました。
その中で丸ノ内中学校の先生からは、「実施したい研修」として
(1)「職員自身の『探究の学び』を引き続き進めること」
(2)「今年の歩みを新しい職員集団で引き継いでいくために、オリエンテーションを行うこと」
の2点が提案されました。(2)について、他の学校からも同様の課題意識が寄せられ、「3校合同の研修を行っては?」という意見が共有されました。
このような学校を越えた「学びのコミュニティ」が各学校の歩みを一層進めます。
2月に行われる丸ノ内中1,2年生のポスターセッションを、開智小、田川小の6年生が参観することも決まっています。
12月11日 更新
リーディングスクール 明善小学校
2年生と年長さんがペアになって、スタンプラリーをしながら学校探検をしました。「ここはね、図書館って言うんだよ。入ってみる?」「部屋に入るときは『失礼します』って言ってね。」など2年生が年長さんにやさしく関わる様子がありました。

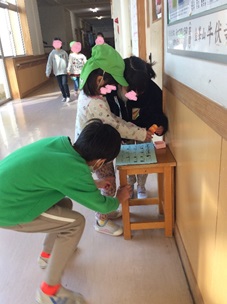
5月に2年生が1年生に学校紹介をした時とは変化が見られ、自信をもって案内や紹介をする頼もしい姿が見られました。年長さんからは「たのしかった!」「お姉ちゃんたちとみんなで楽しくスタンプが押せてよかった。」、2年生からは「ペアの子が笑顔で楽しそうでよかった。」「みんながケガをしないで楽しくスタンプラリーができてよかった。」等たくさんの感想発表がありました。
リーディングスクール 鎌田中学校
3学年のある学級では、総合的な学習の時間「Kmdタイム」で「自分の大切なものを地震から守る」ためにできることを、様々な観点から問いを立て解決に導くこととしています。
生徒は5つのグループに分かれて活動しています。このなかで「防災減災マップ」グループでは、鎌田地区周辺の危険個所を実地調査し、実際に感じた危険度をもとに独自のハザードマップを作成しています。また「火災発生時の風向によって延焼範囲は変わるのでないか」という問題意識を出発点として、風向別の延焼範囲を示すハザードマップ作りにも力を入れています。
 ←実施調査の結果を地図に落とし込む
←実施調査の結果を地図に落とし込む
 ← 調査結果をもとに延焼範囲を記した地図について、学びのプレゼンテーションをする
← 調査結果をもとに延焼範囲を記した地図について、学びのプレゼンテーションをする
「もし地震がきても、住民全員が安全に過ごせるようなマップを作成していきたい」と熱意を持って取り組んでいます。
学びの改革パイオニア校 開智小学校
全校で「探究的な学び」に取組む開智小学校。5年1組の子どもたちは、幼稚園の年長組の園児たちとの交流活動に取組んでいます。10月に第1回の交流会を実施した子どもたちは、「もっと楽しい交流にしたい」という願いを高め、2回目の交流会の計画を練り上げました。(詳しくは学びの風便りNo13 [PDFファイル/739KB]参照)
こうして迎えた11月の2回目の交流会。5年生は前回よりさらに主体的に園児に関わります。言葉で説明した時、よくわかってもらえてない!と判断するや、実際にやって見せるなど、目の前の園児をよく見て、その場でより細やかに配慮する、そんな素敵な姿がいたるところで見られました。


「探究の学び」の効果はここにとどまりません。「国語や算数など、他の授業でも、ちょっとした折に自然な話し合いが始まったり、困ったときに気軽にヘルプを出せるようになったりなど、子どもたちの主体性やコミュニケーションが豊かになりました。」と担任の先生は振り返られます。そして「この学習に取組んで、学級が一層仲良くなりました。本当に取組んでよかったです」とにこやかに語られました。
「探究の学び」から、育まれる確かな「力」。それを子どもたちが豊かに物語ってくれます。
12月4日 更新
リーディングスクール 中山小学校
11月初旬に地域の文化祭で『泉小太郎』の劇を発表した4年生の子どもたちは、11月21日(火曜日)全校に向けて劇を披露しました。自分の母が龍なのかもしれないことを知り、うろたえる小太郎の気持ちを声色や抑揚で巧みに表現するナレーション、龍(小太郎の母)が小太郎の前から去っていく際に、後ろ髪を引かれるように小太郎の周囲をぐるぐると周りながら舞台の裾へ消えていく演出等、これまで様々に振り返り、演技に組み込んできたものが見事に表現されていました。他の学年の子どもたちは終始、劇に引き込まれていました。

劇が終わり、会場が大きな拍手に包まれた後、4年生の子どもたちは一つの輪になってこの発表の振り返りをしていました。「今回は、前回よりもとてもよかったと思う」「前回も今回もとてもよかったよ」「もっともっと、発表したい」など、演じながら感じた手応えや次の活動への願いが率直に語られました。劇づくりを通じ、同じ目標に向かって工夫を重ねてきた仲間としてのつながりが、より一層深まったように感じられました。

リーディングスクール 清水中学校
11月17日、1年生の技術・家庭科(技術分野)の授業が、市内の教職員向けに公開されました。単元「生活をちょっと豊かにする私の棚」のなかの、既存の技術を理解する授業場面でした。生徒は、経済性・機能性・安全性の視点から既存の製品に施された工夫を見つけ、Sky Menuの「気づきメモ」に記録していきました。この「気づきメモ」はチャット形式でリアルタイムに更新されていくため、クラス全員の考えを瞬時に共有できる利点もありました。「気づきメモ」に投稿された友の考えを読み、その根拠について友と直接、対話する姿があちらこちらで見られました。

【写真】「気づきメモ」に投稿された友の考えを読み、考えの根拠について友に問いかける生徒
清水中学校は今年度の全校研究テーマを「表現力が育つ~すべての活動を通して~」としています。今回の授業は、技術分野ならではの根拠を添えて自分の考えを表現する場が、一人ひとりに確保されていました。だからこそ、自分の考えとは違う考えに触れた生徒は、自然と対話をしたくなっていったのでしょう。参観した他校のある先生は、「挙手をした生徒だけが発言するという形に限定せず、一人ひとりが力をつけられるように表現方法を支援していることが参考になりました。今後もこういった参観の機会がございましたら幸いです」と語っていました。
リーディングスクールとしての授業改善の機運が、他校の先生にも広がる一日となりました。
学びの改革パイオニア校 田川小学校
全校で探究的な学びの実践に歩み出して8ヵ月。田川小学校では11月24日、探究の学び公開授業研究会を開催しました。
公開授業は2年生生活科と6年生の総合的な学習の時間の2本です。
2年生「大ずさん、いつしゅうかくしようかな」は、それぞれの子どもが収穫期を迎えている「わたしの大ずさん」の様子を観察し、「今、大切だと思うこと」を思い描き、思い思いに大豆に関わる時間でした。大豆を一粒ずつさやから取り出し丁寧にスケッチする子ども、最後の成熟を期待して根の周りに土寄せする子ども…自分の大豆との「くらし」の中で深めてきた大豆への思いの深さがいたるところで感じられる時間でした。

6年生「田川のはてまで行ってQ」では、田川地区の神社・寺院など、それぞれのグループが「気になって調べた」場所について、いろんな人たちに興味を持ってもらうための「クイズづくり」にクラス全体で取り組みました。「問題」の「解答と解説」を考える中で、これまで調べてきたものを見返し、さらに調べたいことを見出すなど、新たな問いを立てる子どもたちの学びがありました。

授業後の研究会は、今回も「田川小方式」で実施。参観者は観察した子どもの写真をタブレットで示しながら、その行為の背景にある思いを想像し語り合います。一つの行動の「解釈」を交流させることで、みんなで子ども理解や指導観を深め合う時間となりました。

11月27日 更新
リーディングスクール 筑摩小学校
先日行われた5年理科「電磁石のはたらき」の自由進度学習でのようすです。
電磁石の磁力はどうすればもっと強くなるのか、それぞれ予想を立てた子どもたちは、自分で巻いたコイルを手に電流の強さやコイルの巻き数を変える実験を行いました。
Aさんは同じ机で実験する友と関わりながら、自分のペースで実験を進めていきました。「これでいいのかな」「そろえる条件はなんだっけ」「もう一回やってみよう」などのつぶやきや会話から、客観性・実証性・再現性などの科学的な考え方をはたらかせていることが分かります。
Aさんは、隣のBさんの手元をのぞいて実験の方法や結果を確認していました。また、別のテーブルで実験していたCさんの「電池2個のときはどうつなげるんだっけ」という問いかけに、自分の机の回路を指さして答えるなど、多くの友と関わりながら実験し、「電流を強くするかコイルの巻き数をふやすと電じ石は強くなる」と考察しました。

自由進度学習の中でそれぞれの子どもが主体的に事象とかかわる「個の学び」を進め、さらに友とかかわりながら互いの学びを深めている姿がありました。
リーディングスクール 筑摩野中学校
筑摩野中学校では、4人一組のグループをもとに、対話を基盤とした授業づくりに力を入れています。
10月30日の2年生の英語の授業では、前を向いてスタートし、途中で4人組になりました。4人組になると、自然と「ここは、こう?」「だから…」というような声が生まれます。社会の授業では、「なぜ東京に人が集まるのだろうか」という問いの答えを教科書や資料集、インターネットなど自由に使って調べ、話し合う様子がありました。どの学年、どの教科でも『「問い」と「対話」とにより主体的に学ぶ生徒を目指して』研究を進めています。

また、先月、授業づくり推進チームが発足し、全職員で9つのラーニンググループ(Lg)をつくりました。職員会議の中にLg学習会を位置づけ、授業づくりを検討する場を設けています。11月15日の職員会議で、1回目のLg学習会を行い、グループのテーマに即して、これまでの取組やこれからの見通しを、和やかな雰囲気で話し合いました。

学びの改革パイオニア校 波田小学校
5年生の算数の学習では、2クラスを「じっくりコース・ぐんぐんコース・どんどんコース」の3つのコースに分けて進めています。
「ぐんぐんコース」では、「平均とその利用」の単元(6時間)を、自分のペースで学習を進めていくことができるように、1時間ごと自分でここまで進もうという「今日のゴール」を定めて授業に取組んでいます。

共通課題の「学習プリント(平均の問題)」を一人で黙々と追究したり、友と相談し合ったりしながら解き終えると、自分で答え合わせをし「わくわく算数」の類題を解きました。その後、チャレンジ問題に進んだり、「体感コーナー(りんご3個の重さを実際に測定し、りんご20個分のおよその重さを自分で求める)」に挑戦したりするなど、自分の解きたい問題にトライしていきました。

1時間授業の中で、自分のペースでチャレンジしたい問題に取組み学びを深めていく姿に、波田小が目指す「多様性を受容する授業づくり」の一端をみることできました。
学びの改革パイオニア校 波田中学校
相談室に通う生徒にも「卒業生のその後を知ってもらいたい」と願い「相談室進路講話」を実施しました。
3年前に波田中を卒業した松本筑摩高校在籍のYさんが、進路選択の経緯や現在の心境などについて語りました。
「私は中学校の時不登校状態でした。そんな私ですが嫌でも時間は過ぎていきます。…ぐるぐる考え続け迷っていた私にこの学校を教えてくれたのは、当時通っていた相談室の先生です」と当時の心境を語り始めたYさん。

高校入学当初心配だった学習面も、高校の開設講座の工夫により心配することなく受けることができたこと、現在は生徒会の役員になり大変な分、達成感があることなどを力強い言葉で語りました。相談室、自・情障学級、あかり教室在籍の生徒たちが、Yさんの話に最後まで聴き入っていました。
「子どものもつ可能性のすばらしさ・自分の輝ける場所がある大切さ」等を改めて実感し、「明日への希望」へとつながる進路講話でした。
11月20日 更新
リーディングスクール 寿小学校
寿小学校では、「さあ、やってみよう」の合言葉のもと、単元内自由進度学習部会のチャレンジが、他の部会にも共有されています。
社会科部会では、自分の願いに向かって、主体的・協働的に学ぶ子どもの姿を目指した授業研究が進められてきました。
11月13日(月曜日)には、社会科部会による校内研究授業が行われました。4年「地震からくらしを守る」の単元の導入では、2011年に発生した長野県中部地震(松本地震)について、ゲストティーチャーとして当時の寿公民館長から、多くの被害が出た話を聞くとともに、市内の被害の様子を写真や動画を見聞きすることで、当時の大変さを知りました。
単元のはじめに関心を高め、自分ごととして捉えた子どもたちは、学級全体で複数の学習課題をつくり、身近な地域資料から、課題解決に向けて個人で資料を選び追究を進めました。教室には、写真だけでは伝わりにくい「液状化現象」の体験コーナーなどが用意され、学びを深めました。自由進度学習の要素を含んだ学習環境が、子どもたちの学びを変え、学習を楽しむ姿につながっています。

リーディングスクール 開成中学校
2年生の数学の授業です。本時は【△ABCで、∠Aの二等分線を引くと、AB:AC=Bd:Dcになることを証明する】授業でした。初めに作図してみて、『AB:AC=Bd:Dc』が成り立ちそうだという実感を持った生徒に「証明しよう」と先生が投げかけます。生徒が「難しそうだけれども辿り着けそう」と意欲と見通しをもてる「学習問題」でした。「問いの大切さ」をあらためて感じます。
しかし、いざ証明しようと考えてもなかなか思うように進みません。そこで先生は「平行線の性質」という既習事項をヒントとして提示します。これによって考えが進み始めた生徒が数名見られるようになりましたが、全体としてはなかなか進まない生徒が多い様子です。
そこでグループ学習を促すと、教室のあちこちに学びの輪ができ(図1)、少しずつ広がり始めます。「なるほどそこか」「分かりそうだけど、○○の説明が高度過ぎてわからない」等々、様々なつぶやきが聞こえてきました。生徒たちの対話が大いに盛り上がり、授業の残り時間があとわずかとなったところで、先生が生徒たちのアプローチのうち、代表的ないくつかを黒板に紹介しました(図2)。
 図1
図1 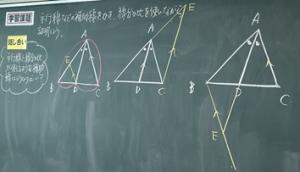 図2
図2
これによって「なるほど!こう考えれば行けそうだ!」と収束していく生徒もいれば、「それでも自分のやり方を何とか貫きたい!」と追究を続ける生徒もいました。子どもたちが自ら学んでいくエネルギーを体感する一時間でした。
学びの改革パイオニア校 丸ノ内中学校
11月6日、三年生は「忠恕ポスターセッション」として15ブースを開設し、保護者・1・2年生に向け、探究の学びの発表会を実施しました。(詳しい様子はリーディングスクール通信「学びの風便り」11号をご覧ください。)

自分たちの学びの足跡を発表した生徒たちに、「学んでよかった、と思うことは何ですか?」と質問したところ、
「松本の街をもっとよくするにはどうしたらいいか自分ごととして考えるようになりました。これまでの自分にはなかったことでした。」
「多くの人とかかわって話をきき、松本のよさや課題を深く知ることができました」
「伝統工芸について深く知ることができました。そして、今、それが途切れかけていることも切実に感じました。自分が伝えていきたいと強く思うようになりました。」 等、それぞれの生徒が自分の言葉で活き活きと、豊かに話してくれました。その表現力に心動かされるとともに、自分たちの学びのよさを実感し、誇りに感じていることが伝わってきました。

11月9日、この3年生の姿に触れた1,2年生が「一日忠恕」に取組みました。
「子どもたちの学びに、すごく勢いが増した!」(校長先生談)充実した一日になりました。
11月13日 更新
リーディングスクール 明善小学校
1年生の生活科。9つのグループに分かれて自分たちのやりたいことをどんどん見つけています。「先生!絵の具ちょうだい!」の声に応えて先生が絵の具を用意してくれました。筆はありません。どうしようか考えた子どもたちは…「手でやっちゃおう!」とペタペタぬりぬりし始めました。
なければ考える、やってみる、うまくいかなかったらまた考える、試行錯誤の連続です。


リーディングスクール 鎌田中学校
1学年の社会科の授業では、南アメリカ州について学んでいます。この単元では、生徒たちが自分の興味関心に沿って自由に探究する学習形態をとっています。テーマは、南アメリカ州の環境保護と経済発展のメリットとデメリットを調査すること。
「ボリビア」に興味をもった生徒は、「ボリビアは貧困国であることを知り、興味が湧きました。ボリビアは多文化国家で、文化間の対立が起こることもあります。次回の授業では、この問題について調べたいし、先生から教えてもらった児童労働についても調べたい」と述べ、学びを力強く進めています。
先生は、机を回って生徒と対話する機会を頻繁に設けています。生徒は、対話から生まれる新たな問いの解決に向けて学びを深めています。

学びの改革パイオニア校 開智小学校
11月10日、3年生から6年生の一クラスずつが2校時から5校時に分かれ、総合的な学習の時間を公開する「開智探究の日」が開催されました。
全校研究授業も兼ねた授業学級の5年生は、10月実施した聖十字幼稚園年長児との2回目の交流に向けて「園児にもっと楽しんでもうらために」をテーマに、活動グループで交流計画を話し合いました。「年長さんが鉄棒で遊ぶと危険だから、校庭で説明をしてから芝生に移動した方がよい」など、園児のことを配慮しながら意欲的な話し合いが展開されました。

授業終末のグループ発表後の質問タイムでも「もっと楽しんでもらうために、手加減の具合を考えた方がいいと思う」など、園児への相手意識を考慮した意見が出されました。

授業研究会は事前に観るグループを決め、グループごと1時間の子どもの様子を語り合い、子どもの成長と「子どもに任せよう」と努める先生の支援のよさを確認し合う、温かい時間となりました。
担任が願う「主体性、相手意識、表現力」が見事に具現化された探究の学びの時間となりました。
11月6日 更新
リーディングスクール 清水中学校
1 年間の折り返しの 10 月、全校生徒対象に第2回学習オリエンテーションを開催しました。清水中学校では全校研究テーマ「表現力が育つ~すべての活動を通して~」の具現に向け、判断の根拠を添えて表現することを重点に据えています。
今回は全国学力・学習状況調査の結果と考察を全校の生徒と共有し、全校研究テーマとのつながりを考える機会を持ちました。
それとともに、「判断の根拠を添えること」を具体的にイメージできるよう、1枚の写真を題材にして、各教科ならではの見方・考え方を働かせて気づいたことを表現し合う活動を行いました。
同じ写真を「国語」「社会」「数学」「美術」…等、それぞれの視点で見た時に得られる気づきを、全校が一堂に集まった中で豊かに述べ合う生徒たち。発言のたびにどよめきや笑い、拍手などが響き合いました。
根拠を添えて表現し合うと学びや人生がより豊かになることを、生徒と教師が一体となって実感できる場となりました。
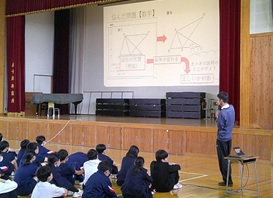
学びの改革パイオニア校 田川小学校
全校で「探究的な学び」に取組んでいる田川小学校。4年生は、これまでさまざまに準備を重ねてきた「保育園児との交流会」を10月末に開催しました。
交流する保育園は2つ。それぞれの子どもたちを招待し、2回の交流会を実施します。
第1回目。はじめての経験であることから、子どもたちはやや緊張気味。無我夢中で交流会を終えました。1回目を振り返る中で「もっと園児が自分で動けるように工夫したい。そのほうが楽しんでもらえると思う」という視点を共有しました。

そして迎えた第2回。1回目の学びを活かし子どもたちは様々な活動の工夫をしました。例えば「しっぽとりゲーム」。勝敗を決める際、前回は4年生が単純にしっぽを数え、勝ち負けを決めて発表していたのですが、今回は「しっぽを持っている人!」と園児に活動を促し、集まってきたしっぽをみんなで声をそろえて数えて、勝ち負けを確認する方法にシンカさせました。園児たちが声を上げて喜ぶ様子に触れ、4年生もうれしそうでした。

体験し、それを振り返り、再挑戦することで、学びを深めていく子どもたちです。
10月30日 更新
リーディングスクール 筑摩小学校
理科専科のA先生は「普段の授業が子ども主体になるように改善していきたい」という願いをもち、日々の授業や教室環境の改善に取り組んでいます。この机の配置は、黒板の字の見やすさと、グループでの観察・実験や話し合い活動のしやすさを両立するために試行錯誤する中で生まれたものです。全員が黒板に向かって学ぶことも、それぞれの机を囲んで活動することもできますよね。

あたり前だと思っていたことを少し視点を変えて見直すことで、学びを一歩ずつシンカさせています。
リーディングスクール 筑摩野中学校
筑摩野中学校では、授業づくり推進チームを発足しました。授業づくり推進チームのメンバーがリーダーとなってラーニンググループをつくり、全職員がいずれかのグループに入ります。テーマは次のとおりです。
1 魅力的な学習問題
(1)生活に結びつく必要感・必然性のある問いは?
(2)生徒が問いを持つためには、どうしたらよいか?
(3)問いで単元を構成する自由進度学習は?
2 学習の足あとがわかったり評価につながったりする振り返りは?
3 思考が深まるワークシートは?
4 4人一組のグループのアイディアは?
5 人間関係づくり(エンカウンターなど)は?
6 ユニバーサルデザインは?
ラーニンググループで学習会を行い、授業を見合い、“「対話」と「問い」により主体的に学ぶ生徒”を目指して授業づくりの研究を全職員で進めていきます。
学びの改革パイオニア校 波田小学校
「子ども理解」と「授業改善」を柱に研修を進めている波田小学校。今回は、算数の学習に困難さを感じている子どもたちへの理解を深めるために、松本大学教育学部山本ゆう先生を講師に「算数障害の理解と指導法」について学び合いました。
算数障害とは、「4年生になっても指を使って計算している・九九を覚えられない」など、その子の努力の差ではなく「加減乗除のような基本的な計算能力の習得の困難」なことを言い、わかりにくさをもっている子どもたちの実態からその「困難さ」や個に応じた指導例を学びました。
講演の最後には、「3年生でも指を使って計算をする子へのわかりやすい声掛けがあったら教えてください」など、合理的配慮や個別の支援について積極的に質問が出されました。

このような多様性な子どもへの理解を深め、授業改善を一歩ずつ進めていきます。
学びの改革パイオニア校 波田中学校
1年生では、信州大学の高橋史先生の指導・助言のもと、「自己肯定感」の醸成に向けて「行動を選ぼう!」(心理教育学習)の授業実践をスタートしました。
まず「人生すごろく」を行い、「ブラック企業に入る」「酒におぼれる」「お金持ちになる」など人生におこることは予測できないことを実感し、「こんな人生はいやだな」など、楽しく班ごと話し合う姿が見られました。その後、自分の人生に起こってほしいことを6つ選び、人により価値観が様々なことを知りました。
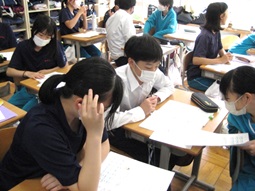
最後に「雨がよく降る町で…」必要な道具を選び、多くの生徒が「かさ」「タオル」を選ぶ中、「トランペット」を選び「雨の日でも室内で演奏できる」と発想する生徒がいました。雨のせいにするのではなく、雨をどう乗り切っていくかというプラスの考え方をもつ大切さを分かち合いました。
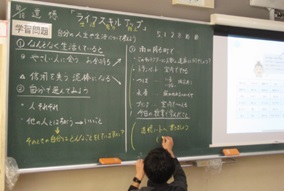
今後も高橋先生の助言を受けながら、この実践を毎月1回ずつ行い、自己肯定感の醸成に向けて歩んでいきます。
10月23日 更新
リーディングスクール 寿小学校
寿小学校職員4名は、10月に県内外2つの先進校の取り組みを視察しました。先進校では、「学びは子どもがつくる」という考えのもと、授業者が多様な選択肢を子どもに提供し、子どもたちが自己決定していくことができる「学習コーナー」を充実させていました。子どもたちは、体験的学習要素が多く含まれた学習コーナーで、触れたり、操作したりしながら思考力・判断力・表現力を養う姿がありました。

視察後、自校での重点研究部会では、視察した子どものよさが語られました。単元内自由進度学習部会では、11月中旬に、1年生と5年生の授業公開を予定しています。主体的、自律的に学ぶ子どもたちの姿を想像しながら、一歩ずつ進めていきます。
リーディングスクール 開成中学校
2年生の社会科地理的分野、近畿地方の京都に焦点を当てた授業を紹介します。学習問題は「京都市内にパリ風の歩道橋をかけるべきかどうか」。この問いに答えるため、賛成の立場であれ、反対の立場であれ、「京都の特徴」や「京都の置かれている現状」等について考えざるを得ません。1人1人が夢中になって考えている姿がとても印象的でした。個人個人が追究した後、グループで自分の意見を発表し合い、グループ毎に結論を出しました。
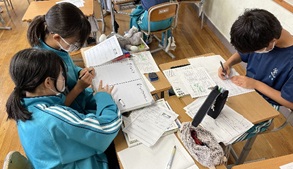
授業の最後で「話し合いをするのが面白かった」との感想が出ました。自分自身で考えたこと、それを話し合う過程が楽しかったようです。さらに、授業後に授業者の先生も、問いを大切に考え「生徒が学ぶ授業」を構想し、実際に目の前で学習を楽しむ生徒の姿を見ることができて「楽しかった」と話されました。
「問い」の大事さを知った先生の授業が変わり始めました。そして、それによって生徒の姿も変わり始めました。「教師が変われば生徒が変わる!」それを実感する授業でした。
学びの改革パイオニア校 丸ノ内中学校
第1回の「一日忠恕の時間」で、「街を歩く様々な人たちとの対話」を求めて、初めて「街中カフェ」を開いた3年生。
活動の振り返りで出された反省を踏まえ、10月5日の第2回では、より多くの人と対話ができるよう、以下のような準備をしました。
自分たちの活動が伝わるよう、看板や案内表示を制作。
話題を精選し、自分から話しかけるようにすることを確認。
コーヒーを倍の量(約100人分)準備。

こうして迎えた10月5日の当日。カフェには前回の倍以上の人が訪れ、その方々と生徒たちとの会話が大いに盛り上がりました。

1回目から2回目への大きなシンカの手応えを得た、一日になりました。
10月16日 更新
リーディングスクール 中山小学校
秋も深まり、4月からおもいをかけてコメを育ててきた5年生は、いよいよ稲刈りを迎えました。育てたうるち米ともち米のうち、特にもち米がたくさん収穫できました。収穫したコメをどうするか。子どもたちからは、「調理して食べたい」「もち米はたくさんとれたから販売したい」などの願いが出されました。

収穫したコメをどうするか。新しい課題に子どもたちは向き合います。
リーディングスクール 明善小学校
バスに乗って松本市内へ遠足に出かけた2年生。
遠足の感想を先生が用意した紙ではなく、「学びノートにかきたい!」との声が子どもたちから上がりました。先生は子どもたちが出し合った感想を受け、「『すごかった』の中身を詳しくかいてね」と投げかけました。
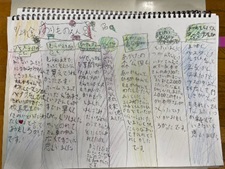
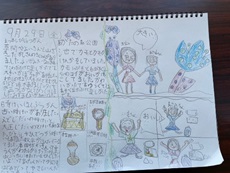
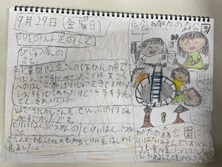
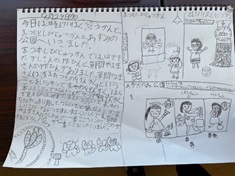
見たこと、聞いたこと、体験したことなど、一人ひとりの『すごかった』思い出が、学びノートからあふれ出ています。
学びの改革パイオニア校 開智小学校
10月4日、キッセイ文化ホールで創立150周年記念式典を開催しました。開智小では今回の式典を、学年・学級ごと積み重ねてきた開智学校や地域についての探究的な学びの発表の場にしようと準備を進めてきました。
6年生は「つなげよう 私たちの宝 ~松本城・旧開智学校・松本市の観光~」をテーマにクラスごと探究的な学びの成果を紹介しました。1組は、松本城について調べてきた自分の思いを短歌にまとめ、一人ひとりがオリジナルのプレゼンを作成し自分の句を詠みあげました。

2組は、旧開智学校校舎が移転した経緯、校歌や校訓が大切にされてきたこと、玄関前に植えられているシンボルの黒松が贈呈された由来などを発表し、地域に支えられてきた学校の歩みについて紹介しました。
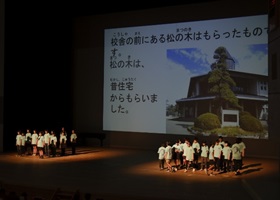
3組は、松本の観光客の月ごとの推移数や外国人観光客数が多い国などをクイズ形式で会場に問いかけ、松本がもっと魅力的な観光都市になってほしいという自分のたちの思いを伝えました。
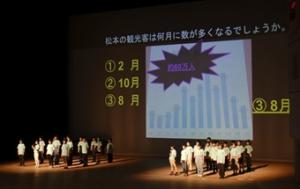
今まで学校全体で積み上げてきた「探究的な学び」の成果を披露し、「子どもが主人公」を体現した記念式典となりました。
10月10日 更新
リーディングスクール 清水中学校
9月14日に2年生113人は、松本県ヶ丘高校探究科の2年生80人を招いて、探究活動の成果を発表しました。7月に行った職場体験学習を基に、「働くこと」に関わるテーマを各自が設定し、ここまでに学んだことを高校生に発表しました。

高校生からは、「テーマ設定の理由がしっかりしている」といった中学生にとって励みになる言葉とともに、「探究は、問いに対する仮説があって、それを検証していくものだと思う。特に仮説をしっかりもつことが大事。探究のサイクルを自覚して回せるといい」「インタビューやアンケートの回答をただ紹介するだけでなく、なぜ大人がそう考えているのか、その奥にある大事なことは何かまで深めて発表できるといい」など探究活動の先輩からの助言もありました。

高校生との交流を通じて生徒それぞれに生まれた気づきや問いを大切にして、さらに探究が進んでいくものと期待されます。
学びの改革パイオニア校 田川小学校
全校で探究的な学びに取り組んでいる田川小学校。今年度の教育課程研究協議会(特別支援教育)では、4年生の総合的な学習の時間を授業公開しました。保育園の子どもたちを招いて実施する交流会の計画をグループで話し合う場面で、子どもたちは園児や学級の友達の気持ちを思い描きながら、活発に協議し、計画を具体化していきました。

授業後の研究会は、田川小学校がこれまで取り組んできた「子どもの様子をとらえ、その様子と行為の意味を分かち合う」形式で実施しました。どの先生からも具体的な姿から読み取った「子どものよさ」が語られ、研究会場が、とても温かな雰囲気に包まれました

10月2日 更新
リーディングスクール 筑摩小学校
「子どもの“学びデザイン力”を育てる」ための2学期の実践がスタートしています。
6年社会科では、室町時代について、北山文化と東山文化を入り口に単元内の自由進度学習を行い、その一部を9月19日に「リーディングスクール公開授業」として実施しました。
この単元の学習では、発展学習として能の歩き方や、水墨画の技法を動画で学び体験できる場を設定しました。基本の学習カードを終えてから取り組む子や、資料をまとめるうちに水墨画への関心が高まり、思わず筆をとる子など、対象との関わり方を選択できることで、それぞれの子どもにとって価値のある学びが生まれている様子が感じられました。
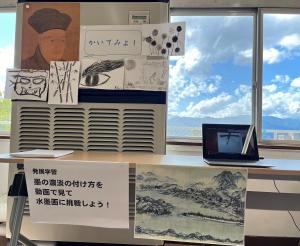
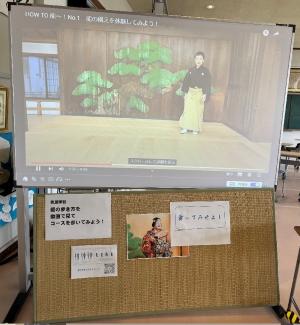
研究会では、信州大の伏木久始先生から、先行事例を具体的に紹介していただきながら、単元の教材研究を充実させつつ、無理のない範囲で自由進度学習を導入していく必要性について、お話しいただきました。
リーディングスクール 筑摩野中学校
筑摩野中学校では、「健康教育」でも4人組グループによる対話を基盤とした実践を重ね、9月5日の教育課程研究協議会(健康教育)で授業公開しました。
参観者の先生方からは、「対話を基盤とした授業づくりで、グループ活動を普段からしていて、安心して発言できる環境づくりができている」等、好意的なご意見を多くいただきました。指導者の先生は、筑摩野中学校の研究について「友との関係性を基盤とした自分を好きになる健康教育」と評されました。


2学期は、授業改善の取組として「聴き合う学級づくり」を進めています。「生徒同士が互いの話を聴き合う雰囲気を学級内につくる」ことを大事にして、教師の聴く姿勢、教師の目線を低くすること、困っている生徒が「わからない」と言いやすい雰囲気をつくることを意識しています。
「聴く学校」として、さらに対話を基盤とした「協働の学び」に取り組んでいきます。
学びの改革パイオニア校 波田小学校
「波田地区再発見~波田をPRしよう~」という総合的な学習の時間の取組から、身近な波田地区のお祭りについて調べ、お囃子に親しんだ5年生の子どもたち。音楽の授業で「おはやしのリズムや音を使って旋律をつくり、友達とつなげよう」とメロディーづくりに挑戦しました。その際、一人一人の演奏技能の有無で活動が滞らないようにするため、ICT機器を活用しました。そして、授業の終末にはみんなが「自分の旋律」を作り上げ、「友達とつなげてみたら楽しい盛り上がる旋律になった」などの感想や振り返りを語り合いました。


当日は、教育課程研究協議会音楽科の授業公開。参観者からは「ICT機器を使うことにより、演奏技能のハードルが低くなり、誰一人として活動が滞ることがなく、子どもたちが達成感をもって活動していた」などの意見をいただきました。
このような「多様性を受容する授業づくり」を一歩ずつ進めていきます。
学びの改革パイオニア校 波田中学校
波田中学校では、「明日も学びに来たくなる学校」づくりを目指し、「子どもが主人公となる2学期」という目標実現に向けて、「授業の充実」に力をいれています。
9月の教育課程研究協議会社会科の授業の一場面です。「なぜ日本は、20年で復興することができたのか」という学習問題について、ICT端末を活用し、友と考えを交流しながら「復興に大きく影響した出来事とその根拠」を自分の言葉で説明しあうなど、活き活きと学ぶ生徒の姿がありました。

この公開授業に向け、授業者の先生は夏休み明けから「他教科の視点から助言をいただきたい」と毎時間授業を公開しました。また、有志を募って模擬授業を行ったところ、20名以上の先生方が集まり、生徒の立場にたって授業の改善点を協議しました。公開授業の生徒の学びの姿は、先生方のチーム力の成果でもありました。

波田中学校では、これからも「子どもが主人公となる授業」の実現に向けて、教科を超えた授業研究の輪を広げていきます。
9月25日 更新
リーディングスクール 寿小学校
寿小学校の先生方は、1学期に、5年生で公開された単元内自由進度学習の授業を参観し、夏休みに、単元内自由進度学習を通して養われる力や、その価値について考える職員研修を行いました。このことで、自由進度学習の良さを感じ、部会以外の先生からも「自分のクラスでもやってみたい」「こんな子どもたちの姿を目指したい」という声が増えてきました。
2学期も、先進校への視察を計画し、11~12月にかけては、授業実践も行う予定です。
また、リーディングスクール事業で配置された先生を中心に、寿小の歴史や地域に関する資料を展示する「地域資料室」の整備が進められています。先日は、150周年記念を機に、6年3組が総合的な学習の時間に作成した「年表」を掲示しました。

学校全体で、「さあ、やってみよう」と、学ぶ雰囲気を高めています。
リーディングスクール 開成中学校
「探究的な学びには問いが大事だ」ということを職員研修で確認し、各教科で探究的な学びを構想することになりましたが、その時に大きな役割を果たしたのが「自主研修」でした。
「問いが大事だ」ということはわかったので、次は「どのように単元をデザインしていくか」を考えるために設けられた自主研修。夏休み中であるにもかかわらず「ぜひ参加したい」という職員が何人もいました。しかも、「ぜひ参加したいが、その日は都合が悪い…」という職員もいたことから、自主研修は2回の開催となりました。
このような経過を経て、各教科が選定した単元は下図のとおりです(※詳しい内容を確認したい方は「ダウンロードする」をクリックしてください。pdfがダウンロードできます)。
「生徒が学ぶ学校」を目指し、問いを大切に考えた授業が、ここから始められていきます。
学びの改革パイオニア校 丸ノ内中学校
丸ノ内中学校では、「忠恕の時間(総合的な学習の時間)」のカリキュラムに「1日忠恕」を位置づけ、生徒が学校内・外で自分たちのテーマに沿って、心ゆくまで探究的な学びに取り組むことができる機会を作っています。この日の活動に向けて、生徒たちは学びの計画を立て、準備を進めてきました。
当日の朝、リュックを背に校外へ出かけていく生徒、教室で活動の準備に取り組む生徒など、学校は学びの活気に包まれました。探究活動への生徒たちの期待感に満ちているようでした。
街中の井戸に注目し、現地で情報を集める(1年生)

「端切れ」を再利用し、魅力的な小物造りに挑戦する(3年生)

小学校を訪問し、6年生の協力を得て「運動と健康」についてのデータを集める(2年生)

街中にカフェを開き、市民のみなさんや外国人環境客との対話を楽しむ(3年生)

時間に縛られず、思い切り活動に取り組む中で、様々な「思いがけなさ」に出会った生徒たち。この経験をもとに、それぞれの学びを一層深めていきます。
9月19日 更新
リーディングスクール 明善小学校
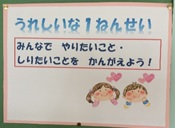
1人ひとりが「学びノート」に記した「みんなでやってみたい!してみたい!」ことを、学年の友だちと共有し合った1年生。生活の中で見聞きしたことや、幼保園や地域、家庭での経験をもとに子どもたちから様々な「やってみたい!」が出されました。

先生は、その話し合いと1人ひとりが「学びノート」に描いた「やってみたい!」を大切に考え、「うんどうあそびグループ」「えんそくグループ」「やきいもグループ」など、9つのグループに分かれてそれぞれが活動の計画をすることを提案、グループごとの話し合いがスタートしました。


子どもたちは、自分たちで計画・実行することにワクワク!目がキラキラ!これからどんな風に活動が展開していくのか楽しみです。
リーディングスクール 鎌田中学校
1年生社会科の授業では、ヨーロッパ州について学んでいます。ある学級では、「なぜEuに入りたい国とEuから出たい国が存在するのだろう」を問いとして学びを進めています。この授業は、子どもに学びを委ねている点で、黒板の書き写し型のいわゆる「チョーク&トーク」の授業とは異なります。
社会科の先生は授業の冒頭に、Euに加盟する国がある一方でEuに加盟できない国があり、さらにEuから離脱した国があることを写真と動画を用いて示した後に、先ほどの問いを示しました。「それでは学習を進めてください」と言うや否や、子どもたちは各自の関心事を探究していきます。ある生徒は「軍事的なメリットがあると思う。もし困ったら助けてくれる」と加盟するメリットを予想しています。それぞれの予想の検証と疑問の解決に向けて、教科書を読み、外務省HPの資料を読み、あるいは教育用の動画コンテンツを視聴しています。



↑ 生徒自身が立てた問いの解決に向けて学習を進めています。
授業を終えた感想には、次のようなものがありました。「イギリスのEu離脱の理由は、宗教が関わっているのではないかと思った。確かにEuの加盟には、特定の宗教では加盟しづらいという理由もあるようだけど、もっと違う理由もあるみたい。次はこのことを調べてみたい」 「自分たちが調べたいことを自由に、それぞれのスピードで学ぶことができる。それがいい」
心を惹き付ける「難題」により、子どもたちの思考する力は一層深まっていきます。
学びの改革パイオニア校 開智小学校
開智小学校では、10月4日に「創立150周年記念式典」を催行します。この式典のメインに位置付けられているのが今年度、全校で取り組んでいる「探究の学び」の発表会です。「開智小学校の150歳の誕生日を、私たちの『学び』でお祝いしよう!」と子どもたちは晴れの舞台に向けて最終の準備を頑張っています。
今年、初めての「総合的な学習の時間」で六九、縄手、中町など「開智小の周りの地域」について探究してきた3年生は、地域の神社で出会った「お神輿」を自分たちも作り、地域を盛り上げたいと願いをもちました。子どもたちの願いを受けとめた開智の地域の皆さんが、法被(はっぴ)やたすきなどを、子どもたちのために集めてくれました。


↑ 発表に向けて準備を進める子どもたち
子どもたちが地域のたくさんの皆さんと共に作った学びが花開く「150周年式典」はもうすぐです。
9月11日 更新
リーディングスクール 中山小学校
夏休みが明け、中山小ではリーディング研修として「前期リフレクション」を行いました。
「クラス全体のめあてをつくり、そこを基にグループのめあてと個人のめあてを立てることを大切に実践してきたが、子どもたち対話しながら解決する姿が見られてよかった。」「休み時間にも修学旅行の内容をレクレーション係が自分から考える姿があった。班長会など、係ごとに集まって考える姿が見られた。」「総合だけでなく図工の時間にも夏祭りのプレゼントをつくった。図工の時間だけでなく、家でも工夫して持ってくるなど自分から考える姿があった。」など、子どもたちが自ら考え、自ら学習を作り出していく姿が共有されました。4月からの、子どもたちの願いを真ん中に置いた実践の着実な成果が確かめられました。

2学期で大切にしたいキーワードは、「経験をつむ」、「ねがいをもつ」、「自分が興味をもつこと」、「グループごとだと力を発揮できる」、「個人の経験を全体で共有する」、「自己選択」と据えられました。中山小学校は、職員全員が成果と課題を共有しながら、これからも歩み続けます。
リーディングスクール 清水中学校
2学期の授業改善に向け、今年度の重点教科である数学科と社会科の研究部会が開催されました。全校研究テーマ「表現力が育つ~すべての活動を通して~」を、日々の授業でより一層具現していくために、盛んに意見交換がなされました。
数学科授業研究部会では、現実社会のデータを教材として用いることの魅力と配慮点や、生徒が根拠をもとに表現し合いたくなる授業構想について話題になりました。社会科授業研究部会では、「生徒が探究したくなる単元を貫く問いの立ち上がりを、どう支援したらよいか」や「根拠をもって表現するためには、生徒が見方・考え方を自覚的に働かせていくことが欠かせない」などの意見が出されました。
どちらの部会も、先生方が明るく前向きな雰囲気のなかで、授業づくりについて語り合っていました。

↑ 活発に意見交換をする数学科研究部会の先生方
学びの改革パイオニア校 田川小学校
田川小学校では、「自己肯定感をもてる子」を目指す姿とし、また、「子どもの行為の意味を価値づける」ことを大切にしながら、「探究的な学び」への実現に向けて、月に1回の研修に取り組んでいます。
夏休み明け、1学期に取り組んできた生活科・総合的な学習の時間の学びを2学期へどうつなげていくか、さらに子どもの主体となる学びをどう深めていくか、「チュ―ニング」という対話を通した職員研修を行いました。

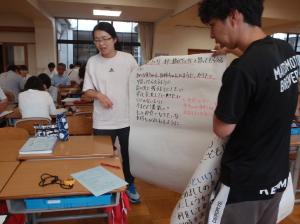
研修には、中信教育事務所から1名、風越ラーニングセンターから2名、丸ノ内中学校や開智小学校のコーディネーターの2名、計5名の先生方にも参加していただき、対話を通して、活発な話し合いとなりました。研修は、4つのグループに分かれ、各グループ内でファシリテーターが中心となり、提案者となる先生から、2学期への授業構想の提案を受け、同じグループの先生から様々な意見交流が行われました。提案者は自分の悩みを素直に相談したり、また、同じグループの先生は、自分の体験を通して、アドバイスをしたり、相談できる雰囲気が心地よい研修となりました。

研修を通して、「限られた時間だったけれど、見通しをもちながら会話ができとてもよかった。」「アイデアをもらい、明日からできるものがあったのでやってみたい」「こうやって他の先生方と意見交流することがとても楽しかった。アドバイスいただいたことを活かしていきたい」と感想があり、一人ひとりの先生方にとって、とても有意義な研修となりました。
9月4日 更新
リーディングスクール 筑摩小学校
7月の2・4学年での実践をとおして、自由進度学習に取りくむ子どもの実際の姿を職員で共有することができました。また実践後のふり返りから本校のテーマ「子どもの“学びデザイン力”を育てる」を実現するために、「学習環境」と「教師のかかわり」をブラッシュアップしていくことが見出されました。
K先生は算数科の自由進度学習で「子どもがワクワクして取り組みたくなる応用課題を設定したい」という願いを持っています。身の回りにある課題を、単元で学んだことを生かして、実物にふれながらが取り組めるよう、課題の設定や具体物の整備などの学習環境を進めています。このような学習環境づくりを大切にしながら、2学期も各学年で実践を進めていく予定です。
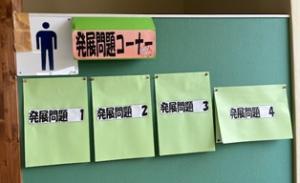

リーディングスクール 筑摩野中学校
筑摩野中学校では、8月21日に聴き合う学級づくりを目指して職員研修を行い、研究主任から、スリンプルプログラム「筑輪タイム」の提案がありました。スリンプルプログラムは、週1回の短時間グループアプローチでソーシャルスキルトレーニングと構成的グループエンカウンターの要素をもった活動です。実際に、「アドジャン」を職員で行ってみました。4人グループでじゃんけんのように0~5本指を示して指の数を足し算し、その1桁の数字のお題について端的にメンバーは答えていきます。それを90秒行い、その後フリートーク(90秒)で話したお題について、語り合いました。短時間でしたが、50人近い職員集団がアットホームな雰囲気に包まれました。

この「筑輪タイム」を月曜の思学(朝の時間)に全学級で1ヶ月計4回行っていきます。28日には1回目が行われ、生徒たちも、笑顔でメンバーの話に頷きながら話を聞いたり、話したりしていました。フリートークでは「なんで○○って答えたの?」など問い返していました。筑輪タイムで身につけたスキルや関係づくりが協働的な学びにもつながっていくと思います。2回目以降はメンバーを替えたり、お題を変えたりしながら進めていきます。

学びの改革パイオニア校 波田小学校
「学びに、遊びや体験を(第3次松本市教育振興基本計画)」につながる授業づくり研修の機会にしたいと願い、Jfa小学校体育サポート研修会担当講師北野孝一先生を招き、実技と講義を交えた「体育の授業づくり」研修会を実施しました。最初にアイスブレイクを通して、仲間づくりや集団のルールづくりの大切さを、体験を通して学びました。続いて道具や教師の問いかけの工夫により、体育が「得意な子も苦手な子も、両方に学びとなる」いくつかのゲームを体験する中で、「がんばれ」「ナイス」などの言葉が自然に飛び交う「集団の和づくり」にもなることを実感しました。その後、講義で、実技で体験した「道具の工夫・環境設定の大切さ・問いかけの重要性」の意味について振り返りました。


教師の問いかけの工夫により、運動能力が異なる子どもたちであっても、全員にとって体育の時間が楽しくなり得ることを体験したので、この学びを、多様性を受容する授業づくりに生かしていきたいです。

学びの改革パイオニア校 波田中学校
波田中学校では、全ての子どもの自己肯定感を高める支援のあり方について共通理解を図り、学校でできる支援の一助となればと願い、信州大学教育学部准教授高橋史先生を招き、職員研修を実施しました。講演を通して、「不登校の発生要因(過去)と維持要因(現在)を理解すること・すべての子どもに対して『ストレスチェックと日々の声かけ』をする大切さ・安全な雰囲気づくりをコツコツと重ねていく重要性」等について研修を深めました。


演習を通して「好きな遊びを楽しんでいるときの気持ちは100点中何点をつけますか?」等の質問を例に、「楽しい」「うれしい」などの感情をあらわす言葉も、人それぞれとらえ方が違うことを体験しました。この研修での学びを、多様な生徒への対応にいかし、自己肯定感の醸成につなげていきたいと思います。
8月28日 更新
リーディングスクール 寿小学校
1学期は、自分で学習計画を立て自分のペースで進める、単元内自由進度学習「寿小マイプラン学習」が実践され、子どもたちの学習活動をさらに活発にしていきました。
授業学級の児童を対象に実施した事後アンケート調査では、「寿小マイプラン学習をまたやりたい」と90%の児童が回答しました。また、自由記述欄には、「わからないところをゆっくり考えて取り組めた」「自分でやる力が身につく。だから、大変でもまたやりたい」などの記述も見られ、主体性や自己調整力の高まりが、感じられました。
そこで、単元内自由進度学習部会では、夏休み初日の7月20日(木曜日)に、全校職員の研修を企画し、「寿小マイプラン学習」の実践における成果と課題を発表しました。そして、2学期は、「自律した学び手」の育成を目指した単元内自由進度学習の取り組みを、他学年でも進めていくことを全職員で共有しました。

1学期の取り組みを振り返る職員研修
リーディングスクール 開成中学校
「生徒が学ぶ学校」への転換を目指し、6月~7月にかけて授業公開をしてきた開成中学校。
夏休みには職員研修や自主研修でその成果と課題を共有しながら、8月~10月までの間で「考える」生徒が育つ授業をしていくことを確認しました。具体的には、各教科で「追究」できる単元を決め出して、「探究」のサイクルが回るように計画を立てます。今は、2学期に各教科1単元、探究のサイクルを回せそうな単元を選定していることころです。
とにかくまずは実践してみること。上手くいかないことが前提で、とにかく実践事例を積み上げ、教師の知見を積み上げていくことを大切にしたいと考えています。

2学期の終わりには、実践を通して生徒の変容や改善点等を共有し、さらに次の方向性を定めていきたいと思います。
学びの改革パイオニア校 丸ノ内中学校
丸ノ内中学校では、総合的な学習の時間「忠恕の時間」で、プロジェクト学習に取組んでいます。生徒の意識調査に基づいていくつかのプロジェクトテーマ(講座)が設けられ、生徒たちはクラスの枠を越えて、エントリーします。各プロジェクトの中で生徒たちはサブテーマ(課題)を決めだし、グループで探究を進めます。今年度は全学年がこの形で探究的な学習に取組みます。
2学期最初の「忠恕の時間」。各学年の生徒たちはそれぞれのステージでプロジェクトを進め、学校全体が活気に満ちた時間になりました。

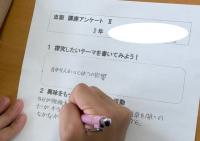
↑1年生、2年生はプロジェクト学習のスタート。これからの探究に向け、見通しを持ちます。


↑ 一歩先行する3年生。「一日忠恕」に向け、それぞれの探究を進めます。
8月22日 更新
リーディングスクール 明善小学校
2学期最初の研究会です。先生方は子どもたちに、自ら考え動ける力をつけてほしいと考えています。
近隣の保育園参観等から、子どもの捉え方や環境構成について明善小の先生方が学び、子どもたちから出てくる「やってみたい!」「どうしてかな?」の問いについて一緒に考えたり、子どもに問い返したりすることを通して、子どもたちが思考力を働かせられるような授業を子どもと共に作ろうとしています。
2学期に子どもたちから、どんな「やってみたい!」が出てくるのか楽しみにしています。

リーディングスクール 鎌田中学校
社会科の授業を、驚きと発見のある時間にしたい!
本校では、探究的な学びを、総合的な学習のみならず教科学習においても進めるために授業改善を図っています。今年度着任した新卒の社会科の先生は、わくわくしながらつい解決したくなる問いを工夫することで探求的な学びを目指しています。先日の授業では「幕府はなぜ鎖国を行っていたのだろうか」を学習問題として生徒の声を引き出します。これからも「えー」「そうなんだ」と発見に満ち、感嘆する経験を味わってもらうために、問いの在り方を模索していきます。

学びの改革パイオニア校 開智小学校
夏休みの1日、開智小学校では2学期の探究の学びの充実をめざし、職員研修を行いました。
研修はコーディネーターの先生を中心に、若手の先生も発表者を務めるなど、先生方が主体的に企画しています
研修は「プロジェクト・チューニング」「思考ツール」「探究における知識・技能の力の見極め」「教科における探究的な学び」という充実した内容でしたが、これまでも、対話的な研修を重ねてきた開智小の先生方は、今回も和気あいあい、かつ積極的に協議されました。先生たち自身の主体的・協働的な学びに満ちた時間となりました。


「プロジェクト・チューニング」 総合的な学習の時間の構想をグループの先生方に相談。様々なアイディアを交換し、見通しを高めます。


「ワークショップで学ぶ『思考ツール』」 児童が探究的な学びを進める中で活用できる「思考ツール」(ベン図、統計処理など)をワークショップで実感的に学びます。
8月7日 更新
リーディングスクール 筑摩小学校
7月からスタートした2・4年生の算数科での単元内自由進度学習がそれぞれ単元の終盤にさしかかりました。どちらの学年でも、子どもが自分のペースで学習を進める中で、学びが深まったり、個で学びながら関わりあったりする姿が見られています。
2年生は100より大きい数を学んでいます。始業のチャイムの前から、子どもたちは自分の必要なものを机の上に用意して学び始めていました。Aさんは真っ先にタブレット端末を取りに行くと、オンラインのドリル教材を黙々と取り組んでいました。授業の後半になる頃にはタブレットを片付け、単元の学習計画表をじっと見つめました。これまでの学習で少し不安のあった部分を見つけると、プリントコーナーへ行ってその部分の問題を探し、再び黙々と鉛筆を走らせていました。問題を解き終え、振り返りの時間になる頃にちょうど丸つけを終えたAさんは「よしっ」と小さくうなずきました。タブレット端末とプリントでの学習を行き来して学ぶことで理解を深め、力の高まりを実感していました。
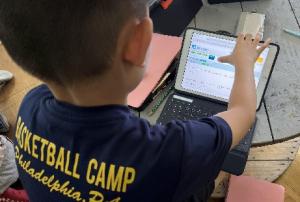
4年生は小数について自由進度で学んでいます。「廊下の長さは何kmでしょうか」という発展問題にチャレンジしたCさんは、巻き尺を手に一人で何度も廊下を行き来しながら長さを測っていました。自分で測った長さをこの単元で学習した考え方を使ってkmの単位に換算して答えを求めることができました。同じ課題に取り組んでいたDさんを見つけると、二人でノートを突き合わせて「やった!」とガッツポーズ。個の学びが重なって、学びの達成感や喜びが生まれた瞬間でした。
リーディングスクール 中山小学校
1学期末のある日、3年生の子どもたちは校内の「自然ふれあい広場(ビオトープ)」に様々な生き物が住みついてくれることを願い、グループ毎でめあてをもって広場へ入っていきました。「池の外のアヤメの花を広場へ移植したい」という目当てを持ったグループの子どもたちは、株がまっすぐに立たないという「思いがけなさ」に出会い、広場の中で地盤が強そうな場所を探したり、盛り上げた泥の中に植えようとしたりするなど、目の前の「問題」の解決に向けて知恵を振り絞っていました。

子どもたちの学びを見守る先生は、行動をためらっている様子の子どもに「どうやってやろうと思っているの?」と見通しを顕在化させる問いかけをするなど、子どもたちの問題解決を背後から支えていました。一人ひとりの子どもの願いを把握し、子どもに乗り越えさせたいこと、子どもに任せたいこと・任せられることを頭におきつつ、ゆったりと見守る先生の支援のもとで、子どもたちは思い切り学んでいきます。

リーディングスクール 清水中学校
3年生は7月5日、松本の魅力に関する各自が設定したテーマに合わせて、校外の関係各所でインタビューや現地調査を行いました。このうち、「中学生が考える住みやすい松本市」について探究してきた生徒2名が臥雲市長を訪問し、成果を発表しました。3年生へのアンケート結果をもとに、放課後や休日の学習スペースの整備や、公園の整備等について提案をしました。市長からの質問に的確に答えたり、メディア各社からの取材にも堂々と対応したりする姿がありました。全校研究テーマ「表現力が育つ」が具現化された生徒の姿でした。
さて、今回の市長訪問の新聞記事を目にした地元の公民館の方が、早速、学習スペースとしての公民館開放に動き出してくださいました。地域で、地域の方々と学び、そして「地域に貢献するとは何か」という問いをもって探究してきた生徒達にとって、地域の一員になって暮らしている実感を持った出来事になりました。

自分達が想定していなかった視点からの質問を市長から受ける生徒

市長への提案後、メディア各社の取材に対応する生徒
7月31日 更新
リーディングスクール 筑摩小学校
筑摩小学校では年度当初から準備を進めてきた自由進度学習について、4年生は算数科「小数」の単元でスタートしました。はじめのガイダンスでは「楽しみなことも心配なこともある」と話していた子どもたちでしたが、どの問題をどこで学ぶのか、自分で学習計画を立てて意欲的に学び始めています。

Aさんは廊下に並んだベンチで、小数を10倍したときに各位の数字がどう変わるかについて、プリントで学習していました。「これでいいのかな」「1つずれるってことだよね」と隣のBさんと言葉を交わしながら問題を解いていきました。時間が終わると「あー集中した!」と思わず声が出ました。自分のペースで学ぶことは自分の精一杯の力を出すことだと実感している姿でした。

同じ廊下の一角には巻き尺やはかりなどがそろえられた「算数コーナー」があります。もっと知りたいと願う問いに出会った子どもたちは、きっとここにある道具を使って学びを深めていくことでしょう。
リーディングスクール 筑摩野中学校
筑摩野中学校では、7月18日、麻布教育研究所所長の村瀬公胤先生を招き、授業クリニックを行いました。3校時に社会、4校時に英語を共同参観授業とし、職員全員がどちらかの授業を参観しました。

放課後に授業懇談会、村瀬先生のご指導の時間をもちました。授業懇談会では、生徒と同じく、職員も4人組になり、具体的に生徒の名前と姿をあげて気になった理由を発表し、手だて(指導法)ではなく、授業から自分が学んだことを語り合いました。


村瀬先生のご指導では、協働的な学びは、グループで考え合うことで、その生徒が一所懸命説明しようとする瞬間が学びの瞬間であり、生徒の「なんで?」「だって、~」「でも、~」というつぶやきが大事であることが示唆されました。「考えた」・「学んだ」結果の交流ではなく、「考える」・「学ぶ」過程の共有を目指していきたいと思います。
教科書の単元がどうしたら協働的な学びになるか、子どもたちの学びが深まる問いを教科会などで検討し、考えていきます。
学びの改革パイオニア校 田川小学校
田川小学校では、今年度の研究で「子どもの行為の意味を考える」ことを大切にしています。
7月の授業研究会は、参観の先生方が授業で着目した子どもの姿をカメラに収め、それをもとに、その時の子どもの様子と、そこから想像される子どもの想いを語り合うという形で行われました。授業後、研究会に先立って、先生たちは撮影した写真を協働編集のスライドに貼り付け、コメントを追記します。
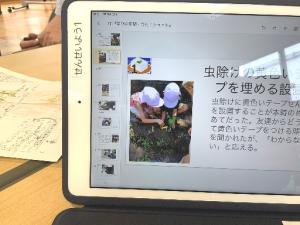
研究会では、まず、各グループで写真を見ながら、その子どもの学びを振り返り、その後それを全職員で共有していきます。写真を示しながら、豊かにその子の想いを想像し、その学びのいきさつを語る先生方。

子どもをしっかり見ることの大切さの実感や、子どもの見方(子ども観)が先生たちに共有されていく時間となりました。
7月24日 更新
リーディングスクール 寿小学校
寿小学校では、6月下旬から、5年生の算数「合同な図形」と社会「暖かい/寒い土地の暮らし」の単元で、自由進度学習を始めました。
子どもたちは、この時間を心待ちにワクワクしている様子で、チャイムと同時に、一斉に算数用の学習室や社会用の学習室、ホームルーム等、それぞれが選んだ「学びの場」へと向かいました。
Aさんは、教科書や、タブレット、様々な資料を広げるため「床」を選び、準備を整えると「よーし」と気合を入れて学習を始めました。しばらくしてAさんは、隣のBさんに静かに話しかけ、「これすごいよ!この屋根、なんでこんな形しているか分かる?」等、驚きや疑問を分かち合いながら学んでいきました。

終了のチャイムが鳴った時、「うわぁー、楽しかった」と誰に言うともなくつぶやいたAさん。心の声が自然に出てきてしまうほど、充実した時間となりました。
当初、初めて体験する学び方に戸惑いを見せていた子どもたちですが、自分のペースで、自分自身が進める学習の楽しさに気付くとともに、自分なりの学び方に自信を持ち始めたようです。
リーディングスクール 開成中学校
「教師が教える学校」から「生徒が学ぶ学校」への転換に挑戦している開成中学校。
知障学級の「理科」、物体の体積を求める授業の一場面です。先生は、体積を測定する必要感が生徒の中に生まれるよう工夫をこらしました。比較する素材は「一見しただけでは大小がわからない微妙な大きさ」であり、どうしても測定しなければなりません。
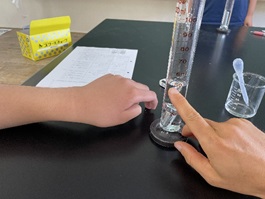
何度も何度も手に取って予想し、予想を確かめるため、メスシリンダーを使い、夢中になって測定する生徒たち。「あたま」「からだ」「こころ」すべてを動員して「生徒が学ぶ姿」がありました。
開成中学校では、すべての学級でこのような学びの実現を目指していきます。
学びの改革パイオニア校 波田小学校
「多様性を受容する学校」を目指している波田小学校。職員研修として、Aさんに関わった担任が「支援を通して学んだこと」について実践発表を行い、職員が各自、自身の指導を振り返りました。

例えば、日頃教師がついやってしまいがちな「板書しながらの指示・何かを配りながらの指示(表情、口元が見えない)、巡回しながらの指示(注意を向けることが難しい)」などは、不適切な支援だと知ることができました。
また、教科指導における支援の基本は「(1)視覚的支援 (2)語彙に関する支援 (3)話し方に関する支援 (4)活動場所の環境に関する支援」の4点であること、特に視覚的支援について、プール指導で実際に提示したカードを見ながら、視覚支援の大切さについて確認しました。

「Aさんに対してだけでなく、他の多くの子どもたちに対しても大切な支援」という実感を、全職員であらためて共有しました。
学びの改革パイオニア校 波田中学校
波田中学校では、「明日も学びに行きたくなる学校」具現のための「まなプロ」(学びの改革プロジェクト構想)を作成し、職員会で共有しました。プロジェクトは「(1)授業充実 (2)小中連携 (3)学びの場の見直し」の3つを柱に、「生徒の自己肯定感の醸成」を目指して取り組んでいきます。
柱の一つである「授業の充実」の取組として、研究主任の先生が自らが授業を公開しました(2年数学「どの電球を買いますか?(一次関数の導入)」)。4人が机を合わせ、対話しながら学習を進める「協働的な学び」による実践で、生徒たちは困ったり迷ったりした点について友と相談し合いながら、考えを深めていきました。


学期末には職員研修として、信州大学教育学部准教授 高橋史先生を講師として招き、「全ての子どもの自己肯定感を高める支援のあり方」について研修を深める予定です。
7月18日 更新
リーディングスクール 明善小学校
6月下旬、研究部会の先生方が学校近くの内田保育園の参観をしました。年長児がクラスの友だちとイメージを共有しながら、夢中になって遊ぶ姿が見られました。一人で描き進めるうちに友だちの描いたものと合体して互いにストーリーを発展させたり、もっとこうしたいという願いが生まれ試行錯誤したりする様子が垣間見られ、遊びの中に大いなる学びがあることを実感することができました。

また、ダイナミックな活動を行うに当たり、活動場所であるホールの机やいすの配置、道具や材料が安全に扱えるような配慮、遊びの満足感を得られるような受容的な声がけ等、一人ひとりの遊びが充実したものになるよう環境調整されている様子について、参観された先生は、小学校でも参考になることが多いと感じられていました。


リーディングスクール 鎌田中学校
「総合的な学習の時間」では、各学級が決めたテーマに沿って学びを深めています。
3年生のある学級では、かき氷シロップと水まんじゅう作りに挑戦しました。「りんご(をもう少し細かく)切ったほうがいいんじゃない?」「これでいいんだって」「いや、やってみようよ!」などと声を掛け合いながら調理に励んでいました。

この学級は、校区を流れる田川の水質を調査してきた2年生の時の学びが発展し、田川の水を活用した料理ができないかという発想を抱いています。

今回は水道水を利用しましたが、田川の原水を活用するための清浄化方法が課題です。調理を行うメンバー以外にも、浄水について調べるメンバーもおり、飲料水を扱う会社に浄水のシステムについて質問してみたいという願いをもっています。
今後、この学びはどのように展開していくのか楽しみです。
学びの改革パイオニア校 丸ノ内中学校
丸ノ内中学校では、全校を挙げて探究的な学びを進めるにあたり、先生自身が「題材を決める、問いを立てる、協働追究をする、効果的にまとめる…」といった「探究のプロセス」を体験することを大切に考え研修を進めています。研修が先生方自身によって企画され、いろんな先生方がその都度、交代で講師を務める等、ボトムアップ型で実施されているのも丸ノ内中の研修の特色です。

7月5日には、生徒が調べたデータを統計処理するうえで必須となる「ヒストグラム」について、数学の先生を講師として先生方が学び合いました。「生徒に説明する」という目的を超えて、「中央値、平均値、最頻値の違いは?」「グラフをどう読めばいい?」など、先生方が「材」の魅力を感じながら探究的に学ぶ、大盛り上がりの研修会となりました。
7月10日 更新
リーディングスクール 中山小学校
学校全体で取り組んでいる「探求の学び」のある日の一コマです。
田植えを終えた5年生は、1学期の終わりまでの6時間を使ってお米のために自分は何ができるかを考えました。
「ぼくはイネの病気のことを調べたいです。なぜならば、(イネを観察したとき)イモチ病があって、何とかしないとおいしいお米にならないと思うからです」など、自分がこれまで目の当たりにした事実を足場としながら、子どもたちはおいしいお米がたくさん収穫できることを願い、そのために自分が取組んでいきたいことを語っていきました。

こうして、「生き物」「水の管理」「病気」「調理」「観察」の5つのグループができ、6時間でどのような取組みを進めるかを計画しました。
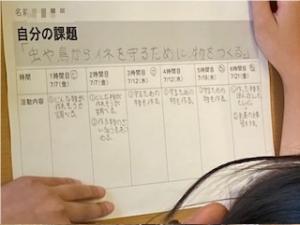
教室には、理科の「植物の発芽と成長」で観察用にまかれた種子が置かれていました。インゲン豆を使うことが多いこの学習ですが、イネも育てられていました。子供たちのイネへのおもいが、このようなところからもうかがえます。
リーディングスクール 清水中学校
清水中学校では研究テーマ「表現力が育つ~すべての活動を通して~」の具現に向け、職員研修をシンカさせています。
職員会の中に、互いに語り合う「トークタイム」を新たに設定しました。6月14日のトークタイムは、前の週に実施された授業公開週間の振り返りを行いました。

「単元導入時の子どもの姿から、単元を通してどのような支援をしたらよいか」「根拠をもって説明する場の設定はどうしたらよいか」など、子どもを主人公とした授業づくりについて活発な意見交換がなされました。

学びの改革パイオニア校 開智小学校
「探究の学び」に全校で挑戦している開智小学校。6年2組の子どもたちは、「旧開智学校」を題材に、自分たちで立てた「問い」についてチームで調べた内容を1年生に伝える会を企画しました。前日の授業では、「楽しく」「よくわかる」発表をめざして最後のリハーサルを行いました。
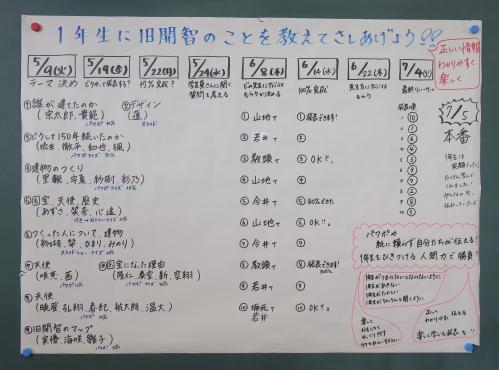
授業の終わり、「一番しっかり伝えたいのは『クイズ問題』。ゆっくりわかりやすく話したい。」「『受け』をねらいすぎず、1年生が『うんうん』となるように話したい。」と願いを語る子どもたち。相手意識を高め、大切にしたい目当てをあらたにする姿がありました。
そして迎えた発表会当日。6年生の思いが伝わり、1年生は、とても集中し興味津々で参加していました。

「自分で考え、工夫する学びの楽しさ」が、こうして先輩から1年生に受け継がれていきます。
7月3日 更新
リーディングスクール 筑摩野中学校
筑摩野中学校では、5月以降、全校で4人グループによる協働的な学びづくりにチャレンジしています。
6月9日、3年生の英語の授業では、英語で書かれたヒントカードをグループの皆で解読し「犯人」を考える活動を通して、現在完了形の3つの用法を実感的に学びました。自ら考え、かかわりあう必要感により、豊かに対話・協働しながら学ぶ生徒たちの姿がありました。

他の授業でも、個で取り組む、隣の生徒に尋ねる等、グループの中で自然に学ぶ姿が生まれています。

先生たちは、この学習スタイルの成果と課題を日常的に話し合い、より深い学びを目指して模索しています。
学びの改革パイオニア校 田川小学校
6月9日、田川小学校の地域の大切な財である「田川」に出向き、実際に材と向き合い、どのような探究ができそうか考えあう校内研修を実施しました。
川に詳しい地域の専門家の方にも参加していただき、人の材にも触れる研修となりました。

まずは教職員が実物と実際に関わることを通して「探究の学び」を体験します。
そして、「こんな探究ができそう…」と、田川で先生方が考えた「探究の学びの可能性」をまとめ、共有しました。

このような研修を重ねていくことで、先生方自身の探究のサイクルを積み上げていきます。
6月26日 更新
リーディングスクール 寿小学校
~「単元内自由進度学習」の実践を前に~
6月上旬に、「単元内自由進度学習」を既に実践している県内の小学校へ視察に行ってきました。
そこには、自分のペースで学習に取り組み、とことん課題に向き合っている子どもの姿がありました。
また、実際の教室環境や準備された教材を目の当たりにすることで、寿小での実践のイメージを掴むことができました。

視察後、重点研究会の議論の中心は、子どもが自立的に学びを進める「単元構想」と「学習材・環境づくり」についてでした。
現在、「単元内自由進度学習」の実践を目前に、子ども一人一人の学びの姿を予想しながら、単元全体を見通して学習の流れを考え、ていねいに教材開発に取り組んでいるところです。
リーディングスクール 開成中学校
開成中学校は6,7月の研修として、グループで授業を見合っています。
それに先立ち、「1年生の社会科の例」を通してポイントを全員で共有しました。
この授業で子どもたちは、自分で課題を設定し、情報を収集して整理し、分析や考察を行って、自己課題に対する解答をまとめるというレポートを作成しました。
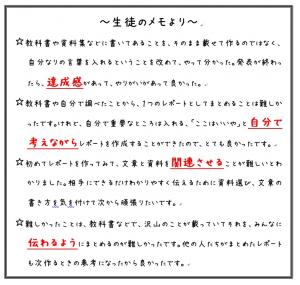
生徒の振り返りからは「達成感」「自分で考えながら」「関連させる」「伝わるように」という今後の支援のポイントになるキーワードも出てきました。ここに、探究的な学びの一端があり、生徒自身が達成感や充実感を感じられることが分かります。
また、情報を取捨選択したり根拠をもとに考察したりすることの難しさを感じてもいます。さらに、相手意識をもって自分の考えや意見を表現することに難しさを感じてもいます。
こうした事例を共有した上で、授業実践を繰り返す。その中で子どもも教師も変わっていく、それを見合うことで広がっていく。
開成中はそんな2カ月間をスタートさせています。
学びの改革パイオニア校 波田小学校
波田小学校では、子ども理解を深め、子どもたちが「明日も来たい」と思える学校になることを願っています。特に相談室が、その子にとっての教室となり「今日はこういうふうにやっていこう」と自分でカリキュラムをつくることができるような場になればと考えています。

ある日の相談室の様子です。子どもたちは中庭の一角にさつまいも畑をつくり、さつまいもの観察と水やりをしました。子どもたちは「クラスのみんなに食べてもらいたんだ。大きくなれ」と言いながら笑顔で活動しています。
さつまいもの観察・世話が終わると相談室に入り、一人ひとりが国語のプリント学習を行いました。

1枚終わると担当の先生と相談し、わかったところ、不十分なところを確かめながら、自分のペースで「できた!」を積み上げます。
学びの改革パイオニア校 波田中学校
波田中学校には、波田小学校に通うほとんどの卒業生が入学してきます。また、あかり教室(松本市中間教室)も中学校のすぐ近くにあります。

そこで、これまで以上に波田小学校・あかり教室との連携を深めていくことが大切だと考えています。その一環として、波田中学校の相談室に通う生徒とあかり教室に通う児童・生徒が一緒にりんご滴摘果作業を行いました。

このような活動を通して、これまで以上にあかり教室との交流を深めていきたいと思っています。
6月19日 更新
リーディングスクール 明善小学校

5月に行われた研究部会では、1年生が幼保園時代にかいた『あそびのーと』と入学してから今までにかいた『まなびノート』を見て部会の先生方が自由に語り合いました。「この子の絵には友だちがいっぱい出てくるね。」「きっと竹馬に乗れるようになったんだね。」「保育園のころは絵が中心だった子が、1年生になったら文字ばっかりになっている。一生懸命書こうとしてる感じがするね。」「この日は絵の感じがいつもとちがう。何かあったのかな。」など2冊のノートを見て子どもたちのあそびや学びに思いを馳せ、目の前の子どもたちのありのままの姿を捉え共有しようとする先生方の姿がありました。
リーディングスクール 鎌田中学校
外国で過ごしてきた生徒にとっては、文章を読むこと自体が学びの障壁になります。まして漢字となると文意をつかむことは容易ではありません。国語科の先生は、「授業を通じて自分の思いを表現してほしい」という願いから、漢字にルビを振った自作の教材を作成することで、多様な生徒が安心して学ぶことのできる環境を整えていました。

先生がルビを振れなかった際には、やさしく教える子どものかかわりがありました。

学びの改革パイオニア校 丸ノ内中学校
探究的な学びにおいて、生徒が結論を導く根拠として、数学で学習する統計的処理を用いることが期待されます。統計的処理の有効な手段の一つとして、中学2年で学習する「箱ひげ図」を活用し結論を導くことが予想されます。丸ノ内中では、生徒が探究的な学びの中で根拠として活用できるように、通常2年の3学期の単元である「箱ひげ図」を1学期に学習するようにしました。
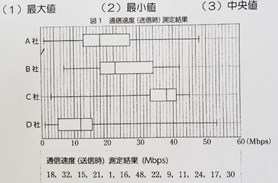
今回は職員研修として、数学科の職員が、実際授業で使用した教材を用いながら、「箱ひげ図」とはどんなもので、どのように活用することが有効なのか、職員へ研修を実施しました。生徒が根拠を活かした学びをするためには更に職員の支援・指導のスキルアップが求められると考えたからです。「探究的な学び」が教科の学習と結びつく体験を職員が実感する研修会となりました。

6月12日 更新
リーディングスクール 中山小学校
5月24日に各学級の年間指導計画を全職員で共有しました。特に「中山っ子の時間」(生活科、総合的な学習の時間)の部分については、担任の葛藤や困り感について語り合いました。担任の思いだけで「こうしよう」とはせず、子どもを中心に据えようとするからこそ、葛藤や困り感が生まれてきます。

そして、各学年の「中山っ子の時間」の活動が少しずつスタートをしてきました。5年生の子どもたちは数回のミーティングを行い、今年の米作りについての見通しを持って活動がスタートしました。

リーディングスクール 清水中学校

6月5日からの1週間、研究テーマである「表現力が育つ」授業をすべての教科で公開しました。校内の先生方はいくつかの参観グループに分かれ、互いの授業を参観し合い、授業づくりについて語り合いました。

また、校外からも20名近くの先生方が来校し、子どもたちが主体的に学ぶ授業を参観しました。
先生方が互いに学び合う薫りが広がっていました。
学びの改革パイオニア校 開智小学校
開智小学校では、「150周年記念式典(10月4日)」での学年ごとの「探究的な学び」の発表に向けて学校全体で研修を深めようと取り組んでいます。同じパイオニアスクールとして「探究的な学び」を研究している丸ノ内中学校の探究コーディネーターから、軽井沢風越学園で行われている「プロジェクトチューニング」の説明を受け、職員で実践しました(6月6日)。

「進行役」「タイムキーパー」を決めて、「参加者全員が進行役のつもりで自分ごととして考える。否定的な意見は避け、建設的な意見を述べる」ことに留意し、考えを述べ合いました。約30分間の「チューニング」の実践は、先生たち自身の協働的な学びが実現した、有意義な研究会となりました。

6月5日 更新
リーディングスクール 筑摩小学校

5月17日の校内研修で、自由進度学習を実践している県外の学校の授業動画を視聴しました。冒頭のミニレッスンから、各自の計画を確認し、個別の学習に取り組む様子等を見て、実践に向けての一歩を踏み出しました。
リーディングスクール 開成中学校

5月17日(水曜日)5校時に、社会科の授業が公開されました。賑やかで、和気あいあいとした空気で始まった授業の中で、生徒の皆さんは安心して、自身の考えを発表していました。
一気にクラス全体が集中モードになる瞬間や、テーマの本質に迫るキーワードをジャムボードに書き込む生徒の姿等、見どころ盛り沢山の50分は、『自らの学びに舵を取る生徒の育成』を目指す開成丸が、力強く出港した瞬間でした。
学びの改革パイオニア校 田川小学校
5月22日の「探究」研究部会の一コマ。

子どもたちの学習カードをもとに、前時からの意識のつながりや、興味の在処など、
意見を交換しあい、「こどもの理解」を深めました。
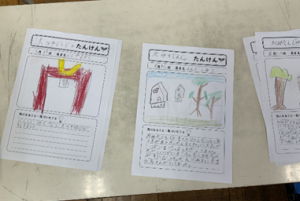
こうした中から「学びの種」をみつけ、子どもたちが自分からどんどん学んでいく授業を構想します。
授業づくりは「先生の探究」そのものです。
5月29日 更新
リーディングスクール 寿小学校

玄関に掲げている「あいことば」

奈須先生との研修会
4月20日(木曜日)には、上智大学総合人間科学部教育学科教授の奈須正裕先生に授業参観をしていただき、子どもの主体性をはぐくむための研修を実施しました。
6月には、個別最適の学びと協働的な学びを一体的に実現するため、「単元内自由進度学習」の先進校へ視察に行き、6月下旬からは、本校でも実践していく予定です。
リーディングスクール 筑摩野中学校

より一層の対話を基盤とした授業づくりを目指して、5月8日(月曜日)から、全学級で教室での4人1組のグループ座席での授業がスタートしました。

「学習問題を出したとき、生徒が素直に反応しやすくなった」「個別学習にしたときの集中度が高まった」等の声が上がっています。
学びの改革パイオニア校 波田小学校
波田小学校では、集団に入りにくい児童の気持ちに寄り添い、その子の「今」に適した学びの継続を考えていくために、「子ども理解研修」に取り組んでいます。年度当初に、吃音のある児童・難聴の児童の理解と支援について、5月には、読み書きに困難さがある児童の理解と支援について研修会を実施しました。

昨年、働き方改革の取組みにより日課変更を実施し、生み出した放課後時間で、先生方が職員室で「授業の様子や子どもの姿」について語り合う機会が増えています。
学びの改革パイオニア校 波田中学校
波田中学校では、「中1ギャップ」解消に向けた取組みを、今年度波田小学校と連携を図りながら進めています。

中学校紹介コーナーの作成
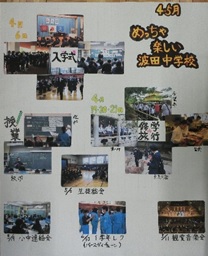
今年度は、小学校の6年生教室棟に設置した「波田中学校紹介コーナー」の掲示を定期的に更新し、生徒の手により中学校生活の様子を発信。6年生が中学校をより身近に感じ、不安を解消し、楽しみを抱いてもらうことを願っています。
5月22日 更新
リーディングスクール 明善小学校
入学してから1ヶ月余りが経ちました。少しずつ学校の様子がわかり生活が広がってきた1年生に、2年生が明善小学校のきまりや生活の中で気をつけることなどについて伝えました。

10グループに分かれ、どうしたら1年生に分かりやすく伝えられるかを仲間と考え発表準備を進めてきた様子がうかがえました。1年生からたくさんの質問も飛び出し、それに一生懸命答える2年生の姿が頼もしく感じました。
リーディングスクール 鎌田中学校
日常の国語の授業の一コマ。小グループでホワイトボードを囲み気がついたことを気軽に語り合う生徒たち。

お互いの違いに寛容で、安心して学ぶことのできる関係性は、多様な子どもたちが同じ教室で学習を進めていく基盤です。
鎌田中学校では、安心して自分の思いや考えなどを表現できる学級や学年集団にしていきたいと考えています。
学びの改革パイオニア校 開智小学校
開智小学校では本年迎える創立150周年を「探究の学びの年」としようと児童・先生が歩みを踏み出しました。
取組のスタートに当たって、「探究の学び」について、すべての先生が学ぶ研修を実施しました。

県教育委員会学びの改革支援課の鈴木指導主事より「探究の学びとは」「学びに係る子ども観」「探究で育む資質能力」「単元づくりの基本」等について学びました。

熱心に話し合う先生方。講義の後、先生方から質問が相次ぐ等、前向きな雰囲気に満ちた研修会になりました。
5月15日 更新
学びの改革パイオニア校 丸ノ内中学校
昨年度より「探究の学び」への取組を始めた丸ノ内中学校。今年は軽井沢風越学園と連携しつつ、「探究の学び」の全校展開を図ります。


4月14日の第1回職員研修の様子。探究コーディネーターの上條先生が「探究の学び」の意義と具体的なイメージを、昨年度の3学年の実践の記録を中心に先生方に説明しました。先生方は温かく前向きな雰囲気で聞き入ります。後日、生徒にも「探究オリエンテーション」として同様のプレゼンテーションを行い、学びのイメージの共有を図りました。
リーディングスクール 中山小学校

4月後半のこの日、生活科、総合的な学習の時間の立ち上げについて意見交換を行いました。子どもの興味関心に乗っかるか、教師主導で始めるか。
導き出された結論は、「いずれのスタートであっても、体験を通して子どもたちの中に問いが生まれているかが大切ではないか」でした。
いよいよ各学級で子どもの問いを真ん中に据えた活動が始動します。
リーディングスクール 清水中学校

表現力についてのガイダンスを開催し、生徒と教師がイメージを共有しました。

ガイダンスの後日に開催された生徒総会では、判断の根拠を添えて表現する姿が見られました。