本文
窪田空穂記念館のみどころ
窪田空穂記念館の展示は、空穂の足跡を辿るかたちで展開しています。作品、書簡、原稿と愛用品などで展示を構成しています。
新体詩から短歌へ
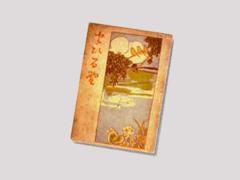
新体詩に興味をもっていた文学少年・空穂が短歌を作りはじめたのは、二十代になってからです。やがて與謝野鉄幹(寛)に認められ『明星』に参加します。処女詩歌集『まひる野』は、清麗で浪漫的な傾向の強いものです。
自然主義文学との出会い

東京専門学校(現・早稲田大学)卒業後、新聞記者や女学校の講師となります。田山花袋等と交わり、自然主義的な潮流のなかでさかんに短編小説を書きました。(短編小説『炉辺』など)また、『日本アルプスへ』などの紀行文も残しました。
古典研究

四十代、母校早稲田大学の教壇に立った空穂は、このころから古典研究を精力的に行います。万葉集、古今和歌集、新古今和歌集の三大評釈は、特に高い評価を得ています。
空穂の短歌
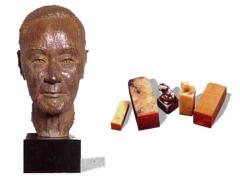
日常生活の周辺を歌いながら、人生の喜びと内面の苦しみ・悩み等の自分の心の動きに合わせ詠い、「境涯詠」ともいわれています。晩年になると、天地自然とともにある生命が、静かに、しかし強い意志力をもってとらえられています。
空穂の長歌

万葉集以来歌われることの少なくなった長歌を新しく現代に再生しました。特に亡き妻や子を詠った長歌は、その代表作といわれています。
空穂をめぐる人々
與謝野鉄幹を始めとして空穂と交流のあった人物を紹介しています。

