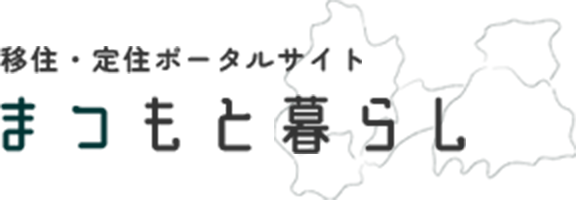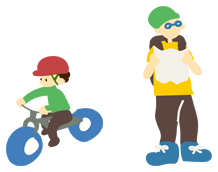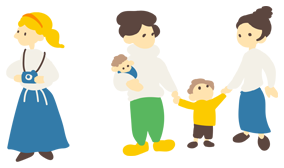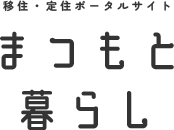本文
移住者インタビュー(黒澤さん)
黒澤さん(東京都から移住/4人家族)
「農業をやりたい」という思いを叶えるために松本に移住した黒澤さん。
ブドウ農家としてスタートして、現在4年目。
黒澤さんにとっての農業の師匠であり、20年前に松本に移住した中川さんと一緒にお話をお聞きしました。
▲中川さん(左)、黒澤さん(右)
Q. 松本市に移住するまでの経緯を教えてください。
黒澤さん:長野県茅野市(※1)出身で、大学は信州大学(※2)の繊維学部に入ったので、1年間を松本市で過ごして、その後大学院卒業までの5年間を長野県上田市(※3)で過ごしました。
大学院での専攻が微生物で醸造関係の就職先が多かったので、就職で福岡県久留米市に行って、お酒について研究しながら現場で焼酎を作ったりしていました。
その後転勤で山梨県韮崎市に行き、お酒のコストカットとか品質を上げるための研究をしていました。
その頃にはもう結婚して子供もいたので、全国転勤の会社だと負担が大きいと感じて転職しました。
転職したのは東京のコーヒーメーカーで、スティックコーヒーの開発を10年程やりました。
ずっと自然が大好きで、それこそ山に行って山菜採ったり釣りに行ったり…。
なので大学生くらいから、いつかは農業をやりたいっていうのがずっと頭にありました。
東京に住んでいた時、市民農園を借りて野菜を作っていたんですが、本格的に農業をやろうと決意して、2020年の8月に松本に転入しました。
(※1 長野県南信地方の市。)
(※2 松本市旭(あさひ)にある国立大学。2年生以降は学部によりキャンパスが分かれます。)
(※3 長野県東信地方の市。)
Q. 移住を考えたきっかけは何ですか?
黒澤さん:農業をやりたいっていうのがずっと頭の片隅にあって、でも子供がどんどん大きくなって中学生とか高校生になってからだと、なかなか動けないなと思ったので。
2020年は娘も息子も小学生だったので、いろいろ考えて早い方がいいと。
自分もそのとき40歳だったので、体力的にも今かなと思って。
―移住することを決断したときの家族の反応はどうでしたか?
黒澤さん:妻は東京の生活に慣れて楽だったのもあって、あんまり変化を望まないような感じではあったんですけど、妻も長野市出身なので、戻るっていうようなイメージではありました。
そんなに反対という感じでもなく、「いいんじゃない」と言ってくれました。
子供たちも自然が好きだったので、引っ越しに関してもかなり前向きに捉えてくれて、全然嫌がってなかったです。
Q. 移住先を松本市に決めた理由は何ですか?
黒澤さん:最初は、地元の茅野市で農業をやろうってずっと考えていました。
でも実はその頃から両親と姉が松本に住んでいたこともあって、いろいろ重なってもう松本の方がいいじゃんっていう話になりました。
ただ一応、近場で安曇野市(※4)とかも考えてはいましたね。
2020年の1月に、東京の池袋で「新・農業人フェア」(※5)っていうイベントがあって、松本市のブドウ農家さんが来られるっていう話を聞いたので参加しました。
その農家さんが中川さんで、それが中川さんとの初対面でした。
中川さんからブドウのお話を聞いたことがきっかけで松本に決めました。
その時に中川さんからはブドウのことだけじゃなくて、農園がある地区のこともいろいろ教えてもらいました。
市街地に近くて、公立高校もある程度のレベルに合わせて選べるし、自転車で通える範囲にあるっていうような話ですね。
農業に関することだと、初期の資金がどのくらいは必要だとか、どのくらいの面積をやるとどのくらいの収入があって最終的にはこのくらい、そうすると1人ではできないから人も確保が必要とか、本当にいろいろ。
中川さん自身も移住者で同じ経験をされてきて、その経験に沿って説明していただいたので、そのときに結構イメージは沸きましたね。
元々果樹をやりたくていろいろ調べていた結果、その中でもブドウは反収が良い方だと思っていたので、実際に育てている中川さんから「ちゃんとやればこれだけお金になる仕事だよ」っていう話を聞けて、自分のライフスタイルとか含めて条件に合うところが松本市だなって感じました。
(※4 松本市の北側に隣接する市。)
(※5 年に数回、首都圏で行われる就農フェア。ホームページはこちら<外部リンク>)
▲黒澤さんの自宅周辺から見える景色
Q. 就農のための支援制度は利用しましたか?
黒澤さん:実際に利用した制度は、技術習得の支援として長野県の「新規就農里親研修事業」を2年間。
それに抱き合わせという形で、経済的な支援として松本市の「新規就農者育成対策事業」を3年間。(※6)
2020年8月に松本に引っ越してきてエントリーして、同じ年内にはスタートしました。
「新規就農里親研修事業」というのは、就農希望者の支援に積極的な熟練農業者の方を「里親」として登録して、就農を希望する方に紹介して農業研修をサポートする制度なんですけど、私の里親を中川さんが引き受けてくれました。
2年間のうち最初の1年間は、小諸市(※7)にある長野県農業大学校(※8)に月1回ぐらい通って研修を受けました。
ただその頃コロナ禍だったので、ほとんどオンラインだったんですけど。
農業の基礎とか刈払機の使い方、鍬の持ち方から始まって、病害虫を防ぐとか、農薬のお話とか、そういう基礎的なことを学生と一緒に学びました。
それと同時進行で、「新規就農者育成対策事業」で月に7万円の生活補助を受けながら、JAが借りた畑を使って、里親さんから学んだことを実践して作って、それで出来たものは全てJAに出荷するという流れでやっていました。ただし売り上げは全部自分のものになりますよっていう制度でした。
里親である中川さんのところに通いながら教えてもらうんですけど、結構1年目から自分でやる面積が多くてですね…。
基礎を教わって、自分の畑で実践してみたいなところから始まって、ただもう4月~5月になって芽が出てきたらノンストップなんですよね。
ちょうど中川さんの畑では、早生種っていうか、私の畑よりも1週間くらい早く進んでいたので、中川さんの畑で教わりながら一緒にやって、それを次の週に自分の畑で実践するという繰り返しでなんとかやってきましたね。
―研修を受けてみてどうでしたか?
黒澤さん:良かったと思います。というのも、実践的っていうか、「ここは責任持ってあなたがやるんだよ」って初年度から畑をしっかり与えてもらって、その売り上げも自分に返ってくるところが良かったです。
作ったものをちゃんとお金に変えてくれるところがないといけないと思うんですよね。
私も農業を始める前は、自分で売るための販路は分かるし、今こういう時代だからインターネットで…とか思っていたんですけど、いざ自分でやってみると大変で。
今私がちゃんと成り立っているのは、産地で集荷してそれを全部買い取ってくれるっていう流れがあったからだと思うので、それはすごく大事だったなと思います。
―中川さんはどのような流れで里親を引き受けることになったのですか?
中川さん:あのときは黒澤くんともう1人新規就農希望の人がいたんだよね。
それでその人の里親候補が、私自身が新規就農制度を受けた当時の同期生で、「じゃ、1人ずつ持とうか」みたいな感じでした。
その頃ってまだあんまり地区の中で新規就農者っていないから大きな動きがなくて。
やれ里親とか新規就農とか、人がいないと産地が持たないみたいな発想があんまりなかったんだよね。
ところがだんだん空き農地も増えて、高齢化でブドウやめちゃう人もそれなりに出てきて、畑は空くし人はいなくなるしね。
次にやる人いないよっていうようなことが、みんなだんだん分かってきて、このままじゃいけないよねっていう空気が出てきたときだった。
―中川さんの農園のホームページを拝見したら、松本の新規就農事業を受けて独立した人は継続率が高いと書いていましたね。(※9)
中川さん:継続率が高いというか、そもそも農業を志す動機や意志とか覚悟が曖昧な人は初めから排除される(笑)
松本のこの事業に採択されるためには、何回もミーティングするんですよ。長野県とか市役所とJAも含めて4回も5回も。
そこで覚悟がない人とかビジョンが不明確な人、実際話聞いてみたら自信なくなっちゃう人は白紙に戻したり、「もう1年考えます」ってことになってどんどん篩にかけられます(笑)
初めのハードルが結構高いです。
黒澤さん:面接があるんですけど、これが結構大変で。10対1の面接で、決意表明の場ですね。
―中川さんは今までも何回か里親をされていたんですか?
中川さん:いやいや、黒澤くんだけだよ。
―やってみてどうでしたか?
中川さん:こういう人(黒澤さん)が出来上がる(笑)
(※6 松本市では、新規就農したい方に合わせて様々な支援制度をご案内しています。詳しくはこちら)
(※7 長野県東信地方の市。)
(※8 農業に関する理論と実技を同時に学ぶ実践型教育を行う県立の専修学校。)
(※9 中川さんの農園「なかがわ葡萄園」ホームページはこちら<外部リンク>)
▲黒澤さんが育てた色づく前のデラウエア
Q. 物件探しはどのようにしましたか?
黒澤さん:一軒家を借りている状態なんですけど、そこを借りられることになったのは、中川さんがその地区の当時の町会長さんに話をしてくださったことから始まって…。
その町会長さんがその家の所有者さんに話をしてくださったことがきっかけでした。
そのときに1回会いましたよね?
中川さん:そうだね。コロナの中、公民館で会った。みんなマスクしてた(笑)
黒澤さん:そう、コロナがね、ちょうど出始めた頃で。
そのときに松本に行って、中川さんや町会長さん達と打ち合わせとかさせてもらって。
東京から田舎に来るってことで、町会(※10)のこととか心配していろいろ教えてくれたり、今住んでいる家が当時空き家だったので所有者の方に連絡を取ってくださったり…。
―物件を工面してあげるのは、よくあることなんですか?
中川さん:全然ない。普通、こんなことまではしません。
ただ、Iターン新規就農者が農業を始める前に一番最初にやらないといけないことは、まず住むところを探すことなんです。
空き家って実はそれなりにあって、所有者さんはそれなりに管理はするけれども、人に貸すとか売るっていう発想を持っていないことが多い。なので情報として表に出てこない。
当時の町会長さんが、若い人たちに定住してもらわないと町会自体も世帯数が減ってしまうので、なんとかしないといけないという危機感を持っておられたこともあって、その家の所有者さんに、農業をやりたくて家を探している若い人がいるから貸してくれないかって熱心に説得してくれたっていう経緯です。
黒澤さん:中川さんや町会長さんがそこまでやってくださったのもありますし、正直その当時もうコロナで松本に行けなくなっちゃって、家を探せなくて他に選択肢が無かったのもあります。
これから農家をやる人向けの物件って特殊でなかなか見つからないので、本当に良かった。
(※10 松本市では「町会」と呼ばれる居住地区の区域内の世帯で構成される自治組織があります。町会ごとに特色ある活動が行われており、集会は月1回という町会もあれば、年1回という町会もあります。活動内容や頻度は、所属する町会により異なります。町会の詳細はこちら)
Q. 移住してから家族に変化はありましたか?
黒澤さん:妻と私が逆転しました。
妻は土日に農業を手伝ってくれたりするんですけど、外で正社員で働いているんです。
なので、今は平日は私がご飯をほとんど作っていますし、子供と過ごす時間がとても増えました。
別にどこかに遊びに行くとかじゃなくても普段の生活の中で子供と接する時間が増えましたし、参観日とかも私が行くことが増えました。
そこはかなりの変化でしたね。
Q. 地域との関わりはどうですか?
黒澤さん:東京にいて会社員をやっていると町内会っていうものはほとんど関わりが無いので、地方に来ると一気に距離が近くなってギャップではありますよね。
町会費もかかることがあると思うんですけど、関わってみると分かるのは、本当に必要な経費なんですよね。町会を維持していくために必要なお金なので。
町会の役員も回ってきて、去年は部長をやったり、今は交通安全協会の支部長で朝に通学路で旗を持って立ったりしています。
大変ではありますけど、楽しんでいます。
就農支援の研修を受けていた頃にJAの方から、「今までは会社員として企業にいたと思うけど、農業をやるということは、その地域に就職するということです。」って言われたことがあって…。
実際に4年間やってみて、本当にそうだなって実感しています。
中川さん:町会費って高く感じるんだよね、実際安くないと思う。
だけど、実際どういうふうに使われているのかというのは、町会で総会をやるときに必ず会計報告ってあるからね。
その会計報告を一つ一つ細かく見てみると、やっぱり全部必要なんだよね。だからこそ、楽しくやるしかない。
Q. 松本での生活の満足度はどうですか?
黒澤さん:とても満足しています。
自分基準にはなるんですけど、やりたかった農業ができているので。
いろんな方の協力があって、もちろん大変ではあるけど割とスムーズにできました。
今年4年目ですが、もう軌道に乗っているというか、十分生活していけるくらいになったので良かったです。
今住んでいる地区は市街地や松本駅も割と近いですし、東京から友達が遊びに来たりしてもアクセスが良い。
空港もあって、去年の今頃は松本からFDA(※11)で大阪方面に行きました。
あと土日とか時間があれば、子供と安曇野市の方まで行って釣り堀で釣りしたり、そばを食べたり、おやきを買いに行ったり、あと温泉も行きます。
例えば「遊園地に行きたい」ってなると、そういうところは近くには無いけど、逆に公園とかアウトドアをやろうと思ったときは、いくらでもできる。
松本での生活は普段からちょっとアウトドアなので、そんなところもいいですね。
(※11 株式会社フジドリームエアラインズ。信州まつもと空港に就航する航空会社。信州まつもと空港のホームページはこちら<外部リンク>)
▲農園で作業する黒澤さん